やっぱりあいつの頭ってどうかしてる。いっそのこと病院にでも送ってやろうかしら。留まることをしらない相手への罵倒は、口にしなかったが内心はそれで溢れ返っていた。大広間へ向かうカップルの目を浴びていることなど露も気にせず、私はサファイアブルーのドレスの裾をなびかせて人の流れに逆らって誰も居ない場所へと向かっていた。今日はホグワーツの恒例行事のプロムがある日だ。卒業生、在校生問わず夜遅くまで教師を含めみんなが、罰則も減点もなしで起きていられる日だ。私は今日でここを去る卒業生。
プロムには誘ってきた同じ寮のダンケロ・マクヒューザーと一緒に行く予定だったが、待ち合わせ場所に行けば目を疑う光景があった。なんとマクヒューザーが、他の女子と腕を組んで大広間に行ってしまったのだ。彼とは何の接点もなかったので何も言わず帰ってきたが、流石にあれはどうかと思った。向こうから誘っておいて急に約束を違えるなんて、とんだ非常識な男ね!しかもレディをこんな日に一人にさせるなんて。ありえないわ!ということで私は怒り心頭に発する。
「ほんと信じらんない!」
やってきたのは学校の裏庭で、そこにはぽつんとひとつの小さな池があった。どっぷりと日が沈み白い月が空から小さく輝いている。その月の光を池の水が反射する。しんと静まった裏庭には私以外に人なんて居なくて、その上つんと澄んだ冷たい空気が頭に昇った熱い血を冷ましてくれたので、先程よりかは少しだけ気分が落ち着いた。
「最悪なプロムね」
芝生の上に腰を下ろす。草の先端が少し刺さるがまあいい。サファイアブルーのドレスも、こうも暗い場所だと深い紺色に見えてくる。綿より軽い素材のレースが使われているドレスは、ワンピースにも見える。首元まで伸びるアメリカンドレススタイルのワンピースみたいなものだ。疎らに散らばった白いストーンは光が当たるたびきらきらと瞬く。まるで夜空に輝く星々だ。綺麗なドレスだとは思うけど、置かれた状況からしてとても嬉しくなれる気分にはなれない。
「あんな奴、さっさと振られればいいのよ」
口でいくらあいつを貶しても気分は上がらないし溜め息も止まらない。今更私から他の男性に「パートナーに捨てられたから一緒に踊ってくれない?」と聞くのもはばかられる。第一惨めなので絶対にしたくない。私は悪くないのよ、何も言わず他の女の子と行ったあいつが悪いの。なんで私が辱められなければいけないの。
「先帰ろうにもホグワーツ急行は未だ来てないし、寮に戻ろうにも絵画の女性もどこかに行って入れないし。ドレスの格好で図書室行くのも嫌だわ、絶対浮く」
最悪だ。こんなことなら一、二冊本を携帯すれば良かったわ。いつもは間違いなく持っていたのに。私ってばプロムで浮かれ過ぎたのよね、きっと。ちょっとやだ、視界まで歪んできちゃったじゃないの。はっきりと見えていた月の輪郭がぼやける。白と紺色が混ざって、いよいよ眦から一筋の涙が零れた。それを皮切りに涙はどんどん溢れて流れる。首元のレースにぽつ、ぽつと涙が染み込んでいく。
「惨めなことこの上ないわね」
膝を丸めて両手で抱え込んだ。膝頭に顔を押し付ける。何事にも勉強が大切だと、勉強一筋だった私でも、今日は楽しみにしていたのよ。ホグワーツに居られる最後の日だから。それなりに思い出深かったので余計に辛かった。なんで大切な日をあんな奴に台無しにされないといけないのよ。そうよ。
「そうだわ。あんな奴のせいで泣くなんてそれこそ恥ずかしいわ。ドレスだろうかなんだろうか楽しめばいいのよ」
いいわ。この服で図書室でも地下牢教室でも行ってやるわ。意志が固まり勢い立ち上がると、木の茂みがガサッと動いた。一瞬にしてそちらに意識が向く。眼差しを剣のようにして睨んだ。ガサガサと葉っぱが擦れ、姿を現したのは拍子抜けにも、一人の男子生徒であった。木の影から顔を出すと、白い月の灯りに照らされて彼の容姿が明瞭に浮かび上がった。水に濡れたような瑞々しい艶を放つ黒い髪に、凛とした鋭い黒の眼差し、ローブから伸びた手首は細くてまるでに女子かと見間違うほどだった。私は間抜けにもその男子生徒がどこの寮かも忘れて容姿に現を抜かしてしまった。絵画から抜け出してきたかのような美しさと、すぐに死んでしまいそうな儚げさをまとった彼に、どこか羨望の眼差しを送っていた。あまりにも見つめすぎたからか、彼が私を見遣る。
「あっ」
ばちりと視線が交わってしまい、ばつの悪い思いをしてそそくさと顔を背けた。だが、彼が私を向いて解ったこともある。彼はスリザリン生だということ。そして多分在校生だということ。後者は完全に憶測だが。
「こんなところで何をしているんですか?」
「え? わっ、いつの間に」
ぴったり背後から声がし振り向けば、いつの間にか美しい彼はすぐ後ろで見下ろして立って居た。びっくりして後退りしてしまう。化け物でも見たかのような反応に彼はムスッと眉を寄せ「失礼ですね。普通に歩いて来ましたよ」と言った。
「そ、そうよね、ごめんなさい。貴方は在校生? それとも卒業生?」
「人の質問に答える前に質問をするとは、卒業生の方は随分偉いようですね」
ツンと突き放すような言い方に、カァッと全身が熱くなった。
「そんなつもりはないわ! 歳上にそんな口の利き方をする貴方の方が、随分立派と思っているんじゃなくて?」
「血筋で言えば貴女より立派ですよ」
「そういう話をしているんじゃないのっ」
なんなのこの子。可憐な容姿に見合わず随分ズケズケ物を言う子ね!? 見とれていた数分前の私をぶん殴りたい。もういい、彼と話していたら貴重な時間が無くなってしまう。最後の最後まで読めなかった本を今日こそ読むんだから。
「悪いけどもう行くわ。じゃあね」
「ああ、ひとつ教えてあげますが、マダム・ピンズなら大広間に居るので図書室は閉室されていますよ」
「えっ!? そうなの!?」
「嘘を言ってどうするんですか」
そ、そんな。衝撃の事実に膝が支えを失ってしまい芝生の上に力なく座り込んでしまう。どうしてくれるの、あいつ!図書室にも行けない大広間にも行けない、手元に本はない。行動に暗礁が乗り上げるなんて、私って何かしらの呪いでも受けているのかしら。
「どうしよう」
「大広間に行けばいいでしょう」
溜め息を吐くと、平然と言ってのける彼に少しムスッとした。
「行けるワケないでしょう。一人で食事してろと?」
「パートナーに捨てられたんですか?」
「うるさい」
言い当てられてしまってつい言葉がキツくなってしまう。彼は何を考えたのか、上半身を曲げて手を差し伸べた。私は訳が分からず目を点にする。
「一曲でしたら相手しますよ」
「終わるって時に大広間に行くの?」
「いいえ。うるさいのは嫌いですので、ここで踊りましょう」
幸いにも大広間から差ほど遠くない場所なため、軽快な音楽が大音量でなくとも、リズムがはっきりと解るくらいには聴こえてくる。あ、ちょうど音楽が変わった。今度はゆったりとした曲調だ。
「Would you like to dance with me?」
「Willing」
微かに微笑む彼を見て、私はにこりと笑んで手を重ねた。手を引かれ腰を抱き寄せられる。ゼロ距離の密着に、年下のスリザリン生であると理解していながらも、心臓は恋する乙女のようにドキドキと激しい鼓動を刻んだ。密着した胸のせいでもしかしたら緊張していることも、ドキドキしていることも伝わってしまうんじゃないかと思った。
「先輩、緊張しているんですか?」
伝わっていたようだった。
「男子とはあまり接する機会がないから、少しだけ戸惑っているだけよ」
「では、こうしてください」
腰に回っていた手が私の後頭部を軽く押す。彼の薄い胸板にこつんと当たってしまった。彼は顎を引いて私を見つめたまま「こういう時は男に全てを委ねてください」と月を背にして言うもんだから、不覚にも心臓が大きく波を打ってしまった。ゆったりまったりとした曲調に合わせて、意外にも彼は流れるようにステップを踏んでいく。滞る様子もなく、ダンスのイロハなんて解らない私をしっかりリードしながら踊る様からして、彼は多分いいとこのお坊ちゃんなのだろうと思った。スリザリン生のお坊ちゃんであれば社交ダンスの一つや二つは心得ているはずだから。にしても、
「私の寮の男子とは段違いね」
グリフィンドールの男子といえば、大雑把でガサツな男子が大半だ。女子にも悪戯する奴は居るしレディファーストなんて言葉すら知らないんじゃないかって思うくらい雑に接する。だけど彼はそんな彼らとほんとうに同じ性別なのかと疑いたくなるほど、繊細に丁寧に私の体を扱ってくれる。これがもし最初のパートナーなら、踵を踏むわ手を引っ張るわで、きっと居た堪れない酷いダンスをするところだったろう。そう考えれば、これは不幸中の幸いというものかもしれない。
「グリフィンドールと一緒にしないでください」
ムスッとしたのが声で解った。くすりと笑みが零れる。
「ええ、そうね。聞いていなかったけれど、貴方の名前はなんて言うの?」
上を向いて尋ねれば、彼は正面を向き何か検討するように幾分かの時間を置いて私を見た。
「お互い一夜きりのパートナーなんですから、知らないままでいいでしょう」
「言われてみればそうね。解ったわ」
残念な気持ちも否めないが、教えてくれそうにもなかったのでやめておいた。また曲が変わりテンポが少し速くなった。男性が女性に強く、激しく気持ちを主張しているような熱い曲だ。ひとつひとつのステップの時間が短いので、足の動きも自然と速くなる。それは彼のリードから見て取れた。
「貴方こういうのも踊れるのね。意外」
「これくらいの速度でしたら踊れます。馬鹿騒ぎする人が好む姦しい曲は踊れません。踊ろうとも思いませんが」
「うるさい曲は私も好きじゃないわ。だからって眠たくなるような曲も好きではないけれど」
「図書室を好むような方ですからね」
「それ関係ないでしょ」
彼は話す方だった。自分から話題を振ることはしないが、私から話をすればひとつひとつに答えを返してくれる。最初にあった緊張やドキドキは薄れていって、自然と彼と話すのが楽しいと思えるようになった。気付けば曲は止んでいた。休憩したいと言えば彼は解りましたと手を離す。二人して芝生の上に座る。彼に触られたところは暖かい熱を帯びたままだった。涼しい風が髪を攫う。空中に浮く髪を抑えつつ、空を仰ぐ。月は白いままで空に浮かんでいた。変わったといえば場所だろう。上がったばかりの東から、今は真上に移動している。それを見て「結構な時間が経ったんだな」と思うと同時に胸がギシッと痛みに軋んだ。
「後少しね、ここに居られるのも」
七年間世話になった学校から、気付けば去る歳になった。入学の時の初々しさや期待で膨らんだ胸の高揚感も鮮明に覚えている。組み分け帽子に告げられた寮の名前、初めての授業で先生に褒められたこと、初めての呪文が成功したことや、箒に上手く乗れなくて転けたことまでも。ビデオレターのように全てのシーンが頭の中で流れる。七年間なんて長いようであっという間だ。気付いたのはこの歳になってから。入ってきた頃はまだ十一歳で、七年間なんて長いものだと思っていたが、卒業する歳になって解る。
「貴女が読みたかった本はなんですか?」
隣で空を見上げていた彼は尋ねる。不思議に思いながらも答えた。
「『闇の魔法呪文百選』というやつよ」
「貴女グリフィンドールですよね?」
これには驚いたようで、私を見たまま目を瞬かせる。
「闇だろうがなんだろうが、魔法は魔法よ。私は知りたいだけなの。勿論闇の魔法を人に使う気はないわ」
「勉強熱心ですね」
「そのためにここへ来たんですもの」
「いいですよ。ぼくが貴女に送ります」
「え?」
「その本、ぼくが持っているので差し上げます」
思いもよらない嬉しい誘いだが、果たしていいのだろうか。闇の魔法に関する本は多く出回らない上に購入審査だってそれなりに厳しい。未成年の魔法使いが高度な闇の魔法を勉強するとなると悪用しかねんと言うことで睨まれる可能性だってある。その上で持つということは、それほど欲しかった物ではなかろうか。それを易々。そんな私の心情を察したように彼は言った。
「いくらでも購入手段はあるので大丈夫です」
「なんか、いけないことを聞いた気がしたわ」
「貴女が心の内に留めておけば、無い話も同然ですよ」
「聞かなかったことにするわね。本のことだけど、貴方がほんとうに手放しても良いのだったらぜひ送って欲しいわ。ずっと読みたかったの」
「解りました。では学期が明けたら送りますね」
「ありがとう」
最悪な日だと思っていたけれど、あれは撤回ね。これほど最高な日はないわ!なんていったって、美しい彼と踊れた上に読みたかった本が手に入ったんですもの。最後の日としては最高の締め括りね。家に帰るのが待ち遠しいわ。お母さんとお父さんに自慢しなくちゃ。二人も手を叩いて喜んでくれるはず。帰ったらまず何から手を付けようかしら。
「あ、あれ?」
嬉しいはずなのに目から溢れる涙を止めることができない。何故?どうして?涙が出るの? ワケが解らず目を点にし笑いを零すと、ばさっと頭に黒いローブが降り掛かった。芝生の上に裾や袖が襞のように四方に散らばる。柔軟剤の優しくほんのりと甘い花の香りが鼻をくすぐる。
「何するのよ」
彼は私を見たまま呆れたように息を吐く。
「泣きたい心で笑っても、気持ちは晴れませんよ」
前を向いた彼は「それなら誰にも見られません」と付け加えた。その気遣いに、いよいよ我慢の限界がきた。ぼろぼろと大粒の涙が頬を伝う。膝頭に顔を埋めて声を殺して泣いた。悲しいというか、寂しいというか。この感情に名前を当てはめられるほど器用ではない私は、学校のことを思って涙を流した。その間も頭の中では学校で味わった様々な出来事が流れる。友人作りが下手な私にも卒業後も関係を続けられるくらいの友人ができたり、食べたことも見たこともないような食事を食べたりなど。どれも単純で、もしかしたらここでなくても体験できそうなものだけど、それらは全てここで体験しここで得た物だ。それは変わらない。七年間一緒の部屋を過ごした彼女たちともこの夜が明ければ会うことはないかもしれない。明日からはみんなバラバラで生きていくのだ。
「もっと居たかった」
それが本音かもしれない。寂しいよりも悲しいよりも、それがぴったりだった。もっと居たい、もっと勉強したい、もっと皆と過ごしたい。それが痛いほど胸に突き刺さる。楽しいばかりの思い出ではないけれど、辛いものも悲しいものでさえも今となってはどれもが大切な思い出だと痛く感じる。
「貴女はそれほどこの学校が好きなんですね」
涙が勢いを弱めた頃、呟くように彼が言った。その横顔は少し寂しそうで。長いまつ毛の奥に隠れた瞳は、一体何を思っているのだろうと気になった。涙が乾き切ると顔をハンカチで拭いくすっと笑みを零した。
「ええ、好きよ。十八にもなって子供みたいと思うかもしれないけど、ホグワーツはそれほど好きな所なの」
来て良かったと今なら心から言える。
「学校を好きになれなんて言わないけれど、貴方にもここが少しでもそう思えるような場所であることを願うわ」
「ぼくにはただの学校という認識しかありませんよ。魔法の制御と知識を学ぶ場、それだけです」
「そう、それでもいいんじゃないかしら。最悪な学校と言われないだけマシね」
「好き過ぎですよ、貴女」
「自分でも思う」
くすくすと笑いが零れるくらいには、さっきの痛みは拭えていた。彼のおかげで明日からまた前を向いて歩けそうだ。
「フクロウ便で私に送る時の名前、決めましょうか」
「ぼくのをですか?」
「ええ。互いが互いの名前を決めるの。面白そうじゃない?」
しばらく考えるような素振りを見せ、
「いいんじゃないですか? ではまず貴女から決めてください」
面白そうだと頷いてくれた。
「そうね」
顎に指を宛てがい考える。黒い髪と黒い瞳に心を奪われたから、単純に “ブラック”という名前はどうかしら。ああでも安直過ぎるわね。せっかくなら凝った名前にしたいわ。
「WhiteMoonなんてどう?」
「『白い月』ですか」
「ええ。貴方が出てきた時白い月に照らし出されたのが印象的だったから、付けてみたの」
「極めて普通ですね」
「う、うるさいわね、自分でも捻った名前が出てこなくて悔やんでるから、言わないでちょうだい」
「次はぼくですね」
遮らないでちょうだいよ。考え込んだ彼。私は無言の邪魔をしないようにうっすらと流れるラップ調の曲を楽しみながら待つことにした。ぐるりと視界を見渡せば慣れ親しんだ建物の光景が映る。ごつごつとした岩のようなもので作られた柱や廊下。ゴシック調のホグワーツにはいくつもの小さく鋭い塔が軒を連ねている。上から見た時のホグワーツといったら、そりゃあもう綺麗だった。朝に見ると威厳を含んだ立派な城と思うが、夜に見ると一転しとても美しい城だと思う。まるで女性のようだ。決して自分を言うわけじゃないが、朝に見せる凛とした姿も、夜になれば華奢で柔くどこか可憐な雰囲気を漂わせる。二面性を持つ女性のそれと同じと言う意味だ。ホグワーツから仕事の依頼が来たりしないかしら。ここで働けるのなら、タダでも構わないわ。食住さえ提供してくれるならだけど。
「Amichevoleです」
白い紙にインクを落としたように、ぽつりと言われた。だけど聞いたことのない発音と言葉に首を傾げた。
「ごめん、なにそれ? どこの言葉?」
「秘密です」
「それくらいいいじゃない」
「どうせ一回しか使わないのだからいいでしょう」
よく解らないけど一応納得したように頷いたら睨まれた。なんで?
「そろそろ時間ですね」
「ええ」
腕に巻いた時計を見ると、ホグワーツ急行がホグズミード駅に来る時間に近付いていた。そろそろ寮に戻り着替えないといけない。ここから寮に行くには時間がかかる上に動いたり消えたりする階段に引っかかった時のことも想定すると、そろそろ移動しないと間に合わなくなる。心残りが多い心境でのそのそ立ち上がった。
「一回出てしまえばもう戻れないのよね」
スッキリしたはずなのに少しづつモヤモヤが心にかかり始める。霧のように薄らと、雷雲のようにどろりと黒く。座っていた彼がまた溜息を吐く。自分でも嫌なほどうじうじしてることは解ってるわよ。
「戻れないのはどの道を選んでも一緒です。貴女が学校に入ってしまえば入る前の生活には戻れない。一度寮に組み分けされてしまえば、される前には戻れない。どれも貴女が既に経験しているものです。貴女はその時戻りたいと泣きましたか?」
「いいえ」
「貴女はその時寂しいなんて思わなかったはずです。でしたら今も大丈夫ですよ。明日から新しい生活のことだけを考えられます」
「励ましてくれてる?」
「また泣かれても面倒なので」
「子供みたいに言わないでよ」
彼にそう言ってもらえて自然とやる気が出た。今度は満面の笑みで彼に「ありがとう」と言う。照れくさいのか、気恥しいのかは知らないが、そっぽ向いて「気にしないでください」と言った。なんだか素直でない子供みたいね。歳下らしい可愛さにくすりと微笑みが零れる。睨まれるのも御免なので、私はそろそろ帰る準備をしようと決める。
「じゃあ私、もう行くわね」
「はい」
「本のこと忘れないでちょうだいよ?」
「忘れませんよ。自分で言い出した事なので」
「それは良かった」
くるっと踵を返すとひらりとワンピースの襞が花のように開いた。校舎内の光を白いストーンが跳ね返す。ネイビーのヒールを鳴らして帰ろうとしたが、寸でで止まった。もう一度振り返って。
「貴方と話せて良かった。これ以上のものがないってくらい楽しい夜だったわ。貴方ってリードが上手なのね。もしどこかで会えたらまた手を取ってくれるかしら?」
尋ねれば、彼は面を食らったかのように目を瞬かせる。そしてふっと笑った。
「ええ。会えたら一緒に踊りましょう」
その返事に私は凄く嬉しくなった。心が楽しそうに躍る。笑顔を浮かべたまま小さく手を振った。
「ありがとう。さよなら」
そう言って今度こそ私は後ろを振り返ることなく廊下を駆けた。寮へ向かって一直線に。もし、私が彼と会わなければ泣くことも振り切ることもできなかっただろう。彼に触れられた熱も、掛けられたローブの匂いも、彼に言われた言葉の温かさも、どれも鮮明に記憶に刻まれた。同時に私は思う。きっと彼以上に美しく儚げな紳士は居ないだろうと。それくらい心が躍ったのだ。ふふと零れる笑顔は間違いなく彼がくれた、最高のプレゼント。もしかしたら読みたかった本以上に嬉しいプレゼントかもしれない。名前も知らない彼に溢れんばかりの幸せを、私は贈りたい。
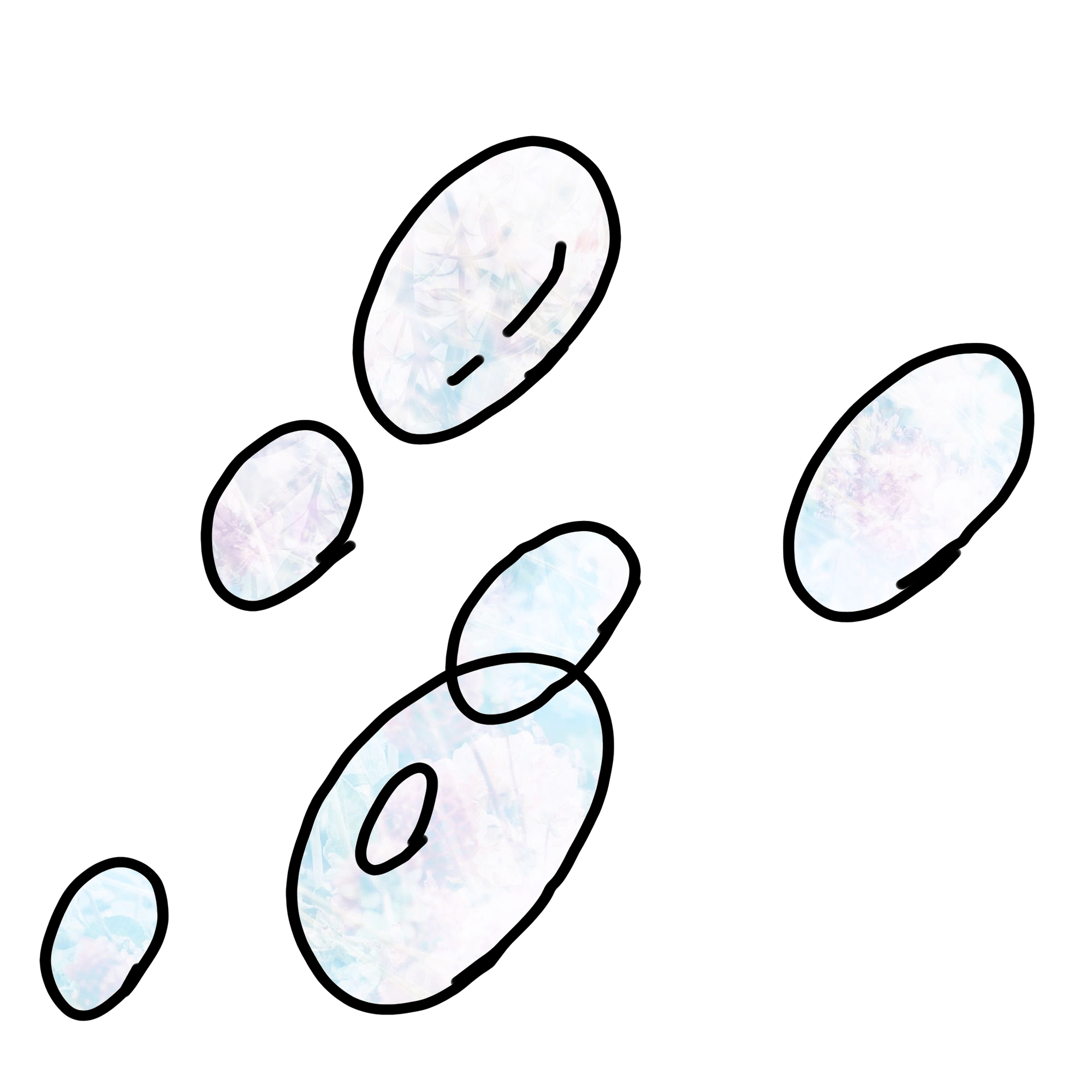
ホワイトムーンのプレゼント
、