怖い夢を見たような気がする。何か大切なものが欠けてしまったかのような夢。起きた時のシーツの音と心臓の音が鮮明に覚えている。汗だくのまま私は引っ張れるような足取りでひとつの部屋を訪れた。
「ねえレジー、起きてる?」
コンコンとノックするとやや遅れて中から女性にしては低いけれど男性にしてはやや高めな声が返ってくる。
「起きていますよ。入ってきて構いません」
「うん」
ドアノブを押して入る。人ひとりにしては広すぎる彼の寝室は電気おろか蝋燭一つ灯されていない。大きな窓から射し込む月明かりだけが部屋を照らしていた。流石ブラック家の跡取りなだけあって部屋の調度品ひとつひとつが相当な値打ちする物である。彼が座っているアンティーク調の椅子でも、売ればこの先一ヶ月の生活には困らないだろう。闇のように暗く、宝石のように輝く彼の緑の黒髪は彼がこちらを振り向いたことでカーテンのように揺れる。黒い双眸は知的を孕んで私を映していた。レジーが両手に持つは本棚に収められていた本の一冊。それを月明かりのみで読んでいるとは、彼の視力はもしかして下がらない代物なのだろうか。
「寝ないの?」
「必要ありませんよ。貴女は寝ないんですか?」
「寝たいんだけど……」
怖い夢を見た、と言うのは少し躊躇われた。いい歳した大人が、というよりかは何とはなしに言葉が口から出てこなかったのだ。大した意味は無い。なのに言葉は喉の奥で突っかかったように出てこない。しどろもどろに言い淀んでいると、それを見ていた彼は「寝ましょう」と静かに言って読んでいた本をぱたんと閉じる。
「僕も少し眠たくなりました」
「一緒に寝てくれるの?」
「ええもちろん。それにここには生憎と長身が横になれるようなソファはありません」
むしろそんなものがあれば私がそこで寝るのだが、実際問題彼の言うとおりこの部屋にはそんなものはない。大の大人が二人寝てもスペースが余るほどの大きなベッドと本棚、そして彼の座っている椅子と上質な壁紙にはめ込まれた天井にまで届きそうな大きな窓がひとつ。彼の部屋にはそれしかなかった。今日は一段と月明かりが眩しい。太陽にも似るその明るさにはけれども太陽のような温かさはない。だけど体を覆うシーツの冷たさも月明かりの冷たさも、傍に彼が居ればそれだけで体が冷えることはない。上質なシーツと彼の腕に包まれて瞼を下ろす。この部屋には私と彼しか居なくてとても静かだ。
「ねえレジー」
「はい」
「明日も一緒に寝てくれる? なんだか落ち着くから」
「いいですよ」
「ほんと? じゃあ明後日も?」
「はい」
「ありがとう。嬉しい」
ふふと頬を綻ばせれば、彼の指が頬を撫でた。埋めていた彼の胸からもそっと顔を持ち上げる。見下ろす彼の瞳は柔らかくて温かく感じれた。猫を愛撫するような手付きに擽ったさを覚えて、目を眇める。ずっとずっとこうしていたい。彼と二人だけで、ずっとこのまま。視界も思考も少しづつ歪み始めてくる。微睡みに溶けていく自分の頭が最後にはっきりと捉えた彼の言葉はひとつだけだった。
「ここでは悪夢に魘されることもなく、この先ずっとぼくと貴女だけですよ」
そういえば私はどんな夢を見ていたんだっけ。決して手放せない、手放してはいけないものが両手から抜け落ちてしまったような夢を見ていたはずなのだけど。そもそも私は誰?
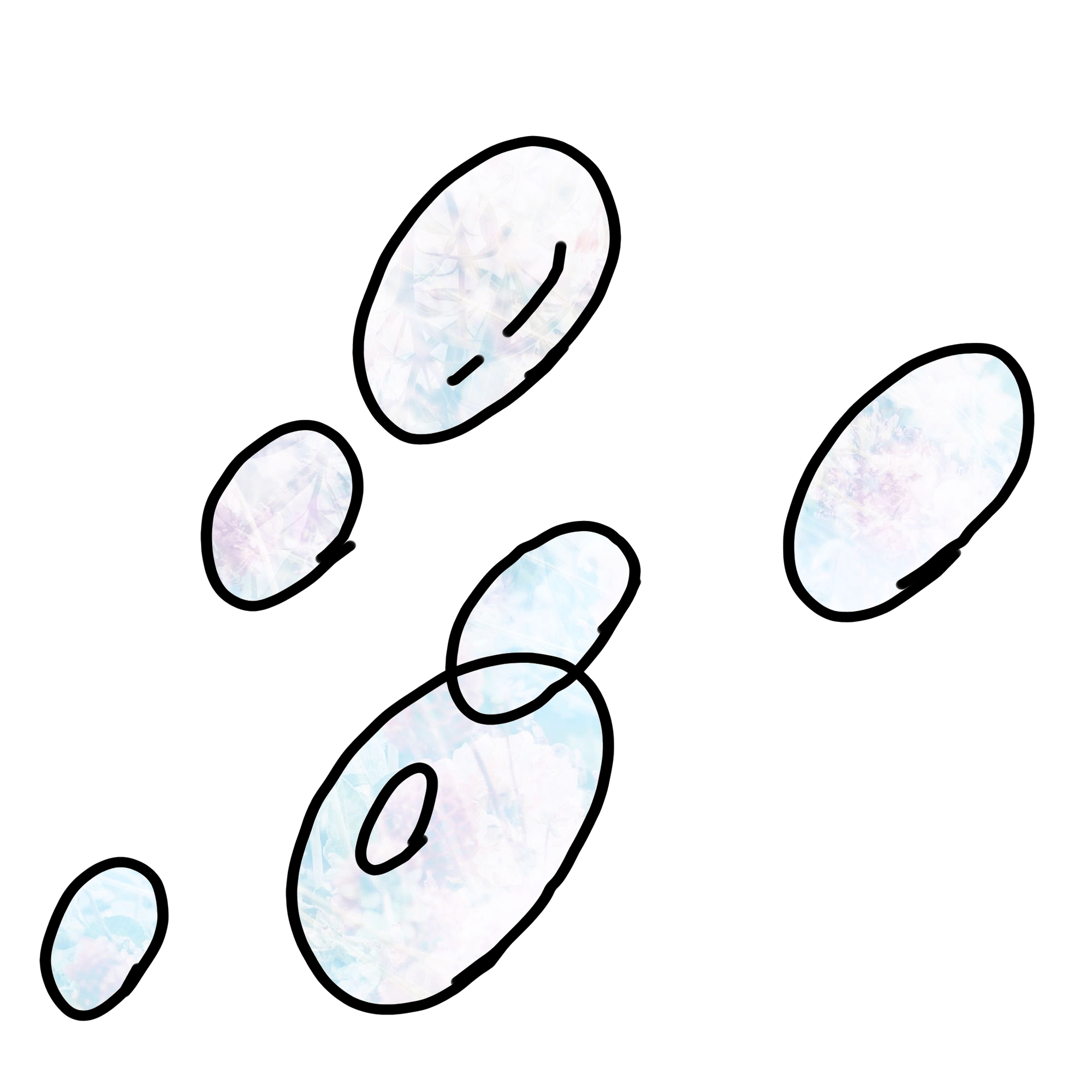
夢に堕ちて
、