私は今から人生一大サプライズを巻き起こす。それはこの大広間に居るホグワーツ全生徒が驚きに目をボールのようにしてしまうくらいの、どデカいサプライズ。いつも厳格なマクゴナル先生も、フレンドリーなスラグホーン先生も、おじいちゃんのような温かさを持つダンブルドア校長だって。スリザリン寮、グリフィンドール寮、ハッフルパフにレイブンクロー。寮、性別、出身、それらを問わず皆が皆私を見、沈黙に臥すことだろう。
それだけでかい事を起こすわけだから、当然のように全身がこれまで以上の緊張を帯びる。パンを齧ろうとしてスプーンを思い切り齧ってしまうくらい緊張している。同時に歯が痛い。とまあ、それはさておき。ワイワイガヤガヤ賑わうグリフィンドール寮には今日も悪戯仕掛け人が中心だ。私はそれを横目に今度こそパンを齧る。離れた所にはスリザリン寮の長い机があって、そこではサプライズを届ける相手が黙々と食事を摂っていた。ごくん、と嚥下する。今しかない。
「よう」
「どこへ行こうとしていたんだい?」
「げっ」
椅子から立ちスリザリン寮の机に行こうとしたら、運悪くさっきまで別の人と話していた悪戯仕掛け人のジェームズとシリウスが行く手を阻んできた。心無しか彼らの笑みに裏があると警報が鳴る。眦が吊り上がった。今日だけは邪魔されたくない。そんな思いが殺意となって抜きん出る。
「邪魔しないでよ。今したら二度と私に話しかけられないくらい後悔させるからね」
「おーおー、怖ぇ女だな」
「具体的にはどんなことするの?」
「茶化さないでジェームズ!」
「解った解った。今日は手を出さないでおくよ」
降参粧すように両手の平を左右に軽く振る。シリウスは驚いた顔で彼を見た。私も私で、あっさりと身を引いたジェームズに驚きと訝しげを隠せないでいる。
「いいのかよ」
「僕はこれでも良識は備えている方なんでね。流石に女の子の一大決心のお披露目会を邪魔するなんて無粋なことはしないよ」
「ジェームズに良識なんてあったんだ」
むしろそっちに驚きだ。無粋なことしないなら今までもそうしてほしかったな? だけどそれを言って話を長引かせたらスリザリンの彼は出て行ってしまいそうなので、私は「ありがとう」と言うに留めた。通り過ぎようとした時、ふとジェームズの言ったことに違和感を覚えた。なんの根拠もない違和感が、次第に膨れて胸を埋める。緊張はどこか、今はその違和感が気になってしょうがない。なんだろうと思考を巡らせるも答えに辿り着くまで時間は要さなかった。弾かれたように振り向き、彼を見た。ジェームズは気付いたかと言わんばかりの意地の悪い笑顔を浮かべている。
「私がすることなんで知ってるの!?」
「勘だよ。まさか当たっていたとは」
白を切る彼に恥ずかしさが弾ける。隣に立っているシリウスにもどうやら私の行動はお見通しのようだ。カッと頬が熱くなる。なんて言い返そうかと脳漿を絞っているとそれよりも早くシリウスが言った。
「いいからさっさと行けよ。じゃねぇとあいつ、出て行くぞ」
「あっ」
それは確かだった。指されたスリザリンの彼は自身の皿に乗っている食事を全て平らげていた。これはいよいよまずい。今行かないと私の岩よりも固く熱より熱い意思が、雲のように揺らいでしまう。ジェームズとシリウスに言いたいことは山ほどあったが、それは全て後回しにしよう。
「行ってくるっ」
背を向けてスリザリン寮の机へ歩いていく。自然と足早になってしまうのは、逸る想いを伝えるためか今にも帰ってしまいそうな彼を留めるためか。スリザリン寮の机に少しづつ近づくたびに、私の首元のネクタイカラーを見たスリザリンの女子生徒が訝しげな表情をする。そりゃそうだ。深紅と金色のネクタイが彼らの嫌いな対象にならないはずがない。私を見る男子生徒や女子生徒はきっと「何をする気だ」と警戒心を剥き出しにしていることだろう。だけど逐一それに気を取られていたら彼の元へ辿り着く前でUターンしてしまう。見てないフリ見ないフリで膝を叱咤し歩かせる。
いよいよスリザリン寮の守備範囲に入ってしまえば否でも全員の目線を浴びなければいけないことになった。視線を合わせないように目線を少し下にやってもばちりと合うし、終いには小声で私のことを話す会話も聞こえてきた。自分の周りはこれほどザワついているのに、サプライズを仕掛ける相手の彼は読んでいる本からぴくりとも視線を動かさない。端整な顔立ちや品を窺わせる姿勢は、動かなかったら完全に人形のそれだ。そしてそんな彼を真っ直ぐに見下ろして傍に立つ。
「レギュラス」
声を絞り出すとそこでようやく彼は顔を上げた。良かった、情けない声を出さなくて。緊張しているからと言い第一声そうそうに声が裏返ったらあまりの恥ずかしさに手当り次第にオブリエイトを唱えてしまいそうだ。
「どうしましたか?」
表情こそ変化はないが、声音は優しかった。いつも凛としていて流れるように綺麗な言葉が紡がれる。先生に対しても私に対しても、それは変わらない。ドキドキがいっそう増したが、そこはグリフィンドールの意地が背中を押した。グリフィンドール寮生たるもの、自身が決めたことを貫き通さないのはらしくない。
「貴方に伝えたいことがあるのっ!」
「はい」
あ、やばい、心臓が痛い。張り裂けそうだ。ばくん、ばくん。心臓の動悸が嫌に大きく聞こえる。あまりの緊張にお腹が痛くなり吐きそうになった。だけど拳をぎゅっと握って一切を堪える。今言わないといけない。今じゃないとダメなんだから、逃げちゃダメよ自分。知らぬ間に大広間は静まり返っていて、彼の隣に座るクラウチJr.だって私達の話に耳を立てている。この部屋の全ての意識が私達に向けられているのだ。レギュラスは不思議そうに小首を傾げている。とうとう腹を決めた私はすっと息を吸い込み肺を空気で満たす。それを一気に吐き出すように口を開いた。
「私と結婚を前提にお付き合いしてください!」
寿命何十年分を使い果たした気分だ。スカッと空になる肺。激しい運動をした後のように体が熱い。水を打ったように一瞬静まり返った大広間は、瞬く間にどこからかヒューヒューと口笛を吹く音や「くっ付いちまえ」と冷やかしの声などの喧騒に包まれる。怒り薬を飲んだかのように真っ赤なになっているだろう私を見て、レギュラスはぱちくりと目を瞬かせている。
「あ、あの、私純血だし箒に乗るのも上手、ではないけど、でもっ、好きだし。その、レギュラスが好きですっ」
いろいろ滅茶苦茶で、自分でも激しく落胆した。ほんとうは彼のようにスマートに「好きです。付き合ってください」と言うつもりだった。なのにいざ彼を前にして口を開いたらこれだ。もしかしたら彼も同じく落胆したのかもしれない。たどたどしい女なんて嫌だったのかも。授業の時やどうでもない時も結構話すから次第に私は彼に惹かれたけど、彼もそうであるとは限らない。一方的な好意だったかも。
彼も私と同じ気持ちだという自信はあまりなかったけど、言った後に改めて考えると言わない方が良かったかもなんて弱気な気持ちが首を擡げる。ああ神様。できるなら数分前に戻してください。決心したはずなのに揺らぐ辺り私はほんとうにどうしようもない逃げ腰女だと自責したくなる。待てども待てども彼は返事をしない。私をじっと見るだけで何も言わない。大広間はレギュラスの返答待ちで、一言も聞き漏らすまいと挙句先生達まで結末に興味津々で聞き耳を立てている。
「ええっと、あの、好きじゃないならそう言っても」
「いいえ、好きですよ。付き合いましょう」
「わっ、私っ、全然気にしないか、って、え?」
今、彼はなんて言った? 耳が役目を放棄し自分の望む声を生み出したのでないなら、確かに彼は私のこと「すき」と言って「付き合おう」と言ったはずだ。今度は私が目を瞬かせる番だった。いや、もしかしたら驚きのあまり瞬きさえ忘れたかもしれない。彼の言葉が現実であると教えるように大広間が解き放たれた鳥たちの如くわっと騒ぎ立てた。指笛を吹くのも聞こえた。うっすらと笑みを浮かべた彼に、恐る恐る尋ねる。
「ほ、ほんと? 冗談とか、とても早いエイプリルフールの嘘とかじゃなくて?」
彼はおかしなことを言われたようにくすりと笑んだ。
「エイプリルフールの日に嫌いと言えば貴女は信じてしまうのでしょうね」
レギュラスは椅子から腰を上げ私の手を恭しく取った。何が起こっているのか理解できないまま手の甲に唇を落とされる。それは自分のじゃなくてレギュラスの。大広間がまた一段と盛況する。私を見つめる黒い瞳はめらめらと炎が燃え盛っていて、その熱に当てられてしまった自分の体は、燃やされるように熱くなる。耳まで赤いだろう自分の顔をすぐにでも隠したかったけど、体が予想以上に固まっていて、指を動かすどころか呼吸さえままならない。息って口から吸って鼻から出すんだっけ? それとも鼻から吸って口から出すんだっけ? などと思考もおかしなことを考える始末。レギュラスは、そんな私を揶揄する笑みを見せず愛おしいものを見つめるような笑みを浮かべた。思わず綻んだという笑顔だ。はっと息が詰まる。
「ぼくと付き合ってくれますか?」
その告白にもはや私の耳には周りの雑音は一切遮断された。今ここには私と彼だけが居る感じだった。底から溢れ出る嬉しさから首を何度も縦に振る。
「わたっ、私で良ければっ!よろしくお願いしますっ」
声が震えてしまうのも気に掛けずはっきりと答えた。嬉しい。とてもとても嬉しい。この嬉しさはクリスマスプレゼントを貰った時やテストでOを取れた時以上の嬉しいだ。まるでフェリックス・フェリシスを飲んだんじゃないかと疑ってしまうくらいの幸せに、笑顔なんて絶やせるはずもなかった。眦から涙が零れてしまうと同じようにふふっと小さな笑みも口から零れた。
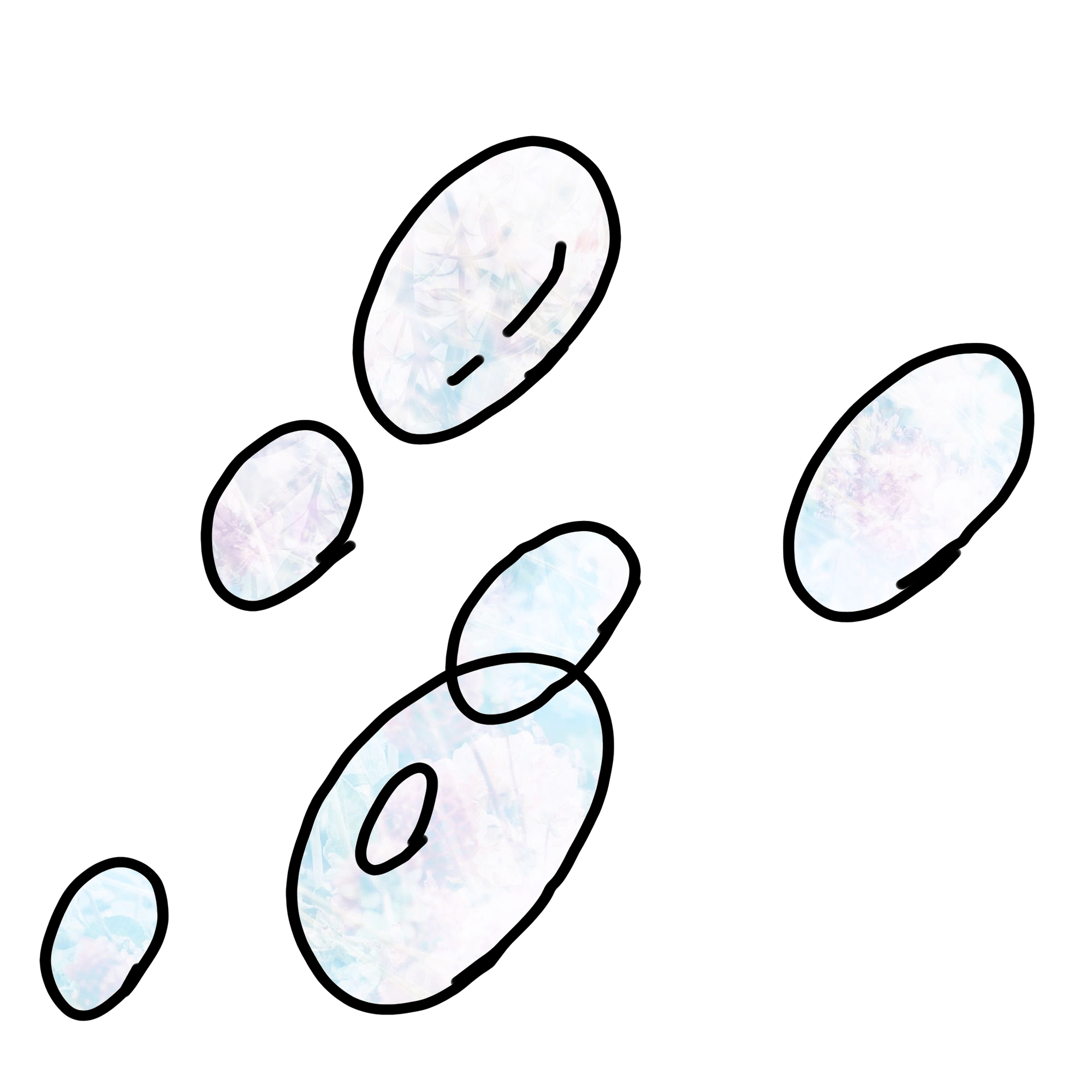
獅子の子供の小さな勇気
、