すっかり馴染んだパブは変わり映えもなく狂瀾怒濤の勢いで賑わっていて、扉を開けると共にちりんと鳴った鈴の音さえ店主の耳に届いているか怪しいくらいに周囲を呑み込む。酒の匂い、煙草の匂い、香水の匂い、料理の匂いが氾濫する渦の中を掻き分けてようやくカウンターの一角に腰を下ろすことができた。クリスマスが近いからと言って何も水を得た魚のように騒がなくてもいい気がするが、そこはそれ、そういう人柄なのだろう。店内にひしめく熱気から、マフラーを外す。
「ディメンターにでも会ったような顔してるじゃない」
「おっそろしいこと言わんでくれます? マダム」
それまで相手していた人とは切り上げたのか目の前には、カウンターテーブルに肘を突きながら私を見て柳眉に皺を寄せるマダム・ロスメルタが居た。
「外は寒かったろう。そら、飲みな」
「やったー、ありがとうございます」
差し出されたのは一杯のホットウイスキーだった。オレンジの照明がウイスキーの色を鮮やかに照らしあげる。小さなグラスを呷れば、温かくもほろ苦い味が破れた水風船のように広がった。岩のように固まる身体の芯を解かしていくようにも感じたそれに、飲み干したら自ずと吐息が零れた。ほっと胸を撫で下ろす様子を見てマダムは前のめりの姿勢を正して眉を下げて笑った。
「注文の際は呼びなさい」
短く伝えて遠くで呼ぶ別の客の元へ去っていった。テーブルに置かれた薄いメニューを取ろうかと逡巡したが、伸ばした手を丸めて置くことにした。パブに来たのはたまたまで、偶然で、ほんとうにそれだけ。別に何かを忘れんがために飲み明かそうと思ったとかじゃない。ほんとうだ。そのつもりなのに瞼の裏には苦々しい記憶ばかりがこびりついてしまって、拭うべく溜息を吐いてもそれは色を増すばかりだった。一年と経たずに告げられた破局、今となっては顔すら朧気な学友、子供のように私情ばかりを優先させる上司。何もかも上手くいかずどん詰まり状態な私。袋小路に嵌った鼠は抜け出さない限りやがて窒息死を招く。その終わりがじわじわと近づく証として、どうも息がしづらいのだ。どこへ行っても何をしても縹渺とした薄い膜が脳に張り付いてまるで生きた心地がしない。自分は何しているんだろう、そんなことを考えては底無し沼に足を浸からせるのだ。なにかひとつ、ひとつでも今の私に機転を起こしてくれれば。結局他人頼みになっているのだから失笑を通り越してもはや笑止してしまう。
「やあ、久しぶりだね」
天井の灯りをぼんやり見つめる私の肩を誰かが触れた。優しげな声に首を回せば、緩慢とした先程の自分は何処かへ、弛んでいた思考回路がけたたましい音をあげて起動再開した。目を見開いて硬直した私に構わず隣の椅子に腰掛けメニューを開く男性。ぷち、己を纏縛する縄が切れて私は口を開いた。
「会えるとは思ってもなかったよ、リーマス」
「そう? 私は会いたいと思っていたよ君に」
「奢らないよ?」
「手厳しいな」
眉を下げて笑う顔を見て長らく思い出さなかった学生時代の記憶が蘇ってきた。同じ寮で同じ学科を多数受けていた私達が交流を深めることに時間はかからなかった。甘いものが好きで、同じフレーバーティーを好み、監督生も務めた。よく思ったものだ、これはもう運命なんじゃないかと。その頃私はリーマスが好きだった。ライクじゃなくてラブの方で。だけど六年生にもなる頃にはお互い進路に追われ結局想いの丈を告げぬままそれっきりとなったのだ。その彼が今、私の隣に座ってバタービールを飲んでる。思い出の彼より幾許か老けて白髪もちらほら見える。窶れた頬の肉や継ぎ接ぎだらけのコートを愛用しているところはそのままのようだが、なんとも変な気分だ、初恋の人と酒を飲み交わすというのは。
「ホグワーツで教鞭を執っているんだってね」
「ああ、闇の魔術に対する防衛術をね」
「凄いじゃん。私あれ苦手」
「実技でBばかり取っていたのを思い出したよ」
「基礎はばっちりだったんだしOくれても良かったよね。なんだかむかっ腹が立ってきた、飲んで忘れよ」
遠くで談笑するマダムに酒の名を叫んだ。隣から慌てた制止の声が聞こえてきたが、この際無視して飲んでやろう。当初の気持ちなど霧散した私が酒を呷る手を休めるわけもなく、酒豪とさえ称えられた私はあっという間にふたつの樽を空にした。それでもペースを崩さない私に、リーマスが目を丸くして呟く。
「肝臓だけハグリットと交換したのかい」
「元々強いんだよね。リーマスは飲まないの?」
「飲んでるとも。バタービールをね」
「甘党め」
「お互い様さ」
踏み込まず突き放さずな関係が酒のペースを早める。からん、とグラスの中に浮かぶ氷が壁を鳴らす。オレンジ色の液体を眺めていれば視界は少しづつうっすらとぼやけてきて、伴うように店内に響く声が現実離れしていき鼓膜から離れていく。リーマスは今何してるんだろう。仕事じゃなくてプライベートの方。結婚してるのかな、恋人居たりするのかな。手元写す視線を気だるけに横へずらしてテーブルに浮かれた大きな手のひらを見る。血管が浮き出たそれは、手入れされてない爪だなとか皺が多いなとか、そういうことを伝えるけど肝心のそれは形もない。あるべき場所に輝くそれはなくて、それが重い蓋に針の穴のような隙間を与えた。見つめすぎていたからだろうか、ゆくりなく彼に「大丈夫?」と声をかけられる。手から視線がそそくさと逃げた。
「平気」
「ほんとうかい? 意識飛んでるように見えるんだけど」
「大丈夫だよ」
呆れるような表情して心配するものだから、それが嬉しくて笑ってしまった。顰蹙を買ったことは言うまでもないだろう。その表情さえ私の中の何かを掻き立てて、とっくに本能は手中から抜け出していた。心臓から吐き出される血液が乱暴に、そして本能に呑まれた獣のように私のあちらこちらを刺激して熱くさせる。冷たい酒なんかじゃ到底絆されない熱量だ。何を言うでもなく酒を飲むでもない私の様子に、「大丈夫」の本人の言葉なんて腑に落ちないようだ。好物のバタービールが入ったジョッキをテーブルに片付けて私の肩に手を置く。
「それくらいにしておかないと君」
「ごめん」
緑の厳しい眼差しが滑り込んで私を捕らえる。自分の言葉も言い終わらぬうちに私は口を開いた。優しい、君はいつまでも、いつも優しい。言葉も気遣いもその眼差しも。どんな治癒呪文を使ったか詰問したいくらい彼は優しかった。優しい優しいリーマスなら受け入れてくれるんじゃないかって、胸の奥底に閉じ込めた欲が溢れ出た。継ぎ接ぎだらけのコートの裾をちょい、と引く。
「酔ったみたい」
どうか拒まないで。どうか受け入れて。一時でいいから。情けなく縋り付く私の瞳を見た緑に、揺れる波を見つけた。
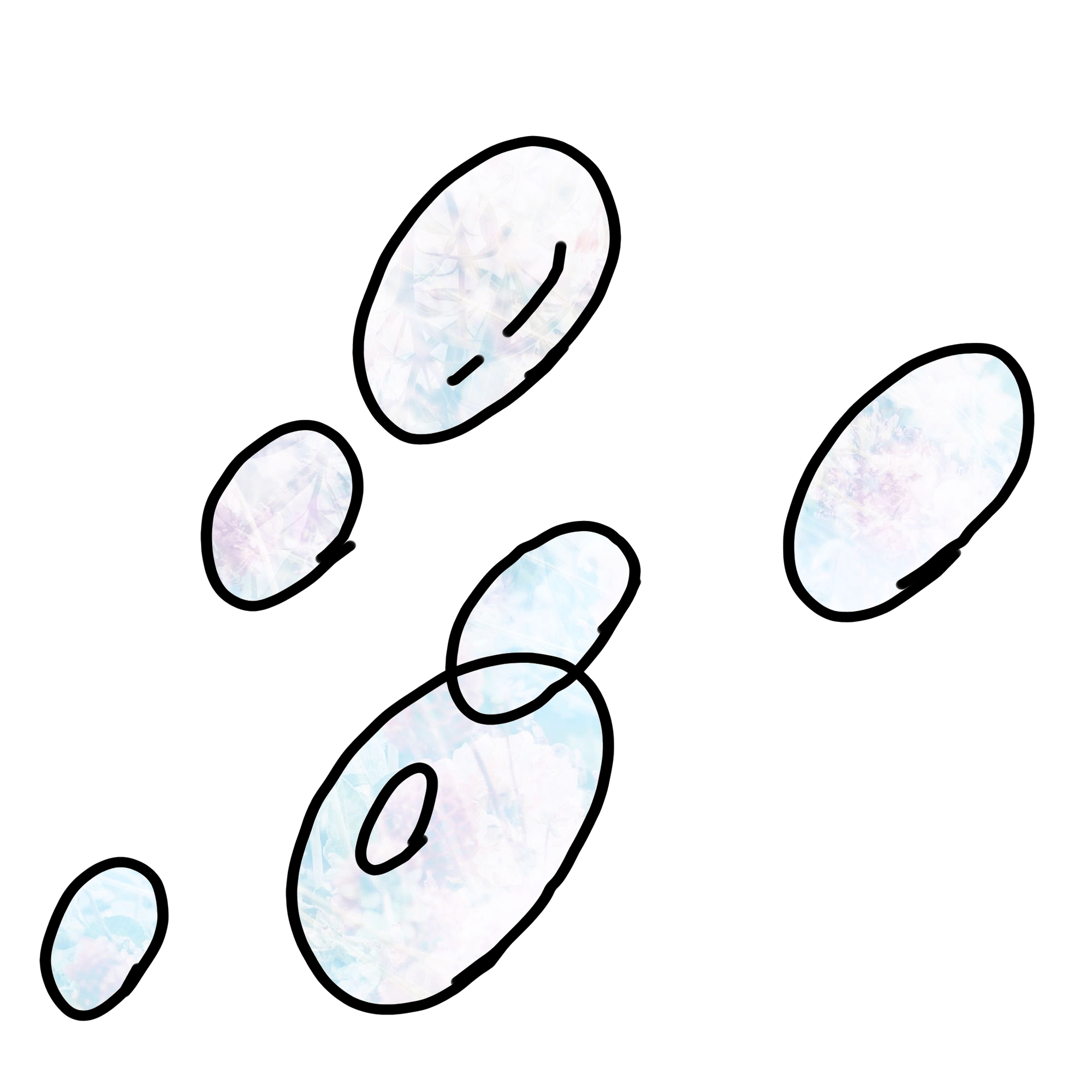
朧気
、