私の友人はよく初恋は実らないと言った。それの起因は知らないけど、あながち間違っていないと思う。初恋は実らない。私の場合は、彼と出会うのが遅過ぎたのかもしれない。それを何度悔いたことか。でも、時間を巻き戻すことは決してできないのだ。
「スネイプ、今日の授業解った?」
「お前は解らなかったのか?」
「ちょっとね」
「先生の話を聞いていたら簡単に理解できることだろ。どこの部分だ? 教えてやる」
「ありがとう。えーっとね」
中庭で本を読む私と同級生のスネイプ。誰が噂したか知らないけど、ねっとり髪と言われている黒髪は実はさらさらで、スネイプはへどろ臭いだのドブ臭いだの言われていた事実は全く違っていて、いつも薬ばかり作っているからか、薬草の匂いがする。これら全部彼と関わって初めて知ったことだ。その髪が、彼が顔を俯かせればさらりと頬にかかる。肩がくっ付いた今の体勢なら髪は私の頬にも触れる。さっきからちょっとばかしくすぐったい。
「聞いてないだろ」
薬草の匂いがするなぁ、なんて現抜かしていたらぴしゃりと言い当てられてしまった。はっと我に返った私は急いで「聞いてる聞いてる」と付け加える。危ない危ない。スネイプの匂いに酔っていましたなんて知られたら、もう一緒に居られない。彼の口から低い声でさっきの授業の内容を丁寧に解説される。つくづく思うのだが彼は教師に向いている。勉強に疎い私でさえも理解出来るのだから、彼の将来の教師の隻腕に全員があっと驚くことだろう。もし彼がホグワーツで働くことになったら、それこそ鼻が高いというものだ。
「そっか。なるほど」
「全く。なんでこれくらいもできないんだ」
「スネイプほど頭が良くないからだよ」
「単純なことしか言っていない」
「それを理解できるスネイプは凄い子だね」
「子供扱いするな」
教師としての腕は確かでも、嫌味連発してそうだから生徒からの人気は無さそう。くすくす笑っていると、そこへ別の声が混じってきた。
「二人は相変わらず仲が良いわね」
鈴を転がすような可愛らしい声。私の心は有頂天になっていたさっきと比べて一瞬で枯れていった。熱した鉄に冷水をかけたような気持ちだ。揺れる赤髪は花の香りを漂わせてスネイプの隣に腰を下ろす。にこにこと微笑む彼女が私は好きでもあり、苦手でもあった。
「リリー」
「なんの話をしていたの?」
「こいつが魔法薬学が全然できないっていう話をしていた」
「でも箒の練習や変身術では軽々とこなしていたわよ。誰だって向き不向きはあるわ」
「甘やかすなリリー」
「セブだってできない教科もあるじゃない」
「それは」
さっきまでの空気から一転し、私は瞬く間に居ない者になった。スネイプもリリーも互いの顔を見て話に花を咲かせている。彼は私に教えていた本をリリーに向け、次の薬草はこれだ、とかこれはこの効き目があるだとか丁寧に教えている。私はこの時間が惨めで仕方なかった。突き放される空間が心を萎れされていく。水を得た花はその間は咲き誇るが、水を得なくなると一気に萎れていく。まさにそれだった。スネイプはリリーが好きで、私はスネイプが好き。友人関係に見えて実は三角関係。
もちろんリリーもスネイプも私の気持ちは知らない。教えてないし悟られないよう心配りしてきた。スネイプは自分ではバレていないと思っているようだが、傍から見れば丸出し同然だ。彼はリリーを好いている。それどころか、その気持ちは愛しているにも似ているだろう。だからこそ、私に勝ち目などさらさらないのだ。彼は彼女しか見ていない。私が消えても、彼はリリーしか見てないからもしかしたら消えたことにも気付かないかもしれない。何十本の針に刺される痛みが心に奔る。
「あっ」
「どうかした?」
「私次フリットウィック先生の授業だった」
「残念。私はスプラウト先生の授業だわ。確かセブルスもそうよね?」
「ああ」
「じゃあまた夕飯時に」
「ええ。頑張ってね」
「うん」
「せいぜいヘマをしないようにな」
「しないよっ」
できるだけ傷を見せないように、笑ってその場所を離れた。これ以上あそこに居たらぼろを出しかねないからだ。去り際後ろを少し振り返ってみると、やはり二人は話しに夢中だった。くすくすと笑うリリーとそれを見て頬を微かに綻ばせるスネイプ。慣れた光景なのに酷く心が傷んだ。やはり私では適わない。私が「スネイプ」と呼ぶ時の顔は不機嫌顔か、ああ居たのかという顔。だけどリリーが「セブ」と呼べば瞬く間に嬉しそうに頬を染め声のトーンがひとつふたつ上がる。
見えない花を舞い散らせるオーラをまとうスネイプを見れば、いよいよ諦めるしかない。だけど諦めがつかないのはリリーがジェームズに言い寄られているから。万が一リリーがジェームズを選べば、私にもチャンスが訪れるかもしれない。そんな無に近い期待を捨てきれない。我ながらバカバカしいと思う。あれほど明らかに対応が違うのに、リリーがジェームズを選んでも私を見てくれるとは限らないのに、それでもと僅かな期待を捨てられないのだから。
「惨めだなぁ」
誰も居ない川辺の畔で呟いた言葉が空気に掻き消された。授業なんてない。ほんとうは、ただあの場所から逃れるための口実に過ぎない。何十もの溜息が零れても気持ちは全く零れないのだから、自分でも偉いと思う。万が一にでもバレてスネイプの友人さえできなくなったら、それこそ私は泣き喚いてしまうかもしれない。諦め半分と期待わずかな心境で、私は一体これからどう彼を振り向かせればいいのだろう。リリーという強敵を目の前に、私は彼に自分の武器をどう見せつければいいのだろう。美人で優しく度胸のあるリリーと、彼女と同じ寮のくせに気持ちひとつ伝えられる度胸もなく、勉強もさしてできない上に、顔立ちも平々凡々な私。比べるまでもなくどう考えてもスネイプはリリーに転ぶだろう。私は彼女に勝る武器をひとつも所有していないのだから。
「でも好きなんだよなぁ。スネイプが」
ホグワーツに入ってから彼と話し始めたが、好きになることに時間はかからなかった。話す前から、スネイプとリリーの関係は気付いていたので最初こそは彼は邪魔するなと言わんばかりの目力で睨んでいたが、次第に私が話しかけても睨まなくなった。今は彼の方から話しかけて来る時もある。ごく稀にだが。だけどその程度だ。リリー以上に、私はなれない。彼が彼女に見せる表情は、私では見せられない。だからこそ諦めなきゃいけないのに。頭では解っている。だけど心ははいそうですかと頷いてくれない。話すたび会うたび気持ちは膨れていくばかり。バレちゃいけないのに心ははち切れそうなくらい好きという気持ちでパンパンだ。
「あーもーやだ」
「何が嫌なんだよ」
「そりゃあす、ってシリウス・ブラック!?」
「気付くの遅せぇ」
背後から掛けられた声に振り返れば、そこには制服を着崩したシリウス・ブラックが木にもたれかかって立っていた。相変わらずだらしない恰好だ。なんで女子は、顔色を伺わなければならない相手を好きなんだろう。
「口に出てる。失礼な奴だな」
「スネイプを虐める人とは話したくない」
「お前もエバンズも悪趣味だな。あんな根暗のスニベルスを好きとは」
「スネイプは優しい子だよ。シリウス・ブラックとは違ってね。だいたい何したって彼を虐めるの? スネイプは君達に何もしてないじゃない」
私はスネイプを虐める彼らが大嫌いだった。黒髪で灰色の目が特徴的のシリウス・ブラック、くしゃくしゃした髪と丸眼鏡が特徴的のジェームズ・ポッター、そして明るい茶髪と緑色の瞳に、顔にある傷が特徴的のリーマス・ルーピン。悪戯仕掛け人と名高いグリフィンドールの彼らは事ある事に、それどころか視界に入るだけでスネイプに攻撃呪文をかけて虐めている。スネイプは何もしていないのに。そう言えばシリウス・ブラックは眉間に皺を寄せた。今にでも私に突っかかってきそうなくらい険悪な表情だ。
「目に入るだけで鬱陶しいんだよ、あいつ」
「は、なにそれ。じゃあ君達は単に嫌いだからという理由であんなに傷つけるわけ? 最っ低」
腹の底から殺意に似た怒りがふつふつと込み上げてくる。シリウス・ブラックはそれを気にする様子もなくいつもどおり澄ました顔で言い返してくると思いきや、
「あっそ。だからなんだよ」
つんと冷たい声で短く言うだけだった。それが私には少し意外で、ぽかんとしてしまった。彼がスネイプを虐める時私が何言ってもすぐ言い返してくるのに、今の彼はそれだけだった。
「お前にどうこう言われても俺は変えるつもりなんかねぇよ。嫌いな奴は嫌いな奴。だいたいお前は虐めるっていうけど、俺らからしたらちょっとばかし遊んでるだけだ」
「遊んでる? 人前で木に吊るして下着を晒すのが遊びだって言うの? シリウス・ブラックってスリザリンでは血を裏切る者って言われるけど、何も裏切ってないよ。シリウス・ブラックはグリフィンドールよりスリザリンの方がお似合いだよ」
「んだよそれ。どういう意味だ!」
キレたシリウス・ブラックは私の胸倉を片手で掴み、ぐっと持ち上げた。地面から数メートル浮いたけど頭に血が上った状態では、自分の置かれている立場など鑑みる余裕なんてなかった。彼の灰色の目に眦を吊り上げた険しい顔の自分が映る。同時に私の視界に同様の彼の顔が映った。犬が威嚇する時と同じ顔だ。雄々しく、獣のような殺気を放っている。気弱な子だったら一髪で気絶しているだろう。シリウス・ブラックはスネイプを守ろうとする奴はたとえ同寮生であっても遠慮なく攻撃してくる。
「そのままだよ。君の忌み嫌うスリザリンが根暗でインチキで卑怯者だというなら、シリウス・ブラックは間違いなくスリザリンだよ!勇敢?騎士道?はっ、どこがそうなの?嫌いだから、見ててムカつくから、そんな理由で人を虐める奴のどこが勇敢なの!?」
「女二人に守られるような弱ぇ奴が悪いんだよ!」
「スネイプは弱くないっ、優しくていい子だよ!」
「はっ、気持ち悪ぃな。あれか? お前、あのスニベリーのこと好きなのか?」
「友人として好きだよ」
だけどシリウス・ブラックはにぃっと口角を歪めるだけだった。
「どうだか。スニベリーにいいとこなんかねぇけど、お前は惚れてる。ああでも残念だったな、あいつはエバンズしか見えてねーよ」
鼻っ柱で笑われて泣きたい痛みに襲われた。だからって彼の前で泣くようなことはしたくない。
「知ってるよ、それくらい」
ぱしっと掴まれた手を振り払う。地面に足が付くと私は彼を静かに睨んだ。
「だったら何? スネイプが誰を好きになろうがどうでもいいよ。私は友人としてその助けはするつもり」
私はシリウス・ブラックに背中を向けてその場を走り去った。こんな惨めな表情、彼だけには見せたくなかったから。走って走って、胸が痛むくらい全速力で。彼が言ったとおりスネイプにはリリーしか見えていない。
「充分に解ってるよっ」
私に勝ち目がないことなんて。だけどそれをシリウス・ブラックに言われるのはとても悔しかった。眦に滲み出るそれを流すまいと下唇を噛んで顎を引いた。廊下は幸いなことに教室を移動する生徒でごった返していたので、人混みに紛れることができるし誰も私を見ない。きっと涙を流したって誰も気付かない。私は居ないも同然なのだから。
そう思っていたのに。
「次はフリットウィック先生の授業じゃないのか?」
その声が私の心臓に大きく波を立たせた。錆びたネジよろしくゆっくり顔を上げるとそこには教科書を抱えたスネイプが居た。隣にリリーは居なくて、首を傾げる私にスネイプは「リリーなら先に温室へ向かった」と補足する。
「どうした、顔色が随分悪い」
心配そうな顔で見下ろすスネイプ。ああ、嫌だ嫌だ。こんな顔見られたくない。
「ちょっと日に当たりすぎただけだよ。それで気持ち悪いのかも。少し休めば治るから医務室に行ってくるね」
努めて平静な声を取り繕い、去ろうとして彼の横を通り過ぎたら、手首を掴まれた。びっくりして彼の方を見る。
「嘘だな。フリットウィック先生の教室は日が当たりすぎるような場所じゃない。何かされたのか?」
スネイプはこういう時は嫌になるほど鋭い。私の気持ちには露も気付かないのに。私はこれ以上惨めな姿を見せたくなくて笑って誤魔化した。
「されるようなことしてないよ。心配してくれてありがとう。でも大丈夫だよ、医務室に行くから」
「では何故医務室と真逆の方向に行っているんだ。それにフリットウィック先生の教室からも逆の方から来たな? お前、授業があるなんて嘘だろ。何が遭った?」
嘘は見抜けるのに吐く理由まで解らないんだね。
「大丈夫だよ、ほんとに。うん、心配しないで」
これ以上優しくしないで。気持ちがこれ以上大きくなったら零れてしまうかもしれないから。私は君を諦めたいと思ってる。だから、そんな心配そうな目で見ないで。傷付いたような目で見ないで。
「僕じゃ話せないことか?」
「スネイプが悪いんじゃないよ。ただ言いたくないの」
「はっきり言えばいいだろ。お前には言いたくないって!」
「スネイプだけじゃない、誰にも言いたくないことなの!」
「そうか」
ぱっと離れる彼の手首。掴まれたところには、まだスネイプの薄い熱が残っている。彼は顔を背けて、
「じゃあな」
と冷めた瞳で冷たく言った。待って、と言う暇もなく彼は人混みの中に消えてしまった。
「スネイプ!」
声を上げても返ってくるのは人の視線だけで、一番返って欲しい人の姿はなかった。人の波の中でいくら視線を右往左往させてもあの黒い髪と緑のマフラーは見つからなかった。廊下先まで走っても、そこには彼の姿はなかった。その事実に自分は取り返しのつかないことをしたんじゃないかと心臓が冷えた。
「どうしよう」
嫌われたらどうしよう。友人とさえ思われなかったらどうしよう。もう縁を切りたいと思われたらどうしよう。そんな言葉がぐるぐると頭の中で渦を巻いて心臓の鼓動を速くさせる。熱い血がどくどくと全身に駆け巡る音が嫌に大きく聞こえた。周りの雑多なんて耳に入ってこない。頭がガンガンする。ああっ、どうしようっ!私はなんてことをっ。下唇を噛んで流さないようにしていた涙が、堰を切ったように溢れ出した。指でいくら拭ってもそれは勢いを増すばかりで一向に引く気配を見せない。大粒の涙を流す私にぎょっとして周りが視線を送ってくるのを感じて顔を両手で覆い隠して、その場を走り去った。そしてやって来たのは誰も居ない禁じられた森の中だった。とは言っても奥深くまで来たんじゃないので、すぐに戻れる。
だけどその姿を誰かに見られれば間違いなく厳しい罰則をマクゴナガル先生から言い渡される。私の背中よりも広い木の幹に背中を預けて膝頭を抱え込んでふとももに顔を埋めた。止めるようにふとももに強く顔を押し当てるけど、涙は止まる気配を見せない。つう、と垂れて地面にぽたりと落ちる。嫌われてしまったかもしれない。嫌われないように細心の注意を払って彼と接してきたのに、今ので嫌われてしまったかもしれない。彼はリリーしか目に入ってないから、嫌われたら一生嫌われたままかもしれない。そう考えたらいっそう涙の勢いは増した。
「嫌だよっ、嫌われたくないっ」
好きな人に嫌われたいなんて思わない。振り向かずとも友人として付き合いたかったのに。もしかしたらそれすらも適わないかもしれない。「初恋は実らない」という、その言葉がふと浮かんだ。日本に居た頃、友人がよく口にしていた。私はその言葉が嫌いだった。だって初恋が必ずしも実らないとは限らない。実るかもしれない。そう思っていたのに、現実がこれだ。あの時、間違ってるなんて言った自分に今の自分を見せてやりたいくらい。こんなに想っても彼はそのひとつまみも気付かない上に友人関係も脆く崩れ落ちてしまうかもしれない。ああ、恋愛ってとても苦しい。
「なに泣いてんだよ」
声が降りかかると同時に頭が重くなって更に沈んだ。ばっと顔を上げてみたらそれはシリウス・ブラックだった。次はどんな嫌味を言いに来たのかと思いムスッとするが、彼の表情をよく見たら心無しかバツの悪そうな顔をしているように見えた。勘違いじゃないといいけど、あいにく彼の嫌味に付き合ってあげる精神状態ではない。それに大嫌いな人にこんな姿を見られたのも癪だ。
「なんでもないよ」
ごしごしと目元を荒く拭いた。涙はすっかり引いている。ほんと、こういう時はすんなり言うことを聞くのに聞いて欲しい時には反するよね。自分の体ながら恨めしい。
「可愛くねえ奴。ほんとなんで」
「可愛くなくていいよ。後半聞こえないんだけど、なんか言った?」
「あー、うっせ!なんでもねぇよバカ!」
「なんなの急に」
シリウス・ブラックはいつも変だが今はもっと変。鬱陶しそうに首元まで伸びた黒髪を掻き回すと、私の隣にどかっと腰を下ろした。え、なんなの、ほんとに。胡座をかく彼と少し離れる。
「言っておくが俺は謝らねーからな。俺はスニベリーが嫌いだし」
「好きにすればいいよ。君がスネイプを傷付けるなら、私はそのたびに君に反撃するから」
気分がますます悪くなった。胸くそ悪いと思いながら立とうとすると、シリウス・ブラックに手首をぐっと強く掴まれ行動を制された。若干海老反りな体勢で止まる。恨めしく彼を見下ろすと、シリウス・ブラックは俯いたまま言った。
「んでだよ」
「なに? 聞こえない」
「なんでスニベリーなんだよ」
「は」
驚き以上に驚いて言葉が出なかった。彼はばっと顔を上げ私を見遣る。その瞳に息さえ呑んでしまった。彼が喧嘩を売る時と同じような苛烈の炎が瞳の奥で揺らめいているのが見えた。ひしひしと伝わる彼の熱烈な想い。掴んだ彼の手が力をさらに込める。痛みに顔を歪めた。
「痛いっ」
そう言っても彼は離そうとしない。
「俺にしろよ。あいつじゃなくて」
「言ってること、理解してる? それじゃあ君が私のこと好きみたいだよ」
「ああ、好きだ。お前が好きだ。だからあいつなんて止めて俺にしろ」
「なっ」
なんという告白だろう。私を射抜く瞳に迷いも動揺もない。真っ直ぐに、純粋なまでの気持ちを視線と言葉に乗せて私に送ってくる。逸らすことも許されない空間で、固唾を呑み込んだ。たっぷり一分間私は言葉を発せなかった。彼が私を好きという事実はそう簡単に飲み込めるものじゃないけど、それよりシリウス・ブラック雰囲気に圧倒されて私自身どう返せばいいか解らなかった。だけど全身を振り絞って声を出す。
「ごめんなさい。私、スネイプが好きなの」
バレてるならもうそれでいい。何かの罰ゲームだとして、私の好きな人を広めたいならそれでも構わない。私の好きな人はスネイプ以外にない。それでたとえどれほど泣くことになっても。ふっと笑みが零れた。
「自分でも解ってる、勝ち目がないのは。だけど好きなの。諦めようとしても諦められない。だからごめんなさい。君の気持ちには応えられない」
諦めるって言っておきながらその機会を自分で潰すから、もしかしたらこの先一生諦められないかもしれない。
「それにスネイプを虐める人とは友人関係すら築きたくないよ」
それは頑として譲れないところだった。どんな人でも彼を傷付ける人は許せない。ましてや彼のように単純に嫌いという理由であるなら尚更。
「じゃあ俺があいつを虐めるのを止めたらお前は振り向いてくれるのか?」
「え?」
「お前があいつを好きなように俺もお前が好きだ。だからこそいつも泣いてるお前を放っておけねぇし、そんな顔をさせるあいつが許せない。だが、お前が振り向いてくれんなら俺はあいつを虐めない」
「本気なの?」
「ああ」
どうしよう。スネイプのことを考えればここで「うん」と言うのがベストなんだろうけど、私に彼を好きになる自信はない。こんなにスネイプが好きな気持ちを、彼に向けられるかどうか。迷っていたら手首を強く引かれ油断した私の体は簡単に彼の懐の中へ入ってしまった。見上げる形で横になって彼の胡座の中へはまってしまった私は、彼の顔が近くにあることにどきりとした。上半身を丸めて見下ろす彼の髪が、ふさりと私の頬にかかる。感じたくすぐったさに目を眇めた。
「俺なら泣かせない」
「そんなこと言ったって」
「今すぐ好きになれとは言わねぇよ。そのうち好きになればいい」
「好きにならないかも、しれないよ」
「好きになる。好きにさせる」
「どこからそんな自信が出てくるの」
思わずくすりと笑みが零れた。
「スネイプが好きだし、もし君が彼を傷付ける真似をすれば私はまっさきに彼を助けに行く。彼が疑われることがあれば私は彼を信じる。彼が死にそうになっていたら、私は自分の命なんて顧みずに助けに行くよ。私はそれくらいスネイプが好きなの。君とスネイプどちらか選べって言われたら、私はスネイプを取る。悪いけど君を信用することは、まだできない。君は、それでも私を好きにさせる自信があるの? そのつもりはあるの?」
昨日今日で手のひらを返すほど、私は甘くない。いくら好きと言われたからって、好きな人を傷付けるなら私は迷わず杖を向ける。私はまだシリウス・ブラックを一人の人間として好きでは居ないのだ。その言葉に彼は傷付いた色を見せたが、それもすぐに消えて真剣に私の瞳を見つめ返した。
「ああ。お前がいくらあいつを好きと言っても、信じると言っても、俺はお前を振り向かせる。好きにさせる。それに言っただろ、もう虐めねぇって。あいつがしてきたら別だけどな」
「ちょっと」
「でも俺からはもうしねぇよ。絶対に。だから信じろとは言わない、だが信用させる気概はある」
彼の真っ直ぐな瞳は嘘偽り混じりっけのない純粋な気持ちだけを帯びていた。私はまだ彼を信用できるか解らない。好きになるのかも。だけど、彼の言葉が嘘でないなら、その言葉を少しは信じてみようという気になれるかもしれない。荒れ果てた心にお湯が注ぎ込まれるような気持ちだ。
「うん、解った」
その日の夜、リリーに諭されたスネイプが謝りに来た。仲を取り戻した喜びに跳ねたら、シリウス・ブラックに睨まれた。次の日からシリウス・ブラックはスネイプを見かけたら舌打ちやガンを飛ばすことはあっても、決して杖を振るうことはしなくなった。それが私の前であってもなくても。約束の日に私の手のひらにキスをした彼の唇にキスをする日はまだ遠い先の話になる。
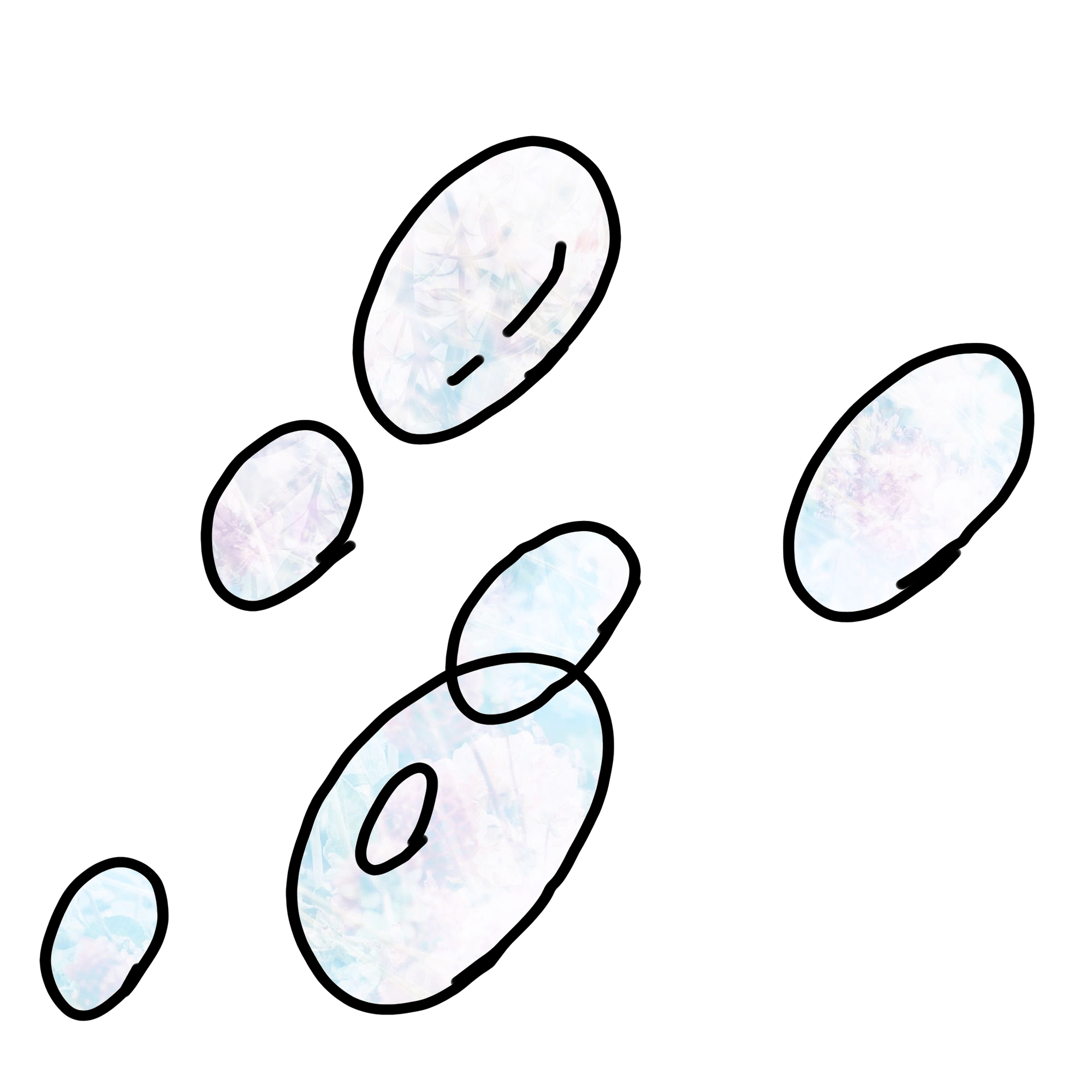
初恋より次の恋
、