「ルーピン先生っ」
昼食後の教室に私の声が響いた。その教室は闇の魔法の防衛術に対する教室であり、当然ながら教師は一人しか居ない。名前の主は反応するように振り向いた。白髪混じりの明るい茶色の髪が、窓から射し込んだ太陽の光に照らされる。彼の表情と一緒で瞳も明るい緑色だ。優しそうな顔には似つかわしくない痛々しい傷跡が頬から輪郭にかけて裂かれたかのように伸びている。
「やぁ。どうしたんだい?」
ふんわりとした物言いも、生徒からの人気のひとつだ。だけど彼は優しいだけではなく時に怖い。怒らせたら、怒鳴ったり無視したり手を出したりはしない。そういう恐怖ではない。彼は父のように言葉で諭すのだ。それを以前イタズラした生徒にしていたのを、見かけたことがある。
「授業で解らないところがあって。今、大丈夫ですか?」
意識せずともおずおずとした物腰になってしまうのは、相手が先生だからとか男性だからとか怖いからではない。むしろそう言った負の感情とは真逆の感情を持っている。決して口にすることの許されない感情。バレなければ墓まで持っていくほどの。
「勿論だよ。ちょっと待ってて。紅茶を淹れるから」
「はい」
教員室に招き入れると、椅子に座らせ先生はそそくさと紅茶の準備をした。なんのデザインもない至ってシンプルのティーカップは、紅茶を淹れる容器というよりかはコーヒーを飲むそれに近い形状をしている。薄い緑色の液体を注ぎ込む。それは温かいようで、ほくほくと白い湯気を立てている。漂ってくるのは嗅いだこともない葉っぱの香りだ。なんの紅茶だろう? と首を傾げると、先生が得意げに教えてくれた。
「『リョクチャ』と言うんだよ。ジャポンで愛される茶葉を使った飲み物なんだ。飲んでみて」
ささ、と薦めるルーピン先生を見て、可愛いなと思いつつカップの取手に指を絡ませる。持ち上げて口に近付けると、白い湯気と共に茶葉の少し苦い香りがいっそう漂ってきた。恐る恐る一口嚥下してみる。すると、
「美味しい!」
それは取り繕った意見ではなく、心から零れた素直な気持ちだった。日本の緑茶はただ温かいというわけではなく、体の芯から温まっていき、そして指先、爪先までその温かさがゆっくり広がっていく感覚を味わえる飲み物だった。ぱっと明るくなった私の顔を見て、ルーピン先生もぱっと華やかな笑顔を浮かべる。嬉しそうにはにかむ彼の目元にいくつもの皺ができるが、それすらも子供の笑顔のように可愛らしいと思える。私は、この先生が好きだ。ここでいう好きは、先生として好きだとか人間として好きではなく、一人の男性としての純粋な好意を指す。生徒が教師を好きになってはいけないことは重々承知だが、それでも私はルーピン先生を好きになってしまったのだ。
「それは良かった。緑茶に合うお菓子もあるから食べて」
「いいんですか? 先生が食べたいから買ったんじゃないんですか?」
先生が甘党なのは周知の事実だ。先生は子供のように笑って。
「一口くれたら嬉しいな」
ああ、やっぱり好きだな。そんなふうに笑うところも。全てが、好きだ。好きで好きでどうしようもないくらい。だけどこの気持ちは言ってはいけない。彼は教師で私はその生徒。それ以上に、彼は私を見てくれるような人じゃない。だって彼に振り向いてもらえるような要素は、ひとつだって持っていないんだもの。ルーピン先生との接点は、彼の受講する闇の魔法の防衛術と、解らないところの教えを乞う時間だけ。彼に覚えていてもらうのも、その時間だけだ。宥めるたびにそう言って自分に言い聞かせるけど、そのたびに心が締め付けられる痛みに襲われる。一生気付いてもらえない気持ちと、彼に気付かれないような自分が、とても情けない上にとても悲しかった。私が卒業してしまえば、それこそ接点がなくなるのだから気持ちはここに置いていくしかない。解っているけど、辛いのだ。
「なにか、あったのかい?」
顔を覗いてくるルーピン先生が視界に入って、我に返った。心配するように眉を下げるルーピン先生。私は急いで「大丈夫です」と理由を取り繕った。
「なんでもないです」
「勉強熱心なのはいいけど、自分が傷ついている時まで叱咤して奮い立たせてしまえば、泣くタイミングを失ってしまうよ」
よしよしと頭を撫でてくれた。崩れ落ちた心の一欠片を掬ってくれた気持ちになってしまい、みるみる視界が歪んでしまう。ルーピン先生もそれに気付いたようで、慌てて拭う私の指を取った。
「良いアドバイスができるかどうか、私には解らないかもしれないけど、もし君がそれでもと思ったら私に話して欲しい」
「ルーピン先生……」
「ボガードに変な格好をさせるのも手だよ」
「なんですかそれ」
ふふと笑みが零れた。悟られてはいけないけが、話してみようかと、ふとそう思った。
「私、好きな人が居るんです」
「うん」
「だけど好きになってはいけない人で。だからいつもバレないように必死に押し隠してるんですけど、でもどうしても好きなんです。諦めないといけないのも解ってるんです。先生は、好きな人を諦める呪文は知ってますか?」
ルーピン先生はしばらく考える素振りを見せて、口を開いた。
「私自身恋愛の経験は疎くてね。こういう時は、恋愛経験豊富な人がいいのかもしれないけど、少なくとも私は諦める必要はないと思うよ。この世の中に好きになってはいけない人なんて、居ないんだからね」
「でもその人が、自分とは全く釣り合わない人なら? 凄い遠い場所に居て、手を伸ばしても届かない場所に居る人なら? 先生はそれでも諦めるなと言うんですか?」
「釣り合わないのなら釣り合うように頑張ればいい。何が釣り合わないか、君は解っているんだろう? 頑張れば全てが報われるとまでは言わないけど、何もせずただ好きなままで指を銜えて見ているよりかは、いいんじゃないかな」
ルーピン先生は私の好きな人は知らない。だから言える言葉なんだろう。解っているけど、それでも少し希望が見えてしまうのは、好きな人自身がそう言っているからだろう。信じてはいけない言葉と解っていながらも。何やってるんだろう私。好きな人に好きな人のこと相談しても自分が期待するようなことは起こらない。なんか、惨めだなぁ。泣きたいような、笑いたいような気持ちになった。大人の女性ってこういう時どうするんだろう。いやまず、大人なら構わずアタックするよね。しない理由がないんだもの。
「ありがとうございます。ルーピン先生のおかげで少し気が楽になりました」
両手で包み込んでいたカップをテーブルに置く。差し出されたお茶菓子は手付かずのままだ。ラズベリーレッドみたいなベールに包まれた柔らかそうなお菓子だ。何で作ったのだろう?
「ほんとうにそう思ってる?」
「え?」
「私が相手で気が楽になった、心からの言葉ではないだろう?」
「そんなことは」
ない、と言い切りたかった。だけど言葉が続かない。気が楽になったとか、思ってない。ただこれ以上彼に相談しても惨めな思いをするだけだと思った。だから話を終えたかったんだ。だって、そうじゃない。相談してもどうせ現状は変わらない。変えられないのだったら、これ以上好きな人に応援もされたくないし、なにより少しでも期待したくないのが本心だ。そんなはずはない、と何度言い聞かせても、ほんの少しだけ「ほんとうは先生は私の好きな人を知っていて、その上で応援してるんじゃないか」と、そう期待してしまう。それが嫌だ。勘違いして取り返しのつかないことをしたくない。先生に好印象を持たれている生徒という関係を崩したくない。だからこそ、ここで終止符を打たなければ。そう思って話を変えようとした。
「いいんだよ、話し相手としては物足りないと言ってくれても。自分自身解っているんだ、恋愛未経験の人が言う言葉なんてたかが知れてるってことは」
「違うんですっ」
自虐的な笑みを見せつけられて我慢ならなかった。急に声を荒らげた私に、先生はきょとんとしている。そんな顔でさえ好きな私はもはや重症なのかもしれない。
「決して不十分とか物足りないとかそんなことを思ったわけじゃありません! ただ、これ以上口にすることのない気持ちについて話を広げるのも虚しいな、って思ったんです。だって、私ではその人に不十分すぎるって痛いほど解ってるんですから」
ふっと笑みが零れた。先生の淹れてくれたお茶を飲む。ああ、美味しい。ほんとうにこのお茶は温かい。ぬるま湯になっても、お茶は余す所なく体の至るところまで浸透していき、じんわりと熱を与えてくれる。体を温めてくれると同時に、悲鳴をあげるまで締め付けた心の楔を容易く引き裂いて自由にさせてくれる味だ。泣きたい時に泣かせてくれる、柔らかく温かな手に頭を撫でられている感じだ。だからこそこのお茶は今飲むべきものじゃないと、その感覚を覚えて瞬時に悟った。だって、このお茶を飲んだせいで涙が溢れそうなんだもの。泣き顔を晒して困らせたくないのにな。
「すみません、次の授業があるのでもう行きます」
あれだけ一緒に居たいと思ったこの空間でも、今は一秒でも早く逃れたい気持ちでいっぱいだった。空になったカップを置いて席を立つ。先生も、心ここに在らずといった様子だったが、私が動いたことによってはっと我に返った。
「そうだね。次は何だい?」
「薬草学です」
「スプラウト先生か。なら急いだ方がいい。今日は温室で授業するのではなく、教室ですると言っていたからね」
「そうなんですか?」
「ああ。三階の東棟に、雨傘を差したカエルの絵があるだろう?その奥にある部屋だ。急げば間に合う」
「あ、はい。ありがとうございます!」
「うん、気にしないで」
教科書を持って先生の部屋を出る。さっきまで人一人居なかったのに、今ではちらほら廊下に人の影が見えた。走ってるあたり移動教室なんだろう。なんて感心してる場合じゃなかった。私も急がないと。スプラウト先生は優しいけど遅刻したりすると容赦なく減点してくる。寮の点数を落とすようなことをしちゃったら、後から上級生に何を言われるか。考えただけで背筋に嫌な汗が伝ってしまう。
「ありがとうございました」
「いいよ。解らないところがあったらまたおいで」
微笑んでくれる顔は、傷のせいで痛々しい。また来てと言ってくれる言葉の裏に他意がないことは解っていた。「解らないところを聞きに来る勉強熱心な生徒」。彼の中の私はそれ以上もそれ以下の意味はない。だからこそ私はもうここへ来るのはやめようと決めた。
「はい」
一礼して教室を出る。翻したローブで私の涙が隠れていたらいいなと思った。私と彼の間にこれ以上の進展はない。それは私がたとえ彼に気持ちを伝えても一緒だ。彼の中での私はただの生徒でしかない。これ以上ルーピン先生に相談することはないし、第一そんなことをしても惨めな思いしか味わえない。もういいんだ。この気持ちはすぐに消えるものじゃないけど、時間が経つにつれていずれ消えていく。そしてその頃には素敵な思い出として語れる。それまでいくつもの涙を流すはめになろうと、私はこの恋に在学中で終止符を打たなければいけない。
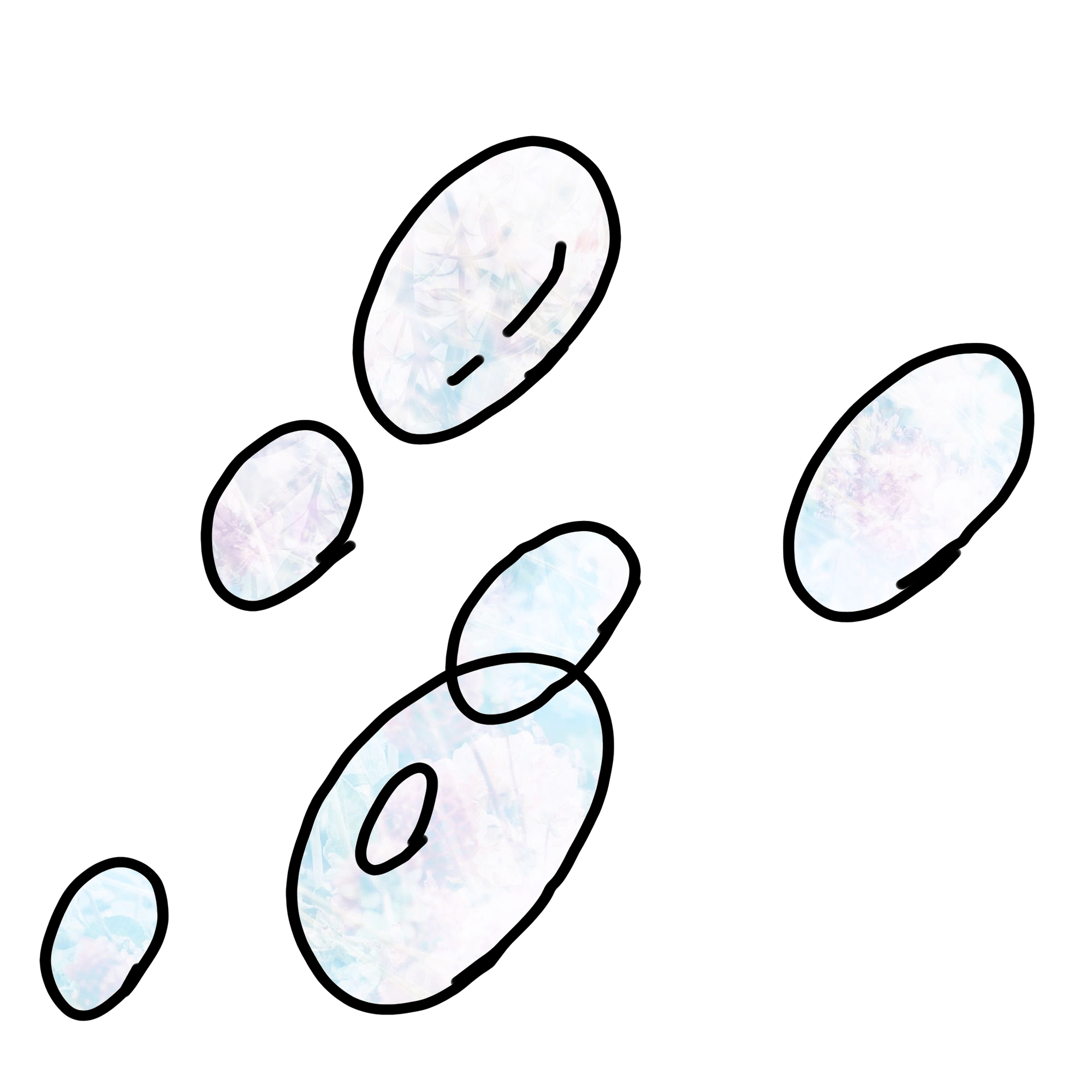
零れた気持ちは下に落ちる
、