親ってなんでああもどうでもいいことで張り合うんだろう。私がどっちに何を言ったかとか、何をあげたとか何をしたとか、いちいちマウントを取り合って、ほんとうにめんどくさい。マウント取られた方は、私が悪いみたいな目付きで見てくるし挙句泣いたり縋りついたり怒ったりする。逆にマウントを取った方は機嫌を良くし、私の好きな物や欲しい物を買ってくれたり、食べたい物を作ってくれる。だけど、それは父も母もどっちも同じことをするから、どっちかだけの味方はできないし、どっちかだけの敵もできない。どっちもめんどくさい。
「そりゃ、娘はこうなるよねぇ」
夜の八時を回っているにも関わらず、十一になったばかりの私は、誰も居ない公園で飴を舐めながら空を見上げていた。雨が上がったばかりの真っ黒な空は、どの夜空よりもどんよりと澱んでいて、黒のペンキで塗り潰されたように月の明かりをもってしても雲の色なんて全く見えない。一番星さえ見えないどこまでも闇が広がっている空を見てどれくらいの時間が経ったのだろう。舐めていた手のひらサイズの飴は、噛んだらすぐに口の中で粉々になった。大好きな苺味を堪能しても、胸はスカッとしない。空を覆う分厚い闇のように、自分の心も分厚い闇が広がっている気分だった。
「帰りたくないなぁ」
家を出る直前まで言い合いをしていた。長い時は一日喧嘩をしていた人達だ、数十分の間を置いて家に帰ってもどうせ喧嘩をしているに決まっている。娘が夜道をほっつき歩いていても、あの人達は興味が無い。見つかったらいつものように「なんでちゃんと見てなかった」の押し問答が始まるだけだ。結局、あの人達は離婚する際親としてどっちが立派だったか、私に決めて欲しいだけなのだ。「自分は悪くない。向こうが悪いから離婚するしかない。この子だってそう言っている」と、そう言いたいんだ。だから家に帰りたくない。
「何してんだお前」
「だれ?」
向こうからやってきたのは、ひとりの男の子だった。私と同じくらいの背丈の男の子で、髪は短い黒髪。傍に立っている街灯は使い物にならないので、光っては消えるを繰り返しているが、光っている時に見えた彼の服装を見るに、いいとこのお坊ちゃんなんだろう。私はそう思った。向こうからやってきたのは、ひとりの男の子だった。私と同じくらいの背丈の男の子で、髪は短い黒髪。傍に立っている街灯は使い物にならないので、光っては消えるを繰り返しているが、光っている時に見えた彼の服装を見るに、いいとこのお坊ちゃんなんだろう。私はそう思った。
「そういうお前はだれなんだよ」
「女の子に乱暴な口の利き方をしたらだめだって、教わらなかったの?」
命令するような口ぶりが嫌で、少しツンケンしてしまった。すると彼もムッと眉をひそめて「名乗らない奴に名前を聞いただけだろ」と吐き捨てるように言った。
「ねえ、なんで君はここに居るの?」
彼はお坊ちゃんなのだから、今頃たくさんの屋敷しもべ妖精が探しているのかもしれない。ここは魔法使いの住まう所だから、マグルってことはないだろう。第一気弱なマグルだったらこんな闇の深い時間に出歩いたりしないはず。
「カンケーねぇだろ、別に」
「あっそ」
意地悪なやつ。私はそう思った。顔はかっこいいのに、言葉や態度が乱暴で上から目線なのが、とても気に入らない。自分の思うようにならないとすぐに怒るあの人達に似ていて、どこか話すのが嫌になっていた。私が座っているのを知っているにも関わらず、何も言わずにひょいと隣に座った。しかもベンチから押し出すように体当たりをして。
「何するの!」
「邪魔だからあっち行けよ」
「は、それならそっちがどっか行ってよ。私が先に座ってたんだから」
「なんで俺が行かなきゃいけねぇんだよ。お前があっち行け」
「嫌よ!」
私も負けじと体当たりをして彼をベンチから追い出してやった。やり返されるとは露も思わなかったのか、簡単に地面に転がる。びちゃ、とぬかるんだ土に横倒しになっているのを見て、笑いが込み上げてきた。手を叩いて笑う。
「ださっ。いい気味だね」
「てめぇ!」
「そっちが最初に手を出したんでしょ!自業自得っ」
「俺に譲ればいいだけの話だろ!器ちいせえな!」
「人の座ってたところにずけずけ入り込んで追い出すそっちの方が器小さいんじゃないの?」
八時を過ぎた人気を感じない公園で、私達の言い合いが熱を増していった。この頑として謝らない俺様坊ちゃんはどうしてくれようか。
「女のくせに力強いとか、将来嫁にいけねーよ!」
「男の子なのに女の子に優しくできないなんて、ほんっと最悪! そっちだって嫁入りしてくる女の子なんて居ないわよ絶対っ」
「品を弁えろ!」
「ちょっといいとこのお坊ちゃんだからって調子に乗らないで!あんた自身がすごいってわけじゃないでしょ!親がすごいんだから!」
「好きでブラック家に産まれたんじゃねえ!」
彼の放った名前にぽかんとしてしまった。言い返さなかったので、すぐに沈黙が流れる。チカチカと点滅していたランプが彼の顔を照らし出す。その表情は、下唇を噛んで般若のように眦を吊り上げて怒っていた。だけど泣きそうでもあった。そんな顔をするとは思ってなかったから、なんて返せばいいか解らなくて、私は黙り込んでしまった。すると彼が言った。
「なんだよ、笑いたきゃ笑えよ。あのブラック家の息子がこんなんだってな」
「ごめん」
「なんで謝んだ」
「傷付けるつもりはなくて。言い過ぎた」
私が素直に謝るとは思ってもいないようで、彼は目を大きくして不思議なものを見るような顔でぱちくりさせていた。
「お前、素直に謝れたんだな」
今度は私がムッとする番だった。
「なに、そんなに意外? 私は人として最低限の常識くらいある人間だから、謝ることくらいできるよ。人の体を押し出してまでベンチに座ろうとしていたどこかの誰かさんは、知らないけど」
「俺だって謝ることくらいできるっつの!」
「まだ謝ってもらってない!」
「それ言ったら泥んこにされたことにも謝ってもらってない!」
「それは自業自得!謝る必要ないでしょ」
「だったらお前だって譲ればいいのに、頑として動かなかったんだから、こっちも謝る必要ねぇ!」
「君ねぇ!ほんっっと、可愛くないっ」
「お前だって可愛くねぇ!」
「可愛くなくて結構!」
こんな奴に謝った私が馬鹿だった。あの人達の喧騒から逃れたくてここに来たのに、こんな頑固で意地悪な男の子と言い合いしてたらその意味もなくなってしまう。別の所に行こうかなって思ったけど、よく考えたら家から近場で行ったことある場所って言ったらここしかないのを思い出した。まだ早いからって言って、あまり遠くへ行かせてもらったことがない。こんな暗闇で杖先の小さな灯りを頼りに土地勘の全くない場所へ行ったら、間違いなく迷子になる。もう少し明るかったらマシだったんだろうけど、今それを悔いても仕方ない。隣に泥まみれになったお坊ちゃんが居るのは気に食わないけど、背に腹はかえられない。我慢するしかない。
「君、名前なんて言うの?」
釈然としないけど、立ちながら睨まれるのも気分が悪いので隣に一人分のスペースを空けてやった。それをどう捉えたかは知らないけど、彼は座る気配を見せない。なによ、せっかくどいてやったのに座らないつもり? なんのために喧嘩を吹っ掛けてきたんだか。無意識に溜息を吐いていたことを知ったのは、彼がさらに険しい顔をしていたのを見たからだ。面倒だな、なんて思いつつも彼の手を引っ張ってむりやり座らせると、最初こそは文句を言っていたけど、次第に何も言わなくなった。
「は? 知ってたんじゃねーのかよ」
「なんで知ってると思ったの?」
「ブラック家つったら有名だろ」
「いや、まぁ、ブラック家は知ってるけど、君自身の名前なんて知らないよ」
私の家は純血の一族ではあるが、マルフォイ家やブラック家みたいに聖28一族の中に入っているような有名な一族ではない。それに、私も親もさほど純血主義者ではないため、殊更人物名に疎いのだ。名前を知っているような名家であっても、誰がそれなのかまでは知らない。彼にはそれが意外だったようで、びっくりしたように見つめて思いきり笑った。
「お前、魔法使いだろ」
「え、うん、そうだけど」
「てことは今度ホグワーツに入学するんだろ?」
「うん。入学許可証届いたから」
話の先が見えないんだけど。眉を上げて解らないでいる私に彼は、にっと笑った。
「また会った時に教えてやる!」
「今教えるっていうのは、ナシ?」
「それじゃつまんねぇだろ」
「名前を聞くのにつまらないとかある?」
「いーから!そんときにお前も教えろよ」
「はいはい」
さっきの喧嘩腰なんてどこ吹く風で、今は近所に住む幼馴染って感じだ。彼はよく喋りよく笑う。表情が豊かだな、それが彼に抱いた次のイメージだった。そこで気になっていたことを聞いてみた。
「ブラックはなんで家を出て来たの?」
ファミリーネームを出した時にしかめっ面をされたけど、ファーストネームを名乗らない方が悪いんだから知らんぷりしておこう。
「親がめんどくさかったから」
「お坊ちゃんなのに?」
「どういう理屈だよ」
「お金持ちの子って、お父さんとお母さんに大切に育てられるんじゃないの? 好きな物や欲しい物を買ってくれたり、寝る時はおやすみのキスをしてくれたり」
自分の想像のお金持ちの家族を言ったら、お前バカかと言われた。
「じゃあお前はされんのかよ」
「されないよ」
「俺も一緒だ。それにあいつらは俺になんも期待してねぇーんじゃねーの?」
「なんで?」
それがよく解らなかった。彼は笑うし元気よく話すしかっこいい。そんな彼のどこが気に入らないんだろう?
「俺がスリザリンにはぜってー入らねぇって言ったから」
「嫌なの?」
「嫌だな。根暗のスリザリンも、あいつらの言いなりになるのも、もううんざりだ。マグルを端から嫌う奴らの言うことなんか聞くかよ」
「だからブラックは家を出て来たんだ」
どこも一緒なんだ。私の家だけじゃない。どこの家の親も、何かしらめんどくさいところがあって、理解できないところがあるんだ。
「ブラックは親が嫌い?」
「大っ嫌い」
「そっか」
なんだか仲間ができたようで、くすぐったい気持ちになった。
「何笑ってんだよ」
ムスッとした表情で見てくる。私は手を振って「別に、馬鹿にしたんじゃないよ」と誤解を解いた。それでも彼の表情は払拭されない。まあいいか。
「ブラックも大変だね」
「お前も親となんか揉めてんの?」
「私がっていうより親同士が、ってところかな」
そして丁寧にブラックに説明した。親が離婚調停中で、娘の私は自身の潔白さを表すための道具として父と母の間で揺れていることや、どちらも頑固で妥協を嫌う性格であるため日々喧嘩が絶えないこと、そして私がどっちかに着いたら片方は家を出ていくことも。ブラックは、他人である私の身の上話を静かに聞いてくれた。さっきの喧嘩腰とは全然違う。
「めんどくさいんだよね、親の顔色を伺って、どっちの味方をしなければならないとか考えるの。だってどっちも自分のことしか考えてない。娘のご機嫌取りに必死なあの人達見てたら、家に居たくなくなって出てきたの」
母を選ばなかった日は、その日一日中無視されたり、仕事で父が家を空けるためご飯を作ってくれない母に代わって自分の分を作ろうとして怪我をしても知らんぷり。逆に父を選ばなかった日は、高圧的な態度を取られたり、勉強を教えるという名目上で、明らかに今習うような魔法じゃないものを実践させたりする。それで怪我を負っても「実力がないからこれしきでそうなるんだ」と私を責めてくる。
だけど母を選んだ日は、ちゃんと一日三食温かいご飯を作ってくれたり、怪我をした時や何か困ってるとすぐに助けたりしてくれる。外に行くと新しい服や可愛らしい靴も買ってくれる。
同様に父を選んだ日は、怒った時の高圧的な態度を疑ってしまうくらい優しく接してくれたり、私が読書好きなのを知って、この歳でも読めそうな解りやすくて好奇心をくすぐられる本をたくさん買ってくれる。
「祖父母の方が好きなんだけど、遠いから一人では行かしてくれないの。まあ、別にいいんだけどね。ホグワーツに入っちゃえば、喧嘩ばっかりのあの人達の姿を視界に入れずに済むし」
「お前も大変だな。そんなわがままな親を持って」
「お互い様じゃない? ホグワーツってどんな所だろう。ブラックは知ってる?」
「聞いたことはあるが、どれも悪口ばっかだ」
「うわ、嫌だなそんな家。疲れちゃう」
「そう考えると俺の親とお前の親、結構似てるんだな」
「そう?」
「だってよ、俺の親はマグルの悪口を言って、お前の親は互いの悪口を言う。似た者同士じゃねぇか」
「あ、ホントだ」
ブラックに指摘されてくすりと笑みが零れた。彼が私の笑った顔を見て肩を落とすのが解った。月や星を一点も残らず覆い隠していた何層もの分厚い雲がようやく薄れつつあることに気付いて、空を見上げた。どろりとした湿った空気が漂っていたのに、気付けばそれも薄くなっていて、肺を空にするつもりで息を吐いて、新鮮な空気をまんぱんに取り込むように息を吸う。つんと冷気混じりの冷えた空気が入ってくるけど、心までは凍らなかった。むしろぽかぽかと温かい。うっすらと月の顔が見えたのが、今のスッキリした私の気分と似ているように思えて少し親近感が湧いた。
「宿題多いのは嫌だなぁ」
「んなもん、燃やせばいいんだよ」
「ブラックは間違いなく問題児になるね」
「縛られんのが嫌なんだよ」
「私、ホグワーツに入ったら箒を乗りこなせるようになりたいなぁ。それでね、クディッチに出るの。ビーターやってみたいかも」
「やめとけ。お前の頭にブラッジャーが飛んできて終わる」
「そんなこと言うんならもうサイン書いてあげなーい。有名になってナショナルチームに入っても、ブラックにだけは握手もしてあげないんだから」
「随分ケチな大人になるんだな」
その後も学校に入学したらどんな授業を受けるんだとか、この授業はこんなことをするんだとか、在籍する先生の名前とか、あとブラックが今できる魔法も少し教えてもらった。おかげで錯乱呪文と爆発呪文を覚えられた。だけどお返しができるような物が手元になかったので、私は「オーキデウス! 花よ!」と唱え手のひらに花弁を開かせた真っ赤な花を作り出した。何する気だと怪訝そうに見つめる彼に笑って、花のブローチを作った。目を宝石のように輝かせるブラックに説明してあげる。
「ネリネっていう花なの。これあげる。キングス・クロス駅ってごった返すってよく聞くから見失わないように、付けてきてね」
彼の胸元で輝く花は、雄しべと雌しべが突き出ていて、存在を知らない人が見ればユリと間違えてしまうような花である。だけど名前はネリネ。似ているようで別の花。真っ赤なネリネは薄暗い空の下だとあまり綺麗とは思えないだろうけど、雨上がりの快晴の元、青空の下で見れば、その花は瑞々しく赤色のどの宝石よりも輝いて見えることだろう。会う日まで枯れないように呪文をかけておく。ブラックは、その花をどこまでも嬉しそうに見つめていた。
「気に入ってくれた?」
「ああ」
「ありがとう。ネリネってユリと間違われるくらい似てるけど、別の花なの。これってブラックみたいだよね」
「俺か?」
「うん。ブラック家って一括りにされて純血主義者扱いされるかもしれないけど、君自身をよく見たら根っこから全然違うって解る。そう考えたらネリネと君って似てるよね」
私は薬草学が好きなため色々な薬草について調べた。もちろん魔法薬についても調べたが、普通の薬草やマグルの薬草や植物にも関心が向いたので調べのである。私が彼と話しててぴったりな花がネリネであると思い至ったのは、ついさっきのこと。お礼になにしようかと首をひねらせていると、ぱっと思い浮かんだ。
「お前も付けてこいよ、これ」
「私が?」
「じゃねぇーと俺が見つけられないだろ」
「あ、そっか。解った」
彼の時と同じように呪文を唱え手のひらに出す。自分で付けようと胸元に近付けたが、上手く付けられない。針がなかなか収まらないのだ。
「む、難しい」
「何やってんだよ」
「あ」
孤軍奮闘を見かねたブラックが、ひょいと取り上げてしまう。何するのと言う前に彼が付けてくれた。だけどそれは彼と同じの胸元ではなかった。
「なんで髪?」
髪に付けてくれた。これじゃブローチじゃなくて髪留めじゃない。花の髪留めなんて初めてだけど、何故髪留めなのかが疑問だった。それを聞いただけなのに、ブラックは何故かいきなり頬を真っ赤にさせ「お前っ、馬鹿か!」と怒鳴られた。理不尽に怒鳴られて静かで居る私ではない。すぐさま反論した。
「誰が馬鹿よ!聞いただけじゃん!」
「自分で何言ったのか理解できてねぇのか!?」
「もー。何に一体そんなに怒ってるの?解るわけないでしょ!」
「性別考えろ馬鹿!」
「性別?」
私は女でブラックは男の子。そんなの改めて考えなくても解る。
「あ」
「遅ぇよ」
ブラックが何故頭に付けたのか、それを聞いた時怒った理由が解った。自分でも無意識だったのでみるみる顔が赤くなっていってしまう。街灯は使い物にならないし、いくら雲が薄くなりつつあるっていっても、夜だからまだ暗い。今が昼じゃなくて良かったと感謝したのは、さっきの自分とは考えられないものだなと思った。恥ずかしさで、少し気まづくなってしまう。
「ご、ごめん」
「全く。ほんとに品のない奴だな」
前言撤回。全然恥ずかしくない。むしろ、ちょっと良い奴かもと思い始めた私を助走を着けてぶん殴りたいレベルだ。けっ、と鼻で笑うブラックが、良い奴なわけない。ただの意地悪で、俺様頑固様なブラックだ。笑い合っているうちに公園に来てだいぶ時間が経ったことに気づいた。魔法使いであってもお互いはまだ子供。十一になったばかりで、これ以上放浪するのは危ないと思って、ベンチから降りた。
「私、そろそろ帰るね」
「おう」
「また会った時、名前聞かせてくれる?」
「そのための花だろ。今度からは名前で呼べよ。家の名前で呼ばれんのは嫌いなんだ」
「花を失くしたりしないで再会できたら、名前で呼んであげる」
「絶対見つけるから待ってろ」
「私も見つけるから」
またね、と手を振って彼とは真逆の道を歩く。ここを訪れた時の胸のもやもややイライラは帰る時には完全になくなっていて、逆に来るべき日へのわくわくとどきどきが止まらなかった。公園で会った彼の名前はなんだろうと、そればかり帰り道考えていた。月に照らされた帰り道は、まるで別の所を指してるようとも思えた。私と公園の彼が出会うのは、もう少し先の話になる。
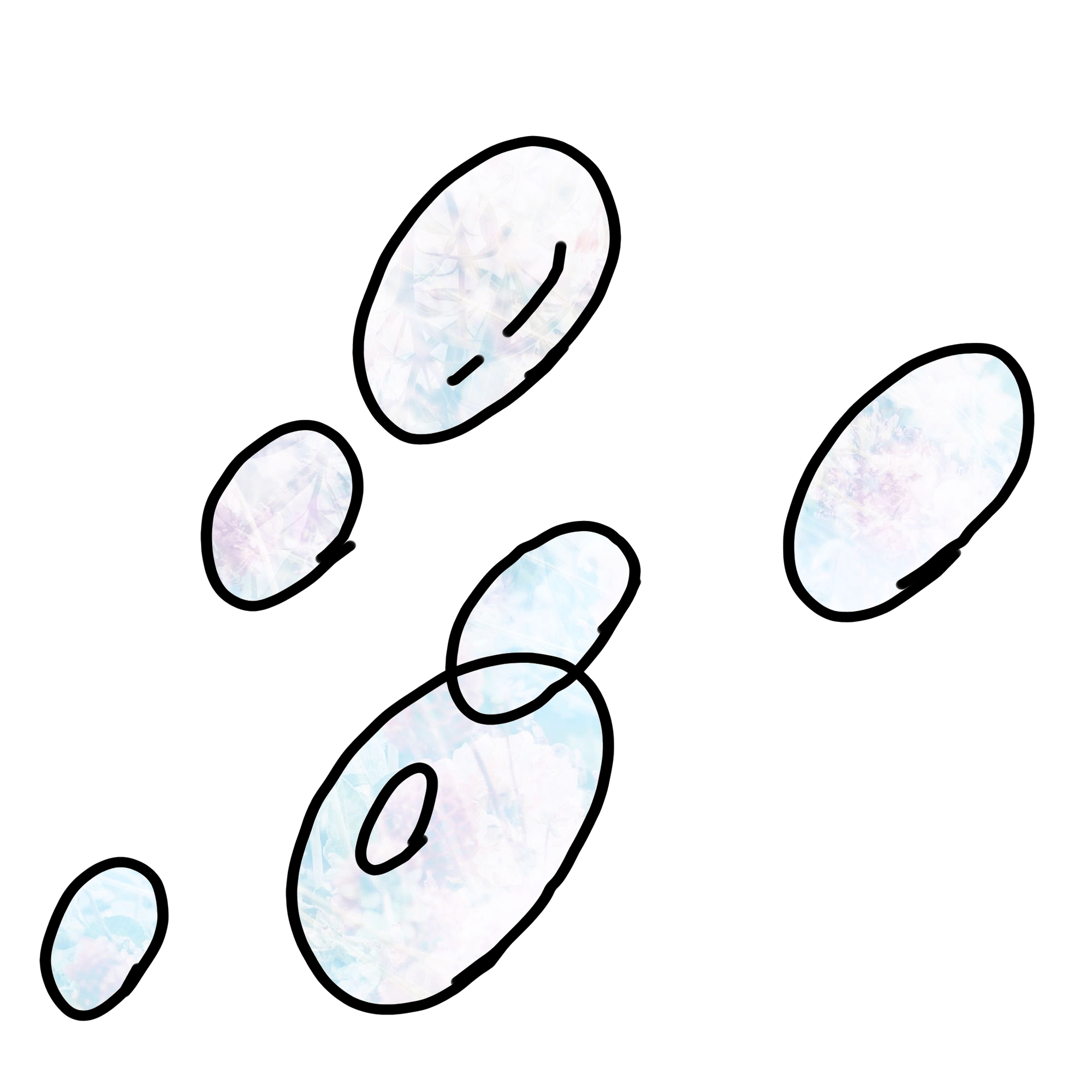
また会える日を楽しみに
、