夜の冷たい風を遮断するように暖炉の火で温まった談話室には、カリカリと硬い羊皮紙に羽根ペンが滑る音が響く。流れるようなリズムに、私の目は動く手を追うようになってしまった。おかげで自分の宿題の進行が止まっていることにも気が付かずに。レギュラスの字って綺麗だなぁ、とうっとりするようになったのはいつ頃だったか。思い出すことさえできない頃から彼の筆跡に見とれていたんだと思う。しばらく見つめていたら、ふと羽根が止まった。吐かれる息に釣られて顔を上げればそこには、整えられた眉を寄せている彼が見下ろしていた。
「ガン飛ばすのはやめてくれませんか」
「そんな睨んでた私!?」
「少なくとも不快になるくらいには見つめられていましたよ」
「不快って、ひどっ」
レギュラスったら恋人である私にだけやけに冷たく当たっている気がする。今に始まったことじゃないのであまり気にしていないけど、たまには彼のデレが欲しいと思う今日この頃。私は、長いまつ毛の奥に隠れた灰色の瞳を見つめた。
「レギュラスってさ」
「はい」
「なんでレギュラスなの?」
なんの脈絡もなく尋ねれば、彼はみるみるその綺麗な顔を険しい表情に歪めた。
「ロミオとジュリエットですか」
「よく知ってたね」
「どこかの誰かさんが読んでいたので」
本を燃やさなかった自分を褒めたいですね、なんてにこりともせず言ってしまうから彼のマグル嫌いは筋金入りだ。マグルだけではなくその人達が生み出した物語さえ嫌ってしまうのだから。私は生憎そういった思想はないので地雷なく様々な分野に足を踏み入れてはすぐにまた別のところに浸けるを繰り返している。
「ねえねえ。どうしてレギュラスなの?」
「親がそう名付けたので」
「どうしてレギュラスは髪が黒いの?」
「遺伝です」
「どうしてレギュラスはシーカーなの?」
「箒に乗るのが得意だったので」
「じゃあレギュラスはクディッチが好きなんだ」
「嫌いだったらしませんよ」
興味が失せたのか、また羊皮紙に顔を向け羽根ペンを動かし始めた。黒いインクが滲むのを見つめつつ私は話すのを止めようとはしなかった。レギュラスが私の話に興味を失くすなんてザラにあることなので慣れた。明日の変身呪文学で提出しなければならない宿題が手元にあることに相変わらず気付かない私は、当然のことながらインクの器に差し込んだ羽根ペンを手に取ろうとはしない。このままではいつもの彼に懇願するはめになるが、それも、気付かない。
「じゃあレギュラスは、私のこと好き?」
ぴたりと彼の羽根ペンが止まった。顔を俯かせていた彼が睨むように私を見つめる。そんなダメなこと聞いた!? 内心ひやひやものだが顔にはそれらを出さなかった。私は耳がいいし、机を挟んで向かい合うこの距離だったら相手のどんな小言さえ聞き漏れらしはしない。ゆえに「面倒な」という心から疎ましく感じるような彼の声もしっかりキャッチした。恋人なのに面倒って酷い!
「その紙は何のためにあるんですか?」
ペン先で指されたのは手元の羊皮紙だった。大小様々な文字が並ぶ文章は、三行程度で止まっている。提出しなければならないこの羊皮紙は全行埋めてこいと言われているものであることに気が付いて「あっ!」と絶望的な声を上げた。軽く十行以上のスペースが空欄でることに、みるみる目が潤んでいく。や、やってしまった。目の前で彼が肩を竦める。決して迷惑をかけたわけでもないのに、肩が縮こまって「ごめん」と謝っていた。
「終わらせますよ」
「手伝ってくれるの!?」
「スリザリン寮の点数を引かれては困りますので」
「うっ、それはごめん。でもありがとう!助かるっ」
彼ってばなんだかんだ提出期限までに終わりそうになかったらこうして宿題を手伝ってくれる。ぶっきらぼうで一見素気無いように見えるけど、でも実際は私のことをよく見てくれているんだなと身をもって理解する。今だって軽く腕を摩っただけなのに、どこから出したか知らないけど白い湯気が立つココアの入ったコップを「どうぞ」と差し出してきた。私はいつもマシュマロを熔かすのだが、その時の甘い香りが湯気と共に顔を覆う。マシュマロ入れてくれたんだと解るのは貰ってすぐのことだった。
「私がコーヒーを飲めないの覚えてたんだ」
「貴女みたいに記憶力は悪くないので。それに徹夜する気がないのでココアにしたまでです」
「そっか。ありがとう」
「味はそれでいいですよね」
「うん。すっごく美味しい」
「そうですか」
今度はもうひとつのペン音が談話室に響いた。二つのペンがそれぞれのリズムで羊皮紙の上を滑っていく。インクの匂いとココアの香りが部屋に充満するのだけど、別に嫌な匂いではなかった。彼に指摘されながらも私が自身の羊皮紙を黒い文字で埋め尽くしていくと、突然彼が言った。それはあまりにも急で、あまりにも静かだった。
「嫌いな人の好物を覚えたりしません」
紙にインクを一粒落としたかのような声音だった。聞き返す前に彼は「何をぼうっとしているんですか。貴女に時間はありませんよ。ぼくの貴重な睡眠時間まで削るつもりですか?」と息継ぎする間もなく言われてしまったので、さっきの言葉を理解することはできなかった。だけど宿題も終わり「おやすみ」と言葉を交わして部屋に戻る途中で私は言葉の真意に気づく。それと同時に言葉にしてもしきれないくらいの喜びに体の芯が燃えた。レギュラス貴方って人は!私も好きよ! 結局寝られなくて、次の日彼に「まるで血みどろ伯爵ですね」と言われてしまうのはまた別の話。
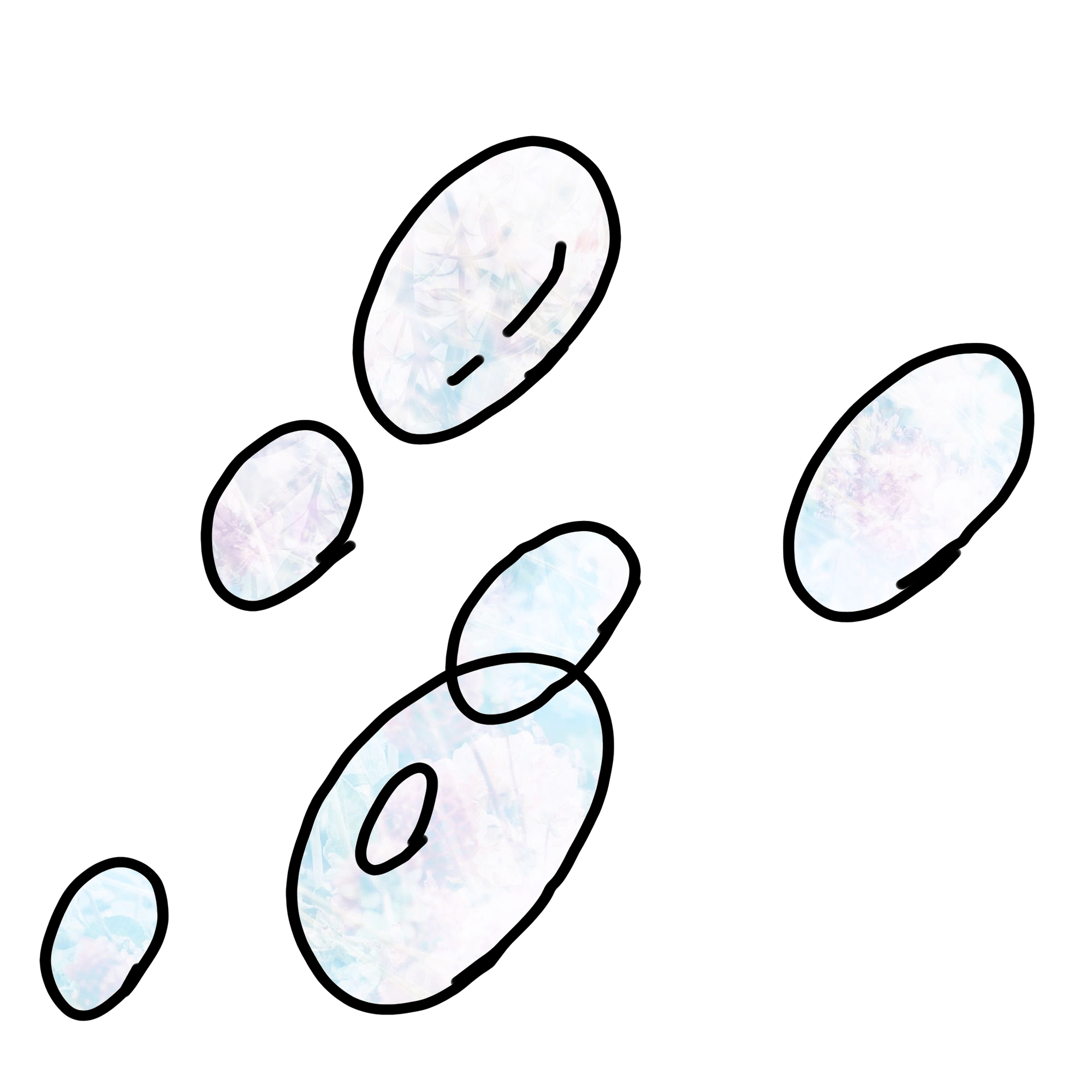
見落とし注意!
、