食後って憂鬱になると思う。昼食後に、大嫌いな授業だったら尚更。我が寮の寮監であるスネイプ先生の声は、抑揚がない。そして高くない。低くて一定の音程で、しかもスニッカーズのようなねっとりとした喋り方をするから、満腹の上にその条件が合ってしまい睡眠が促成されてしまう。だけど彼の授業で寝ようものなら、頭に遠慮をしらない強さで手刀が落ちてくることを身を持って知っているので、寝ようにも寝られない。だからこそ、隣の彼の存在はとてもありがたい。
「寝るなトンマ」
「ひどーい。美少女にトンマなんて」
「どこにそんなものが居るんだ」
薄暗い地下牢でも一際目立つブロンドの髪を持つ男子、ドラコだ。二人分の長さがある古びた木を使った机には、一つの黒々とした釜と二人分の教科書と、やり直しが効かない量の材料がある。先生に聞かれたら鎌より鋭い視線を送られるので、声量を耳元で飛び回るハエと同じくらい小さくして喋る。
「寝るな。スリザリンの評判が落ちるだろ」
「流石監督生。言うことが違うねー」
「茶化すな」
上級生である私とドラコ。頭の出来も性格の悪さもハリーの嫌い度も成績の良さも私よりうんと上である彼は、今年晴れてスリザリンの監督生となった。ドラコが監督生になった日のパンジー・パーキンソンの劈くような歓喜の叫びを未だに覚えている。あの日ほど彼女に殺意を抱いた日はない。
「眠い、眠い眠い眠い」
「うるさい」
「眠いよー。どうせスネイプ先生減点しないんだし寝てもいいんじゃない?」
「頭痛を抱えたいのなら寝ろ」
「起きます」
手刀のことをすっかり忘れていた。にしても眠い。釜からひっきりなしに立ち込める紫色の暖かな煙は、ほんとうにダメだよ。だって暖かいせいでうんと眠くなるもん。
「ダメだ、ねる」
瞼が限界を訴えたせいで、徐々に重くなっていく。抗う力なんてないので、流れに身を任した。そして視界が真っ黒になる。首がかくんと折れたのが解った。持ち上げる力もないので、机に突っ伏すことにした。机のささくれが所々肌に刺さって痛いが、睡魔には勝てないので、気にしないようにした。
「った!」
もう少しでノンレム睡眠の海に沈むところだったというのに、突如頭上に襲いかかった痛みが、一気に睡魔を吹き飛ばしてしまった。もしやスネイプ先生に見つかってしまった? と思って後頭部をさすりつつ、頭を上げてきょろきょろ辺りを見回すが、スネイプ先生は付近には居ない。他の生徒も前で説明するスネイプ先生に釘付けだ。私達の席は後ろなので一瞬で前に戻るということは不可能だろう。そして気付く。そんなことができるのは、一人しか居ない。
「前もって忠告したはずだ。頭痛を抱えたいのなら寝ろと。だからお前は頭痛を抱える結果になった。おっと、恨むなら授業中に寝たお前自身を恨め」
「そうだけど」
女子の頭を叩いていけしゃあしゃあとできるのは、ドラコ一人だけだろう。女子の扱いに慣れていないどころか子供過ぎて雑な扱いさえしてしまうロナウド・ウィーズリーだって女子の頭は叩かない。頭じゃなくても手は出さない。全く。なんでスリザリンの男子ってこうも暴力的で冷たい人が多いんだろう。
「各自始め」
教室に響き渡る声で生徒が動き出した。そして事は滞りなく順調に進み、スネイプ先生の魔法薬学の時間は終わりを迎えた。終始グリフィンドールの生徒に嫌味と減点を言い渡していたのを、眠気混じりに遠い目で見つめていたが、改めてスネイプ先生の語彙力に感嘆した。よくもまああれだけの嫌味がつらつらと出てくるものだ。私がスリザリンだから聞き手に回れるが、これがグリフィンドールならば、叱られ手になっていたことだろう。毎度毎度ご愁傷さまと思わずには居られない。
「きちんと歩け。僕の隣でふざけた顔でだらけた歩き方をするな。品位が落ちる」
前言撤回。スネイプ先生に言われなくてもドラコに言われるから、私自身もご愁傷さまだ。一瞬にして聞き手から叱られ手に回ってしまったじゃないか。次の授業であるシルバヌス・ケルトバーン先生の魔法生物飼育学までは結構な時間があるので、ほぼ垂れ流し状態で聞いていたスネイプ先生の授業の内容を、日当たりの良い中庭のベンチに座って復習することにした。勿論一人でできるはずもなく、ドラコに教えを受けることになっているのだが。
「何故そうなった、この薬を作るのにこの材料では失敗するに決まっているだろ。お前は失敗する薬と称して先生に提出するつもりか?」
「治す薬を作るのならば混ぜすぎるな。台無しになってしまう。なんだ、攪拌の回数も覚えられないのか? 一体何を聞いていたんだ」
「違う。ここも違う。これはスペルミスだ。これがスネイプ先生だからAにしてくれるが、マクゴナルやスプラウトだったら間違いなくPだぞ。評判を地に落とすくらいなら眠り薬でも飲んで授業は終始寝ていてほしいものだ」
凄く帰りたい。というか寝たら殴るの誰だよ。スネイプ先生の毒舌と悪口の饒舌も拍手ものだが、ドラコの時間みたいに止まることなく動く舌の滑舌と呂律も拍手ものだ。だけど授業でOを取る頭の良さを毒舌に活かさないでほしい。彼の舌は一体いつ休息を取っているのだろう。今度身近にある意外なものをレポートにまとめろと言われたら、彼を観察しようと決めた。
「寝ようとするな」
「違うのー。ドラコの長ったらしい説明が理解できないのー」
「とんだ馬鹿だな」
「ドラコはとんだ舌使いだね」
「何を言っている。本題に戻るぞ」
「うげ」
彼を見てつくづく思う。なんで私、ドラコと付き合ってるんだろうと。周りは誰一人として知らないが、私と彼は付き合っている。それも結構前から。変に囃し立てられたくないのと、噂好きなスリザリンがいつ他の寮にバラしても可笑しくないのを懸念して誰にも言っていない。まあ、そんな理由もあるけど、私の中では言う必要がないのと知らせる相手が居ない。友人も居なければ先生と仲が良いというわけでもない私が、一体誰に言うのだろう。パンジー・パーキンソンや、ご身分と鼻持ちが高いご令嬢なら、好きと解った瞬間に海のように周りに言いふらすだろうが、私はそんな悪趣味はない。周囲から目を向けられるより影で閴かに生きていたいタイプの人間なので、殊更この交際が広がることはない。当初は彼に魅了されるところがあったんだと思う。
でなきゃ身長と比例するような高さのプライドと知名度を持つマルフォイ家の長男と付き合ったりしないし、好きにならない。もしかしたら身長を優に超すかもしれない。だけど今はどうだろう。付き合ってだいぶ経つが、恋人らしいことは特にしたことはない。それが悲しくないとか寂しくないとか聞かれれば、うんと頷けないけど、噂の広がりが星よりも早いホグワーツの中で、恋人らしいことをする気には到底なれなかった。だから別にそれはいい。気付けば彼が最後に好きと言ったのはいつだろう。本の内容を解りやすく教えるドラコの目に、私はそんなことを考えていた。手を繋いだのはいつ? 抱き締められたのはいつ? 純粋に愛でられたのはいつ? ぐるぐると頭の中に絶えず浮かび上がるいくつもの気持ち。
それは次第に疑問へ変わっていき、最後には「彼のどこを好きになったんだろう」に思い至った。遠い記憶を手繰り寄せても解らない。遠すぎて手が届かないのだ。好きになった証拠はあるのに、その理由が解らない。遠すぎて、それが思い起こせない。
「僕の顔ばかり見ているが、答えは教えないぞ」
彼の顔をじっと見ていたようで、はっと我に返ると顰蹙した彼が居た。せっかく教えているのに聞こうとする姿勢を見せない私に苛立っているのだろう。だけど私には、授業や宿題よりも大事な疑問があるのだ。それが解消するまで他のことに着手する気にはなれない。
「んー」
「なんだ」
「んーん。なんでもない」
この質問は彼に聞けない。というか、彼が答えを知っているワケないし、一応恋人であるドラコに「私って君のどこを好きになったのか解らない」なんて言えるわけない。失礼すぎるでしょ私。だから自己解決するしかないのだが、果たしてそれができる日は一体いつなのやら。
「なんだか騒がしくない?」
物思いに耽っていて周囲の雑多を認識していなかったが、その喧騒は徐々に増してる気がする。どうやらドラコも同じことを思ったようだ。
「ホグワーツの奴らはうるさいのが大好きな連中が多いからな。勉強を疎かにし、遊びに耽っている奴の末路なんて、火を見るより明らかだな」
私は別にそこまで思っていません。誰に弁明するでもなく内心そう思った。中庭を取り囲む廊下の吹き抜けには、瞬く間に生徒で溢れ返った。校舎の奥からトロールでも襲ってきたのか、彼らは群れをなして中庭に集まる。日当たりの良い静かな中庭は、一瞬で喧騒甚だしい場所へと変貌してしまった。
「うわぁ。うるさ過ぎ」
「眠り薬をばら撒きたいと今日ほど強く思ったことはない」
隣で呻くように呟く。勿論それを拾う者は私しか居ない。皆真ん中に居る人物に、目どころか体の神経が全て一身に向けられている。高低差の激しい身長の中からちらりと見えたのは二つの頭と、キャロットを連想させる短い赤い髪だった。それは箒に乗ってみるみる上昇する。はっきりと現れた人物は、顔が瓜二つのいたずらっ子として有名なあの人達だった。
「ジョージとフレッドじゃん」
よく飽きないなー、と思った。彼らの存在はドラコには不快なものらしく、双子の顔を見た途端ハリーを見た時と同じ、汚物でも見るような蔑む目をした。
「忌々しいウィーズリー兄弟め。あいつらはどこまで悪事を働けば気が済むんだ」
どちらかと言えば悪事を働くのは、いつもスリザリンじゃない? そんな疑問は口にしないでおいた。ウィーズリー兄弟に向けられている視線を浴びるのは御免だ。上空に浮遊している兄弟の手には各々杖が握られている。
何をする気だろう。それに答えるように彼らは、学校中に響く声量で言った。言葉までハモるのだから流石ウィーズリー兄弟といえよう。
「これを発明するのに時間をだいぶ使うことになるとはな。なあ兄弟?」
「そうだな兄弟。だがこれを発明したのは魔法界で俺たちだけだ!」
「さあさあさあ。退屈な授業の合間に少しの楽しいことを挟まないかい? 人生退屈より楽しい方がいいだろ? 口を開けて餌を待つペットみたいな君達に、いいものを見せよう!」
「これぞ俺達が手間隙かけて作った超大作!その名も『生きるドラゴンの粉』だ!」
フレッドだかジョージだか似過ぎて区別が付かないが、そのうち一人がローブから取り出したのは一つの球体だった。手のひらで収まるような球体。それを親指と人差し指で挟んで天高く突き出す。皆はどんな大きく派手なものかと期待していただけに、目に見えて落胆するのが解った。
「フン、ついにふざけたイタズラグッズの発案のストックも底をついたか」
ウィーズリー兄弟がげんなりされているのを見てか、それともうんざりするような発明を目にしなくていいのか、ドラコはとても嬉しそうに鼻で笑った。私はあの兄弟の底なし沼のような発案が底をついたというドラコの発言に同調はできなかった。
「これからだよ」
「なんだと?」
結末がどうなるのかと、風船のように軽く弾んだ気持ちで彼らを見上げる。ドラコは何が不満なのか、さっきの笑みから一転し不機嫌そうに見上げた。ウィーズリー兄弟は生徒の落胆した顔をものともせず笑みを消さない。どうやらこうなることは予想していたらしい。成績は悪いのにこういうことには人一倍敏いから、彼らの商品には期待させられるんだ。
「おっと、予想よりも小さなボールが出てきて残念がらないでくれよ?」
「そうそう。最初からフィナーレなんてそれこそつまらないだろう?」
「ここからが本番だぞ、瞬きさえ惜しいくらいのびっくりする物見せるから!」
「開けてやれフレッド!」
「おうともジョージ!」
フレッドが右手に持っていたボールを二つに開けて、空中へ零す。遠すぎて色や形状まではっきりと見えないが、太陽の光で粉はダイヤのようにきらきらと輝いていた。
「なんだ? フレッドの奴、ここに居る奴ら全員食べるつもりか?」
ドラコはあの粉を調味料などと思っている。それが面白くて噴き出してしまう。隣から、最初ウィーズリー兄弟に送られた視線がとうとう私に送られてしまった。きらきらと輝く粉は生徒達に掛かることなく空中で一つの物へ変わる。それがはっきりと理解したのは、ウィーズリー兄弟の真下で群がっている生徒のうち誰か一人が叫んだ言葉によってだった。
「ドラゴンだ!!」
その声を掻き消さんばかりの大きな声を、色んな生徒が発した。驚く声、嬉しがる声、怯える声など。色んな叫び声が雷が落ちた時と同じように中庭に響き渡る。ドラコと私はそれに一瞬眉を寄せた。
「うるさい」
「それはちょっと解る。耳が痛い」
下手したらパンジー・パーキンソンの百人分くらいの叫び声を聞いている気分になる。大きな骨組みが形成されていき、最終的には炎より深い赤い色の皮膚を持った何十メートルもあると思われるドラゴンに変貌した。鋭い目や、大地を揺るがさんとする咆哮によって見える二つの太い牙は果たしてこれはほんとうに粉によって出来たものなのかと思ってしまう。触らずとも解る全身堅い鱗で覆われた大きな体には、それよりも大きな翼が左右に広がっている。フレッドとジョージの近くで飛んでいるドラゴンを見て「彼らは大丈夫なの? 食べられたりしない?」と心配する人も居れば「ドラゴンなんて初めて見た!触りたい!」と幼稚さながらにはしゃぐ人も居た。はち切れることも構わずに必死に腕を天空に伸ばす生徒に、ウィーズリー兄弟は言った。
「これは粉だからな。触れないよ」
それで肩を落とす生徒だが、次の瞬間真っ赤なドラゴンが、鮮明な色の炎を噴いたので、皆はすぐにまた歓喜の声を上げた。やっぱりどの子も大きな物や、迫力のある物は好きなのだろう。授業に遅れるかもしれないという危機感の色は全く感じられず、この場に居る全員が彼らのドラゴンに夢中になっていた。かく言う私も、ドラゴンなんてトライ・ウィザード・トーナメントでしか生で見たことはないために、結構夢中になっている。粉であることも忘れて、その高いリアリティとクオリティに言葉を零すことも忘れ意識が囚われていた。ドラコが鼻を鳴らすまでは。
「くだらない。ドラゴンなんて父上に言えばすぐに見れる」
相変わらず素直じゃないな。ドラコだってしばしの間言葉を発せずに居たのに。彼の鼻を枝に括ったような態度は今に始まったことではないので、あまり気にしないようにした。
「すごい」
「お前はあんな紛い物が好きなのか?」
「紛い物って。いや、粉であれだけのものが作り出せるのは凄いって思っただけだよ」
「フン、ますますくだらない。あんなので満足するとはな。今度ノルウェー・リッジバック種のドラゴンを見せてやる」
「いや、大丈夫」
別に本物のドラゴンが見たいわけじゃない。魔法界はドラゴンの飼育は許可していないし、それに私自身そこまで興味があるわけじゃない。気難しい上に獰猛であると、ハグリットやケルトバーン先生から散々聞かされたので正直会いたくない。ウィーズリー兄弟の紛い物で充分だ。燃やされたりなんかされたら嫌だし。そしてポンフリー先生のとてつもなく苦い薬なんて飲みたくない。それがいくら万能薬だとしてもだ。
「あの炎って熱くないのかな?」
「お前までもあの不出来なドラゴンに現を抜かしているのか?バカバカしい」
「単に気になっただけだよ」
それでもドラコは腑に落ちた顔をしない。私がウィーズリー兄弟の味方をしていると思っているんだろう。これだから両極端の人は扱いに困る。別に味方をしてるつもりはないんだけどな。言ってもおそらく聞かないだろうから、何も言わないことにした。なので「おい、まだ話は終わっていない。何勝手に終わらせてるんだ」と睨むのは止めてくれないかな。ドラゴンは未だ箒で飛んでいるウィーズリー兄弟の傍で再び咆哮した。鼓膜が割れそうで割れない程度の咆哮の後、炎を吹く。真っ赤で大きな炎は地上に向けて放たれ、生徒達を丸焦げにするつもりなのかと思った。それが地上に近付くにつれ、あれほど馬鹿騒ぎしていた生徒や冷やかしで見ていたドラコや、凄いなぁなんて感心していた私も、さっと血の色が失せた。
「えっ、やばいんじゃないの? これ」
それが精一杯だった。消える気配が全く感じない炎は、バチバチと火花を散らせながらゆっくりと広がって中庭を覆い隠した。もうだめだ、そう感じた私は目をぎゅっと力一杯に瞑ることにした。
「あれ?」
ぱちりと目を開ける。熱さは確かに感じるが、だけど体が焼かれている感触はなかった。生きながらに生肉が焼かれる音も、焦げ臭い匂いも、喉を刺すような悲鳴も、噎せ返るような煙の臭さも全く感じられない。恐る恐る目を瞬かせ周りを見ると、炎は円を作っていた。もっと詳しく言えば、太いロープで丸を作ったように、中庭に居る生徒を囲むように炎が円を作っていたのだ。誰の体にも火は燃え移っていない。恐怖交じりに見ていた子達も、それが解った途端スゲーと声を上げる。
「危ないけど、凄いね」
「つい数秒前まではハムスターのように丸まっていたくせに、それが幻覚だと解った途端鶏みたいに鳴き出すとは。こいつらには怒ることはできないのか」
「ドラコもビビってたもんね」
「この僕がビビるわけないだろ」
じゃあ微かに震えている手はきっと震え呪文でも掛けたんですね。内心で留めておくことにした。生徒の歓喜の声は止むことを知らず未だに叫び続けている。ウィーズリー兄弟も笑い続けている。いつまでこの炎に囲まれなくてはいけないんだろ、そう思った。瞬間。
「危ないっ」
「わっ!?」
隣に座っていたドラコが私の肩を引っ張って、距離をぐっと縮めた。頭の位置が低くなる。ちょうどその上を火花が通り過ぎた。ドラコに引っ張られなかったら、私の頭は燃えていたのだろうか。サーッと血の気が引いたが、炎はあくまで粉が模したもので、実在するものじゃないと思い出したので、顔色が良くなった。
「ディセン・ディウム! 分解せよ!」
彼が杖を振ると頭上で踊っていた火花は、細かく千切られた紙みたいに粉々になって消えた。ぱらぱらと塵よりも小さな火の粉が舞い落ちる。服や髪を掠っても火は燃え移らなかった。
「大丈夫か?」
ドラコが見下ろして尋ねる。その声はほんとうに心配しているようだった。私でも気付いたくらいなんだから、ドラコがあの炎は燃やす力などないことくらい気付いているはずだ。なのに私を火花から守った。私の肩を掴んでいる手はとても力強くて、この手でもし手を繋がれたらそれだけで守られてるって気になる。誰かに触られるのを嫌う私でも、ドラコに触られている今はそんな気持ちなんて一切ない。ドキドキ。心臓の鼓動が早くなる。彼の顔をまともに見られなくなるのはいつ以来だろう。
「お、おい、怪我したのか?」
一言も発せずに頭をあげない私に、心配の色はますます濃くなる。掴まれた部分の熱によって心臓が忙しなく動く中、私が何故ドラコを好きになったのかという疑問に対しての答えを見つけた。それは凄く身近で起きた出来事の連続だった。彼は守ったり守られたりするのを好むような人じゃない。むしろ悪事を働きとんでもないことを招くのはいつだって彼だった。だけど、それと同じくらい私が危険な目に遭う時、真っ先に助けてくれたり守ってくれたのは、誰でもない、ドラコだった。
確かに大事を招いたのは彼だが、守ってくれたのも間違いなく彼だった。そんなドラコに次第に私は惹かれていったのだ。会う度思いつく限りの暴言を浴びせ、私が少しでも他人を褒めたら、子供のように相手の悪口を言って評判を下げて、その上そいつと比べて僕の方が凄いだろと後日言ってくる。今思えば、最後のは嫉妬だったんだ。くすりと笑みが零れて胸が温かくなる。笑った私を見てドラコは首を傾げる。
「怪我はないのか?」
前のめりに沈んだ体を持ち上げて、私はドラコを見ながらしっかりと首を横に振った。
「ないよ。ドラコが咄嗟に沈めてくれたから、何ともない」
「そうか」
たった三文字の返事をして、手元の本へ目を移してしまった。素っ気ない返事だろうが、私が怪我はないと言った時の安堵感は、はっきりと目に滲み出ていた。心からほっとしたんだろう。彼が不器用な人であることも知っているし、何より彼が私の身を心から案じてくれたことに対しての嬉しさが、中庭で赤く燃え盛る炎よりも強く大きく胸をいっぱいに満たしたので、それだけで満足した。
「にしても鬱陶しい炎だな。いつ消えるんだ?」
「私はあと少しだけあってもいいと思うけどね」
彼はまた不機嫌そうに私を見る。ほんとにドラコって感情の波が激しいっていうか、自分に素直っていうか。そんな彼も好きなので、私は別にいい。ベンチの上に置かれた彼の角張った大きな手の甲に、自分の手を置いた。行動に、彼はブロンドにも負けない白さをもつ肌を真っ赤にさせた。
「なっ、なにをっ」
「ドラコ、キスしてもいい?」
どうやらキャパオーバーらしいドラコは、顔を真っ赤にしゴールドフィッシュのように口をぱくぱくとさせ、言葉を出すことさえ出来ていない。その光景はいつもの悪口オンパレードの彼とは全然違っていて、初々しい女の子みたいだった。そしてきょろきょろと周りを見渡す。彼が言いたいのは「人が居るからダメ」ということだろう。だけど私は彼がそう言うことは見越している。悪巧みを考えるような笑みを浮かべて、顔を近付けて言った。声量はスネイプ先生の授業で話した時と同じくらい。お互いの瞳にはお互いの顔しか映らない。
「大丈夫。皆炎に夢中だから」
逃げる理由のない彼の唇に、私は自分の唇を重ねた。
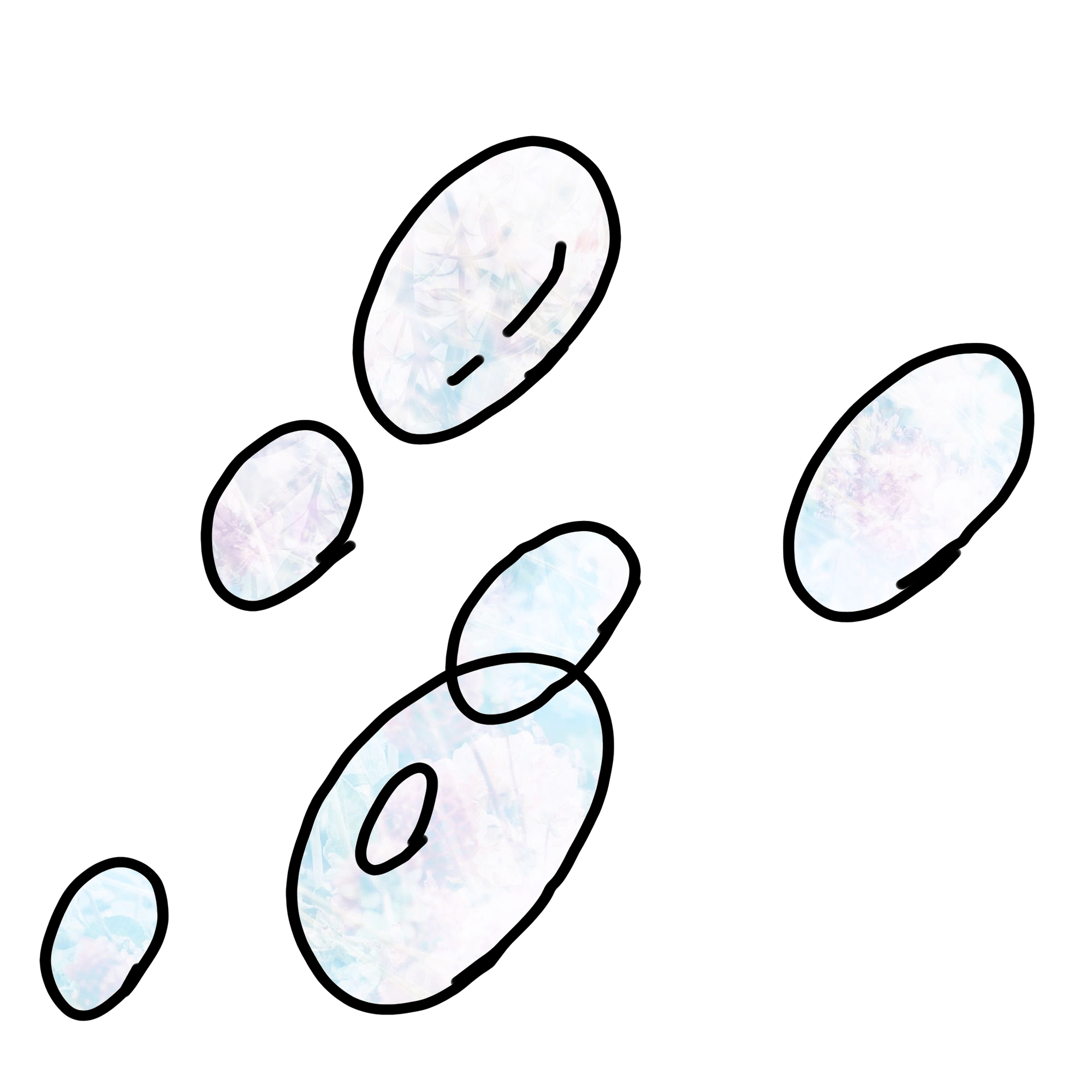
夢中になる一歩前
、