ざざざ。
その日は満潮だった。気晴らしにやってきたここは、何歳来ても変わらない。何度も見てきた海面は、いくつにも砕いたダイヤモンドが散りばめられたような美しさを放っている。それは見る角度や時間帯を変えれば、ルビーにもダイヤモンドにも、時にはサファイアにさえ見える。かの有名なブルーダイヤモンドのネックレスは、もしかしたら海から見つけ出された宝石なのかもしれない。職業柄、自身の人柄から程遠い考えを頭の中で広げて、わたしはただ海を見つめていた。砂浜に座っているせいで、足の裏どころか甲にも粉のような砂が覆ってしまっている。太陽が西へ傾き始めている今、わたし以外にも砂浜に訪れている人は多い。恋人や家族連れ、中にはご高齢の方まで幅広い年層の人が、海にやって来ていた。
ざざざ。
水に足を入れ、ばしゃばしゃとそれを掛け合う子供たち。きゃっきゃっと無邪気に甲高い声を上げながら笑い合っている。砂浜にパラソルを立て休んでいる保護者らしき人たちも、その光景を微笑ましそうに見つめている。
「帰らないといけませんかね」
ぼそと口から出た。帰らないといけないわけでもないが、これ以上ここに留まる理由もない。それに、少し暑くなってきた。帰るべき場所なんてないが、家主に許可を求めている以上、わたしはそこに帰りたかったんだと思う。少しでも傍に居たかったんだと思う。それがなければわたし達の紐は、とうの昔に切れているのだから。歳という歳なわけでもないのに、立っただけで膝が痛んだり腰が痛んだりする。まだまだ現役をやれる歳だというのに。新調したスーツというわけでもないが、前職に就くと知った時親が大金を叩いて買ってくれた、この薄いベージュのスーツは、愛用していて且つ大事なものでもある。臀部を叩いて砂を落とす。暑くなったせいで、手の平に滲み出た汗に今度は掌に砂が付着してしまった。汗ばんだ手にじゃりじゃりと異物が引っ付くのは、異常な暑さも相まってイラつきが増した。やはり暑さというのは、どこまでも人を苛立たせてくれるらしい。首を回すと偶然視界に入った公衆トイレへ向かった。公衆トイレなので、当然綺麗に掃除されているわけでもなく、ましてや電気などある筈もない。
隙間から射し込んだ僅かな太陽の光を頼りに、室内が微かに見えた。湿度が高いこの空間は、外以上にじめじめとしていて、人の吐く生温い息と同様に気持ち悪さを感じた。一秒でも長居したくないと思って、蛇口を捻った。長年誰も使ってないようで、名ばかりの水こそ流れるものの、洗面器はところどころ黒く変色していて、罅すら入ってしまっている。赤錆の付いた蛇口を捻るのも少し時間を要した。ちろちろと出てくる水滴にも似た水流で掌を洗う。だけど、あまりにも少量で完全に落とすということはできなかった。あらかた落ちたんだし良しとしよう。ハンカチを出すとそれで手を拭く。まだ異物感は残るが、さっきよりは幾分か良くなった。気がする。公衆トイレを出るのと同時にポケットに入ってた携帯が振動した。着メロなるものは設定しない主義なので、いつもバイブレーションで着信に気付く。胸ポケットから携帯を出し、ディスプレイに表示された名前を見た。今住まう家主の名だった。漢字二文字を見て頭に主の顔が浮かぶ。仕事かお使いかは知らないが、わたしは傍にあった木陰に入り応答ボタンを押した。
「はい、もしもし」
『今どちらに居ますか』
機械越しに聞こえた声は、ボイスチェンジャーを使われていない素の声だった。何度も聞き慣れた声なので、異常に低い声にも最初とは違い、耐性が付いていた。
「近くの海辺に来ています」
『そこから二キロ先で人質立てこもり事件が起きています。警官ではない貴女に依頼するのも可笑しい話ですが、できますか?』
どこ行っても警察沙汰は収まらないようだ。これで何度目になるのだろうか。警察官という職から退いたわたしが、電話越しの家主もとい、竜崎からの依頼でこうして出動するのは。
「わたしは何をすればいいんでしょうか」
警官ではないわたしに依頼するのはおかしな話。それもそうだ。国家公務員の資格を持ち合わせていないわたしは、今やただの一般人でしかない。だが、それでもわたしは元警官なのだ。相手を蔑するような言葉はそう易々と流せるものではない。あるいは、一般人の貴女が行かなくても良いと言いたいのだろうか。どちらにしろムカついたことには変わりない。余計な気遣いなど、返って癇に障る。
『犯人は五階建てのマンションの406号室に居ます。人質は五歳の少女、犯人の所有する武器は包丁です。人質の救助をお願いします』
「解りました」
『健闘を祈ります』
向こうの方から通話は終了された。一方的に掛け、一方的に切る。やることなすこと全て一方的だ。なのに、わたしを必要とするような言葉を紡ぐ。時々腹も立つが、何分彼の言うことは間違ってないし、それに彼がそういう人柄だということは、重々承知しているので、これくらいで目くじらを立てたりしない。
「行きますか!」
物言いに腹が立っていたとは言え、こうして活動できるのは彼が居るからでもある。先程のイラつきの一切が風に吹き飛ばされ、心に残ったのはこれから向かう場所への緊張感と、絶対助けるという使命感だけだった。
「戻りました」
仕事も終わり無駄にでかく造られた建物に帰宅する。開かれた扉の間から広がる部屋に、わたしの声が大きく響き渡る。中央に位置する三連に並んだパソコンの前にうずくまって座っている彼は、椅子を回してわたしを見た。
「お疲れ様です。犯人は逮捕、人質の少女も傷一つなく保護されたようですね」
「人命救助がわたしの仕事でしたから」
「貴女も無事ですか?」
「かすり傷ひとつないです。なにせ素人でしたので」
「お見事です」
「チョコを食べながら言われても嬉しくありません」
袋を左右に開いたスーパーなどで売っているチョコを口に放りながら、味を堪能している。ついで感覚で賞賛されて喜べと言う方が無理だ。
「すみません」
彼はそんなことは微塵も思っていないようだ。証に彼は、悪びれもなく飄々と次のチョコを口へ放り投げている。何度言っても聞かない子供のようだ。それでも一応耳を貸す子供の方がマシかもしれない。彼の場合は意見を頭に留めておくどころか、興味無い話には目も貸さない。耳も目も頭も貸さないとは、どれだけ頑固なんだと肩を落としたくなる。よくもまあそんな彼とずっと居れるもんだなと、保護者のようなワタリさんを思い浮かべて苦笑した。あの方は竜崎にお菓子を調達したり人と交渉したり、彼の手足として動く。仕事の依頼だって、端から竜崎の人柄が露呈してしまえば頭が切れるとは言え誰も依頼しないだろう。こういうところで、ワタリさんの手腕が垣間見える。
「海はどうでしたか」
某有名菓子店のマカロンのシンプルな包装紙を剥ぎ取り、味わって食べるなんてすることはなく、口へ放り込む彼がそんなことを聞いてきた。
「あそこは何日、何週間、何ヶ月経っても変わりません」
「また行くつもりですか」
「行ける回数は限られていますからね。行けるうちに目に焼き付けておきたいです」
早朝の海、日中の海、夕方の海、宵の海、黄昏時や逢魔が時の海、そして夜の海、深夜の海。一箇所だけとはいえ、訪れる時間帯によって海は見せる姿を変える。真っ赤な炎を纏う場合もあれば、深い青を纏い、それが遠ざかれば遠ざかる程、深淵の闇に見えて人に底知れぬ恐怖心を植え付ける。大地の母と呼ばれる海は、包容力もあれば畏怖を与える一面も備えているのだ。格段温かさや懐かしさなどは感じないが、情景になる程度にはわたしはあそこが気に入っているのかもしれない。
「後悔してますか?」
背中を向けていた竜崎がわたしを見る。どこまでも深い深い黒い目。同色が目元を縁どって、人相を更に怖くさせる。真っ黒な隈に血色を感じさせない程の白い肌。もし彼の寝ているところに遭遇すれば、わたしは間違いなく死体だと思ってしまうだろう。それ程、この竜崎という男は人間味を感じさせないのだ。
「ノートに貴方の名前を書かせてしまったことは後悔してます」
彼の隣にある一冊の黒いノート。表紙はところどころ破れており、それすらもデザインの一環として見えてしまいまるでアンティークグッズのようだ。だが、実際はそんな可愛らしいものではない。それはここに居るわたしとワタリさん、そして眼前の男、竜崎が身に染みて解っている。“DEATHNOTE” と歪なフォントで書かれたそれは、十七日前に完結した事件の重要証拠だ。大々的に取り上げられ、一時期社会現象をも巻き起こし、人々を恐怖へと追いやった忘れてはならない “キラ事件” 。
「そこですか」
「そこですね」
「理由を聞いてもいいですか?」
「世界にはまだ貴方が必要だからですよ、L」
忘れもしない、キラもとい月君の言葉。一言一句、それはわたしの胸中に深く刺さっていて、今でも感情を含んで底で渦巻いている。何も出来なかった。キラという殺人鬼を生み出してしまったのは、警察官であるわたし達だと、自分は思っている。彼は純粋だった。だから、どうしようもない上層部の闇を知って彼は絶望してしまったのだ。もし、わたし達警官が正義に対し誠実かつ真摯に向き合っていれば、一人の少年を殺人鬼に仕立て上げるようなことは無かったかもしれない。
「私が居なくても、後継人がこれからを担ってくれます」
自嘲かと思いきや、そうではなかった。黒い双眼は澄んでいた。遠くを見据え、“L” という絶対的な地位に彼の選んだ第二のLを座らせ、自分は誰にも知られることなく舞台から去っていく。キラを追うという使命を共にしたわたし達以外、竜崎という彼を知る人物は居ない。影のように支え、また影のように消えていってしまう。そんな彼の傍に居たいと思ってしまったのだ。そう思った時からわたしは想いを馳せてしまったのかもしれない。決して叶うことのない想いだけれど、伝える気もないのだから抱くことくらいは許されてもいいだろう。
「これまでお疲れ様でした」
早いなんて自分でも解っている。まだ時間はある。けれどこれは今言いたかったのだ。
「明日、私も同行していいですか?」
「海にですか?」
「はい」
「珍しいですね。貴方が外出するなんて」
「動ける回数は限られていますから」
わたしは思わず目を丸くした。そして耐えきれず失笑する。人間としては少し不格好だけれど、しかし確かに人間らしく不器用に彼も笑みを浮かべる。
「そうですね」
お互いそんなことは解りきっている。自分のすべきことはないなんてことも、自分たちはもうお役御免だということも、解っている。それでも最期まで “L” としての使命を全うする様は一番人間らしいかもしれない。時間を無駄にするわけでもなく、惰性を貪るわけでもなく、いつもどおり生きるところは、彼という人間の強さを感じる。
「喧騒甚だしいですが、綺麗ですよ」
ならばわたしのすることは、残りの時間を彼の隣に居ることに費やしたい。彼の知らないもの、聞いたことの無いもの、見たことのないものそれらを竜崎に伝え、今まで無縁だと思っていたものと巡り合わせたい。今までの労いもあるが、それ以上に彼に知ってほしいのだ。貴方が守ろうとした世界の全てを。ちっぽけな人間が教えられるのは限りがあるが、それでも知らないまま消えてしまうより、知って消えて欲しい。そして、世界に絶望し道を間違えてしまった一人の少年に見せたかった。善人が報われる世界を作ろうと奔走し、自ら罪人となった彼は、まだ知らなかった。人間の力強さを、間違えても正しくあろうとする様を。もし、知っていたのであれば少しは変わっていたのだろうか。今更どうすることもできないことばかり思い浮かんで胸を幾度となく痛める。
「土産話にしたいですね」
「誰に対してですか?」
「内緒です」
もし、あの世というものがあるのだとしたら、わたしは今度こそ彼に伝えたい。無機質な広い部屋に二人の人間が生きる。充満する空気には、言葉を使っても伝えきれない歴史が含まれているであろう。そんな中生き抜いた二人に残された時間は六日であった。
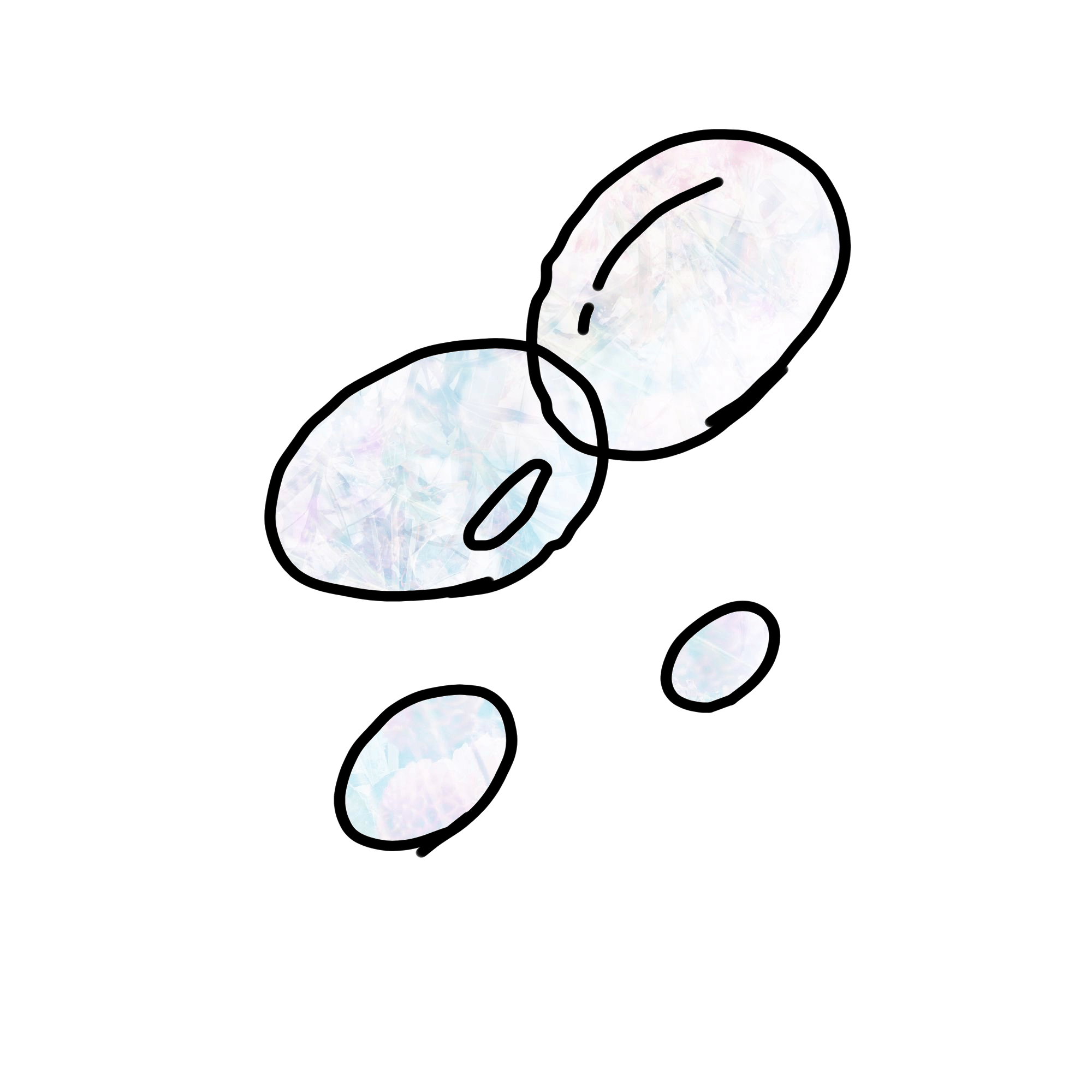
二人の正義と愛すべきひとつの世界
、