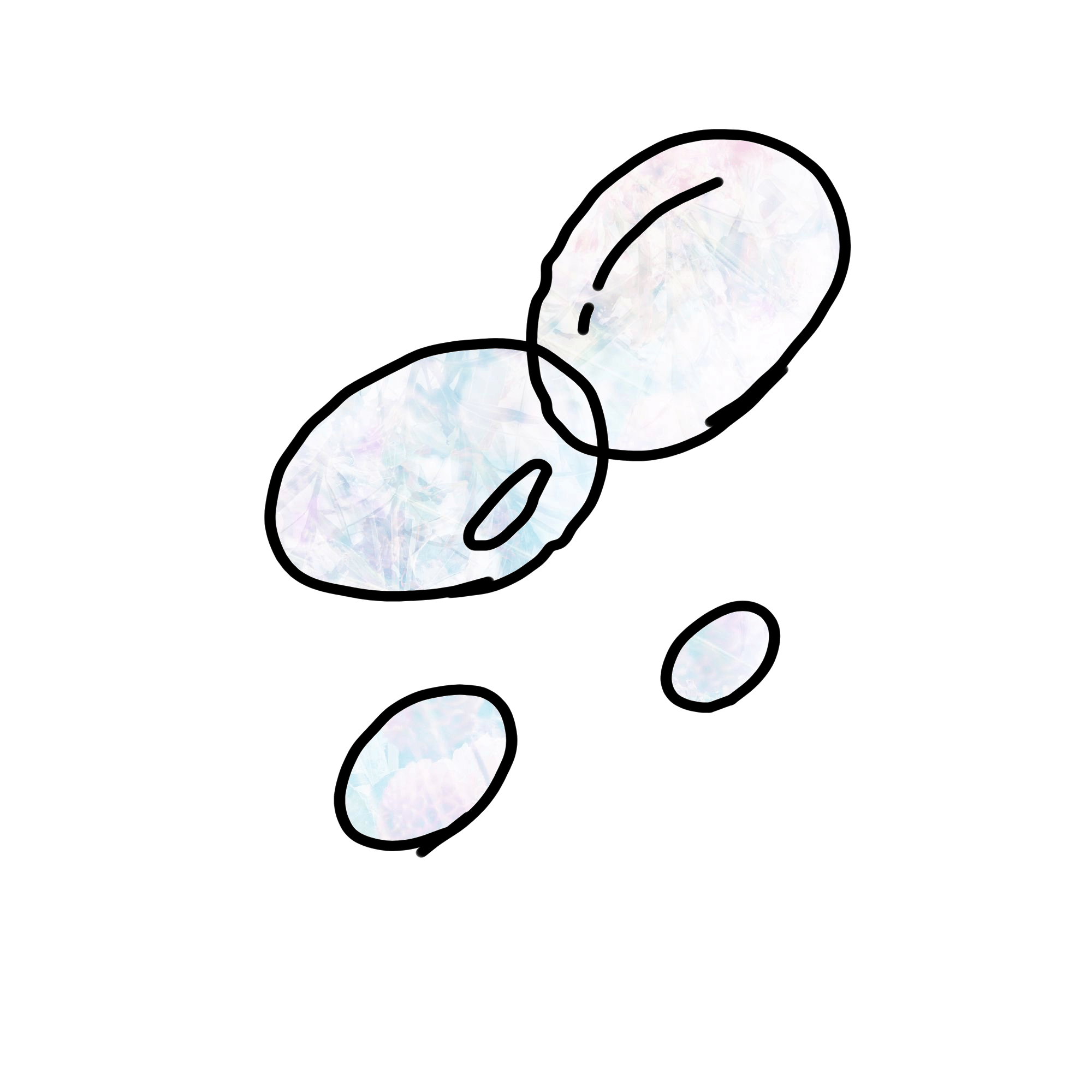「気持ちいいですね」
夏には持ってこいの冷風が頬を滑る。スーツより私服の方が良かったかもしれませんね。見下ろす自身の格好は、相変わらずのスーツだった。ベージュのスーツにインナーは、白のシフォンブラウスだ。大きく開かれた胸元には飾り気のない鎖骨が剥き出しになっている。その分、潮風が当たり涼しくなるので良しとしよう。格段暑いというわけでもないが、斜め左下には想い人が居るので、女性らしい服装をするべきだったかと、なけなしの女心が疼いたのだ。
「縮こまってないで、海に足を入れて来たらどうです?」
肩を竦めながら顔を左に向けた。正しくは、左下だが。そこには白いワイシャツとジーパンというわたしと同様に見慣れた格好をした想い人、竜崎が、膝を折りしゃがみ込んでいた。
「冷たいのは嫌いです」
海に来たいと言ったのは誰であろうか。そう言いたくなるが、わたしはそうですかとだけ言い、再び海に目を向けた。平日の朝とあって人はだいぶ少ない。目を凝らせば、遠くに一人二人居るくらいだ。以前来た時より気はだいぶ休まる。目の前に広がる青い海は、どこまでも続いているのだろう。わたし達が追いつくことができないくらい遠く、遠くまで続いている。自分が見ているこの海は、全体の一割にも満たない姿なんだ。太陽の光を反射し燦然と輝くこれは、きっとこの先を生きることになったとしても、全貌を見ることは叶わないだろう。
「あそこでかき氷が食べれますよ」
ちくりと傷んだ胸を見ない振りをして、わたしは遠くにある店を指した。風に揺れる旗には筆文字で氷と書かれてある。竜崎はそちらに一瞥し、こくっと首を小さく傾げた。それがまるで子犬みたいで愛らしい。これを他の人に言えば趣味が悪いと一蹴されてしまうが。
「食べたことはありません。美味しいんですか?」
「シロップの掛っているところは、美味しいですよ。わたしが一つ買ってきますから食べましょう。味は何にしますか?」
「何があるんですか?」
「苺、ブルーハワイ、メロン、レモン、練乳、抹茶、巨峰、マンゴー、パインです」
「沢山ありますね」
「かき氷ですから」
蜃気楼のように揺らめくかき海の家は、歩いて数分で着く場所にある。メニューを言えるのは、わたしがそこの常連であるからだ。小さい頃から度々ここに足を運ぶので、特別におまけをしてもらったり安くしてもらったりなど、そこの店には何かと顔が利く。
「おすすめはありますか?」
竜崎が聞いてきたので、わたしは少し考えてから口を開いた。
「苺と練乳のミックスですかね。苺の酸味が主張し過ぎないので、好きです」
「それでお願いします」
「解りました。ここまで待っててくださいね」
わたしは彼にそう言い聞かせ、背を向けた。砂浜を歩く時は常時裸足であるため、すぐに砂まみれになってしまう。爪の間にも入ってきていい気分はしないが、それでも不思議と靴を履く気にはならなかった。太陽の熱で温まった砂が足に覆い被さると、自身の熱と相まってさらに熱くなる。歩く度に砂に埋もれてしまう足を懸命に前へ進ませると、店に辿り着いた。天井には風鈴がぶら下がっていて、風が吹く度にころん、からんとガラスを鳴らす。この風鈴はいつも付いてるわけではなく、夏が過ぎれば取り下げられてしまう。その音が夏の訪れを教えてくれるのだ。
「いらっしゃい!」
溌剌とした声がわたしに投げられた。
「今日も元気ですね、
「夏なのに元気がないわけないだろう?」
からからと辺り憚らずに笑うその女性は、
「スイカかい?」
「いえ、かき氷をお願いします。練乳と苺のミックスをひとつ」
「かき氷?」
わたしの注文に安伊子さんは目を丸くした。そしてカウンターに腕を乗せ身を乗り出した。
「お前さん、かき氷嫌いだろう。どうしたんだい?」
わたしは苦笑した。よく見てるんですね。安伊子さんはいつだってそうだ。見てないだろうと思っていた部分もしっかりと見ていて、人が気にするようなものでも笑って流してしまう。懐が広く深い彼女は、わたしが小さい頃から尊敬している女性だ。
「食べさせたい人がいるんです」
そう言うと、一転し目を輝かせさっきより興味津々に質問をしてきた。
「恋人かい? 成長したねぇ、もうそんな歳か」
根も葉もない妄想に入ってしまう前に現実を伝えておこう。
「恋人ではありませんよ」
好きな人ではありますがね。すると、安伊子さんは瞬く間に表情を変え肩を落とした。はあと吐く溜息にわたしは苦笑を返す。
「がっかりしたよ、恋人じゃないなんて」
「上司ですよ」
「おやまあ、上司と二人でかい? もしかして」
「安伊子さん」
これ以上の詮索はやめて欲しいという思いを込め、言葉を遮断した。安伊子さんはその意図を汲み取り「ごめんなさいね」と笑う。
「苺と練乳のミックスよね! 少し待っててちょうだい」
「お願いします」
くるりと背を見せ、かき氷の専用機器に向き直った。ハンドルを回しながら氷を砕いていく。わたしは出来上がるそれを待つため、外に出た。やはり外は暑い。竜崎を待たせてしまっているが、大丈夫なのだろうか。倒れてはいないだろうか。男性にしては痩せ細った体を思い浮かべ、苦々しく笑う。今頃「暑いですね」とか言って機嫌を損ねてそうですね。そんな彼も見てみたいと思うのがわたしである。
「お待たせ! できたわよ」
カウンターに置かれたかき氷を見て、隣に小銭を置く。
「また来てちょうだいね」
そう笑う安伊子さんにわたしもうっすらと口角を上げた。
「はい」
赤色のシロップの上に練乳がたんまりと掛けられたかき氷には、スプーンが一つ付いていた。かき氷が入ったカップを掴んでいる指に何かが当たる。ぴらぴらとしたもの、まるで紙のような。疑問に思ったわたしは、くるりと回してそれを目にする。
「付箋ですか」
剥がしてそこに書かれてある文字を読む。川のように流れている字体だがはらうところは、折り曲がって突き出ている。癖の強い文字を読み終えると、くすりと笑みが出た。なんでもお見通しってわけですか。今頃他の客を対応しているであろう安伊子さんを思い浮かべる。あの人はほんとうに観察眼が鋭い方だ。「頑張ってね」短いが、それだけで解ってしまった。彼女はわたしの気持ちに気づいていると。彼女のにまにま顔が脳内にありありと浮かび上がってくる。小さい時から何かと隠し事してもすぐにバレてしまうが、成長してもそうだとは思わなかった。ほんのり胸が温かくなる。さて、わたしの想い人は一体何をしているのだろうか。砂浜でうずくまっていた上司を思い出して自然と歩幅が大きくなった。
「お待たせしました」
来てみれば、彼はさっきとなんら変わりないポーズで微動だにしていなかった。動くのが嫌なんだろうかなんて何度思ったことだろう。
「遅いですよ」
「すみません」
彼の隣に腰を下ろして、どうぞと突き出す。彼は目を数回瞬かせかき氷に対して首を傾けた。
「スプーンで食べるんですか?」
「はい」
「頂きます」
「感想聞かせてくださいね」
なんてわたしの言葉も耳に入っていないようだ。かき氷に意識が向いているのは、一目瞭然だ。かき氷ひとつに無防備な姿を取るとは、これがほんとうに世界の切り札なのか疑ってしまいたくなる。だが事実、彼は世界の切り札だ。かき氷にひとつに目を輝かせる様は逆に言えば一度もかき氷を見たことがないと言える。
「買って良かったですね」
彼のこんな一面も知れるのなら、嫌いなものでも好きになりそうだ。
「食べないんですか?」
「わたしは遠慮しておきます。貴方に買ってきたものですから」
「一人では食べきれません」
「解りました。わたしも食べます」
嫌いなものではあるが、残すのも気が引ける。のでわたしは渋々彼の渡したスプーンを握り、氷を掬った。口に含み噛み砕くと、氷の冷たさが口腔を満たした。わたしはこの冷たさが嫌いだ。歯がきんと痛むし、なによりも飲み込んだら、今度は喉が痛くなる。冷えにはめっぽう弱い自分は、アイスといったものは避けてきた。
「大丈夫ですか?」
顰めた表情を見て、竜崎が顔を覗き込む。なんとか飲み込んでから頷いた。
「かき氷を食べるには、少し早すぎましたね」
正午を回ってない朝に食べるには、これは冷た過ぎた。昼を過ぎた辺りからだんだんと暑くなるので、その時が食べ頃だろう。
「置いておきましょう」
「え?」
「溶けるまで待てば飲めます」
かき氷をジュースにするつもりだろうか。だが、今完食しろと言われても到底無理なのでわたしは、そうですねと頷いて傍に置いた。倒れないかと心配だったが、風は吹かない上に波も自分達の居る場所まではこない。砂浜を支えにして倒れる気配を見せないかき氷のカップに対し、そんな心配は杞憂に過ぎなかったと思う。
「海を見て、どう思いましたか? 竜崎」
膝を折り曲げ、手を膝裏に滑らせる。足の爪全てに塗られたトップコートが、綺麗に輝いている。
「人が多い時に来れば最悪ですが、少ない時に来ると悪くありません」
「そうですか」
抑揚のない低い声だが、主の言葉に胸がじんわりと温まっていく。嬉しいのだ。自分の好きなものを、想い人にも好きと言ってもらえることが。
「可笑しいことを言ったつもりはありませんが」
拗ねたかのように若干不機嫌になる彼は、笑みを零したわたしに不服らしい。
「いえ。また来ますか?」
「考えます」
「良い答えを待ってますね」
何か言いたげな視線は気づかないでおこう。
「竜崎は美術館に行ったことはありますか?」
「美術館ですか。ありません」
「では今度行きませんか?」
近くの美術館では今、とある画家の展覧会がやっていた筈だ。美術館や博物館などには頻繁に赴く。警察官を目指す前は、画家か考古学者になろうと思っていたのだ。小学生に抱いた夢は徐々に風化して、高校に上がる頃には警察官になると決めていた。何をきっかけに警察官になろうとしたかは今でも覚えているが、考古学者や画家になろうとした理由は覚えていない。きっと何かに感銘を受けたのだろう。幼少期は何事にも敏感で好奇心旺盛で、それでいて感性が豊かだ。現実などそっちのけで猪突猛進。それはそれで羨ましいと思う時がある。
「ここより静かで涼しいですよ」
子供の時にはなくて、今はあるもの。それは彼が居るか居ないかだろう。わたしはそう思う。仕事があっても金があっても、彼が居なければ誰かに惹かれることも、一生を添い遂げたいと思うことも、命を差し出そうと思うこともなかった。自然とわたしはそれらを邪魔とは思わず、逆に人間らしいんじゃないかと思って、全てを享受した。初めてだったのだ。こういった感情を抱くのは。
「楽しみにしています」
貴方の発する一言一言が、こうやってわたしの胸を満たしていくのだから、拒絶なんてできるわけがないんだ。心地の良い潮風が吹く。それはうっすらと熱をまとった頬を冷やすには、充分なものだった。