私は一度だけ、彼に問うたことがある。「何故人を裁くのか」と。その日は寒い冬の日だった。窓外はしんしんと降り積もる真っ白な雪が空から止むことなく降り続けていて、窓辺に近付いた時は下框が冷え切っていたことにびっくりして、思わず飛び退いたことも記憶に明瞭として焼き付いている。暖房に暖められた部屋でも、窓辺付近は外気の冷気が漂う。長居しては風邪を引くと思って暖炉で手を暖めることにした。ぱちぱち、と火花が暖炉内で瞬く。弾ける音も、薪の焼ける匂いも、ミルクココアが入りましたと言ったワイミーさんの優しげな声も覚えている。あの時私は、暖炉の近くにあったふわふわな椅子に座り淹れてくれたミルクココアを飲んだ。冷えた氷にお湯をかけるように、身体中が瞬く間に隅まで温かさが伝わっていく。
「ふぅ」と私は息を吐いた。ワイミーさんの淹れるミルクココアはとても甘くて私の大好物だった。マシュマロに砂糖にミルクココアの粉。とびきり甘くてとびきり温かい。だから、冬に入るとついつい一日三、四杯と頼んでしまうのも、私の苦い思い出の一つだ。私がワイミーさんの淹れてくれたミルクココアを飲んでいる傍に彼は居た。真っ黒な蓬髪に底知れぬ闇を写した黒い瞳。肌は死人のように白く、着ているT シャツの白さが目立つのが逆に不思議と思えるほど。デニムジーンズを履いたラフな格好は彼のいつものスタイルだった。私より二個下の男の子はいつも手に何かしらの分厚い本を抱えていて、それを、躓く様子もなく常に一定のペースで読み進めていくのを、私はいつしか覚えていた。だからある時ついに気になりメーターなるものが振り切って、彼に話し掛けたのだ。
「ねえ」
今思えば我ながらよく頑張った方だと思う。十数年前の過去となるが、今の私であったなら彼のような人には一切関わり合いたくないと心底思うだろう。何故なら初対面にも関わらず、彼は私に「随分回転の遅い頭をしているんですね」や「私は人の思考回路に合わせて喋るというのが苦手です」などと言って幼心の好奇心を瞬く間に萎えさせたのだから。今となれば無関心の一途を貫く私だが、あいにくと幼少期の私の性格は、売られた喧嘩は買うという負けん気の強い人格者であった。ゆえに私は愚鈍じゃないと証明するべく、あれから約二ヶ月間もの間彼に勝負を持ち掛け続けたのだ。
どんな些細なことでもバカにされた相手に負けるのは悔しいからと、嫌いで堪らなかったブロッコリーも残さず食べ、苦手だった数学やケミストリーも必死こいて勉強し、なんとか院内で上位に入るまでの実力を身につけた。だけどそれでも彼はその先をいっていた。私が必死こいて勉強した問題も、彼はまるでスプーンを持ち上げるようにさらりと解いてしまい、ブロッコリーだって顔色ひとつ変えずに咀嚼して嚥下してしまう。そう、どれだけ血を滲ませて努力しても、どれだけ苦手なことを克服しても、彼には到底及ばなかった。足元どころか存在さえ認識させるほどの人物にさえなれなかった。
だが、どういう風の吹き回しか、あれだけ何処吹く風だった彼が、自身から私に話し掛け関心を持つようになったのだ。最初の一週間は当然困惑し何か裏があるんじゃないかと疑いもした。だけどそこは子供だ。一週間も話しているうちに、敵愾心などごっそり削ぎ落とされ、終いには自分の中で友人という立ち位置にまで彼を昇格させていた。そして十二年という歳月が流れた。とうとう院を出ていなければならない歳になった私。年下の彼はあと二年の時間が残されている。十二年という間にも、あれ以来私には彼への敵愾心を再三芽生えさせることもないまま、友人としての付き合いを続けた。十八となった時には彼以上の付き合いが長く信頼を置ける友人は居ないだろうというほど、私は彼に全幅の信頼と信用を置いていた。私には、先にワイミーズハウスを卒院しイギリスの然る機密機関で解析員としてのキャリアが約束されていた。幼少期の血が滲むような努力が功を奏したのだ。彼より一足先に社会に出、そして二年後に社会へ足を踏み入れる彼に、社会人としてのあれこれを伝授するつもりだった。
彼が、ある日突然姿を消すまでは。
再び私が彼と出会う時には、彼は人を裁く仕事に身を置いていた。一室に長時間籠り、カーテンを締め切って、眼前に置かれたコンピューターに一日の半分の時間を注いだ生活を気づけば送り始めていた。真っ黒な部屋に溶け込んでしまいそうで白く浮かび上がる彼。目元には瞳と一緒の真っ黒な隈が、目のラインを沿ってできてしまっていた。ご飯を食べる時間よりも短い間部屋の外に姿を現した時、私は彼に言った。
「ねえ。なんで人を裁くの?」
その言葉に “何故あなたがそれをするのか” という意図が隠されていることなんて、彼の前では隠されてもいないに等しいだろう。これまで口にしなかった言葉でさえも彼は汲み取ってくれた。たぶんそれは彼が持つ並外れた洞察力と観察眼によるものだと思う。でなければ相手の心の言葉を汲み取るなんてむりだ。そう思うと、彼は不思議な人物と言えよう。彼ほど人の無関心で人の気持ちを汲み取り、その瞳に人と同じ強い光を宿す人は私は今まで見たことがなかった。人に興味ないだろうに、なんでそんな彼が人を裁くのかを尋ねるのは、未だに燻る好奇心というメーターが振り切った挙句の行動だった。くねぇっと湾曲を描いた背中を直そうという様子を見せるわけでもなく、限度を知らない闇の双眸が私を静かに捉えたままに、彼は口を開いた。
「私は人が作った正義を、尊び重んじているからです」
その答えはあまりにも現実味がなくて、現実像からかけ離れていて、さながら子供が、限りなく不可能に近い夢を語っているようにも見えた。だけどあまりにも平然と、そして平静に語るものだから、私は一瞬目の前の彼は何を言っているのだろうという疑問に駆られて目を瞬かせることしかできなかった。しばしの沈黙は、彼の言い分に凄いと思ったからでもなく、共感したからでもなく、また戯言などをという不快感を覚えたから黙り込んだわけでもない。ただあまりにも意外すぎて、そして似つかわしくないまでに強い意志を瞳に宿していたから、それにどう答えればいいか、その言葉は真意なのかと解らなかったゆえからきた沈黙である。だって彼はいつでも周囲の人間に興味のきの文字も示そうとはしなかった。隣に居るワイミーさんにも私にも。他者の感情がまるで理解できないといわんばかりに考慮も配慮もしない言動が日常な彼が、「正義を重んじる」と言ったのだ。しかも人間が持つものを、と。
もし目の前で肉食獣が飛び出してきたら、あなたならどうするだろう。逃げる? 恐れ戦く? はたまた立ち向かうだろうか? いいや、そのどれも人間には当てはまらない。人間は脳の処理が遠く及ばない出来事に直面した時、脳は役目を放棄する。思考を放棄し考えることをさせなくなる。私は今、まさにその状況に直面している。眼前の男の放った言葉が、私の思考を麻痺させ回路を絶たせた。だが次の瞬間私の頭は回路を復活させ言葉を理解する。そして意味が解ると同時に、その言葉は決して取り繕いの嘘でも、冗談でもないことに気が付く。そう。その一言一句はまさに彼の心そのものだったのだ。なおのこと目を見開いた。いや、それはいい。彼が人の正義に脱帽していることは、よく解った。であるならば彼の正義とは一体なんだと言うのだろう。彼が重んじる正義とは即ち “法律” 。法律は国の正義であって彼個人の正義とはなりえないだろう。そうであるならば、彼の正義とは一体なんだ? 彼が正義を愛するその深さは一体どれほどと言うのだ? その疑問はすぐに解決された。彼が姿を消すその前日の夜に。
その日は、珍しい彼からの呼び出しで、私は然る公園へ赴いていた。時間は夜の十時を回り公園で遊ぶ子供は一人も居ない。空はどっぷりと深いネイビーに覆われ月おろか星の瞬きさえ視認できないほど黒い。つんと肌を刺す冷気に身が震えた。はあっと息を吐くとうっすらとだが、確かに息が白みを帯びる。手袋でも持ってくるべきだったと後悔しつつも、だだっ広い公園の四隅にあるベンチの上に、彼は居た。相変わらず膝を抱えて座るという何度見ても慣れない奇特な座り方をしている。さすがに寒いのか、ブラックのダッフルコートを羽織っていた。だがズボンはいつものデニムジーンズだった。靴下嫌いは直っていないようで、素足にスニーカーシューズを履く。だがそれも踵は踏み潰されていた。苦笑いを浮かべながら彼の隣に腰を下ろす。背もたれに背中を預けると、冷えた鉄の温度が伝わってきて、またすぐに背筋を伸ばした。
「どうしたの?」
「私は日本へ行きます」
短い言葉だったが、彼のやろうとしていることは、すぐに解った。私は世間に興味はない。他人が死のうとそれはごくごく普通のことで、生きるという道から死へ変わっただけのことだと、そう捉えるほどまでに人に無頓着な私だった。どこでこうなったかは今は遠い昔のこと。だが形式的に私は世間の騒動を耳にする。だから日本の現状も把握していた。日本では今、“キラ” と名乗る者が犯罪者を裁いている。それは法ではなく己の剣で、だ。その手段も犯人像も解らない事件を、隣の彼は裁こうとしている。雲を掴むような話だ。さながら自身が神だとでも言わんばかりに、大々的に人を殺め自分を崇高するように誘導するキラなる人物に、この黒白は一体どこまで及ぶのだろうか。
だけどここで止めたとしても、きっと彼は私の言葉なんてするりと交わし日本へ行くのだろう。彼が私の言葉で行動を自粛したことなんて一度もないのだから。ほとほと呆れるしかない、この男には。私がどれだけ牙を向いても、どれだけ吠え狂ったとしても、視線さえ向けないほどに相手にしなかったというのに、どこ知れずの国の内情を知った途端目付きが変わり正義心をめらめらと燃やす。付き添った十二年という歳月で腐って変わってしまったのは私だけだった。彼は院に居た時から寸分違わずそのままで、私のことなど意に介さない姿も健在だった。ああ、私ってとことん相手にされない友人らしい。ならば何故ここへ呼び出したのだろう? 取るに足らない意見しか言わない友人に、何故訪日することを告げたの?
「事件を解決したらまた戻ってきます」
「イギリスに?」
「はい」
「ロンドンに?」
「はい」
「そう」
彼が再びロンドンへ帰ってくる。彼のことだ、どうせ一週間もせずに解決し私の目の前に “アカフク” と呼ばれるお菓子を携えて、顔色を変えずに「帰りました」とでも言ってくることだろう。だからさして気にしていなかった。彼が事件を解決し私の傍に居る。それがいつもの日常だから。だから少し驚いたんだ。
「なので待っていてください」
初めて彼が私を帰る居場所として認識してくれたことに。だって興味無いのかとばかり思っていたのだから。太陽が上がり沈むことが普通になって誰も興味を持たなくなるのと同じように、私が傍に居ることが当たり前になっていつか離れてしまっても、彼は気付かないだろうと決めていたから。驚いた。だけど嬉しさもあった。初めて必要とされた気がしたから。私は驚きつつも、待ってる、と言った。あの日は、嬉しさに眠りが一寸たりともやってこなかった。初めての高揚感と満足感に酔いしれたあの感覚は、今でも鮮明に覚えている。手を握れば爪が食い込むその痛みと共にあの時の感情が首をもたげる。だから私は、いつまで待てばいいのか彼に聞くのを忘れていることに気づかなかった。
あれからいくつもの月が沈み、あっという間に五年もの時間が流れた。待っていてください、と言った本人はまだ現れない。私、もう三十後半だよ。いつ帰ってくるの? 四十路手前に友人をほっぽり出すの? 私が彼と最後話した時はお互いにまだ二十前半だった。あの日の夜を、今年もまた一人で過ごさなければならなくなった。こんなに考えてしまうことならいっそのこと帰国日聞いておけば良かったと悔いたことは数しれず。だけど今年もあのベンチに座って星空を拝むんだろう、私は。未だに帰ってこない彼の姿を夜空に浮かべて、私は白い息を吐いた。私、まだ待ってるの。早く帰ってきて。
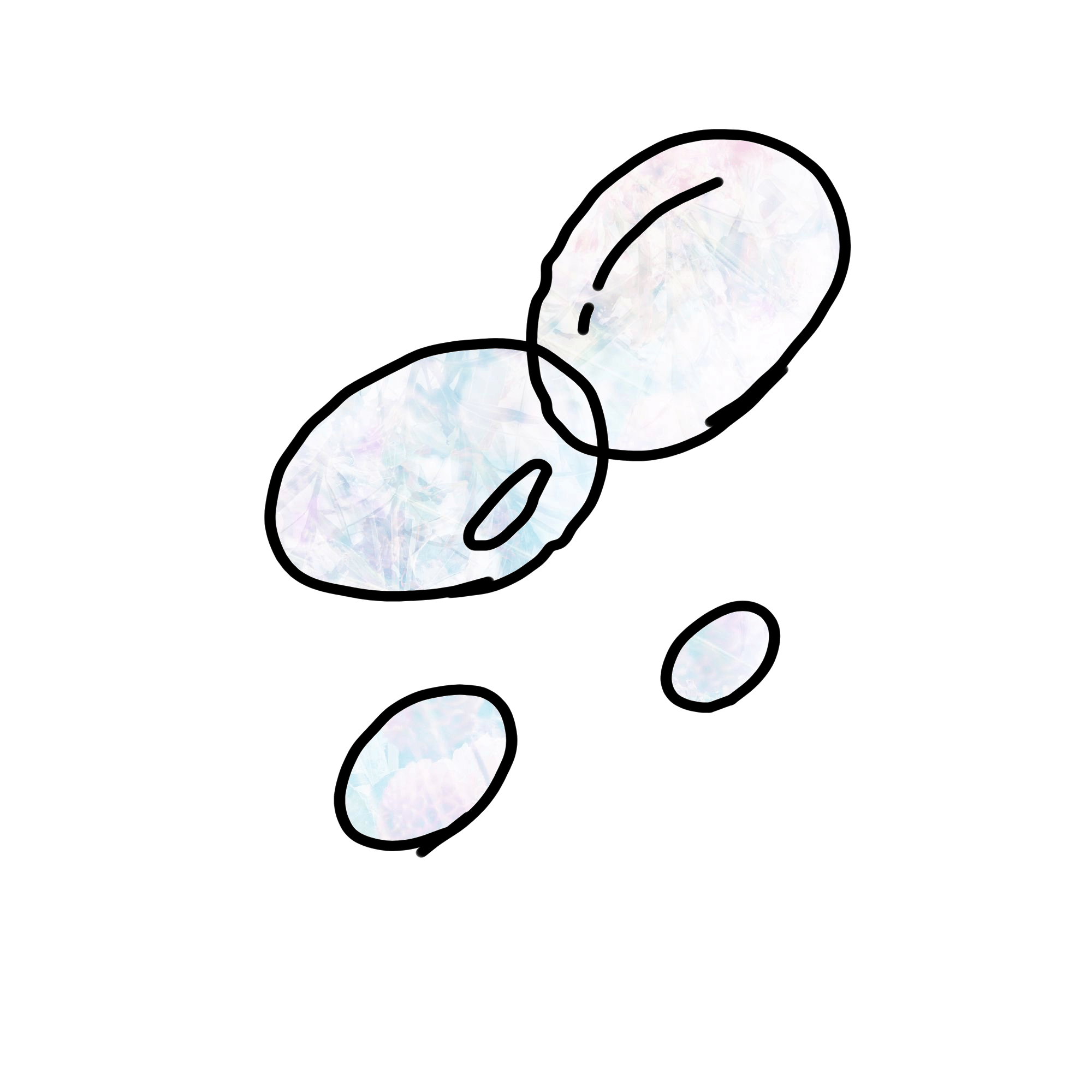
ニヒルなのは私か彼か
、