窓の向こうには冷たい世界が広がっている。グレーで塗り潰した空、止むことなく降り続ける白い細雪、ぱちぱちと点滅を繰り返して今にも消えそうな寂しい街灯。窓辺に寄り添う私の手の指からは、既に熱は奪われていた。部屋との温度差に窓が曇り下框には無数の細かい水滴が浮き出る。その冷水は、今も尚私から熱を奪っていくのであった。
はあ、と息を吐けば窓がほんのりと少しだけ白に色づく。寒いと身体が教えても退こうとは思わなかった。ただなんとなくひとりでに佇む街灯から、目を離せないのだ。蛾すら集らない街灯はまるで童話のマッチ売りの少女のよう。ひとりで温まり、ひとりで消えていく。寂しくて、切なくて。ぼんやりと視界がぼやけた時、肩に手を置かれた。
「何をしているんですか?」
窓硝子に頭を預けていた私は、のそりと重たそうに小さく動かしながら隣を見遣る。ざんばらな黒髪、目元の黒い額縁、白いシャツとジーンズ。竜崎だった。白い袖口から見えた筋肉などないと思わせる細っこい手首もまた服同様に生気を感じさせない。抑揚のない淡白とした声に私は「んー」となんて答えようか決めあぐねながら口を開いた。
「街灯を見てた」
「あれですか」
「そう。その街灯」
私が街灯を捉えるように、彼も硝子を通してそれを見た。窓に映る彼の双眸が闇夜に溶けることなくじろりと動いて私を見る。白い首は傾けられた。
「面白いですか?」
「ううん全く」
「では何故?」
「ただの気まぐれ、気分だよ」
街灯が再び瞬いた。あと少しで完全に火が消えるな、あれ。風前の灯火のような街灯を見る私の瞳は、どこか俯瞰的で冷めていた。テレビで放送される痛ましい殺人事件。それを見る時も他人事のように顎を持ち上げてふうんと一蹴する。それと一緒だ。たとえこの瞬間に灯りが消えたとしても、私は「あ、消えた」と言って窓辺から離れるだけだ。ひとりで生まれて、ひとりで消えていく可哀想でちっぽけな灯り。感じていたことや思っていたことが薄れていこうとした時、竜崎はゆくりなくこう言った。
「ここを発ちます」
静かに告げられた宣言を聞いて心臓が跳ねた。だけどそれも束の間のことで、次第にそれは落ち着きを取り戻した。呼吸も再度平静になったことで彼を見る。罪悪感を感じているわけでも、緊張しているわけでもなかった。そりゃそうか、彼に限ってそんな陳腐なものを持っているわけないか。私を見ている漆黒の双眸は固いくらい微動だにしない。瞬間悟った。いくら話してもダメだろうと。彼の意思は二束三文の気持ち程度では動かせない。ならもう、好きにさせてしまえばいいじゃないか。何も言わずに窓の向こうの灰景色に視線を移した。
「いいんじゃない? 好きにすれば」
我ながら全く可愛いげのない棘だと思った。会社の上司にどれだけ嫌がらせをされてもやんわりと流していたのに、その時の演技が今はどうにもできそうにない。背後で彼が動いたのが解った。出て行くのだろう。気配が扉に近付いたが部屋を出ていく様子がなかった。何を立ち往生しているのだろう、そう思って首を動かそうと思った時それよりも一歩早く彼がこちらに背中を向けたまま低い声を出した。
「私は、貴女のそういうところ結構好きですよ」
とんでも爆弾をひとつ落として彼は部屋を出て行った。ぱたん、と扉が閉まる音が部屋に寂しく響く。なんて物を置いて行ってくれたんだあの人は。私のことなんてむしろ嫌いだと思ってた。だって彼の出立に猛反対してたから。嫌い、いや失望したのだと。幼稚な私のワガママに愛想が尽きたと。でも彼は。喉が迫り上がってくる言い知れぬ何かによってきつく絞めあげられているように息苦しい。心臓から沸騰したお湯にも負けない熱い血が流れるのが解る。感情が溢れる目頭を抑えて、内心切望するように祈った。
お願い、帰ってきて。
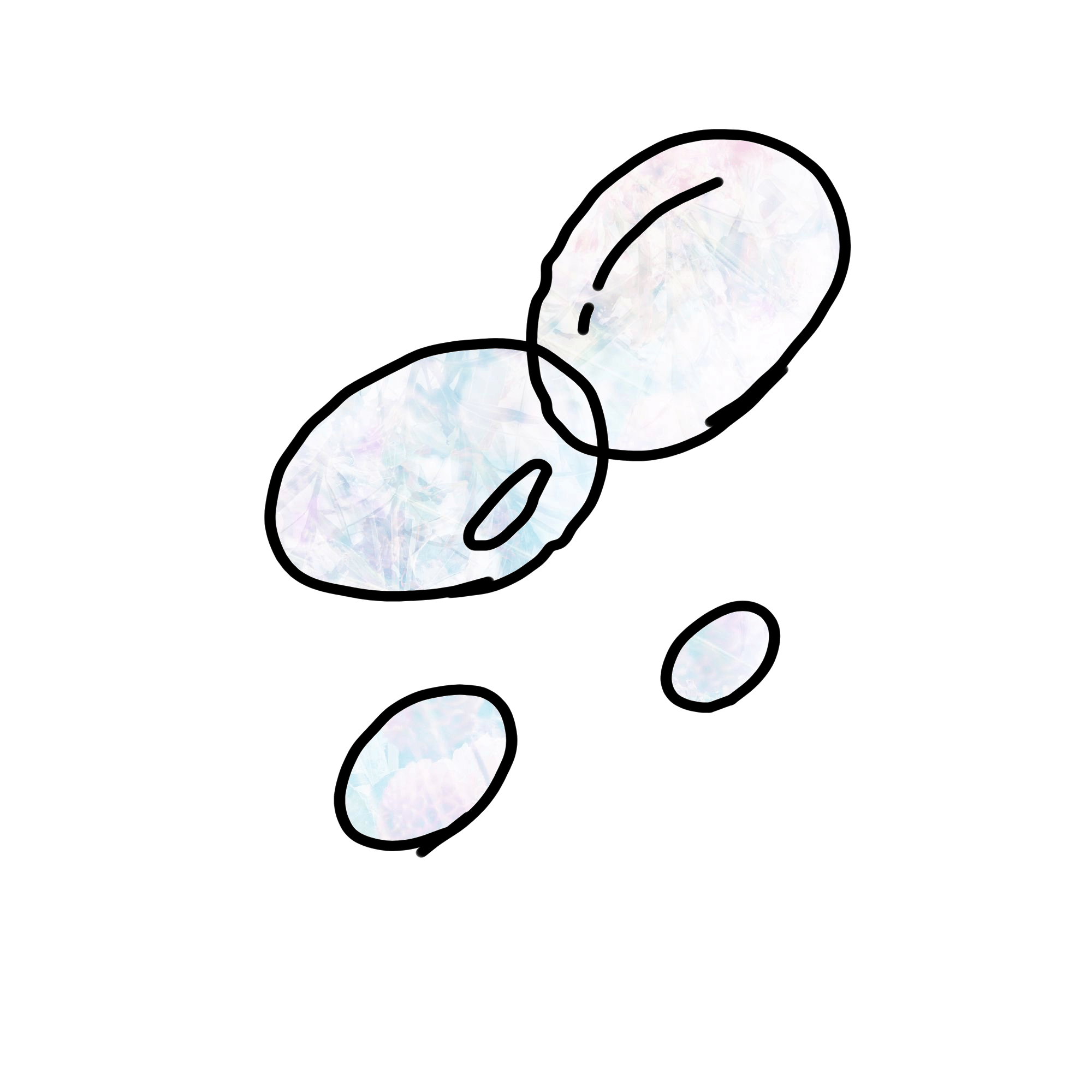
置いて行かれたマッチ売りの少女
、