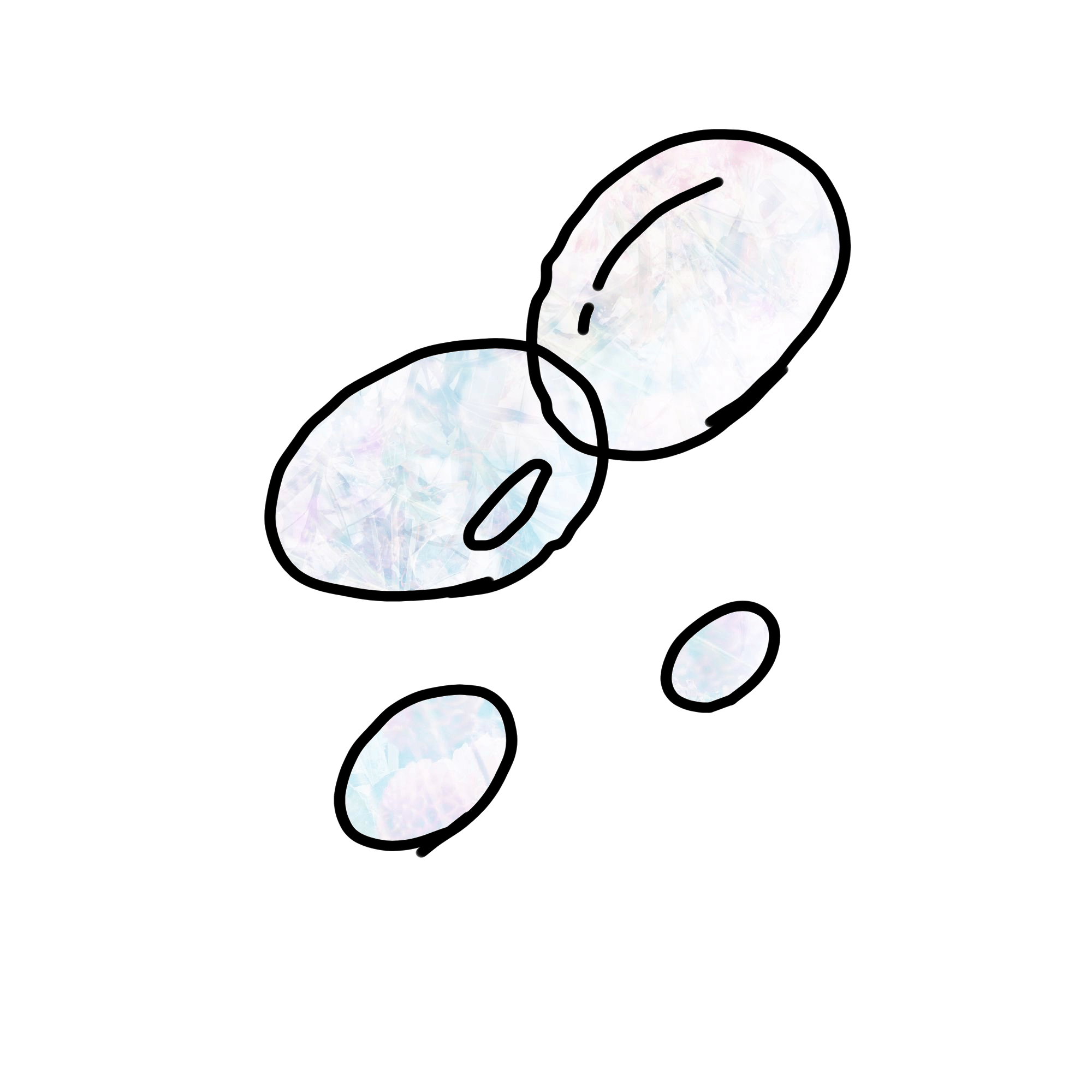「っと、いけないいけない。電話しないとだった」
くっつく一ミリのところで瞼を弾かせた。なけなしの余力を使い切ったといわんばかりに眠気という強敵が足音を立てて近づいてくるが、負けじとベッドから足を放り出してサイドテーブルに置かれたひとつの携帯を手にする。黒色の折り畳み式の携帯。スマホが主流となった現代ではもはやオーパーツとさえ呼べる物で、テンキーに馴染んだ私の指はたまに折り畳み式の携帯のパネルに行き場を失ってしまうことがある。だけど手放さないのはこれをくれた人との唯一の繋がりだから。カーテンを締め、電気を付けない暗い部屋で光るディスプレイは、瞳に強烈な痛みを与える。電気を付けるのも億劫と感じた私は脇目を振らずに番号のパネルを夢中に押していく。携帯を耳に宛がった。
「出るかな」
虚しい沈黙が胸に小さな針穴を開けて広げていく。少しづつ、少しづつ、滲むように。純白のシーツに穿つ一点の異物が己を主張するように。流れるはずの呼出音が反応しないことが降って湧いた焦燥に火を点ける。携帯を変えたのだろうか。番号を変えたとか。いや、忙しくて出れないかもしれない。どくん、心臓が嫌な波を立たせる。何か遭ったのかも。彼にとって良くないことに。もしかして生命に関わることかもしれない。私は彼の今の私生活を知らないし、彼も踏み込ませない。メロみたいに頭の回転は良くないし、知識量だって彼からしたら赤子同然の程度かもしれない。だけど彼が危ないことをしているだろうということは鈍物と言われた私でも気づける。お願い、出て、メロ。携帯を握る手に力が入る。するとプルルと呼出音が鳴った。その音に初めて胸を撫で下ろすことができた。ほっ、と息を吐くのも束の間。すぐにそれは途切れた。
「メロ!」
『名前か』
ぶっきらぼうな声が耳に届いて、呆れられると解っていても「本物だ!」と逸る嬉しさを抑えることはできなかった。案の定携帯から鼻で嗤笑するのが聞こえてきた。
『ニセモノによろしく言っておけ、俺と同じ番号は使うなとな』
「すぐに出ないメロが悪いと思う」
『お前みたく暇人じゃないからな』
「私だって暇人じゃないんだけど? 一年振りなんだから開口一番に言うことは『久しぶり』とか相手を褒めるでしょーよ」
『なんで盆暗を褒めないといけないんだ』
「盆暗じゃないし! ハウスでも上位だったじゃん私!」
『過去の話持ち出すなよ、ガキか』
「中学生に言われたくないですー」
『誰が中学生だ猪女』
「誰が猪だ」
傍らに大人が居たら「子供だな」と失笑されてしまうこと間違いなしの会話に自分が堪らず噴き出してしまった。ハウスではニアに次ぐ天才と言われたメロがこんな会話してるなんて、同期たちは想像もつかないだろうな。肩を揺らして笑う私の耳に「いつまで笑ってんだ猪女」の言葉が届く。
「メロは変わらないなーと思って」
私と粗探しの水掛け論をするところも、木で鼻を括った態度も、だけど年に一度の電話に律儀に出てくれるところも私が知るメロと全く変わらない。ハウスのメロしか知らない私にとってそれは胸が掬われるくらい嬉しくて安心できるのだ。私を知る者が居て、私が知る者が居る。たとえ年に一度しか話せなくても。
『それを言うならお前もだろ』
「私?」
『人の誕生日を毎年祝うなんざ物好きでもない限りやらないだろ』
「じゃあ私物好きでいいや」
『おい』
「いいじゃん、私メロの誕生日祝いたいし」
ハウスの時は「執拗い」だの「鬱陶しい」だの「必要ない」だの言ってやらせてくれなかったのだから、ハウスを出た今は嫌がられても存分に祝ってやるんだ。出なかったら着信履歴百件いれてやるんだから。呆れる溜息ごときで私の意思は吹き飛ばせないのである。
「メロ」
『なんだ』
「HappyBirthday!」
あなたの傍に居れなくても、私はずっとずっと支えていることを忘れないで。呆れながらもどこか嬉しげな笑い声がひとつ、携帯から漏れた。健勝が続く一年でありますように。
**
HappyBirthday Mihael Keehl!
2020.12.13.
2020.12.13.