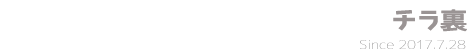体育祭
二回戦
ヒロ×サイ|top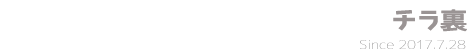
二回戦
二回戦、第一試合・緑谷対轟戦が始まる少し前。
麗日が目を腫らして席に戻ってきた。
「目を潰されたのか!!! 早くリカバリーガールの元へ!!」
真面目過ぎるからこその見当違いな飯田の発言に麗日は手で目元をこすって誤魔化す。
「あの……あんまり擦んないほうがいいかも、あとできたら冷やして、ね?」
前を通り過ぎていく麗日が痛々しく見えて西岐は声をかけていた。
つい最近目を腫らした経験のある西岐には他人事には思えなかったのだ。
西岐が今言った台詞は、熱の下がらなかった三日間オールマイトから度々かけられた言葉だった気がする。
「あ、そうだよね。ありがとうね、れぇくん」
「ううん」
ぱっと目元から手を放す麗日が親しげに自分の名前を呼ぶのを聞いて、あまり話したことはなかったけれどそれだけで急に親しみを感じていた。
「それはそうと悔しかったな……」
「今は悔恨よりこの戦いを己の糧とすべきだ」
「タシカニ……」
敗退してしまった麗日の悔しさに沿うように飯田がポツリとこぼす。
西岐も思わずつられて悔しさを滲ませるが常闇の冷静な言葉が意味もなく落ち込みかけた気持ちを払拭した。
麗日も常闇の言葉に頷き真剣な眼差しを競技台に向ける。
「そうだよね、悔やんでてもしょうがないよね」
いつぞやの自分に言い聞かせるように遠くへと言葉を投げた。
常闇がこちらを向く。
「とこやみくんってすごく冷静でいいな」
自分には全くない要素だ。後ろを振り返って劣等感に苛まれて自分の殻に籠りがちになる西岐には冷静に前を見据える考え方はいつだって新鮮に思える。
「……そうでもない」
「ホントニソウデモナイヨ」
ストレートに放った言葉に少し擽ったそうにする常闇の脇からニュッとダークシャドウが顔を出す。
「うるさい」
「れぇチャント話シテルト心ノ中デギャーギャー言ッテル」
「……うるさい」
一度引っ込んだものの大人しくしているのが嫌になったのか影を伸ばし、常闇から遠い西岐の右肩に乗っかって擦り寄るダークシャドウ。
その言動に常闇は頭を抱える。
「常闇くん、この試合どう見る?」
一連の流れを見ていなかった飯田が常闇に問いかける。
常闇にとってはそれが冷静さを取り戻す助けとなったのか、短く息を吐いて飯田のほうに向きなおる。
「緑谷が轟の懐に飛び込めるかどうかだな」
「うん……、あの氷結、デクくんどうするんだ」
近接格闘を得意とする緑谷に対して轟は中・遠距離戦闘タイプ。勿論轟は近距離にも対応できるスキルはそれなりにあるが緑谷の超パワーを前にしては出来るだけ懐には入らせたくないだろう。
逆に緑谷は攻防兼ねる氷結を前に近寄れなければ勝利が見えてこない。
『今回の体育祭、両者トップクラスの成績!! まさしく両雄並び立ち、今!! 緑谷バーサス轟!!』
プレゼントマイクの紹介に無数の興味の目が競技台に集中する。それでなくてもエンデヴァーの息子の試合だ。観衆の注目度は高い。
戦いの火蓋が切られる。
開始瞬間に走る氷。
構える緑谷の中指が弾かれ巨大な氷を粉砕した。
あまりの威力に会場中を突風が吹き抜け、身体を押された轟が背面に氷を張り凌ぐ。
あの氷を打ち破るのは凄いが色の変わった中指を見てそれが自損覚悟だということが分かる。戦闘訓練やUSJで個性を発揮した後、腕や足がバキバキになっていたのを思い出す。
彼もまた多大なリスクと引き換えの個性のようだ。
二度目の氷結、人差し指での粉砕。
指を一本ずつ犠牲にしていくつもりか。
西岐の見舞いに訪れた時に緑谷は言っていた、自分に心配をさせろと。そういうのならこの戦い方はどうなのだ。
三度目の氷結、薬指での粉砕。
「ゲッ、始まってんじゃん!」
切島が観戦席に駆け戻ってくる。
「お! 切島、二回戦進出やったな!」
「そうよ、次おめーとだ爆豪! よろしく!」
「ぶっ殺す」
「ハッハッハ、やってみな」
明るく軽快な切島の声にその場の空気が軽くなり聞くでもなく耳を傾ける。
「……とか言っておめーも轟も強烈な範囲攻撃ポンポン出してくるからなー……」
「しかもタイムラグなしでな」
確かに爆豪や轟のあの広範囲対応可能な個性は"ズルい"と思っても仕方ないくらい対抗策を叩きのめしてくる。悔しげに言う切島とそれに同意する瀬呂の話を聞きながら脳裏に先程の特大爆破を思い浮かべていた。
すると、いつもの喚き散らすものではなく落ち着いた冷静な爆豪の声が反論する。
「ポンポンじゃねぇよ、ナメんな」
「ん?」
「筋肉酷使すりゃ筋繊維が切れるし走り続けりゃ息切れる。"個性"だって身体機能だ、奴にも何らかの"限度"はあるハズだろ」
西岐は耳だけでなく身体ごと爆豪のほうへ向いていた。
失礼ながら爆豪がそういうことを考えていることに驚いているのだ。直感や本能で動くタイプと思っていたが結構考えるタイプなのかもしれない。
「考えりゃそりゃそっか……じゃあ緑谷は瞬殺マンの轟に……」
切島は爆豪の言い分に納得すると競技台の二人に視線を向けた。
「――耐久戦か、すぐ終わらせてやるよ」
轟がそういうなり巨大な氷の壁が緑谷に迫っていく。
右手の残り一本、小指が粉砕する。
が、すぐさま氷の柱を伸ばしてそれを駆けのぼる轟。
左手で対応する緑谷。
氷が粉砕すると共に轟が飛びあがる。
轟の拳が地面にぶつかるや否や鋭い刃のような氷が地面から突き上げる。打撃と氷結を同時に食らってしまえばひとたまりもないだろう。
寸でのところで避ける緑谷を轟の氷結が許さない。
勢いよく迫り緑谷の足を捉えた、と思った時、今までにない衝撃が氷結を薙ぎ払った。代わりに左腕が色を変えてぶらりと垂れ下がる。
「……腕が」
西岐は思わず口元を手で覆った。
一瞬、USJでの相澤の姿と重なってしまった。
「れぇチャン……」
気配を察したのかダークシャドウが頬に擦り寄ってくる。
気遣わしげに常闇が肩を軽く叩いた。
会場をざわめきが包み込む。至るところでエンデヴァーの息子に対する高い評価が囁かれる。
先程の威力を警戒してなのか接近戦には持ち込まずあくまで得意の遠距離戦、とどめとばかりの氷結が緑谷に向かって走る。
もう緑谷には反撃する"手"が残っていないはずだった。
けれど氷は再び砕かれる。
壊れたはずの指で。
「震えてるよ、轟くん」
痛みからか絞り出すような緑谷の声。
「"個性"だって身体機能の一つだ、君自身冷気に耐えられる限度があるんだろう……!? で、それって左側の熱を使えば解決できるもんなんじゃないのか……?」
痛みに息を詰めながらそれでもその壊れた指を折り曲げていく。
歪な音が"聞"こえてくる。
「みんな……本気でやってる、勝って……目標に近付く為に……っ、一番になる為に! 半分の力で勝つ!? まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。……――全力でかかって来い!!」
曲げた指を力強く握りこむ。
緑谷の言葉が轟を揺さぶっていく。
避けたはずの近距離戦を轟はあえて試みる。近くからなら氷結を防げないとでも思ったのだろうか。
足を踏み出す轟の懐に緑谷が素早く入り込む。
自らの氷結により轟の動きが鈍くなっているのは明らかだ。
緑谷の拳が轟の身体を吹き飛ばす。
場外までに至らなかったということは加減が出来たのかもしれない。しかしそもそもが散々痛めつけた手だ、ダメージがないわけない。
拳が砕けきって握れなくなれば今度は口を使って親指を弾く。
西岐は口を押さえたまま両目を眇める。きちんと見て糧にしたい、けれどとても見ていられない。
どうして……、
「何でそこまで……」
西岐の疑問と轟の声が重なる。
「期待に応えたいんだ……! 笑って、応えられるような……カッコイイ人になりたいんだ!!」
両手が砕けて使えなくても全身で轟に向かっていく。
体当たりで突き飛ばす。
「だから全力で! やってんだ、みんな! 君の境遇も君の決心も僕なんかに計り知れるもんじゃない……でも……」
よろけながらもけして倒れない、目の前の轟をまっすぐに見据える。
「全力も出さないで一番になって完全否定なんてフザけるなって今は思ってる!」
どうして緑谷の言葉が、行動がこれほどに心を揺さぶるのか。
体に霜を張り付けながら何度も氷結を繰り出す轟の頑なさ。食いしばって解けない口。
彼にも積み重ねてきたものがあるのだろう。聞かされた轟の生い立ちや親子関係の話は西岐にも計ることのできないものだろう。
無理やり冷たく凍らせているのは彼の心。
それを全力で打ち砕く、緑谷の叫び。
「君の! 力じゃないか!」
赤く熱いものが駆け巡る音を聞いた気がした。
轟の目が、忘れていたつもりになっていた情熱の色を映していた。
炎が吹きあがる。
「あああ……デクくん……なんてすごいの」
あんなにガチガチに冷え切っていたものに火をつけてしまうなんて……。
会場の冷えた空気が一気に熱される。
感極まったのかエンデヴァーの激励が響き渡る。
轟の身体に纏わりついていた霜が剥がれて汗のように肌を流れる。
二人が同時に構え、轟の氷結、そしてセメントスのセメントとミッドナイトの眠り香が競技台を縦横に走る。
最大威力の氷結をなぞるように左の炎が熱していく。
冷気と熱気が渦を巻き、膨張した空気が壁となったセメントを噛み砕きながら会場を螺旋状に吹き荒れた。
西岐が手のひらをかざして突風を凌いでいると、ダークシャドウが飛んでくる破片を弾いて庇ってくれる。
「大丈夫か」
「うん、ありがとう」
「褒メテ褒メテ」
「よくやったダークシャドウ」
咄嗟に見せる守備力の高さとキャラクターのギャップが激しく、対応しきれないでいると常闇の手が伸びてダークシャドウを撫でる。ダークシャドウもそれはそれで満足らしく風が治まるなり西岐の肩に戻った。
蒸気なのか土埃なのかわからない白いモヤで競技台の状態が全く見えない。
次第にモヤが晴れて入場ゲートに程近い壁に打ち付けられた緑谷の身体が崩れるのが見えた。
「緑谷くん……場外。轟くん――……三回戦進出!!」
観戦席にどよめきと歓声が入り混じる。
担架で運ばれる緑谷を見て飯田たちが立ち上がり階段を駆け上がっていく。
「クロくんごめんね」
肩のダークシャドウをおろし西岐も飯田たちに続く。
本当なら瞬間移動で行けたが、緑谷と常日頃から仲良くしている飯田たちを差し置いて一番に様子を見に行くのは気が引けたのだ。
リカバリーガールの出張保健所の扉を開け飛び込んでいく彼らの後ろから緑谷を伺う。
両腕を布でぐるぐる巻きにされ、固定された足も変色している。
こういうのを満身創痍というのだろうか。
手術するというリカバリーガールに早々に追い出され、見てしまった怪我の状態だけが頭にこびりつく。
あれだけの怪我と引き換えに轟の情熱を取り戻したというのか。
轟を救ったのだろうか。
飯田たちと離れ西岐は一人廊下を歩いていた。
次の次に自分の試合が控えているということもあるし、何より観戦で動揺している自分を落ち着かせたかったからだ。
体育祭に参加していく中でいろいろな感情が内に溢れてくるのを感じていた。
今まで知らずにいた、負けたくないという気持ち、ヒーローになりたいという熱い情熱、誰かを救おうとまっすぐに向かっていく者に対する憧れ……、その裏側にある卑屈さ。
普通にしていればそんなものが生まれることもなかったし、あっても気付かずやり過ごせたはずだ。けれどもう、西岐はヒーローになりたいと思ってしまった。一年前のあの時の気持ちをなかったことにすることはもうできない。
静かな廊下の真ん中で深呼吸を繰り返した。
さて控え室にでも居ようかと身を翻した西岐の目の前にいつの間にかオールマイトに匹敵する体躯の持ち主、エンデヴァーが立ち塞がっていた。
テレビのニュースで見たことはあるし先程観戦席から激励を飛ばしていたのも見た。
だが間近で見るエンデヴァーはやはりプロヒーローの迫力を纏っている。
気圧されて思わず後退っていた。
そのままもう一度反対を向いて走り去ろうかと思った西岐の手をエンデヴァーが捉える。
「君の個性は本当に個性か?」
「……え?」
問いかけの意味が分からず疑問符だけを返す。
「もう一つ、名前があったりするのではないか?」
今度は何も言葉にならなかった。
エンデヴァーの質問の意図が分からず困惑の眼差しでただ見上げる。
「親は?」
「……いません」
「身内は?」
「叔父がいます」
「西岐は叔父の姓か?」
「たぶん、そうだと思います」
答えながらまるで警察の尋問のようだと思った。
なぜ初めて会ったばかりの他人にここまで聞かれないといけないのか疑問に思いながらも律儀に答えていると競技場からアナウンスが聞こえてくる。
どうやら第二試合が終わり自分の出番が来てしまったようだ。
エンデヴァーもそれを察したのか追及をやめ、西岐の手を離した。
「あの、それじゃ俺いくので、すみません」
お辞儀をして入場ゲートまでの廊下を急いで走る。
自分を落ち着かせるための時間だったはずなのに跳ね上がってしまっている心臓を手で押さえた。
例によってプレゼントマイクに大袈裟な紹介をされつつ競技台に立つ西岐と常闇。
先程の動揺がいまだ拭えていないが、強敵の一人である常闇とその個性であるダークシャドウを前にして少しずつ頭が冷えていく。
ほとんど死角がなく広範囲に渡る守備と底なしの攻撃力。普通に戦っていれば当然勝ち目はない。
というより、西岐にはほかに選択肢はない。
先手必勝以外やれることがない。
スタートが切られると同時に背後へと瞬間移動する。背中に手を張り付け、再び移動する前に手首に力を込めて常闇に抑制をかけた。
ダークシャドウを警戒してまずは動けなくしようというのだ。
しかし、
「甘いな」
常闇の一言共に西岐は横っ腹にダークシャドウの一撃を食らっていた。
「――ッな!?」
軽い西岐の身体ではたった一撃でも場外に吹き飛びかねない。ダメージを堪え空中で瞬間移動し元の場所に降り立つ。
確かに抑制は発動していたはずだ。それでもダークシャドウは動けてしまうというのか。戦闘訓練ではダークシャドウにも効果があったと思うが、西岐の抑制を一度食らっている常闇は対策をしてきたのかもしれない。
つまり常闇が微動だに出来なくても別口でダークシャドウが動けてしまうのだろう。
ノーモーションでの攻撃というものの脅威を感じていた。
すかさずダークシャドウが向かってくる。
瞬間移動で距離を詰め常闇に手を伸ばすがすぐにダークシャドウが西岐を捉え弾く。
駄目だ、これでは近づけない。仮に触れられたとしてもかえって攻撃を食らい場外になる可能性が増すだけ。
先程まで仲良く戯れていたダークシャドウがこれほどまでに厄介な対戦相手になるとは。
攻撃を避けながら何ができるのか何が有効なのか考える。
「……得意じゃないんだけどなぁ」
弾き出された答えに前髪の内側で眉を寄せた。
けれど今は常闇とダークシャドウさえ視界に入れていればいい。
ゆっくり息を吸い、肺にためた空気を出来るだけで細く少なくゆっくり唇の隙間から吐き出す。
それと同時に常闇に向かって走った。
西岐の動きに合わせてダークシャドウが手を振りかぶる。
食らう前に背後へ移動するが、それも素早く反応されダークシャドウに弾かれる。
距離をとっては背後を狙い弾かれるを繰り返す。
だが、本当の西岐はダークシャドウから遠く離れ正面から常闇の肩に触れていた。
常闇の足はもう場外ラインの一歩手前にある。
そして一押し。
「常闇くん場外!! 西岐くん三回戦進出!!」
『おいおいどうしたんだよ常闇は! 急に動かなくなっちまってあっさり場外、いったいどうなってんだァ!!? なぁおいイレイザー!!』
「知らん」
ミッドナイトの判定が下り、プレゼントマイクが困惑を大声で撒き散らし、相澤も理解できていないことを隠す気もなく一刀両断する。
それらを聞きながら観衆もまた何が起きたのか分からずしんと静まり返っている。
これほど反応しづらい試合もないだろう。
最後、常闇とダークシャドウの中では確かに西岐と戦っていた。それはあくまで幻影の中での話。常闇に向かっていく西岐は途中から幻影にすり替わっていて、反撃している常闇やダークシャドウを含めてすべて彼らが見ている幻影に過ぎず、常闇はただ棒立ちになり歩いて向かってくる西岐に攻撃も防御も一切することなく場外まで連れていかれたのだ。
「……ごめん」
幻影を解き常闇を開放すると、常闇は何が起きたかわからないまま突然敗退を告げられ混乱した表情を浮かべる。
「今のは……、…………もしかしてUSJのときのあれか」
「おお、さすがとこやみくん、正解、あれです」
「そうか」
「れぇチャンオメデト、ワーイ」
混乱しながらも冷静に状況を把握しようとしているのだろう。一度幻影を目の当たりにしたことのある彼は長考の末、USJの時のことに思い至ったらしい。
悔しげな常闇をよそに、敗退したというのにテンション高く巻き付いてくるダークシャドウに西岐は顔をほころばせた。
試合を終え観客席に戻ろうと廊下を歩いていた。
廊下の先に見慣れぬ男性が立っていたが構わず通り抜けようとして声をかけられる。
「お久しぶりです、れぇ様」
まるで会ったことがあるというような口振りで西岐の名を呼ぶ。
しかし見覚えはない。
会ったことなどないはずだ。
仕立てのよさそうなスーツに身を包み銀縁の丸メガネをかけた、どこか胡散臭そうな笑みを浮かべる柔和な顔立ちの男。
彼は西岐に向かって恭しくお辞儀をしてみせ、そしてこう名乗った。
「私、暗間でございます」
あ、と小さな声で反応する。
暗間とは叔父の秘書だ。生活のことやいろんな局面で必要になる保護者関連など入用になった時、教えられている電話で連絡を取るが、それ以外では接触したことがなく顔を見るのはこれが初めてだ。
叔父の秘書というから勝手にある程度の年齢を想像していたが随分若い。30代前後だろうか。
「あの……えっと、はじめましてれぇです」
奇妙な挨拶だと思った。
向こうはこちらを知っていてこちらは相手を全く知らない。
「あ、の……どうして」
この場にいるのか、すべてを言葉にせずとも理解して受け取ったらしい。
暗間は少し首を右に傾け目を細める。優しい言葉遣いで語って聞かせるように答えた。
「もちろん叔父上様の指示で参りました。れぇ様のこれまでのご活躍を拝見し叔父上様に報告しておりますよ」
ドクンと胸が波打つ。
頬が熱くなる。
「叔父さんが? 俺を? そうなんだ……」
嬉しさが声に表情に滲む。
これまで一度たりとも西岐に対して関心の片鱗さえ見せなかった叔父が、急に自分に何か興味を抱いたというのか。
もしかしたら自分から何かしようとしたことが叔父の気持ちを動かしたのではないか。
実力を知ってもらえたらもっと喜んでもらえるのではないか。
そんな想像が頭の中に膨らむ。
「ですが、この後の試合でれぇ様には負けていただきたいのです」
呆気なく、幸せな想像は砕かれる。
「叔父上様はあなたの活躍を望んでおられません」
暗間の物言いはあくまで優しく丁寧で、西岐は自分が何か聞き間違えているのではないかという錯覚さえ覚えた。耳に入った言葉と理解している意味を取り違えているのではないかと。
けれど暗間は繰り返し言う。
「いいですね、負けてください」
遠くで試合終了のアナウンスが響いていた。
麗日が目を腫らして席に戻ってきた。
「目を潰されたのか!!! 早くリカバリーガールの元へ!!」
真面目過ぎるからこその見当違いな飯田の発言に麗日は手で目元をこすって誤魔化す。
「あの……あんまり擦んないほうがいいかも、あとできたら冷やして、ね?」
前を通り過ぎていく麗日が痛々しく見えて西岐は声をかけていた。
つい最近目を腫らした経験のある西岐には他人事には思えなかったのだ。
西岐が今言った台詞は、熱の下がらなかった三日間オールマイトから度々かけられた言葉だった気がする。
「あ、そうだよね。ありがとうね、れぇくん」
「ううん」
ぱっと目元から手を放す麗日が親しげに自分の名前を呼ぶのを聞いて、あまり話したことはなかったけれどそれだけで急に親しみを感じていた。
「それはそうと悔しかったな……」
「今は悔恨よりこの戦いを己の糧とすべきだ」
「タシカニ……」
敗退してしまった麗日の悔しさに沿うように飯田がポツリとこぼす。
西岐も思わずつられて悔しさを滲ませるが常闇の冷静な言葉が意味もなく落ち込みかけた気持ちを払拭した。
麗日も常闇の言葉に頷き真剣な眼差しを競技台に向ける。
「そうだよね、悔やんでてもしょうがないよね」
いつぞやの自分に言い聞かせるように遠くへと言葉を投げた。
常闇がこちらを向く。
「とこやみくんってすごく冷静でいいな」
自分には全くない要素だ。後ろを振り返って劣等感に苛まれて自分の殻に籠りがちになる西岐には冷静に前を見据える考え方はいつだって新鮮に思える。
「……そうでもない」
「ホントニソウデモナイヨ」
ストレートに放った言葉に少し擽ったそうにする常闇の脇からニュッとダークシャドウが顔を出す。
「うるさい」
「れぇチャント話シテルト心ノ中デギャーギャー言ッテル」
「……うるさい」
一度引っ込んだものの大人しくしているのが嫌になったのか影を伸ばし、常闇から遠い西岐の右肩に乗っかって擦り寄るダークシャドウ。
その言動に常闇は頭を抱える。
「常闇くん、この試合どう見る?」
一連の流れを見ていなかった飯田が常闇に問いかける。
常闇にとってはそれが冷静さを取り戻す助けとなったのか、短く息を吐いて飯田のほうに向きなおる。
「緑谷が轟の懐に飛び込めるかどうかだな」
「うん……、あの氷結、デクくんどうするんだ」
近接格闘を得意とする緑谷に対して轟は中・遠距離戦闘タイプ。勿論轟は近距離にも対応できるスキルはそれなりにあるが緑谷の超パワーを前にしては出来るだけ懐には入らせたくないだろう。
逆に緑谷は攻防兼ねる氷結を前に近寄れなければ勝利が見えてこない。
『今回の体育祭、両者トップクラスの成績!! まさしく両雄並び立ち、今!! 緑谷バーサス轟!!』
プレゼントマイクの紹介に無数の興味の目が競技台に集中する。それでなくてもエンデヴァーの息子の試合だ。観衆の注目度は高い。
戦いの火蓋が切られる。
開始瞬間に走る氷。
構える緑谷の中指が弾かれ巨大な氷を粉砕した。
あまりの威力に会場中を突風が吹き抜け、身体を押された轟が背面に氷を張り凌ぐ。
あの氷を打ち破るのは凄いが色の変わった中指を見てそれが自損覚悟だということが分かる。戦闘訓練やUSJで個性を発揮した後、腕や足がバキバキになっていたのを思い出す。
彼もまた多大なリスクと引き換えの個性のようだ。
二度目の氷結、人差し指での粉砕。
指を一本ずつ犠牲にしていくつもりか。
西岐の見舞いに訪れた時に緑谷は言っていた、自分に心配をさせろと。そういうのならこの戦い方はどうなのだ。
三度目の氷結、薬指での粉砕。
「ゲッ、始まってんじゃん!」
切島が観戦席に駆け戻ってくる。
「お! 切島、二回戦進出やったな!」
「そうよ、次おめーとだ爆豪! よろしく!」
「ぶっ殺す」
「ハッハッハ、やってみな」
明るく軽快な切島の声にその場の空気が軽くなり聞くでもなく耳を傾ける。
「……とか言っておめーも轟も強烈な範囲攻撃ポンポン出してくるからなー……」
「しかもタイムラグなしでな」
確かに爆豪や轟のあの広範囲対応可能な個性は"ズルい"と思っても仕方ないくらい対抗策を叩きのめしてくる。悔しげに言う切島とそれに同意する瀬呂の話を聞きながら脳裏に先程の特大爆破を思い浮かべていた。
すると、いつもの喚き散らすものではなく落ち着いた冷静な爆豪の声が反論する。
「ポンポンじゃねぇよ、ナメんな」
「ん?」
「筋肉酷使すりゃ筋繊維が切れるし走り続けりゃ息切れる。"個性"だって身体機能だ、奴にも何らかの"限度"はあるハズだろ」
西岐は耳だけでなく身体ごと爆豪のほうへ向いていた。
失礼ながら爆豪がそういうことを考えていることに驚いているのだ。直感や本能で動くタイプと思っていたが結構考えるタイプなのかもしれない。
「考えりゃそりゃそっか……じゃあ緑谷は瞬殺マンの轟に……」
切島は爆豪の言い分に納得すると競技台の二人に視線を向けた。
「――耐久戦か、すぐ終わらせてやるよ」
轟がそういうなり巨大な氷の壁が緑谷に迫っていく。
右手の残り一本、小指が粉砕する。
が、すぐさま氷の柱を伸ばしてそれを駆けのぼる轟。
左手で対応する緑谷。
氷が粉砕すると共に轟が飛びあがる。
轟の拳が地面にぶつかるや否や鋭い刃のような氷が地面から突き上げる。打撃と氷結を同時に食らってしまえばひとたまりもないだろう。
寸でのところで避ける緑谷を轟の氷結が許さない。
勢いよく迫り緑谷の足を捉えた、と思った時、今までにない衝撃が氷結を薙ぎ払った。代わりに左腕が色を変えてぶらりと垂れ下がる。
「……腕が」
西岐は思わず口元を手で覆った。
一瞬、USJでの相澤の姿と重なってしまった。
「れぇチャン……」
気配を察したのかダークシャドウが頬に擦り寄ってくる。
気遣わしげに常闇が肩を軽く叩いた。
会場をざわめきが包み込む。至るところでエンデヴァーの息子に対する高い評価が囁かれる。
先程の威力を警戒してなのか接近戦には持ち込まずあくまで得意の遠距離戦、とどめとばかりの氷結が緑谷に向かって走る。
もう緑谷には反撃する"手"が残っていないはずだった。
けれど氷は再び砕かれる。
壊れたはずの指で。
「震えてるよ、轟くん」
痛みからか絞り出すような緑谷の声。
「"個性"だって身体機能の一つだ、君自身冷気に耐えられる限度があるんだろう……!? で、それって左側の熱を使えば解決できるもんなんじゃないのか……?」
痛みに息を詰めながらそれでもその壊れた指を折り曲げていく。
歪な音が"聞"こえてくる。
「みんな……本気でやってる、勝って……目標に近付く為に……っ、一番になる為に! 半分の力で勝つ!? まだ僕は君に傷一つつけられちゃいないぞ。……――全力でかかって来い!!」
曲げた指を力強く握りこむ。
緑谷の言葉が轟を揺さぶっていく。
避けたはずの近距離戦を轟はあえて試みる。近くからなら氷結を防げないとでも思ったのだろうか。
足を踏み出す轟の懐に緑谷が素早く入り込む。
自らの氷結により轟の動きが鈍くなっているのは明らかだ。
緑谷の拳が轟の身体を吹き飛ばす。
場外までに至らなかったということは加減が出来たのかもしれない。しかしそもそもが散々痛めつけた手だ、ダメージがないわけない。
拳が砕けきって握れなくなれば今度は口を使って親指を弾く。
西岐は口を押さえたまま両目を眇める。きちんと見て糧にしたい、けれどとても見ていられない。
どうして……、
「何でそこまで……」
西岐の疑問と轟の声が重なる。
「期待に応えたいんだ……! 笑って、応えられるような……カッコイイ人になりたいんだ!!」
両手が砕けて使えなくても全身で轟に向かっていく。
体当たりで突き飛ばす。
「だから全力で! やってんだ、みんな! 君の境遇も君の決心も僕なんかに計り知れるもんじゃない……でも……」
よろけながらもけして倒れない、目の前の轟をまっすぐに見据える。
「全力も出さないで一番になって完全否定なんてフザけるなって今は思ってる!」
どうして緑谷の言葉が、行動がこれほどに心を揺さぶるのか。
体に霜を張り付けながら何度も氷結を繰り出す轟の頑なさ。食いしばって解けない口。
彼にも積み重ねてきたものがあるのだろう。聞かされた轟の生い立ちや親子関係の話は西岐にも計ることのできないものだろう。
無理やり冷たく凍らせているのは彼の心。
それを全力で打ち砕く、緑谷の叫び。
「君の! 力じゃないか!」
赤く熱いものが駆け巡る音を聞いた気がした。
轟の目が、忘れていたつもりになっていた情熱の色を映していた。
炎が吹きあがる。
「あああ……デクくん……なんてすごいの」
あんなにガチガチに冷え切っていたものに火をつけてしまうなんて……。
会場の冷えた空気が一気に熱される。
感極まったのかエンデヴァーの激励が響き渡る。
轟の身体に纏わりついていた霜が剥がれて汗のように肌を流れる。
二人が同時に構え、轟の氷結、そしてセメントスのセメントとミッドナイトの眠り香が競技台を縦横に走る。
最大威力の氷結をなぞるように左の炎が熱していく。
冷気と熱気が渦を巻き、膨張した空気が壁となったセメントを噛み砕きながら会場を螺旋状に吹き荒れた。
西岐が手のひらをかざして突風を凌いでいると、ダークシャドウが飛んでくる破片を弾いて庇ってくれる。
「大丈夫か」
「うん、ありがとう」
「褒メテ褒メテ」
「よくやったダークシャドウ」
咄嗟に見せる守備力の高さとキャラクターのギャップが激しく、対応しきれないでいると常闇の手が伸びてダークシャドウを撫でる。ダークシャドウもそれはそれで満足らしく風が治まるなり西岐の肩に戻った。
蒸気なのか土埃なのかわからない白いモヤで競技台の状態が全く見えない。
次第にモヤが晴れて入場ゲートに程近い壁に打ち付けられた緑谷の身体が崩れるのが見えた。
「緑谷くん……場外。轟くん――……三回戦進出!!」
観戦席にどよめきと歓声が入り混じる。
担架で運ばれる緑谷を見て飯田たちが立ち上がり階段を駆け上がっていく。
「クロくんごめんね」
肩のダークシャドウをおろし西岐も飯田たちに続く。
本当なら瞬間移動で行けたが、緑谷と常日頃から仲良くしている飯田たちを差し置いて一番に様子を見に行くのは気が引けたのだ。
リカバリーガールの出張保健所の扉を開け飛び込んでいく彼らの後ろから緑谷を伺う。
両腕を布でぐるぐる巻きにされ、固定された足も変色している。
こういうのを満身創痍というのだろうか。
手術するというリカバリーガールに早々に追い出され、見てしまった怪我の状態だけが頭にこびりつく。
あれだけの怪我と引き換えに轟の情熱を取り戻したというのか。
轟を救ったのだろうか。
飯田たちと離れ西岐は一人廊下を歩いていた。
次の次に自分の試合が控えているということもあるし、何より観戦で動揺している自分を落ち着かせたかったからだ。
体育祭に参加していく中でいろいろな感情が内に溢れてくるのを感じていた。
今まで知らずにいた、負けたくないという気持ち、ヒーローになりたいという熱い情熱、誰かを救おうとまっすぐに向かっていく者に対する憧れ……、その裏側にある卑屈さ。
普通にしていればそんなものが生まれることもなかったし、あっても気付かずやり過ごせたはずだ。けれどもう、西岐はヒーローになりたいと思ってしまった。一年前のあの時の気持ちをなかったことにすることはもうできない。
静かな廊下の真ん中で深呼吸を繰り返した。
さて控え室にでも居ようかと身を翻した西岐の目の前にいつの間にかオールマイトに匹敵する体躯の持ち主、エンデヴァーが立ち塞がっていた。
テレビのニュースで見たことはあるし先程観戦席から激励を飛ばしていたのも見た。
だが間近で見るエンデヴァーはやはりプロヒーローの迫力を纏っている。
気圧されて思わず後退っていた。
そのままもう一度反対を向いて走り去ろうかと思った西岐の手をエンデヴァーが捉える。
「君の個性は本当に個性か?」
「……え?」
問いかけの意味が分からず疑問符だけを返す。
「もう一つ、名前があったりするのではないか?」
今度は何も言葉にならなかった。
エンデヴァーの質問の意図が分からず困惑の眼差しでただ見上げる。
「親は?」
「……いません」
「身内は?」
「叔父がいます」
「西岐は叔父の姓か?」
「たぶん、そうだと思います」
答えながらまるで警察の尋問のようだと思った。
なぜ初めて会ったばかりの他人にここまで聞かれないといけないのか疑問に思いながらも律儀に答えていると競技場からアナウンスが聞こえてくる。
どうやら第二試合が終わり自分の出番が来てしまったようだ。
エンデヴァーもそれを察したのか追及をやめ、西岐の手を離した。
「あの、それじゃ俺いくので、すみません」
お辞儀をして入場ゲートまでの廊下を急いで走る。
自分を落ち着かせるための時間だったはずなのに跳ね上がってしまっている心臓を手で押さえた。
例によってプレゼントマイクに大袈裟な紹介をされつつ競技台に立つ西岐と常闇。
先程の動揺がいまだ拭えていないが、強敵の一人である常闇とその個性であるダークシャドウを前にして少しずつ頭が冷えていく。
ほとんど死角がなく広範囲に渡る守備と底なしの攻撃力。普通に戦っていれば当然勝ち目はない。
というより、西岐にはほかに選択肢はない。
先手必勝以外やれることがない。
スタートが切られると同時に背後へと瞬間移動する。背中に手を張り付け、再び移動する前に手首に力を込めて常闇に抑制をかけた。
ダークシャドウを警戒してまずは動けなくしようというのだ。
しかし、
「甘いな」
常闇の一言共に西岐は横っ腹にダークシャドウの一撃を食らっていた。
「――ッな!?」
軽い西岐の身体ではたった一撃でも場外に吹き飛びかねない。ダメージを堪え空中で瞬間移動し元の場所に降り立つ。
確かに抑制は発動していたはずだ。それでもダークシャドウは動けてしまうというのか。戦闘訓練ではダークシャドウにも効果があったと思うが、西岐の抑制を一度食らっている常闇は対策をしてきたのかもしれない。
つまり常闇が微動だに出来なくても別口でダークシャドウが動けてしまうのだろう。
ノーモーションでの攻撃というものの脅威を感じていた。
すかさずダークシャドウが向かってくる。
瞬間移動で距離を詰め常闇に手を伸ばすがすぐにダークシャドウが西岐を捉え弾く。
駄目だ、これでは近づけない。仮に触れられたとしてもかえって攻撃を食らい場外になる可能性が増すだけ。
先程まで仲良く戯れていたダークシャドウがこれほどまでに厄介な対戦相手になるとは。
攻撃を避けながら何ができるのか何が有効なのか考える。
「……得意じゃないんだけどなぁ」
弾き出された答えに前髪の内側で眉を寄せた。
けれど今は常闇とダークシャドウさえ視界に入れていればいい。
ゆっくり息を吸い、肺にためた空気を出来るだけで細く少なくゆっくり唇の隙間から吐き出す。
それと同時に常闇に向かって走った。
西岐の動きに合わせてダークシャドウが手を振りかぶる。
食らう前に背後へ移動するが、それも素早く反応されダークシャドウに弾かれる。
距離をとっては背後を狙い弾かれるを繰り返す。
だが、本当の西岐はダークシャドウから遠く離れ正面から常闇の肩に触れていた。
常闇の足はもう場外ラインの一歩手前にある。
そして一押し。
「常闇くん場外!! 西岐くん三回戦進出!!」
『おいおいどうしたんだよ常闇は! 急に動かなくなっちまってあっさり場外、いったいどうなってんだァ!!? なぁおいイレイザー!!』
「知らん」
ミッドナイトの判定が下り、プレゼントマイクが困惑を大声で撒き散らし、相澤も理解できていないことを隠す気もなく一刀両断する。
それらを聞きながら観衆もまた何が起きたのか分からずしんと静まり返っている。
これほど反応しづらい試合もないだろう。
最後、常闇とダークシャドウの中では確かに西岐と戦っていた。それはあくまで幻影の中での話。常闇に向かっていく西岐は途中から幻影にすり替わっていて、反撃している常闇やダークシャドウを含めてすべて彼らが見ている幻影に過ぎず、常闇はただ棒立ちになり歩いて向かってくる西岐に攻撃も防御も一切することなく場外まで連れていかれたのだ。
「……ごめん」
幻影を解き常闇を開放すると、常闇は何が起きたかわからないまま突然敗退を告げられ混乱した表情を浮かべる。
「今のは……、…………もしかしてUSJのときのあれか」
「おお、さすがとこやみくん、正解、あれです」
「そうか」
「れぇチャンオメデト、ワーイ」
混乱しながらも冷静に状況を把握しようとしているのだろう。一度幻影を目の当たりにしたことのある彼は長考の末、USJの時のことに思い至ったらしい。
悔しげな常闇をよそに、敗退したというのにテンション高く巻き付いてくるダークシャドウに西岐は顔をほころばせた。
試合を終え観客席に戻ろうと廊下を歩いていた。
廊下の先に見慣れぬ男性が立っていたが構わず通り抜けようとして声をかけられる。
「お久しぶりです、れぇ様」
まるで会ったことがあるというような口振りで西岐の名を呼ぶ。
しかし見覚えはない。
会ったことなどないはずだ。
仕立てのよさそうなスーツに身を包み銀縁の丸メガネをかけた、どこか胡散臭そうな笑みを浮かべる柔和な顔立ちの男。
彼は西岐に向かって恭しくお辞儀をしてみせ、そしてこう名乗った。
「私、暗間でございます」
あ、と小さな声で反応する。
暗間とは叔父の秘書だ。生活のことやいろんな局面で必要になる保護者関連など入用になった時、教えられている電話で連絡を取るが、それ以外では接触したことがなく顔を見るのはこれが初めてだ。
叔父の秘書というから勝手にある程度の年齢を想像していたが随分若い。30代前後だろうか。
「あの……えっと、はじめましてれぇです」
奇妙な挨拶だと思った。
向こうはこちらを知っていてこちらは相手を全く知らない。
「あ、の……どうして」
この場にいるのか、すべてを言葉にせずとも理解して受け取ったらしい。
暗間は少し首を右に傾け目を細める。優しい言葉遣いで語って聞かせるように答えた。
「もちろん叔父上様の指示で参りました。れぇ様のこれまでのご活躍を拝見し叔父上様に報告しておりますよ」
ドクンと胸が波打つ。
頬が熱くなる。
「叔父さんが? 俺を? そうなんだ……」
嬉しさが声に表情に滲む。
これまで一度たりとも西岐に対して関心の片鱗さえ見せなかった叔父が、急に自分に何か興味を抱いたというのか。
もしかしたら自分から何かしようとしたことが叔父の気持ちを動かしたのではないか。
実力を知ってもらえたらもっと喜んでもらえるのではないか。
そんな想像が頭の中に膨らむ。
「ですが、この後の試合でれぇ様には負けていただきたいのです」
呆気なく、幸せな想像は砕かれる。
「叔父上様はあなたの活躍を望んでおられません」
暗間の物言いはあくまで優しく丁寧で、西岐は自分が何か聞き間違えているのではないかという錯覚さえ覚えた。耳に入った言葉と理解している意味を取り違えているのではないかと。
けれど暗間は繰り返し言う。
「いいですね、負けてください」
遠くで試合終了のアナウンスが響いていた。
create 2017/10/29
update 2017/10/29
update 2017/10/29