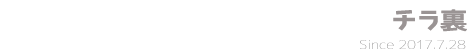林間合宿
辿り着け
ヒロ×サイ|top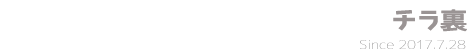
辿り着け
結局あの後もずっと家から一歩も出してもらえず、終業式にも出席しないまま夏休みへと突入し、障子が届けてくれたショッピングモールでの購入品と履きなれた靴と持っている中で一番大きなカバンで旅支度を済ませ、合宿初日を迎えた。
久しぶりの外、楽しみにしていた林間合宿、初めてのバスでの長距離移動。
「西岐は俺の隣だ」
わくわくしてバスに乗り込むと、あれから全く機嫌の直っていない相澤が無情にも隣の席を叩いて座るように促してくる。クラスメイトに囲まれワイワイと過ごすのを楽しみにしていただけに、最前列の担任の隣は物凄く切ない。
あからさまに悲しげな表情を浮かべても、相澤はポンポンと席を叩いている。
どれだけ信用を失ってしまったのかと己の行動を悔いながら従う。
発車すると間もなく、相澤の説明などそっちのけで賑やかになっていく車内。音楽を流してみたり、しりとりをしてみたり、ものすごく楽しそうにしている。後ろを振り返ると誰かがポッキーを持って皆に分けているのが見える。とても羨ましい。
「ポッキーちょうだい」
思わず口に出してしまうが全く届いていない。
「ねぇ、ポッキーをちょうだいよ」
もう一度声をかけてみるが賑やかなみんなの声に負けて誰にも届いていかない。大体にして聞こえていたとしても担任の横に座る西岐のところまでわざわざ誰かが持ってきてくれる気もしない。
バスの中で食べるお菓子も楽しみにしていたものの一つなのだが、買い物にさえ出かけられなかった西岐に入手手段はなく、日々の買い物は相澤がしてくれていたが、ずっと不機嫌なままの相澤にお菓子を買ってきてくれとは頼めなかった。
みんなの様子を見るのはやめてしょんぼりと前を向く。と、西岐の膝に三つの箱が置かれた。クッキーとチョコとキャラメル、西岐の好きなお菓子だ。
相澤は頬杖を突き、相変わらず目を据わらせ、じっと見つめてきている。
箱を開け、個装の袋を破ってチョコを口に含む。
「おいしい……」
口の中で解けていく甘さに顔が綻ぶ。
すっと相澤の手が伸びてきて前髪に触れてくる。あれ以来、死柄木に"崩され"不揃いになった前髪に相澤は度々触れては苛立ちを滲ませた。
そういえばヒーロー殺しに顔を傷つけられた時も傷をなぞっては似たような顔をしていたなと思い出す。
「今後は……心配かけないようにします」
「そうしてくれ」
ため息交じりに相澤がそう言うのと同時にバスが停車した。
降り立ったのはパーキングではなく不自然なほど見通しのいい空き地だった。
柵の向こうは切り立った崖になっており、緑の森と、はるか先には山が連なって見える。
先に到着していたらしい協力者、プロヒーローであるワイルド・ワイルド・プッシーキャッツにより宿泊施設が山のふもとにあると説明される。
告げられる距離と時間、どうして今ここに降り立ったのか、クラスメイトたちがざわざわとしはじめる。
「12時半までに辿り着けなかったキティはお昼抜きね」
嫌な予感から逃れるべくバスに戻ろうとするクラスメイトたちに追い打ちの言葉がかかり、足元がボゴボゴと波打った。かと思うと一気に盛り上がりクラスメイトたちを巻き込んで傾 れていく。
襲い掛かる土砂の質量は想像以上に重く、咄嗟に抜け出すことも出来ぬまま崖下へと運ばれてしまう。
自力で宿泊施設まで来いという話だ。
突然の洗礼に戸惑いながら泥から這い出ると、すぐ目の前に現れたのは土くれで出来た魔獣。
それに向かって迷わず飛び出したのは飯田・緑谷・轟・爆豪だった。
なるほど、"これ"が至る所にいて行く手を阻むというわけか、と彼らの背後で観察する。
しかし出された課題は"倒せ"ではなく"辿り着け"。であればなんら問題はない。
マンダレイが指さした方向をじっと"視"る。建物が密集していたりすると探し出すのが困難になり得るが、ここは森の中。建物があれば目立つ。木々をすり抜け山のふもとを目指して視線を巡らせる。
そして見えた『マタタビ荘』の文字。
「ぱっ」
例によって小さく呟くと"視"えていた景色へと一瞬で移動した。
相澤とワイルド・ワイルド・プッシーキャッツの二人と幼い少年が到着したのは、西岐が宿泊施設に辿り着いてから数時間経った頃だった。
「……おそい」
「わあ、すごいね君」
「もう着いたの! 優秀!」
すっかり待ちくたびれた様子の西岐に、ピクシーボブとマンダレイは目を丸くして驚きつつも褒めてくれる。
相澤は西岐の到着は想定内だったらしく、顔を合わせるなりフンと鼻を鳴らした。
久しぶりに見た相澤の満足げな様子に嬉しくなる。
「さて、俺たちは飯にしますか」
「そうしようそうしよう」
「お昼ご飯はベーコンカリカリ丼定食だよー!」
お昼ごろに着くだろうと言っていた言葉とは裏腹に生徒たちを待つ気はないらしく、外のテーブルに配膳していくプッシーキャッツの二人と、それを手伝う目つきの悪い少年、洸汰。
「あ、俺が持っていくよ」
すまし汁のお椀の乗ったトレーを小さな体で運ぶのを見てそれを上から受け取る。
不意を突かれて見開いた目が、西岐を捉えるとキッと鋭くなり、警戒心と敵意が剥き出しの目は誰かを彷彿とさせる強さがあって思わずたじろいでしまう。
大人しく席に座り、相澤と共にいただきますと手を合わせる。
ベーコンカリカリ丼定食の名にふさわしく、カリカリに焼かれたベーコンと半熟卵がご飯に乗せられていた。
「……おい」
どんぶりの中をじっと見ていると相澤から声がかかる。
西岐の眉尻が情けなく下がる。
「ほら」
差し出された相澤の器にベーコンを移していく。
「え? もしかしてベーコン嫌いなの?」
「すみません、肉全般食べられないんです、こいつ」
マンダレイの問いかけに相澤が答える横で申し訳なさそうに身を縮める。折角用意してもらって好き嫌いするのは申し訳ないのだがどうしても食べられないのだ。
ベーコンだけでなく半熟卵も相澤の方へと移し、海苔とご飯だけの状態になってから箸をつけ始める。
「……軟弱な奴だな」
正面に座っていた洸汰が辛辣に言い放つ。
「そうなの、なさけない」
苦笑いを浮かべて肯定すると再び虚をつかれたらしく大きな目で西岐を見つめ、誤魔化すようにケッと吐き捨てた。
そうして食事を済ませ、相澤とプッシーキャッツの二人は生徒たちの動向に意識を戻す。
西岐も森の方へ目を向けてみると、昼も過ぎたというのにまだまだだいぶ遠いところにいるのが"視"えた。足場の悪さと無尽蔵に沸いてくる土魔獣が、体力と個性を削っていっているようで、辿り着くまでまだだいぶかかりそうだ。
生徒全員が宿泊施設に到着したら食事、その後入浴で就寝の予定らしい。つまり早く着いたところでやることはなく、まだ当分暇を持て余すらしい。
ただぼんやり待つのも退屈なので食事の片づけをしている洸汰の手伝いをすることにした。
食器を調理場に持っていき、洗い物を始めた洸汰の隣に立つ。
「洗ったやつ、拭いて片付けていくね」
声をかけるが無視されてしまう。
機嫌が悪いのか嫌われているのか判断がつかないが、断られなかったのでせっせと食器を拭いていく。五人分の食器はあっという間に拭き終わり、洸汰が鍋などの大きなものを洗っている間に棚へと戻していく。
が、西岐は大概要領が悪い。
高い場所に置こうとして手が滑った。
「わ、わ、わわ」
受け止めようと手を動かすが指先で弾いてしまい派手な音を立てて床に落ちる。
強化ガラスでできているらしいそれは何とか割れずに原形を留めていて、西岐はほっと息をついた。
「……すみません、もう一回洗ってください」
情けない声で食器を差し出すと、何だこいつと言わんばかりの目が向けられてより一層居心地が悪くなる。手伝うと言って手間を増やしているのだから仕方ない。
「お前、本当にヒーローになりたいのかよ。なんかいちいち世話が焼ける」
「え……うん、すみません」
呆れたように言いながら食器を受け取って洗い直す。今度は自分で拭いて棚に戻した。西岐に任せたら割られると思ったのかもしれない。こんな小さな子にまで世話が焼けると言われてしまっては、さすがに自覚せざるを得ない。
洗い物もあらかた終わって手持無沙汰となり、調理場の丸椅子に腰かけた。
「こうたくんは……ヒーロー嫌い?」
問いかけるとギロッと鋭い目が突き刺さる。
「でもほら俺ぜんぜんヒーローっぽくないでしょ、例外ってことでよくないかな?」
ヒーローという言葉を前にした時の嫌悪感、それはひしひしと伝わっていた。どういう背景があるかもわからないし、どうこうしてやれるなんて思ってもいない。ただ一週間も過ごすこの場で嫌悪を向けられたままなのはなんとなく嫌だった。
「いいわけないだろ」
まあそう簡単にいくわけはないのだけれど。
分かっていたがきっぱり言われてしまうと心が萎えてしまう。
「――ったく、しょうがねえなあ」
洗い終えたばかりの鍋をコンロに置き、調理台にまな板と包丁を用意する。勝手口に置かれた大量の野菜の箱と米の袋のいくつかを調理台の近くへと運びながら心底仕方なさそうに言う。
「これからマンダレイと俺で40人分の飯を作るんだ、手伝え」
その偉そうな指示はつまり少しは許容してくれたということなわけで、西岐は嬉しそうに破顔するのだった。
日も傾きはじめる午後五時二十分。
マンダレイと洸汰と西岐で全員分の夕食を用意できた頃、漸く1-A全員が宿泊施設マタタビ荘に辿り着いた。その様はまさしく満身創痍で、瞬間移動でさっさと到着してしまったことを申し訳なく思ってしまうほどだ。
西岐と同じく緑谷も洸汰の存在が気になってしまったらしく、挨拶しようとして強烈な一撃を食らう。
それを相澤は茶番と一蹴し、荷物を運ぶよう指示をして今日のスケジュールを伝える。本日のやることは食事と入浴、そして就寝のみ。本格的な合宿のスタートは明日からだということ。
指示のまま荷物を部屋に運び終えるとA組B組が一堂に会して食事が始まる。昼食抜きで魔獣の森を駆け抜けてきたクラスメイトたちがものすごい勢いで掻き込んでいく。西岐は飲み物や汁物のお代わりを運んでテーブルを行き来する。一人昼食を摂っていたのもあって申し訳ない気持ちから給仕を買って出たのだ。
「ご飯足りてる? おかわりあるよ」
「れぇ、良い嫁になれるぜ!」
「むしろ嫁になってくれ!」
土鍋で炊いたご飯を喜んでいた切島と上鳴に声をかけると、謎の言葉と共に茶碗が差し出される。障子が小さく咳き込みつつも同じく空いた茶碗を差し出した。
男子も女子も大いに食べ、食事を終える頃には山盛りだった皿もすっかり綺麗になっていた。手伝いをした身としては、これほど満足そうに平らげてもらうのは気持ちがいいものだ。
「西岐、手伝いもその辺にしないと風呂の時間がなくなるぞ。というか飯は食ったんだろうな」
ブラドキングとの打ち合わせが終わって食堂に顔を出した相澤がいまだに片づけを手伝っている西岐を見て眉を寄せた。
自分の食事を忘れていた西岐は、口を『あ』の状態に開いてしばし固まる。
相澤の目が思案げに漂う。
「まあ……風呂は俺らの時間に一緒に入ってもいいが」
「ううん、俺もみんなと入ってくる。……こうたくん後はお願いね、ごめんね」
何か含んで呟く相澤に、そういうわけにはいかないと首を横に振った。一人別行動なのはもう散々だ。
舌打ちを背後に聞きながら急いで部屋に行き、着替えとお風呂セットを片手に浴場へと足早に向かった。
「わあー……これが温泉……!」
浴場に入るとそこは露天の温泉で、雑誌やテレビで見たことはあれど実際目にするのは初めてで、感慨深く見渡した。クラスメイトたちはすでにくつろぎお湯を楽しんでいるらしい。
流し場で髪と体を流してから湯船へと足を向ける。
すると……。
「西岐っ」
「ばかれぇっ」
障子と爆豪がタオルを広げて飛んできた。
「タオルくらい巻け!!」
爆豪は顔を真っ赤にして怒りながら西岐の腰にタオルを巻きつける。
何故かさらにその上からタオルを巻きつける障子の顔も赤く表情は険しい。
「エチケットだ、巻いておけ」
どうやら恐らく暗黙の了解のようなエチケットらしい。よく見れば確かにみんな腰にタオルを巻いている。納得して頷くと二人が安堵の息を吐いた。
改めて湯船に近付き、足先からゆっくりとお湯に入っていく。
少し熱めのお湯がじわじわと沁みてくる。
「はあああ……これが温泉かあああ……」
うっとりと顔が綻ぶ。
「……西岐、少しでいいから自覚した方がいいよ」
困ったような声で話しかけてくるのは尾白。意味を汲み取れずにいるとスッと隣を指さした。その先には何故か湯に顔を浸している常闇がいる。
それでも尾白の言いたいことが分からず何が不味いのかと悩んでいる西岐の頬を、轟がガシッと両側から手で挟んで自分の方へと引き寄せた。
「大丈夫、西岐は可愛い」
「……とどろきくん?」
覗き込んでくる轟の顔は先程の爆豪たちに負けず赤い。
双眸がどこか陶然としている。
何が大丈夫なのか分からないし顔がやたら近い。
手のひらで頬を挟みながらその指先が濡れた髪を絡めて擽る。
「よーし待て待て轟、ここは公共の施設だぞー」
「よーしのぼせちまったか、向こうで休もうなー」
バシャバシャとお湯を跳ねさせながら二人の間を割って入ってくる切島と砂藤。二人がかりで轟を西岐から剥がし、だいぶ離れた端の方へと引きずって行ってしまう。
「のぼせたならお湯から出たほうが……」
「違う、違うよ、西岐」
確かにだいぶのぼせていそうだったと思いながら介抱する二人へ声をかけるが、隣の尾白は首を振って脱力する。
「とこやみくんものぼせた?」
ずっとお湯に顔を浸している常闇へそっと近づくと肩を大きく跳ねさせた。
顔を浮上させ西岐を一瞥して勢いよくお湯に顔を鎮める。
「だ、大丈夫? 運ぶ?」
「……闇が暴走しそうだ、放っておいてくれ」
顔を背けてお湯から浮かせてそういうと西岐から距離をとっていってしまった。
気にならないといえば嘘になるが、まあいいかと気持ちを切り替えてお湯に浸かる。温泉の成分のせいか白く濁ったお湯がとろっと身体に纏わりつくようで心地いい。
ただ、やけに背後が騒がしい。何やら峰田と飯田が騒いでいるらしい。
壁の上から洸汰の声がして振り返ると、ちょうど峰田と洸汰が落下するのが目に飛び込んできた。
「――あ、ぶないっ」
咄嗟に飛び出した緑谷が洸汰を、西岐は峰田をキャッチしていた。洸汰は気絶してしまったらしく脱衣場へと緑谷が連れて行く。一方の峰田は落下のショックからか西岐にしがみついて剥がれない。
「くっそー、俺の癒しは西岐のまな板ちっぱいしかないのか。男のくせにすべすべしやがってチクショウ!!!」
いつぞやのように胸に擦り寄る峰田。
温泉だというのにその場の空気が一気に凍り付く。それはもう本当に文字通り。浴場の床の一部に氷が張っている。
更にボンッとニトロが弾ける音が響く。
「ばかれぇ、さっさとあがってろ」
ドスの利いた声に威圧され、すくみあがる。しかし、貼りついている峰田はどうすれば……と迷っていると、ダークシャドウが峰田を咥えて引き剥がした。
「あ、あの、じゃあ俺は、これで」
その場にいる者たちの視線に押されるようにして浴場を後にした。
温泉があるとマンダレイから聞いて楽しみにしていたのだが、あまりゆっくり堪能できなかったなと残念に思いながら、部屋着に着替えるのだった。
就寝前の自由時間、西岐は女子の部屋に呼ばれていた。
お菓子を食べながらお喋りしようということだ。
手招きされて芦戸と耳郎の間に入る。
「そんじゃそんじゃ、恋バナだ!」
「まじか」
「ベタね」
芦戸が拳を振り上げ提案すると耳郎と蛙吹、そして麗日もほんのりと頬を染めた。
「でもそれはお付き合いしていたり好きな相手がいたりすることが前提ですわ、芦戸さんはそういう方がいらっしゃいますの?」
「そうそう、三奈ちゃんは好きな人いるの?」
八百万と葉隠からブーメランが返ってきて芦戸はグゥと言葉を詰まらせる。
みんなのやり取りを聞きながら西岐は持ってきたクッキーの箱を開いて小分けになった袋をそれぞれの前に置いていく。丸くなって座る真ん中にはすでにポテトチップスやポッキーなどが置かれ手を付けた後がある。西岐は『ポッキーだ』と過剰反応し手を伸ばす。
「そんじゃそんじゃ、1-Aなら誰が好き? 誰が一番いいと思う? これでいこう!」
「……どうしても恋バナがしたいんやね」
ポリポリとポッキーをかじっている間に決まったらしい。
ゴリ押しした芦戸のテンションが上がっていく。
「言い出しっぺの三奈ちゃんからよ」
「おっけ! 私が一番好きなのはぁー……れぇちゃん!!」
再び拳を振り上げ勢いよく言い放たれた名前にポッキーを持った手が止まる。
誰の名前が出るのかと身構えていた女子たちが弾かれるようにズルいと一斉に声を上げる。
「なにそれ、それならウチの好きな人もれぇちゃんだよ」
「私もですわ!」
「私もれぇちゃんが好きよ」
「そしたら全員好きなのはれぇちゃんってなことで!」
「そんなの恋バナにならないよ!」
会話のほとんどを聞き流していたが突然自分の名前を一斉に連呼されて、流石の西岐も何事かと耳を傾ける。何か怒らせることでもしたかと思ったが違うらしい。
好きという単語がしっかり聞こえた。
話の脈絡は分からずとも好意は純粋に嬉しい。
「俺も、みんな好きだよぉ」
だからつい顔が綻んでしまう。
「わああ……まぶしいぃ」
「れえちゃんってほんといい子」
麗日が眩し気に目を細め、耳郎はまるで幼子にするような感じで西岐の頭を撫でる。西岐が心地よさげに目を細めると、騒がしかった室内が一旦静まり返った。
持ったままになっていたポッキーをポリポリとかじる。
そろそろ時計の針が九時を指そうとしている。普段から夜の早い西岐は段々と眠くなってきて、纏っている空気が緩み始める。思考がふわふわとしてきて眠気を自覚していた。
「ねぇねぇ」
葉隠が身を乗り出す。透明で見えないが服の形が乗り出したかのように動く。
「れぇちゃんはクラスの中で誰が一番好き?」
最後のポッキーのかけらを口に収めると、問いかけてくる葉隠の顔があるであろう場所をじっと見た。
クラスの中で誰が好き。
ゆっくりと頭の中で反芻してみる。
そういうことは考えたことがなかった。
「みんな好きってのはナシで!」
「一人選ぶなら!」
今まさしく全員かなと言おうとしてその前に禁じられてしまった。
一人、と呟いて膝を抱え考え込む。
「うーん……と、……………………あいざわせんせい」
しいて言えば相澤。
西岐がヒーローを目指そうと思う理由・原点が相澤にあるからで、そのぶん特別な思いも大きい。
家族のいない西岐にとって相澤は、今や心の拠り所になっていると言っても過言ではない。
ぽつりと言うと女子たちは甲高い声を手のひらの中に押し込めた。
「ええええええええ、そうきた!」
「まさかの相澤先生だ!」
「年上! しかも禁断ですわ!」
「うわあああ、相澤先生聞いてたらどうしたんだろ」
「相澤先生、道踏み外しちゃうわ」
「これ以上ない恋バナだ! やだ楽しい!」
キャーキャーと盛り上がる女子たちをよそに西岐はうとうととし始め、眠気に抵抗できずに目蓋が下りて行ってしまう。
立てた膝に顔を埋めて静かになった西岐をよそに、就寝時間となって障子が迎えに来るまで、女子たちの"恋バナ"は続くのだった。
久しぶりの外、楽しみにしていた林間合宿、初めてのバスでの長距離移動。
「西岐は俺の隣だ」
わくわくしてバスに乗り込むと、あれから全く機嫌の直っていない相澤が無情にも隣の席を叩いて座るように促してくる。クラスメイトに囲まれワイワイと過ごすのを楽しみにしていただけに、最前列の担任の隣は物凄く切ない。
あからさまに悲しげな表情を浮かべても、相澤はポンポンと席を叩いている。
どれだけ信用を失ってしまったのかと己の行動を悔いながら従う。
発車すると間もなく、相澤の説明などそっちのけで賑やかになっていく車内。音楽を流してみたり、しりとりをしてみたり、ものすごく楽しそうにしている。後ろを振り返ると誰かがポッキーを持って皆に分けているのが見える。とても羨ましい。
「ポッキーちょうだい」
思わず口に出してしまうが全く届いていない。
「ねぇ、ポッキーをちょうだいよ」
もう一度声をかけてみるが賑やかなみんなの声に負けて誰にも届いていかない。大体にして聞こえていたとしても担任の横に座る西岐のところまでわざわざ誰かが持ってきてくれる気もしない。
バスの中で食べるお菓子も楽しみにしていたものの一つなのだが、買い物にさえ出かけられなかった西岐に入手手段はなく、日々の買い物は相澤がしてくれていたが、ずっと不機嫌なままの相澤にお菓子を買ってきてくれとは頼めなかった。
みんなの様子を見るのはやめてしょんぼりと前を向く。と、西岐の膝に三つの箱が置かれた。クッキーとチョコとキャラメル、西岐の好きなお菓子だ。
相澤は頬杖を突き、相変わらず目を据わらせ、じっと見つめてきている。
箱を開け、個装の袋を破ってチョコを口に含む。
「おいしい……」
口の中で解けていく甘さに顔が綻ぶ。
すっと相澤の手が伸びてきて前髪に触れてくる。あれ以来、死柄木に"崩され"不揃いになった前髪に相澤は度々触れては苛立ちを滲ませた。
そういえばヒーロー殺しに顔を傷つけられた時も傷をなぞっては似たような顔をしていたなと思い出す。
「今後は……心配かけないようにします」
「そうしてくれ」
ため息交じりに相澤がそう言うのと同時にバスが停車した。
降り立ったのはパーキングではなく不自然なほど見通しのいい空き地だった。
柵の向こうは切り立った崖になっており、緑の森と、はるか先には山が連なって見える。
先に到着していたらしい協力者、プロヒーローであるワイルド・ワイルド・プッシーキャッツにより宿泊施設が山のふもとにあると説明される。
告げられる距離と時間、どうして今ここに降り立ったのか、クラスメイトたちがざわざわとしはじめる。
「12時半までに辿り着けなかったキティはお昼抜きね」
嫌な予感から逃れるべくバスに戻ろうとするクラスメイトたちに追い打ちの言葉がかかり、足元がボゴボゴと波打った。かと思うと一気に盛り上がりクラスメイトたちを巻き込んで
襲い掛かる土砂の質量は想像以上に重く、咄嗟に抜け出すことも出来ぬまま崖下へと運ばれてしまう。
自力で宿泊施設まで来いという話だ。
突然の洗礼に戸惑いながら泥から這い出ると、すぐ目の前に現れたのは土くれで出来た魔獣。
それに向かって迷わず飛び出したのは飯田・緑谷・轟・爆豪だった。
なるほど、"これ"が至る所にいて行く手を阻むというわけか、と彼らの背後で観察する。
しかし出された課題は"倒せ"ではなく"辿り着け"。であればなんら問題はない。
マンダレイが指さした方向をじっと"視"る。建物が密集していたりすると探し出すのが困難になり得るが、ここは森の中。建物があれば目立つ。木々をすり抜け山のふもとを目指して視線を巡らせる。
そして見えた『マタタビ荘』の文字。
「ぱっ」
例によって小さく呟くと"視"えていた景色へと一瞬で移動した。
相澤とワイルド・ワイルド・プッシーキャッツの二人と幼い少年が到着したのは、西岐が宿泊施設に辿り着いてから数時間経った頃だった。
「……おそい」
「わあ、すごいね君」
「もう着いたの! 優秀!」
すっかり待ちくたびれた様子の西岐に、ピクシーボブとマンダレイは目を丸くして驚きつつも褒めてくれる。
相澤は西岐の到着は想定内だったらしく、顔を合わせるなりフンと鼻を鳴らした。
久しぶりに見た相澤の満足げな様子に嬉しくなる。
「さて、俺たちは飯にしますか」
「そうしようそうしよう」
「お昼ご飯はベーコンカリカリ丼定食だよー!」
お昼ごろに着くだろうと言っていた言葉とは裏腹に生徒たちを待つ気はないらしく、外のテーブルに配膳していくプッシーキャッツの二人と、それを手伝う目つきの悪い少年、洸汰。
「あ、俺が持っていくよ」
すまし汁のお椀の乗ったトレーを小さな体で運ぶのを見てそれを上から受け取る。
不意を突かれて見開いた目が、西岐を捉えるとキッと鋭くなり、警戒心と敵意が剥き出しの目は誰かを彷彿とさせる強さがあって思わずたじろいでしまう。
大人しく席に座り、相澤と共にいただきますと手を合わせる。
ベーコンカリカリ丼定食の名にふさわしく、カリカリに焼かれたベーコンと半熟卵がご飯に乗せられていた。
「……おい」
どんぶりの中をじっと見ていると相澤から声がかかる。
西岐の眉尻が情けなく下がる。
「ほら」
差し出された相澤の器にベーコンを移していく。
「え? もしかしてベーコン嫌いなの?」
「すみません、肉全般食べられないんです、こいつ」
マンダレイの問いかけに相澤が答える横で申し訳なさそうに身を縮める。折角用意してもらって好き嫌いするのは申し訳ないのだがどうしても食べられないのだ。
ベーコンだけでなく半熟卵も相澤の方へと移し、海苔とご飯だけの状態になってから箸をつけ始める。
「……軟弱な奴だな」
正面に座っていた洸汰が辛辣に言い放つ。
「そうなの、なさけない」
苦笑いを浮かべて肯定すると再び虚をつかれたらしく大きな目で西岐を見つめ、誤魔化すようにケッと吐き捨てた。
そうして食事を済ませ、相澤とプッシーキャッツの二人は生徒たちの動向に意識を戻す。
西岐も森の方へ目を向けてみると、昼も過ぎたというのにまだまだだいぶ遠いところにいるのが"視"えた。足場の悪さと無尽蔵に沸いてくる土魔獣が、体力と個性を削っていっているようで、辿り着くまでまだだいぶかかりそうだ。
生徒全員が宿泊施設に到着したら食事、その後入浴で就寝の予定らしい。つまり早く着いたところでやることはなく、まだ当分暇を持て余すらしい。
ただぼんやり待つのも退屈なので食事の片づけをしている洸汰の手伝いをすることにした。
食器を調理場に持っていき、洗い物を始めた洸汰の隣に立つ。
「洗ったやつ、拭いて片付けていくね」
声をかけるが無視されてしまう。
機嫌が悪いのか嫌われているのか判断がつかないが、断られなかったのでせっせと食器を拭いていく。五人分の食器はあっという間に拭き終わり、洸汰が鍋などの大きなものを洗っている間に棚へと戻していく。
が、西岐は大概要領が悪い。
高い場所に置こうとして手が滑った。
「わ、わ、わわ」
受け止めようと手を動かすが指先で弾いてしまい派手な音を立てて床に落ちる。
強化ガラスでできているらしいそれは何とか割れずに原形を留めていて、西岐はほっと息をついた。
「……すみません、もう一回洗ってください」
情けない声で食器を差し出すと、何だこいつと言わんばかりの目が向けられてより一層居心地が悪くなる。手伝うと言って手間を増やしているのだから仕方ない。
「お前、本当にヒーローになりたいのかよ。なんかいちいち世話が焼ける」
「え……うん、すみません」
呆れたように言いながら食器を受け取って洗い直す。今度は自分で拭いて棚に戻した。西岐に任せたら割られると思ったのかもしれない。こんな小さな子にまで世話が焼けると言われてしまっては、さすがに自覚せざるを得ない。
洗い物もあらかた終わって手持無沙汰となり、調理場の丸椅子に腰かけた。
「こうたくんは……ヒーロー嫌い?」
問いかけるとギロッと鋭い目が突き刺さる。
「でもほら俺ぜんぜんヒーローっぽくないでしょ、例外ってことでよくないかな?」
ヒーローという言葉を前にした時の嫌悪感、それはひしひしと伝わっていた。どういう背景があるかもわからないし、どうこうしてやれるなんて思ってもいない。ただ一週間も過ごすこの場で嫌悪を向けられたままなのはなんとなく嫌だった。
「いいわけないだろ」
まあそう簡単にいくわけはないのだけれど。
分かっていたがきっぱり言われてしまうと心が萎えてしまう。
「――ったく、しょうがねえなあ」
洗い終えたばかりの鍋をコンロに置き、調理台にまな板と包丁を用意する。勝手口に置かれた大量の野菜の箱と米の袋のいくつかを調理台の近くへと運びながら心底仕方なさそうに言う。
「これからマンダレイと俺で40人分の飯を作るんだ、手伝え」
その偉そうな指示はつまり少しは許容してくれたということなわけで、西岐は嬉しそうに破顔するのだった。
日も傾きはじめる午後五時二十分。
マンダレイと洸汰と西岐で全員分の夕食を用意できた頃、漸く1-A全員が宿泊施設マタタビ荘に辿り着いた。その様はまさしく満身創痍で、瞬間移動でさっさと到着してしまったことを申し訳なく思ってしまうほどだ。
西岐と同じく緑谷も洸汰の存在が気になってしまったらしく、挨拶しようとして強烈な一撃を食らう。
それを相澤は茶番と一蹴し、荷物を運ぶよう指示をして今日のスケジュールを伝える。本日のやることは食事と入浴、そして就寝のみ。本格的な合宿のスタートは明日からだということ。
指示のまま荷物を部屋に運び終えるとA組B組が一堂に会して食事が始まる。昼食抜きで魔獣の森を駆け抜けてきたクラスメイトたちがものすごい勢いで掻き込んでいく。西岐は飲み物や汁物のお代わりを運んでテーブルを行き来する。一人昼食を摂っていたのもあって申し訳ない気持ちから給仕を買って出たのだ。
「ご飯足りてる? おかわりあるよ」
「れぇ、良い嫁になれるぜ!」
「むしろ嫁になってくれ!」
土鍋で炊いたご飯を喜んでいた切島と上鳴に声をかけると、謎の言葉と共に茶碗が差し出される。障子が小さく咳き込みつつも同じく空いた茶碗を差し出した。
男子も女子も大いに食べ、食事を終える頃には山盛りだった皿もすっかり綺麗になっていた。手伝いをした身としては、これほど満足そうに平らげてもらうのは気持ちがいいものだ。
「西岐、手伝いもその辺にしないと風呂の時間がなくなるぞ。というか飯は食ったんだろうな」
ブラドキングとの打ち合わせが終わって食堂に顔を出した相澤がいまだに片づけを手伝っている西岐を見て眉を寄せた。
自分の食事を忘れていた西岐は、口を『あ』の状態に開いてしばし固まる。
相澤の目が思案げに漂う。
「まあ……風呂は俺らの時間に一緒に入ってもいいが」
「ううん、俺もみんなと入ってくる。……こうたくん後はお願いね、ごめんね」
何か含んで呟く相澤に、そういうわけにはいかないと首を横に振った。一人別行動なのはもう散々だ。
舌打ちを背後に聞きながら急いで部屋に行き、着替えとお風呂セットを片手に浴場へと足早に向かった。
「わあー……これが温泉……!」
浴場に入るとそこは露天の温泉で、雑誌やテレビで見たことはあれど実際目にするのは初めてで、感慨深く見渡した。クラスメイトたちはすでにくつろぎお湯を楽しんでいるらしい。
流し場で髪と体を流してから湯船へと足を向ける。
すると……。
「西岐っ」
「ばかれぇっ」
障子と爆豪がタオルを広げて飛んできた。
「タオルくらい巻け!!」
爆豪は顔を真っ赤にして怒りながら西岐の腰にタオルを巻きつける。
何故かさらにその上からタオルを巻きつける障子の顔も赤く表情は険しい。
「エチケットだ、巻いておけ」
どうやら恐らく暗黙の了解のようなエチケットらしい。よく見れば確かにみんな腰にタオルを巻いている。納得して頷くと二人が安堵の息を吐いた。
改めて湯船に近付き、足先からゆっくりとお湯に入っていく。
少し熱めのお湯がじわじわと沁みてくる。
「はあああ……これが温泉かあああ……」
うっとりと顔が綻ぶ。
「……西岐、少しでいいから自覚した方がいいよ」
困ったような声で話しかけてくるのは尾白。意味を汲み取れずにいるとスッと隣を指さした。その先には何故か湯に顔を浸している常闇がいる。
それでも尾白の言いたいことが分からず何が不味いのかと悩んでいる西岐の頬を、轟がガシッと両側から手で挟んで自分の方へと引き寄せた。
「大丈夫、西岐は可愛い」
「……とどろきくん?」
覗き込んでくる轟の顔は先程の爆豪たちに負けず赤い。
双眸がどこか陶然としている。
何が大丈夫なのか分からないし顔がやたら近い。
手のひらで頬を挟みながらその指先が濡れた髪を絡めて擽る。
「よーし待て待て轟、ここは公共の施設だぞー」
「よーしのぼせちまったか、向こうで休もうなー」
バシャバシャとお湯を跳ねさせながら二人の間を割って入ってくる切島と砂藤。二人がかりで轟を西岐から剥がし、だいぶ離れた端の方へと引きずって行ってしまう。
「のぼせたならお湯から出たほうが……」
「違う、違うよ、西岐」
確かにだいぶのぼせていそうだったと思いながら介抱する二人へ声をかけるが、隣の尾白は首を振って脱力する。
「とこやみくんものぼせた?」
ずっとお湯に顔を浸している常闇へそっと近づくと肩を大きく跳ねさせた。
顔を浮上させ西岐を一瞥して勢いよくお湯に顔を鎮める。
「だ、大丈夫? 運ぶ?」
「……闇が暴走しそうだ、放っておいてくれ」
顔を背けてお湯から浮かせてそういうと西岐から距離をとっていってしまった。
気にならないといえば嘘になるが、まあいいかと気持ちを切り替えてお湯に浸かる。温泉の成分のせいか白く濁ったお湯がとろっと身体に纏わりつくようで心地いい。
ただ、やけに背後が騒がしい。何やら峰田と飯田が騒いでいるらしい。
壁の上から洸汰の声がして振り返ると、ちょうど峰田と洸汰が落下するのが目に飛び込んできた。
「――あ、ぶないっ」
咄嗟に飛び出した緑谷が洸汰を、西岐は峰田をキャッチしていた。洸汰は気絶してしまったらしく脱衣場へと緑谷が連れて行く。一方の峰田は落下のショックからか西岐にしがみついて剥がれない。
「くっそー、俺の癒しは西岐のまな板ちっぱいしかないのか。男のくせにすべすべしやがってチクショウ!!!」
いつぞやのように胸に擦り寄る峰田。
温泉だというのにその場の空気が一気に凍り付く。それはもう本当に文字通り。浴場の床の一部に氷が張っている。
更にボンッとニトロが弾ける音が響く。
「ばかれぇ、さっさとあがってろ」
ドスの利いた声に威圧され、すくみあがる。しかし、貼りついている峰田はどうすれば……と迷っていると、ダークシャドウが峰田を咥えて引き剥がした。
「あ、あの、じゃあ俺は、これで」
その場にいる者たちの視線に押されるようにして浴場を後にした。
温泉があるとマンダレイから聞いて楽しみにしていたのだが、あまりゆっくり堪能できなかったなと残念に思いながら、部屋着に着替えるのだった。
就寝前の自由時間、西岐は女子の部屋に呼ばれていた。
お菓子を食べながらお喋りしようということだ。
手招きされて芦戸と耳郎の間に入る。
「そんじゃそんじゃ、恋バナだ!」
「まじか」
「ベタね」
芦戸が拳を振り上げ提案すると耳郎と蛙吹、そして麗日もほんのりと頬を染めた。
「でもそれはお付き合いしていたり好きな相手がいたりすることが前提ですわ、芦戸さんはそういう方がいらっしゃいますの?」
「そうそう、三奈ちゃんは好きな人いるの?」
八百万と葉隠からブーメランが返ってきて芦戸はグゥと言葉を詰まらせる。
みんなのやり取りを聞きながら西岐は持ってきたクッキーの箱を開いて小分けになった袋をそれぞれの前に置いていく。丸くなって座る真ん中にはすでにポテトチップスやポッキーなどが置かれ手を付けた後がある。西岐は『ポッキーだ』と過剰反応し手を伸ばす。
「そんじゃそんじゃ、1-Aなら誰が好き? 誰が一番いいと思う? これでいこう!」
「……どうしても恋バナがしたいんやね」
ポリポリとポッキーをかじっている間に決まったらしい。
ゴリ押しした芦戸のテンションが上がっていく。
「言い出しっぺの三奈ちゃんからよ」
「おっけ! 私が一番好きなのはぁー……れぇちゃん!!」
再び拳を振り上げ勢いよく言い放たれた名前にポッキーを持った手が止まる。
誰の名前が出るのかと身構えていた女子たちが弾かれるようにズルいと一斉に声を上げる。
「なにそれ、それならウチの好きな人もれぇちゃんだよ」
「私もですわ!」
「私もれぇちゃんが好きよ」
「そしたら全員好きなのはれぇちゃんってなことで!」
「そんなの恋バナにならないよ!」
会話のほとんどを聞き流していたが突然自分の名前を一斉に連呼されて、流石の西岐も何事かと耳を傾ける。何か怒らせることでもしたかと思ったが違うらしい。
好きという単語がしっかり聞こえた。
話の脈絡は分からずとも好意は純粋に嬉しい。
「俺も、みんな好きだよぉ」
だからつい顔が綻んでしまう。
「わああ……まぶしいぃ」
「れえちゃんってほんといい子」
麗日が眩し気に目を細め、耳郎はまるで幼子にするような感じで西岐の頭を撫でる。西岐が心地よさげに目を細めると、騒がしかった室内が一旦静まり返った。
持ったままになっていたポッキーをポリポリとかじる。
そろそろ時計の針が九時を指そうとしている。普段から夜の早い西岐は段々と眠くなってきて、纏っている空気が緩み始める。思考がふわふわとしてきて眠気を自覚していた。
「ねぇねぇ」
葉隠が身を乗り出す。透明で見えないが服の形が乗り出したかのように動く。
「れぇちゃんはクラスの中で誰が一番好き?」
最後のポッキーのかけらを口に収めると、問いかけてくる葉隠の顔があるであろう場所をじっと見た。
クラスの中で誰が好き。
ゆっくりと頭の中で反芻してみる。
そういうことは考えたことがなかった。
「みんな好きってのはナシで!」
「一人選ぶなら!」
今まさしく全員かなと言おうとしてその前に禁じられてしまった。
一人、と呟いて膝を抱え考え込む。
「うーん……と、……………………あいざわせんせい」
しいて言えば相澤。
西岐がヒーローを目指そうと思う理由・原点が相澤にあるからで、そのぶん特別な思いも大きい。
家族のいない西岐にとって相澤は、今や心の拠り所になっていると言っても過言ではない。
ぽつりと言うと女子たちは甲高い声を手のひらの中に押し込めた。
「ええええええええ、そうきた!」
「まさかの相澤先生だ!」
「年上! しかも禁断ですわ!」
「うわあああ、相澤先生聞いてたらどうしたんだろ」
「相澤先生、道踏み外しちゃうわ」
「これ以上ない恋バナだ! やだ楽しい!」
キャーキャーと盛り上がる女子たちをよそに西岐はうとうととし始め、眠気に抵抗できずに目蓋が下りて行ってしまう。
立てた膝に顔を埋めて静かになった西岐をよそに、就寝時間となって障子が迎えに来るまで、女子たちの"恋バナ"は続くのだった。
create 2017/11/21
update 2017/11/21
update 2017/11/21