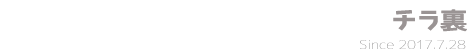林間合宿
伸ばせ
ヒロ×サイ|top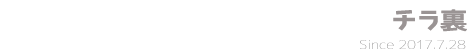
伸ばせ
合宿二日目、午前五時三十分。
寝惚けの抜けきらない頭でどうにかぎりぎり立っていた。立っているといってもほとんど障子に寄り掛かっている。夜早く寝る分、朝には強いほうではあるが早朝の起き抜けである。上目蓋と下目蓋がいまだに離れたがらない。
「西岐、聞いてたか?」
「ん?……んー……ボールが……とんだ」
おそらく障子であろう声によく理解しないまま頷く。
ボゴボゴという音が聞こえる。この音はなんだったかと思いながら薄目を開けると、四方25メートルほどが高い土の壁で囲まれていた。
「ラグドール、こいつの個性見てもらえますか」
いつの間にか西岐を支えていた障子が相澤に代わっていて、初めて見るラグドールと呼ばれた女性が顔を覗き込んでいる。マンダレイやピクシーボブとお揃いのコスチュームを着ていることから彼女もワイルド・ワイルド・プッシーキャッツの一人なのだろう。
丸い目がじっと覗き込んでくる。
随分長く黙って見つめているがパチッと瞬きをして不思議そうに首を傾ける。
「なんも見えない!」
降参とばかりに両手を頭上に上げるラグドールに、相澤は想定していたのかガッカリするでもなく寧ろ納得の表情を浮かべた。
「そしたら他の生徒見てやってください」
「わかった!」
相澤の言葉に元気よく返事をするとラグドールは壁の隙間から外に出て行った。
さすがにすっかり目が冴えてしまい寄り掛かっていた相澤から体を放して自分の足で立つ。
他のクラスメイトたちの姿はなく、壁の内側には西岐と相澤だけだった。遠くから微かに叫び声のようなものが聞こえる。鬼気迫る声だが相澤が反応しないところを見ると強化訓練の一環のようだ。
「個性が分からないんじゃしょうがない、一通り限界まで引き出してみるか」
そう言って相澤は眉を寄せた。
それからどのくらい時間が経ったのか。体感としては随分長く続けていたような気がするがまだ太陽は頭上にも来ていない。壁の向こうからは相変わらずクラスメイト達、特に爆豪の喚き声が聞こえてくる。
西岐はふらつきそうになりながらも両足で地面を踏みしめ、相澤の腕を掴んでいた。
「どうした、動けるようになってきたぞ」
相澤の厳しい声がかかる。その証拠に指先が微かに動く。
歯を食いしばり、手のひらに意識を集中させる。しかし一度パチッと小さく弾けただけでそれ以上は電気が放出されなくなってしまった。
「は……だめだぁ……」
自分の物とは思えないほど重くなった腕が肩からぶら下がる。苦し気に重い息を吐きだす。
手から電気を放出できなくなるほど抑制をかけ続けるなど初めてのこと。大抵その前に限界を感じてやめてしまう。意識的に続けてみれば思いのほか想像より続けられた気がするが、その代償は大きい。体力をごっそり削られた。
「抑制はこれが限界か」
「そうみたい……です……」
相澤が腕をさする。長時間バチバチと静電気のような痛みを感じていただろう。
対人でなければ使えているか分からない能力ばかりの西岐に、相澤がマンツーマンで付き合ってくれていることを思うと申し訳なくて手は抜けない。
「封印はまだ解けてないな」
言いながら抹消を試したのだろう。目は赤く光らず髪も逆立ちはしない。
「解封しないと絶対解けないです……」
なので今も尚、強烈な負荷が全身に襲い掛かってきている。汗で髪が肌に貼りつき、顎を伝ってぽたぽたと落ちる。
指先にじわっと滲む血。
「人数に制限は?」
「たぶん、ない……」
「お前が気を失ったらどうなる」
「えっと……封印されたままで、ひたすら俺の体力がすり減ります」
今でこそ封印と解封という切り替えがあるが、もともとは血が付いただけで個性を封じてしまうという自分の意志が全く介入できない能力だったのだ。特に解封は意識下でなければ行われない。
それを説明しながら西岐は奇妙な既視感を覚えていた。
誰かとこの能力について話したことがあるような。しかし西岐はこの能力に自己否定の気持ちを持っていて人には滅多なことでは見せないようにしている。その自戒を破ってでも話したいような相手など雄英関係者以外でいただろうか。
疲労も手伝って西岐の意識は思考の海に沈み始める。
「ぼんやりするな」
相澤に頬を叩かれてハッと意識を戻す。
「もういい、封印は解け」
言われるまま口の中で《解封》と小さく呟く。
負荷から解放されて急に体が軽くなり、踏ん張っていた脚からも力が抜けてしまい、へなへなと座り込んでしまった。
「あああ……しんじゃう」
「言っただろ、死ぬほどキツイって」
「聞いてない……聞いてないです……」
どっと押し寄せる疲労に目が回りそうになる。
しかし相澤は表情を険しくする。
「次は幻影をやってみせろ」
「うそだああ……」
労わるどころかむしろ今から一番苦手な幻影をやれと言われて地面にへばりつきたい気持ちになる。
あれはうまくできないうえに負担が大きく、出来るだけ使わないようにしてきた。それをよりにもよってこんな疲れている状態ではやれとは……。
せめて休憩を下さいと必死に訴えてみるが完全に無視されてしまう。
「早くしろ、時間がもったいない」
言葉尻に苛立ちが滲んでいる。死柄木の一件以降、機嫌の悪さを引きずっている相澤の導火線は短そうだ。
覚悟を決めて立ち上がる。
目を閉じてゆっくり息を吸い込む。前髪が短くなったことでクリアになった視界に相澤を捉える。瞬きしないように堪えながらゆっくり少しずつ息を吐きだす。
隙間風のような音が微かに鳴る。
ボッと西岐の足元に火が付きそれが螺旋状に伸びていく。あっという間に燃え広がり壁の内側は火の海となった。
燃え盛る炎に囲まれていながら、相澤は平然としていた。
「これは凄い、が、熱くない。炎って選択は好ましくなかったな」
たしかにそのとおり。
これはあくまで幻術であり本物の物質に何か作用することはできず、あくまで見せた相手が思い込んでしまう状況に陥らせるだけのものに過ぎない。
ならばこれでどうだと幻影を変化させる。
無数の手が出現し相澤の脚に絡みつく。
「悪くはないが、隙だらけだ」
絡みつく手に構わず足を踏み出し飛び上がる。相変わらず卓越した跳躍力で間合いを詰め、そして拳を振りかぶった。
思わず構えながら後ろへ飛びのく。
シュッと布が西岐を囲む。
「幻影が消えてるぞ、西岐」
捕縛武器に捉えられる前に瞬間移動で宙へと身を逃す。しかし相澤に言われた通り幻影はとっくに解けてしまっている。これだけ動けば息も切れるし視界に入れておくのは難しくなる。
同じく"目"が武器の相澤が、相手を"視"ながらあれだけの戦闘をしていたことを思い出すと、改めて相澤の凄さを痛感してしまう。
「動きながら幻影が使えるようになれ、まずはそれが課題だ」
落下していく西岐に捕縛武器を投げつける。
あれに捕まってしまえばそもそも動き回るのは不可能になる、つまり全力で逃げ、全力で反撃しながら幻影を使えということか。
そこに至ってようやくこの高い壁の意味が分かった。この壁があれば間違って誰かに幻影を見せてしまい巻き込んでしまうことも、うっかり攻撃の余波が誰かに当たることもない。
そしてこの広さも初めから動き回ることを考慮して用意されたに違いない。
「……合理的」
伸びてくる布から逃れるべくさらに上空にいったん回避する。
広いと言ってもせいぜい25メートル四方、相澤の攻撃を逃れるには厳しい。それにそもそもが幻影を伸ばす訓練であり交戦にばかり気を取られていては何も意味がない。
よし、と気合を入れて息を吸い込んだ。
日が傾き始めた頃。
すべての力を使い果たして西岐は放心していた。
かろうじて目は開けているものの、目に映るものをモノと認識できないくらい脳みそまでもが疲弊している。
「おい、西岐」
感覚がどこか遠くにある。
音が何かに吸い取られてしまったかのように遠ざかっていく。
この感覚には覚えがあるけれど、それが何だったのか思い出せない。思考が回らない。
誰かが何かを話している。声は聞こえない。けれどそれが不快な事だけは分かって耳を塞ぎたくなった。
手が動かない。
動かさなければ。
「……っ、おい」
焦ったようなこの声はいったい誰のものだったか。
「しっかりしろ」
「……あれ、声が聞こえる」
急に視界が開ける。
ぺちぺちと頬を叩かれる感覚がきちんとある。
「死んでないな」
「生きてます」
声はかなりへろへろになっているがここがあの世でなければ確かに生きている。肉体に感覚があって会話が成立しているのだから間違いないだろう。
ところでどうして相澤が擦り傷だらけになっているのか。西岐との手合わせではかすり傷もつかなかったはずなのだが。
何気なく視界を背後にスライドさせて、そこにあった分厚い土の壁がボロボロに砕けているのにも気付いた。
「期末の時言わなかったが、お前もう一つ個性らしき何かがあるぞ」
地面に座り込んでいる西岐の前にしゃがむ。視線を自分に戻させてから相澤は言った。
「手も触れずに壁を砕くってことはおそらく念動力みたいなものなんだろうな……正直参った」
もう一度周りの壁をぐるりと見渡す。取り囲んでいたはずの壁が砕かれてなくなっている。相澤の口ぶりからするとこれを砕いたのはどうやら西岐自身らしい。自分がやったという自覚はない。どうやって行ったのかも健闘がつかない。
そんな能力があるのだろうか。もし、あるのだとすれば……、これだけの破壊力があるのならば……緑谷たちに劣らぬ戦いができるのではないか。
そう考えて高揚していくのを自覚した。
「……あ、俺、……この力を引き延ばしたい」
動揺と期待に声を震わせると、相澤の顔が分かりやすいほど嫌そうに歪んだ。
「まあ……そうだな。明日からはそっち伸ばすことにするか」
表情とは裏腹に口ではあっさり容認する。
『明日』の部分を強調して聞かせ、土を払いながら立ち上がる。
何なら今からでもと急に意欲を見せる西岐だが、つられて立ち上がった途端、眩暈が起こり再び地面に這いつくばる。
残念ながら今日これ以上の訓練を行う余力は残っていないようで、相澤の深い深い溜息を聞きながら、訓練初日を終えるのだった。
夕飯などどうでもいいから風呂に入って寝てしまいたい。
というのがもしかしたら飯田以外のクラスメイト達の本音だったかもしれない。
少なくとも西岐は普段から食事に重きを置いておらず夕飯をとらずに寝ることもしばしばあるし、なんならこの場で寝てしまいそうなくらい疲れ果てていた。
合宿二日目以降の夕食は自分たちで作れ、それが先生方とプロヒーローのお達しで。
けれどなんだかんだで文句を言わず調理し始めたクラスメイトたちを見て、西岐も眠気を振り払ってとりかかる。
自然とクラスメイトたちが《ご飯とカマドの担当》と《材料を切る担当》に分かれて進めていく。さすがヒーロー科なだけあって何事にも積極的かつ整然としている。
西岐は材料を切る担当となって山盛りになっている野菜を処理していく。
「うまいな、西岐くん。結構自炊しているのか」
「ふふふ、最近は手抜きが多いけどね」
でこぼこのジャガイモの皮をくるくると剥く西岐の手元を見て感心する飯田。一応は一人暮らしが長いわけでこれくらいのことは当然できる。
逆に覗き込むと、隣のまな板ではお坊ちゃんの彼らしい不器用さで野菜が切り刻まれており、西岐は微笑ましくなった。
「西岐、こっちの鍋持って行っていいか?」
「あ、待って待って、持ってかないで」
一時的に切った野菜を入れていただけの鍋を轟に持っていかれそうになって慌てて止める。空いている鍋に適量の野菜を移している西岐を、轟が見つめながらほんのり口角を緩めている。よくみると眉も下がっていて何かの感情を噛みしめているようにも見える。
「どうしたの?」
「え?」
「とどろきくん、なんか嬉しそうだから」
そんな表情を見ていると西岐も嬉しくなって緩んでしまう。
「こっち側、人助けに使えばいいって前に西岐が言っていただろ」
言いながら左の手のひらを空に向け、ゆっくりと指を折って握りしめていく。こっちというのは父親から受け継いだ炎熱のことだろう。
「さっき頼まれてカマドの火をつけてる時になんか思い出して、さ……。少し嬉しかった」
あれほど忌み嫌っていた左側のことをこんな風に穏やかに話せるようになるなんて。体育祭からまだ二か月ほどしか経っていないのになんて成長なのだろう。
「よかったねえ……」
目からボロッと涙がこぼれた。
疲れのせいで感情が馬鹿になってしまっているらしい。
まさかこの流れで泣くとは思っていなかっただろう轟が狼狽する。
「な、なんで泣く?」
「玉ねぎじゃないのか!」
「玉ねぎなのか、西岐!」
飯田の見当違いっぷりと轟の天然っぷりが全力で西岐に向かってくる。もしかしなくとも、二人も相当疲れているらしい。
西岐にはツッコミを入れるだけの元気はなく、止まらなくなった涙を押さえようと手で覆うことくらいしかできず、それから暫くして早くしろと爆豪が憤慨しながら乱入して来るまで、この奇妙な光景は続いた。
今日こそは温泉でくつろぎたい。そう思っていた西岐は誰よりも早く浴場に向かい、人が増えてきて賑やかになる前に退散した。
静かな大部屋に戻って濡れた髪をタオルで適当に拭っていると、あとから入ってきた障子が西岐の方に近づいてきた。障子も風呂上りらしくいつものマスクの代わりにタオルを口元に巻き付けている。
「大丈夫か? 派手に個性使い続けたんだろ?」
そう心配そうに訊いてくる。
何度か使いすぎて疲弊しているところを見たからか障子はいつも気にかけてくれる。
「それはみんなおなじだよ」
夕飯時や風呂場で入れ違いになったみんなの様子を思い出しながら首を振った。みんな昨日ほどの元気はなくぐったりしていた。そして終始、会話の内容が訓練のことだった。
自分の能力はすぐ体力が削られ人よりハイリスクだと思い込んでいたが、なんてことはない、みんなそれぞれに限界があってそのなかでうまく使っていただけのこと。それを知った今、自分だけが特別疲れただなんて思わない。
「しょうじくんは今日どういうことしてたの?」
「俺はこういう……複製を増やしたり、早く複製できるように鍛錬したり、だな」
逆に問いかけると、障子は複製してみせる。以前より触手の先が伸びて枝分かれする。長く伸びたほうが手の形になり、短いほうには口が出現する。
「わあ、すごい。かわいい」
「……可愛い?」
西岐の口から出た形容詞に、障子は疑問符をつけて復唱する。
そんなことはもちろん聞き流して、西岐は器用に変化していく触手の先を見て感嘆の声を上げる。
障子はしばらく好きにさせてくれていたが、目が合うとその表情は幾らか沈んでいるように見えた。もう一度触手の先を手の形にすると、その指が西岐の濡れた前髪を摘まんだ。まるで相澤がしたような手の動きに何を意味しているのか分かってしまい、笑顔を消し少し目を伏せた。
「前髪、気になる?」
「そうだな」
「目立つもんね」
障子はため息をつく。
「死柄木に触られてこうなった、それを想像すると背筋が凍る」
「……うん」
直前まで一緒にいた障子を置き去りにして死柄木を追いかけ、そのあとは自宅謹慎。次に顔を合わせた時にはこの髪になっていた。あの時は黙って荷物を渡してくれたけれど言いたいことが山のようにあったのだろう。
「USJの時からそうだが、西岐はいつも一人で勝手に無茶をするから気が気ではない」
「ごめんなさい」
いつもというのには語弊があるように思えたが今は反論する空気ではなく、素直に謝罪を口にして西岐はしゅんと小さくなった。
怒るのとは違う、落ち着いた物言いがかえって申し訳ない気持ちにさせてくる。
「俺……訓練がんばる。もっと力つけて、心配かけないくらい強くなる」
気合いを入れるように拳を握り締めると、障子の目がまたらしくなく遠くへと彷徨う。何か考えているようだがそれを西岐に言うことはなく、前髪をいじっていた手が離れていく。
奇妙な空気が大部屋に漂うが、ガタンという激しい音で掻き消える。
「れぇくん、今日は女子部屋に来な……はわわわっ!」
引き戸を開けて顔をのぞかせたのは麗日。昨日に引き続いて女子の部屋に招こうと訪れたらしいが、西岐と障子を見るなり顔を赤くして慌てふためく。
「あ、俺行った方がいい?」
「いやいやいや、大丈夫です、お気になさらず! 大変お邪魔しました!!」
西岐が畳に手をついて立ち上がろうとするが、麗日はせわしなく両手と首を振り、開けた時と同様派手な音を立てて閉め、足音が遠ざかっていく。心なしか悲鳴のような声が聞こえた気がする。
「え、なんだったの?」
「……さあな」
まるで台風一過ごとく去っていった麗日に、西岐と障子は二人そろって首を傾げるのだった。
誰かの声が聞こえた。
物凄く近くから聞こえるのに何と言っているのか聞き取ることが出来ない。
西岐も何か、言葉を発した。だがそれも聞こえない。自分の言葉なのに何を言っているのか分からない。
西岐の言葉で相手が笑ったような気配だけが伝わってくる。
誰かが近づいてきて大きな手のひらをかざす。
それが西岐の顔に触れ視界を覆った。
「――……」
目を開けると視界は真っ暗でまだ夢の続きなのかと思った。しかし周りからクラスメイトたちの寝息が聞こえてきて、西岐は強張っていた体から力を抜いた。
不思議な夢だった。
いつもの予知夢のように音はなく、それでいてはっきりと覚えている。覚えているのに何の役にも立たないくらい抽象的で、じっとりとした恐怖心だけが胸に残っている。
息を吐きながら顔を覆う。
変な夢を見てしまうのは疲れのせいなのか。
それともこれはやはり予知夢でこれから何かが起きるのか。
判然としないまま心臓が落ち着かず、再び眠ることもできない。
「眠れないのか?」
隣から声がかかる。
暗闇に慣れてきた目に常闇の顔を映す。
「……変な夢見ちゃった」
他のクラスメイトを起こさないように声を潜める。それでも結構響いてしまうから布団のぎりぎりまで常闇の方へと詰める。
「とこやみくんは起きてた?」
「宵闇に覆われる刻が俺の本当の時間だからな」
落ち着いた声で放つ言葉はすぐには理解できず西岐は何度か脳内で反芻した。
夜行性ということだろうか。
影が個性な彼らしいと言えばらしい。
とはいっても完全に夜行性というわけではないようで目が眠そうにショボショボ瞬いている。
真っ暗で時間が分からないがきっとまだ真夜中だ。
「寝ていいよ、俺も寝るから」
「……分かった」
睡眠を促すと常闇はすんなり頷くが、何故か自分の肌掛けを捲って横のスペースをポンポンと叩いている。意味を汲み取れず見ていると、脇から出てきたダークシャドウが西岐を咥え、常闇の隣へ引きずっていく。そして西岐ごと肌掛けをかけ直す。
予想しなかった出来事に驚き、漏れそうになった声をどうにか飲み込む。
常闇の腕が引き寄せるように背中に回され、西岐の頭の横にダークシャドウが横たわる。
どういうことなのか分からず暫く固まっているが、伝わってくる鼓動とぬくもりが遠くあった眠気を呼び戻し、もう一度西岐の目蓋を下ろしていく。それが心地よくて西岐は身を預ける。
ぎゅっと腕に力が籠められるのを感じながら、眠りへと落ちていった。
翌朝、くっついて眠る二人を見てクラスメイトたちが固まり、常闇も覚えのない自分の行動に硬直することになるのだが、それはまた別の話。
寝惚けの抜けきらない頭でどうにかぎりぎり立っていた。立っているといってもほとんど障子に寄り掛かっている。夜早く寝る分、朝には強いほうではあるが早朝の起き抜けである。上目蓋と下目蓋がいまだに離れたがらない。
「西岐、聞いてたか?」
「ん?……んー……ボールが……とんだ」
おそらく障子であろう声によく理解しないまま頷く。
ボゴボゴという音が聞こえる。この音はなんだったかと思いながら薄目を開けると、四方25メートルほどが高い土の壁で囲まれていた。
「ラグドール、こいつの個性見てもらえますか」
いつの間にか西岐を支えていた障子が相澤に代わっていて、初めて見るラグドールと呼ばれた女性が顔を覗き込んでいる。マンダレイやピクシーボブとお揃いのコスチュームを着ていることから彼女もワイルド・ワイルド・プッシーキャッツの一人なのだろう。
丸い目がじっと覗き込んでくる。
随分長く黙って見つめているがパチッと瞬きをして不思議そうに首を傾ける。
「なんも見えない!」
降参とばかりに両手を頭上に上げるラグドールに、相澤は想定していたのかガッカリするでもなく寧ろ納得の表情を浮かべた。
「そしたら他の生徒見てやってください」
「わかった!」
相澤の言葉に元気よく返事をするとラグドールは壁の隙間から外に出て行った。
さすがにすっかり目が冴えてしまい寄り掛かっていた相澤から体を放して自分の足で立つ。
他のクラスメイトたちの姿はなく、壁の内側には西岐と相澤だけだった。遠くから微かに叫び声のようなものが聞こえる。鬼気迫る声だが相澤が反応しないところを見ると強化訓練の一環のようだ。
「個性が分からないんじゃしょうがない、一通り限界まで引き出してみるか」
そう言って相澤は眉を寄せた。
それからどのくらい時間が経ったのか。体感としては随分長く続けていたような気がするがまだ太陽は頭上にも来ていない。壁の向こうからは相変わらずクラスメイト達、特に爆豪の喚き声が聞こえてくる。
西岐はふらつきそうになりながらも両足で地面を踏みしめ、相澤の腕を掴んでいた。
「どうした、動けるようになってきたぞ」
相澤の厳しい声がかかる。その証拠に指先が微かに動く。
歯を食いしばり、手のひらに意識を集中させる。しかし一度パチッと小さく弾けただけでそれ以上は電気が放出されなくなってしまった。
「は……だめだぁ……」
自分の物とは思えないほど重くなった腕が肩からぶら下がる。苦し気に重い息を吐きだす。
手から電気を放出できなくなるほど抑制をかけ続けるなど初めてのこと。大抵その前に限界を感じてやめてしまう。意識的に続けてみれば思いのほか想像より続けられた気がするが、その代償は大きい。体力をごっそり削られた。
「抑制はこれが限界か」
「そうみたい……です……」
相澤が腕をさする。長時間バチバチと静電気のような痛みを感じていただろう。
対人でなければ使えているか分からない能力ばかりの西岐に、相澤がマンツーマンで付き合ってくれていることを思うと申し訳なくて手は抜けない。
「封印はまだ解けてないな」
言いながら抹消を試したのだろう。目は赤く光らず髪も逆立ちはしない。
「解封しないと絶対解けないです……」
なので今も尚、強烈な負荷が全身に襲い掛かってきている。汗で髪が肌に貼りつき、顎を伝ってぽたぽたと落ちる。
指先にじわっと滲む血。
「人数に制限は?」
「たぶん、ない……」
「お前が気を失ったらどうなる」
「えっと……封印されたままで、ひたすら俺の体力がすり減ります」
今でこそ封印と解封という切り替えがあるが、もともとは血が付いただけで個性を封じてしまうという自分の意志が全く介入できない能力だったのだ。特に解封は意識下でなければ行われない。
それを説明しながら西岐は奇妙な既視感を覚えていた。
誰かとこの能力について話したことがあるような。しかし西岐はこの能力に自己否定の気持ちを持っていて人には滅多なことでは見せないようにしている。その自戒を破ってでも話したいような相手など雄英関係者以外でいただろうか。
疲労も手伝って西岐の意識は思考の海に沈み始める。
「ぼんやりするな」
相澤に頬を叩かれてハッと意識を戻す。
「もういい、封印は解け」
言われるまま口の中で《解封》と小さく呟く。
負荷から解放されて急に体が軽くなり、踏ん張っていた脚からも力が抜けてしまい、へなへなと座り込んでしまった。
「あああ……しんじゃう」
「言っただろ、死ぬほどキツイって」
「聞いてない……聞いてないです……」
どっと押し寄せる疲労に目が回りそうになる。
しかし相澤は表情を険しくする。
「次は幻影をやってみせろ」
「うそだああ……」
労わるどころかむしろ今から一番苦手な幻影をやれと言われて地面にへばりつきたい気持ちになる。
あれはうまくできないうえに負担が大きく、出来るだけ使わないようにしてきた。それをよりにもよってこんな疲れている状態ではやれとは……。
せめて休憩を下さいと必死に訴えてみるが完全に無視されてしまう。
「早くしろ、時間がもったいない」
言葉尻に苛立ちが滲んでいる。死柄木の一件以降、機嫌の悪さを引きずっている相澤の導火線は短そうだ。
覚悟を決めて立ち上がる。
目を閉じてゆっくり息を吸い込む。前髪が短くなったことでクリアになった視界に相澤を捉える。瞬きしないように堪えながらゆっくり少しずつ息を吐きだす。
隙間風のような音が微かに鳴る。
ボッと西岐の足元に火が付きそれが螺旋状に伸びていく。あっという間に燃え広がり壁の内側は火の海となった。
燃え盛る炎に囲まれていながら、相澤は平然としていた。
「これは凄い、が、熱くない。炎って選択は好ましくなかったな」
たしかにそのとおり。
これはあくまで幻術であり本物の物質に何か作用することはできず、あくまで見せた相手が思い込んでしまう状況に陥らせるだけのものに過ぎない。
ならばこれでどうだと幻影を変化させる。
無数の手が出現し相澤の脚に絡みつく。
「悪くはないが、隙だらけだ」
絡みつく手に構わず足を踏み出し飛び上がる。相変わらず卓越した跳躍力で間合いを詰め、そして拳を振りかぶった。
思わず構えながら後ろへ飛びのく。
シュッと布が西岐を囲む。
「幻影が消えてるぞ、西岐」
捕縛武器に捉えられる前に瞬間移動で宙へと身を逃す。しかし相澤に言われた通り幻影はとっくに解けてしまっている。これだけ動けば息も切れるし視界に入れておくのは難しくなる。
同じく"目"が武器の相澤が、相手を"視"ながらあれだけの戦闘をしていたことを思い出すと、改めて相澤の凄さを痛感してしまう。
「動きながら幻影が使えるようになれ、まずはそれが課題だ」
落下していく西岐に捕縛武器を投げつける。
あれに捕まってしまえばそもそも動き回るのは不可能になる、つまり全力で逃げ、全力で反撃しながら幻影を使えということか。
そこに至ってようやくこの高い壁の意味が分かった。この壁があれば間違って誰かに幻影を見せてしまい巻き込んでしまうことも、うっかり攻撃の余波が誰かに当たることもない。
そしてこの広さも初めから動き回ることを考慮して用意されたに違いない。
「……合理的」
伸びてくる布から逃れるべくさらに上空にいったん回避する。
広いと言ってもせいぜい25メートル四方、相澤の攻撃を逃れるには厳しい。それにそもそもが幻影を伸ばす訓練であり交戦にばかり気を取られていては何も意味がない。
よし、と気合を入れて息を吸い込んだ。
日が傾き始めた頃。
すべての力を使い果たして西岐は放心していた。
かろうじて目は開けているものの、目に映るものをモノと認識できないくらい脳みそまでもが疲弊している。
「おい、西岐」
感覚がどこか遠くにある。
音が何かに吸い取られてしまったかのように遠ざかっていく。
この感覚には覚えがあるけれど、それが何だったのか思い出せない。思考が回らない。
誰かが何かを話している。声は聞こえない。けれどそれが不快な事だけは分かって耳を塞ぎたくなった。
手が動かない。
動かさなければ。
「……っ、おい」
焦ったようなこの声はいったい誰のものだったか。
「しっかりしろ」
「……あれ、声が聞こえる」
急に視界が開ける。
ぺちぺちと頬を叩かれる感覚がきちんとある。
「死んでないな」
「生きてます」
声はかなりへろへろになっているがここがあの世でなければ確かに生きている。肉体に感覚があって会話が成立しているのだから間違いないだろう。
ところでどうして相澤が擦り傷だらけになっているのか。西岐との手合わせではかすり傷もつかなかったはずなのだが。
何気なく視界を背後にスライドさせて、そこにあった分厚い土の壁がボロボロに砕けているのにも気付いた。
「期末の時言わなかったが、お前もう一つ個性らしき何かがあるぞ」
地面に座り込んでいる西岐の前にしゃがむ。視線を自分に戻させてから相澤は言った。
「手も触れずに壁を砕くってことはおそらく念動力みたいなものなんだろうな……正直参った」
もう一度周りの壁をぐるりと見渡す。取り囲んでいたはずの壁が砕かれてなくなっている。相澤の口ぶりからするとこれを砕いたのはどうやら西岐自身らしい。自分がやったという自覚はない。どうやって行ったのかも健闘がつかない。
そんな能力があるのだろうか。もし、あるのだとすれば……、これだけの破壊力があるのならば……緑谷たちに劣らぬ戦いができるのではないか。
そう考えて高揚していくのを自覚した。
「……あ、俺、……この力を引き延ばしたい」
動揺と期待に声を震わせると、相澤の顔が分かりやすいほど嫌そうに歪んだ。
「まあ……そうだな。明日からはそっち伸ばすことにするか」
表情とは裏腹に口ではあっさり容認する。
『明日』の部分を強調して聞かせ、土を払いながら立ち上がる。
何なら今からでもと急に意欲を見せる西岐だが、つられて立ち上がった途端、眩暈が起こり再び地面に這いつくばる。
残念ながら今日これ以上の訓練を行う余力は残っていないようで、相澤の深い深い溜息を聞きながら、訓練初日を終えるのだった。
夕飯などどうでもいいから風呂に入って寝てしまいたい。
というのがもしかしたら飯田以外のクラスメイト達の本音だったかもしれない。
少なくとも西岐は普段から食事に重きを置いておらず夕飯をとらずに寝ることもしばしばあるし、なんならこの場で寝てしまいそうなくらい疲れ果てていた。
合宿二日目以降の夕食は自分たちで作れ、それが先生方とプロヒーローのお達しで。
けれどなんだかんだで文句を言わず調理し始めたクラスメイトたちを見て、西岐も眠気を振り払ってとりかかる。
自然とクラスメイトたちが《ご飯とカマドの担当》と《材料を切る担当》に分かれて進めていく。さすがヒーロー科なだけあって何事にも積極的かつ整然としている。
西岐は材料を切る担当となって山盛りになっている野菜を処理していく。
「うまいな、西岐くん。結構自炊しているのか」
「ふふふ、最近は手抜きが多いけどね」
でこぼこのジャガイモの皮をくるくると剥く西岐の手元を見て感心する飯田。一応は一人暮らしが長いわけでこれくらいのことは当然できる。
逆に覗き込むと、隣のまな板ではお坊ちゃんの彼らしい不器用さで野菜が切り刻まれており、西岐は微笑ましくなった。
「西岐、こっちの鍋持って行っていいか?」
「あ、待って待って、持ってかないで」
一時的に切った野菜を入れていただけの鍋を轟に持っていかれそうになって慌てて止める。空いている鍋に適量の野菜を移している西岐を、轟が見つめながらほんのり口角を緩めている。よくみると眉も下がっていて何かの感情を噛みしめているようにも見える。
「どうしたの?」
「え?」
「とどろきくん、なんか嬉しそうだから」
そんな表情を見ていると西岐も嬉しくなって緩んでしまう。
「こっち側、人助けに使えばいいって前に西岐が言っていただろ」
言いながら左の手のひらを空に向け、ゆっくりと指を折って握りしめていく。こっちというのは父親から受け継いだ炎熱のことだろう。
「さっき頼まれてカマドの火をつけてる時になんか思い出して、さ……。少し嬉しかった」
あれほど忌み嫌っていた左側のことをこんな風に穏やかに話せるようになるなんて。体育祭からまだ二か月ほどしか経っていないのになんて成長なのだろう。
「よかったねえ……」
目からボロッと涙がこぼれた。
疲れのせいで感情が馬鹿になってしまっているらしい。
まさかこの流れで泣くとは思っていなかっただろう轟が狼狽する。
「な、なんで泣く?」
「玉ねぎじゃないのか!」
「玉ねぎなのか、西岐!」
飯田の見当違いっぷりと轟の天然っぷりが全力で西岐に向かってくる。もしかしなくとも、二人も相当疲れているらしい。
西岐にはツッコミを入れるだけの元気はなく、止まらなくなった涙を押さえようと手で覆うことくらいしかできず、それから暫くして早くしろと爆豪が憤慨しながら乱入して来るまで、この奇妙な光景は続いた。
今日こそは温泉でくつろぎたい。そう思っていた西岐は誰よりも早く浴場に向かい、人が増えてきて賑やかになる前に退散した。
静かな大部屋に戻って濡れた髪をタオルで適当に拭っていると、あとから入ってきた障子が西岐の方に近づいてきた。障子も風呂上りらしくいつものマスクの代わりにタオルを口元に巻き付けている。
「大丈夫か? 派手に個性使い続けたんだろ?」
そう心配そうに訊いてくる。
何度か使いすぎて疲弊しているところを見たからか障子はいつも気にかけてくれる。
「それはみんなおなじだよ」
夕飯時や風呂場で入れ違いになったみんなの様子を思い出しながら首を振った。みんな昨日ほどの元気はなくぐったりしていた。そして終始、会話の内容が訓練のことだった。
自分の能力はすぐ体力が削られ人よりハイリスクだと思い込んでいたが、なんてことはない、みんなそれぞれに限界があってそのなかでうまく使っていただけのこと。それを知った今、自分だけが特別疲れただなんて思わない。
「しょうじくんは今日どういうことしてたの?」
「俺はこういう……複製を増やしたり、早く複製できるように鍛錬したり、だな」
逆に問いかけると、障子は複製してみせる。以前より触手の先が伸びて枝分かれする。長く伸びたほうが手の形になり、短いほうには口が出現する。
「わあ、すごい。かわいい」
「……可愛い?」
西岐の口から出た形容詞に、障子は疑問符をつけて復唱する。
そんなことはもちろん聞き流して、西岐は器用に変化していく触手の先を見て感嘆の声を上げる。
障子はしばらく好きにさせてくれていたが、目が合うとその表情は幾らか沈んでいるように見えた。もう一度触手の先を手の形にすると、その指が西岐の濡れた前髪を摘まんだ。まるで相澤がしたような手の動きに何を意味しているのか分かってしまい、笑顔を消し少し目を伏せた。
「前髪、気になる?」
「そうだな」
「目立つもんね」
障子はため息をつく。
「死柄木に触られてこうなった、それを想像すると背筋が凍る」
「……うん」
直前まで一緒にいた障子を置き去りにして死柄木を追いかけ、そのあとは自宅謹慎。次に顔を合わせた時にはこの髪になっていた。あの時は黙って荷物を渡してくれたけれど言いたいことが山のようにあったのだろう。
「USJの時からそうだが、西岐はいつも一人で勝手に無茶をするから気が気ではない」
「ごめんなさい」
いつもというのには語弊があるように思えたが今は反論する空気ではなく、素直に謝罪を口にして西岐はしゅんと小さくなった。
怒るのとは違う、落ち着いた物言いがかえって申し訳ない気持ちにさせてくる。
「俺……訓練がんばる。もっと力つけて、心配かけないくらい強くなる」
気合いを入れるように拳を握り締めると、障子の目がまたらしくなく遠くへと彷徨う。何か考えているようだがそれを西岐に言うことはなく、前髪をいじっていた手が離れていく。
奇妙な空気が大部屋に漂うが、ガタンという激しい音で掻き消える。
「れぇくん、今日は女子部屋に来な……はわわわっ!」
引き戸を開けて顔をのぞかせたのは麗日。昨日に引き続いて女子の部屋に招こうと訪れたらしいが、西岐と障子を見るなり顔を赤くして慌てふためく。
「あ、俺行った方がいい?」
「いやいやいや、大丈夫です、お気になさらず! 大変お邪魔しました!!」
西岐が畳に手をついて立ち上がろうとするが、麗日はせわしなく両手と首を振り、開けた時と同様派手な音を立てて閉め、足音が遠ざかっていく。心なしか悲鳴のような声が聞こえた気がする。
「え、なんだったの?」
「……さあな」
まるで台風一過ごとく去っていった麗日に、西岐と障子は二人そろって首を傾げるのだった。
誰かの声が聞こえた。
物凄く近くから聞こえるのに何と言っているのか聞き取ることが出来ない。
西岐も何か、言葉を発した。だがそれも聞こえない。自分の言葉なのに何を言っているのか分からない。
西岐の言葉で相手が笑ったような気配だけが伝わってくる。
誰かが近づいてきて大きな手のひらをかざす。
それが西岐の顔に触れ視界を覆った。
「――……」
目を開けると視界は真っ暗でまだ夢の続きなのかと思った。しかし周りからクラスメイトたちの寝息が聞こえてきて、西岐は強張っていた体から力を抜いた。
不思議な夢だった。
いつもの予知夢のように音はなく、それでいてはっきりと覚えている。覚えているのに何の役にも立たないくらい抽象的で、じっとりとした恐怖心だけが胸に残っている。
息を吐きながら顔を覆う。
変な夢を見てしまうのは疲れのせいなのか。
それともこれはやはり予知夢でこれから何かが起きるのか。
判然としないまま心臓が落ち着かず、再び眠ることもできない。
「眠れないのか?」
隣から声がかかる。
暗闇に慣れてきた目に常闇の顔を映す。
「……変な夢見ちゃった」
他のクラスメイトを起こさないように声を潜める。それでも結構響いてしまうから布団のぎりぎりまで常闇の方へと詰める。
「とこやみくんは起きてた?」
「宵闇に覆われる刻が俺の本当の時間だからな」
落ち着いた声で放つ言葉はすぐには理解できず西岐は何度か脳内で反芻した。
夜行性ということだろうか。
影が個性な彼らしいと言えばらしい。
とはいっても完全に夜行性というわけではないようで目が眠そうにショボショボ瞬いている。
真っ暗で時間が分からないがきっとまだ真夜中だ。
「寝ていいよ、俺も寝るから」
「……分かった」
睡眠を促すと常闇はすんなり頷くが、何故か自分の肌掛けを捲って横のスペースをポンポンと叩いている。意味を汲み取れず見ていると、脇から出てきたダークシャドウが西岐を咥え、常闇の隣へ引きずっていく。そして西岐ごと肌掛けをかけ直す。
予想しなかった出来事に驚き、漏れそうになった声をどうにか飲み込む。
常闇の腕が引き寄せるように背中に回され、西岐の頭の横にダークシャドウが横たわる。
どういうことなのか分からず暫く固まっているが、伝わってくる鼓動とぬくもりが遠くあった眠気を呼び戻し、もう一度西岐の目蓋を下ろしていく。それが心地よくて西岐は身を預ける。
ぎゅっと腕に力が籠められるのを感じながら、眠りへと落ちていった。
翌朝、くっついて眠る二人を見てクラスメイトたちが固まり、常闇も覚えのない自分の行動に硬直することになるのだが、それはまた別の話。
create 2017/11/23
update 2017/11/23
update 2017/11/23