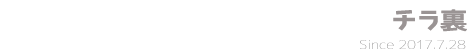林間合宿
家に帰るまでが合宿です
ヒロ×サイ|top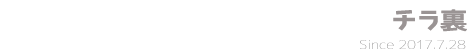
家に帰るまでが合宿です
「本当に大丈夫なんだろうな」
疑わしげな相澤の問いかけに西岐はいい加減タコが出来そうになっている耳を塞いだ。
病院を出て家に寄り、荷物を持って寮の前に来るまで、何度その質問を繰り返されたことか。念のために一日入院を伸ばした上で、医者からも退院の許可をもらっているのだからいい加減信用して欲しいのだが、荷物すら自分で持たせてもらえず、すべて相澤の両肩にぶら下がっていた。
寝具と着替えと学校関連の物、たったそれだけの荷物も負担だと思われているらしい。
しかしあんまり文句を言うと本日の入寮を取りやめにされてしまいそうで大人しく隣を歩く。
校舎から徒歩五分と聞いていたが本当に校舎からすぐ寮が立ち並んでいる。これを三日で建てたというのだから流石は雄英である。
「ここが……!」
大きく1-Aと書かれた棟の前に来ると期待で胸がいっぱいになる。
物心ついた時からシッターに預けられ、ある程度の年齢になってからはずっと一人暮らしをしてきた西岐には、共同生活というものが物凄く魅力的に感じられた。毎日クラスメイト達と過ごせるかと思うとわくわくして仕方がない。
はやる気持ちで玄関をくぐると広い空間とそこに居合わせたクラスメイト数名が目に入る。
「れぇちゃん!」
真っ先に声をかけてきたのは緑谷だ。零れ落ちそうな目を感情で揺らしながら駆け寄ってくる。
「かっちゃんから聞いた、大変だったね」
どうやら昨日、先に寮へ戻ってもらった爆豪がみんなに西岐のことを説明したらしい。
一斉に注目されて西岐は少し後退るが、後ろから入ってきた相澤にぶつかって下がれない。
「……お騒がせしました、あの、もうだいじょうぶだから」
元気だということをアピールするように二つの拳をブンブン振ってみるが、そんなことでみんなの表情が晴れやかになることはなく、困ったように相澤を見上げると西岐の肩に手を置いてその場の全員に視線を巡らせた。
「ま、そういうわけで今日から西岐も入寮だ。部屋は五階の一番奥、あとはお前らで案内してやってくれ」
そう言うと布団袋を緑谷に、着替えなどの入った大きなカバンを轟に渡してさっさと踵を返す。大丈夫だということを後押しして欲しかったのだが、そこへのフォローはなく無情にも扉が閉まる。
「荷物これだけか?」
「少ないね」
荷物を渡された二人は特に疑問にも思わないのか持ったまま、まずは一階を案内すべく奥に向かう。
西岐も靴からスリッパに履き替えて続く。
ソファースペース、ダイニングスペース、キッチン、ランドリー、共同風呂と玄関から時計回りにぐるっと回っている間も、クラスメイトに出くわすたびに大丈夫なのかと聞かれ、相当心配をかけてしまっていたことを思い知ることとなる。
「僕らも様子のおかしいれぇちゃんをみてるんだ、元に戻れてホント良かった」
エレベーターを待ちながら緑谷がポツリと漏らす。
「あ……救けに来てくれてありがと」
あまり覚えてはいないが緑谷たち五人が救出に来てくれたことは相澤から聞いた。あんな場所に来てしまうなんてと恐ろしくも思ったが、何より嬉しかった。
思い出してお礼を口にすると二人の表情がより一層沈む。
「え、どうしたの?」
扉が開いてエレベーターへ乗り込む二人を追いかける。狭い空間で三人だけになるとさらに空気が重く感じる。
「救けれてないし、他のみんな巻き込んで先生に怒られた。褒められることじゃない」
轟の言葉を聞いてそういうことかと理解する。
確かに資格のない彼らが救出に赴いたことはルール違反だし、教師の立場上叱らなければならないだろう。あの相澤のことだ、相当厳しい物言いをしたに違いない。
「ありがとう」
改めて口を開く。
まるで話を聞いていなかったかのように繰り返されたお礼の言葉に二人はきょとんと振り向く。
「ね、どういたしましては?」
相澤に怒られたかどうかなど西岐には関係なかった。まして救い出せたかどうかなんてどうでもいい。あの場所に来てくれたことが嬉しいのだ。
首を傾げて言葉を促す。
「……どういたしまして」
二人の声が綺麗に重なって返ってくる。
「ふふ」
西岐が満足げに笑うと、今度はエレベーター内に何とも言えない奇妙な空気が漂った。
咳払いをして荷物を持ち直す轟と、赤くなった頬を擦っている緑谷。
「やべぇな……今日から共同生活だろ、絶対もたねぇ」
「と、轟くん、ダメだからね、もたせてね」
意味ありげな視線が西岐を挟んで交わされたのだが、小さな電子音が五階に到着したことを告げ、西岐の意識は廊下の先へと向かっていた。
就寝の頃合いになって二人が自分たちの部屋へ戻っていったあと、西岐は寝具を敷いた備え付けのベッドに座って、何をするでもなくぼんやりしていた。照明のリモコンを手にとるが消すのを躊躇って枕元に戻した。
スマホから通知音が鳴って、開くと相澤からだった。物凄く信用されていないらしい。大丈夫かと書かれたメッセージに短く言葉を返す。
大丈夫じゃないとはとてもではないが言えない。
そう言ってしまえば二度とヒーローを目指したいと思えなくなってしまいそうな気がしたのだ。
しかし一人になると、ぞわぞわとした恐怖が足元から這い上がってきて、部屋の電気を消すことも出来なくなっていた。煌々と明かりが照らす中で膝を抱える。
合宿先の森の中からすでに記憶がおぼろげなのに、体の芯が凍るような恐怖は覚えている。大きな手のひらが視界を覆い隠していったその瞬間を頭に描いて、息が苦しくなっていく。
突如ノックの音が鳴り響いた。
身体が硬直する。
コンコン、コンコンと数回繰り返される。
ここは雄英の学生寮でクラスメイトしかいないと頭で分かっているのに動けなくなる。
「西岐、寝たか」
声を聞くなり身体のこわばりが解け、弾かれるように扉に走る。もたつきながら鍵を外して扉を開けると、やはりそこには障子の姿が。
「どうした、顔が真っ青だぞ」
西岐の顔を見るなり目を見開いて肩を掴んでくる。そう言われて血の気が引いているのを自覚した。
「やだな、前髪はやく伸びないかな……」
「バカ、隠すな」
顔を隠すように手を上げて冷たくなった指先で短い前髪を引っ張っていると、障子の手がやんわりと掴んで剥がしてしまう。記憶の中のあの手とは違う、優しい温かみに知らずのうちに視界がぶれる。
「大丈夫か?」
「うん」
「大丈夫じゃないだろ」
「うん」
「俺の部屋に来るか?」
「……うん」
障子の言葉全てに頷いていると、しょうがないなというようにマスクの下で笑って西岐を廊下へと促す。
部屋の鍵だけを持って素直についていく。
障子の部屋はちょうど西岐の部屋の真下だった。西岐もあまり多く物を置かないほうだが障子の部屋はもっと物がない。備え付けのベッドや勉強机も性に合わないのか用意してもらわなかったようだ。一人暮らしをしていた間も時折部屋にお邪魔して知ってはいたが、同じ間取りで見ると空間がやたら広く見える。
そんな部屋の隅にちょこんと置かれているクッションに気付いた。
「……あ……俺の」
「ああ、一応持ってきた」
手触りのいいそれを拾い上げてぎゅっと抱きしめる西岐を横目に、障子はマスクを外して敷いてあった布団に寝転がる。西岐もクッションごとその隣の空いたスペースに潜り込んだ。
寝転がった状態でリモコンのスイッチを押し、部屋が一気に暗くなる。
クッションに顔を埋めていた西岐が『あ』と小さく声を発すると、障子が少しだけ頭を浮かせて覗き込んでくる。
「しょうじくん、なにか俺に用事?」
「……今頃」
わざわざ部屋を訪ねてきたのだから用事があったはずだ。
それを思い出すと障子が脱力して頭を枕に沈める。
「ね、なに?」
「この体勢で話すのか」
「じゃあ起きる」
体を起こしてリモコンに手を伸ばそうとするが、その手を引っ張られ布団に舞い戻る。バランスを崩したせいで頭が障子の腕の上に落ちるが、びくともせず受け止め、もう片方の手が西岐を包むように後頭部に回された。
二人の間でクッションが窮屈そうに潰れている。
「無事でよかった」
吐息のように耳に届く。
西岐は緩みそうになった何かを堪えて、目を伏せた。
「……しょうじくんも、腕斬られたって聞いた」
「複製した部分だ」
「でも……痛いよね」
大変だったのは自分だけじゃない。意識不明で倒れた者も怪我を負った者も大勢いたと聞いた。クラスメイト達の怪我については特に相澤から細かく聞き出して心を痛めていたのだ。
今は癒えているらしいが腕を斬られるというのは、話を聞いただけで泣きそうになったくらいに壮絶だ。
だが障子の手が西岐の口を摘まんで言葉を封じる。
「俺の怪我はどうでもいい」
どうでもよくないという反論がもごもごと口の中にこもる。障子は自分の怪我など本当にどうでもいいと思っていそうで嫌だ。元々誰かのために身を挺することを厭わないところがあるから余計に。
しかし障子の話したいことは別のところにあるらしく、暗闇に慣れてきた目が障子の真剣な面持ちを映し出す。
「こういうことは口に出すと陳腐になるから言うかどうか何度も迷った」
こんな風に前置きをして話すのは珍しい。これまで何度か思案気にしては反らされた視線を思い出し、西岐はもう言葉を挟むのをやめて静かに続きを待つ。
「お前は強いし、俺はお前を守ってやれるほど今は強くない。だけどすぐ何かに巻き込まれていくお前を見ているだけなのは嫌だ。お前は心配かけないように強くなると言っていたがそれも嫌なんだ、俺は心配できる立ち位置にいたい」
落ち着いた言葉遣いで伝えられる障子の気持ちに相槌だけ返す。初めて聞く障子の剥き出しの思いかもしれない。
「だから……俺は今よりもっと強くなる。それでお前を守れるようになる。その決意表明がしたかった」
注がれた言葉を西岐は何度も胸の中で噛みしめた。誰かに守りたいだなんて言われたのは生まれて初めてのことだった。身内からでさえ言われたことはない。
じわじわと嬉しさが滲んで口元を綻ばせてしまう。
「じゃあ……じゃあしょうじくんは俺が守る」
大きく膨らんだ嬉しさが口から勢いよく飛び出していく。いつもの力の入っていないような声が幾らか弾む。
障子は虚を突かれたのか一瞬言葉に詰まった。
「は? いや……」
「俺も強くなるから」
「お前ぜんぜん……」
「一緒に鍛えて行こうね」
「分かってないな……話を聞け」
「そうと決まったら明日からトレーニングだし寝なきゃ」
もぞもぞと寝心地のいい体制を探し、向かい合わせになった障子の顔を真っ直ぐ見つめる。西岐の目が弓なりになると、障子は諦めたように肩で息を吐き、優しく何度か頭を撫でてから目を閉じた。
「おやすみ、しょうじくん」
「おやすみ」
自分の部屋で感じた恐怖心のことはもうすっかり忘れ、西岐も静かに目を閉じるのだった。
疑わしげな相澤の問いかけに西岐はいい加減タコが出来そうになっている耳を塞いだ。
病院を出て家に寄り、荷物を持って寮の前に来るまで、何度その質問を繰り返されたことか。念のために一日入院を伸ばした上で、医者からも退院の許可をもらっているのだからいい加減信用して欲しいのだが、荷物すら自分で持たせてもらえず、すべて相澤の両肩にぶら下がっていた。
寝具と着替えと学校関連の物、たったそれだけの荷物も負担だと思われているらしい。
しかしあんまり文句を言うと本日の入寮を取りやめにされてしまいそうで大人しく隣を歩く。
校舎から徒歩五分と聞いていたが本当に校舎からすぐ寮が立ち並んでいる。これを三日で建てたというのだから流石は雄英である。
「ここが……!」
大きく1-Aと書かれた棟の前に来ると期待で胸がいっぱいになる。
物心ついた時からシッターに預けられ、ある程度の年齢になってからはずっと一人暮らしをしてきた西岐には、共同生活というものが物凄く魅力的に感じられた。毎日クラスメイト達と過ごせるかと思うとわくわくして仕方がない。
はやる気持ちで玄関をくぐると広い空間とそこに居合わせたクラスメイト数名が目に入る。
「れぇちゃん!」
真っ先に声をかけてきたのは緑谷だ。零れ落ちそうな目を感情で揺らしながら駆け寄ってくる。
「かっちゃんから聞いた、大変だったね」
どうやら昨日、先に寮へ戻ってもらった爆豪がみんなに西岐のことを説明したらしい。
一斉に注目されて西岐は少し後退るが、後ろから入ってきた相澤にぶつかって下がれない。
「……お騒がせしました、あの、もうだいじょうぶだから」
元気だということをアピールするように二つの拳をブンブン振ってみるが、そんなことでみんなの表情が晴れやかになることはなく、困ったように相澤を見上げると西岐の肩に手を置いてその場の全員に視線を巡らせた。
「ま、そういうわけで今日から西岐も入寮だ。部屋は五階の一番奥、あとはお前らで案内してやってくれ」
そう言うと布団袋を緑谷に、着替えなどの入った大きなカバンを轟に渡してさっさと踵を返す。大丈夫だということを後押しして欲しかったのだが、そこへのフォローはなく無情にも扉が閉まる。
「荷物これだけか?」
「少ないね」
荷物を渡された二人は特に疑問にも思わないのか持ったまま、まずは一階を案内すべく奥に向かう。
西岐も靴からスリッパに履き替えて続く。
ソファースペース、ダイニングスペース、キッチン、ランドリー、共同風呂と玄関から時計回りにぐるっと回っている間も、クラスメイトに出くわすたびに大丈夫なのかと聞かれ、相当心配をかけてしまっていたことを思い知ることとなる。
「僕らも様子のおかしいれぇちゃんをみてるんだ、元に戻れてホント良かった」
エレベーターを待ちながら緑谷がポツリと漏らす。
「あ……救けに来てくれてありがと」
あまり覚えてはいないが緑谷たち五人が救出に来てくれたことは相澤から聞いた。あんな場所に来てしまうなんてと恐ろしくも思ったが、何より嬉しかった。
思い出してお礼を口にすると二人の表情がより一層沈む。
「え、どうしたの?」
扉が開いてエレベーターへ乗り込む二人を追いかける。狭い空間で三人だけになるとさらに空気が重く感じる。
「救けれてないし、他のみんな巻き込んで先生に怒られた。褒められることじゃない」
轟の言葉を聞いてそういうことかと理解する。
確かに資格のない彼らが救出に赴いたことはルール違反だし、教師の立場上叱らなければならないだろう。あの相澤のことだ、相当厳しい物言いをしたに違いない。
「ありがとう」
改めて口を開く。
まるで話を聞いていなかったかのように繰り返されたお礼の言葉に二人はきょとんと振り向く。
「ね、どういたしましては?」
相澤に怒られたかどうかなど西岐には関係なかった。まして救い出せたかどうかなんてどうでもいい。あの場所に来てくれたことが嬉しいのだ。
首を傾げて言葉を促す。
「……どういたしまして」
二人の声が綺麗に重なって返ってくる。
「ふふ」
西岐が満足げに笑うと、今度はエレベーター内に何とも言えない奇妙な空気が漂った。
咳払いをして荷物を持ち直す轟と、赤くなった頬を擦っている緑谷。
「やべぇな……今日から共同生活だろ、絶対もたねぇ」
「と、轟くん、ダメだからね、もたせてね」
意味ありげな視線が西岐を挟んで交わされたのだが、小さな電子音が五階に到着したことを告げ、西岐の意識は廊下の先へと向かっていた。
就寝の頃合いになって二人が自分たちの部屋へ戻っていったあと、西岐は寝具を敷いた備え付けのベッドに座って、何をするでもなくぼんやりしていた。照明のリモコンを手にとるが消すのを躊躇って枕元に戻した。
スマホから通知音が鳴って、開くと相澤からだった。物凄く信用されていないらしい。大丈夫かと書かれたメッセージに短く言葉を返す。
大丈夫じゃないとはとてもではないが言えない。
そう言ってしまえば二度とヒーローを目指したいと思えなくなってしまいそうな気がしたのだ。
しかし一人になると、ぞわぞわとした恐怖が足元から這い上がってきて、部屋の電気を消すことも出来なくなっていた。煌々と明かりが照らす中で膝を抱える。
合宿先の森の中からすでに記憶がおぼろげなのに、体の芯が凍るような恐怖は覚えている。大きな手のひらが視界を覆い隠していったその瞬間を頭に描いて、息が苦しくなっていく。
突如ノックの音が鳴り響いた。
身体が硬直する。
コンコン、コンコンと数回繰り返される。
ここは雄英の学生寮でクラスメイトしかいないと頭で分かっているのに動けなくなる。
「西岐、寝たか」
声を聞くなり身体のこわばりが解け、弾かれるように扉に走る。もたつきながら鍵を外して扉を開けると、やはりそこには障子の姿が。
「どうした、顔が真っ青だぞ」
西岐の顔を見るなり目を見開いて肩を掴んでくる。そう言われて血の気が引いているのを自覚した。
「やだな、前髪はやく伸びないかな……」
「バカ、隠すな」
顔を隠すように手を上げて冷たくなった指先で短い前髪を引っ張っていると、障子の手がやんわりと掴んで剥がしてしまう。記憶の中のあの手とは違う、優しい温かみに知らずのうちに視界がぶれる。
「大丈夫か?」
「うん」
「大丈夫じゃないだろ」
「うん」
「俺の部屋に来るか?」
「……うん」
障子の言葉全てに頷いていると、しょうがないなというようにマスクの下で笑って西岐を廊下へと促す。
部屋の鍵だけを持って素直についていく。
障子の部屋はちょうど西岐の部屋の真下だった。西岐もあまり多く物を置かないほうだが障子の部屋はもっと物がない。備え付けのベッドや勉強机も性に合わないのか用意してもらわなかったようだ。一人暮らしをしていた間も時折部屋にお邪魔して知ってはいたが、同じ間取りで見ると空間がやたら広く見える。
そんな部屋の隅にちょこんと置かれているクッションに気付いた。
「……あ……俺の」
「ああ、一応持ってきた」
手触りのいいそれを拾い上げてぎゅっと抱きしめる西岐を横目に、障子はマスクを外して敷いてあった布団に寝転がる。西岐もクッションごとその隣の空いたスペースに潜り込んだ。
寝転がった状態でリモコンのスイッチを押し、部屋が一気に暗くなる。
クッションに顔を埋めていた西岐が『あ』と小さく声を発すると、障子が少しだけ頭を浮かせて覗き込んでくる。
「しょうじくん、なにか俺に用事?」
「……今頃」
わざわざ部屋を訪ねてきたのだから用事があったはずだ。
それを思い出すと障子が脱力して頭を枕に沈める。
「ね、なに?」
「この体勢で話すのか」
「じゃあ起きる」
体を起こしてリモコンに手を伸ばそうとするが、その手を引っ張られ布団に舞い戻る。バランスを崩したせいで頭が障子の腕の上に落ちるが、びくともせず受け止め、もう片方の手が西岐を包むように後頭部に回された。
二人の間でクッションが窮屈そうに潰れている。
「無事でよかった」
吐息のように耳に届く。
西岐は緩みそうになった何かを堪えて、目を伏せた。
「……しょうじくんも、腕斬られたって聞いた」
「複製した部分だ」
「でも……痛いよね」
大変だったのは自分だけじゃない。意識不明で倒れた者も怪我を負った者も大勢いたと聞いた。クラスメイト達の怪我については特に相澤から細かく聞き出して心を痛めていたのだ。
今は癒えているらしいが腕を斬られるというのは、話を聞いただけで泣きそうになったくらいに壮絶だ。
だが障子の手が西岐の口を摘まんで言葉を封じる。
「俺の怪我はどうでもいい」
どうでもよくないという反論がもごもごと口の中にこもる。障子は自分の怪我など本当にどうでもいいと思っていそうで嫌だ。元々誰かのために身を挺することを厭わないところがあるから余計に。
しかし障子の話したいことは別のところにあるらしく、暗闇に慣れてきた目が障子の真剣な面持ちを映し出す。
「こういうことは口に出すと陳腐になるから言うかどうか何度も迷った」
こんな風に前置きをして話すのは珍しい。これまで何度か思案気にしては反らされた視線を思い出し、西岐はもう言葉を挟むのをやめて静かに続きを待つ。
「お前は強いし、俺はお前を守ってやれるほど今は強くない。だけどすぐ何かに巻き込まれていくお前を見ているだけなのは嫌だ。お前は心配かけないように強くなると言っていたがそれも嫌なんだ、俺は心配できる立ち位置にいたい」
落ち着いた言葉遣いで伝えられる障子の気持ちに相槌だけ返す。初めて聞く障子の剥き出しの思いかもしれない。
「だから……俺は今よりもっと強くなる。それでお前を守れるようになる。その決意表明がしたかった」
注がれた言葉を西岐は何度も胸の中で噛みしめた。誰かに守りたいだなんて言われたのは生まれて初めてのことだった。身内からでさえ言われたことはない。
じわじわと嬉しさが滲んで口元を綻ばせてしまう。
「じゃあ……じゃあしょうじくんは俺が守る」
大きく膨らんだ嬉しさが口から勢いよく飛び出していく。いつもの力の入っていないような声が幾らか弾む。
障子は虚を突かれたのか一瞬言葉に詰まった。
「は? いや……」
「俺も強くなるから」
「お前ぜんぜん……」
「一緒に鍛えて行こうね」
「分かってないな……話を聞け」
「そうと決まったら明日からトレーニングだし寝なきゃ」
もぞもぞと寝心地のいい体制を探し、向かい合わせになった障子の顔を真っ直ぐ見つめる。西岐の目が弓なりになると、障子は諦めたように肩で息を吐き、優しく何度か頭を撫でてから目を閉じた。
「おやすみ、しょうじくん」
「おやすみ」
自分の部屋で感じた恐怖心のことはもうすっかり忘れ、西岐も静かに目を閉じるのだった。
create 2017/12/03
update 2017/12/03
update 2017/12/03