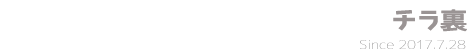仮免許
必殺技
ヒロ×サイ|top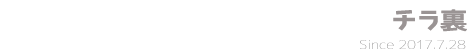
必殺技
必殺技。
これすなわち必勝の型・技のこと。
戦闘とはいかに自分の得意を押し付けるか。
技は己を象徴する。
ということでクラスメイト達がすでに取り掛かっている圧縮訓練に、西岐も遅ればせながら加わった。
「必殺技……か……」
順調に進んでいるらしいクラスメイト達を見渡して、西岐は途方に暮れた顔をしていた。
「……必殺技」
繰り返し呟いてみるが何かが浮かんでくる気配はない。
元々ヒーローを目指していたわけではないということもあってか、思い描いていた自分だけの技というものが西岐にはなかった。
そもそも、瞬間移動は瞬間移動、抑制は抑制。アレンジを加えて違う使い方をするなんて考えたこともなければ、そんなことが出来る気もしない。
自分の発想力の乏しさに頭を抱えそうになっていると、横から蹴りが飛んでくる。
「ヌボーットスルナ」
寸でのところで後ろに飛びのいて避けると、エクトプラズムの蹴りが二手三手と追いかけてきて結局横っ腹に一撃食らってしまう。
「……あたた、……せんせぇ、なんも浮かばない」
トン、トンと大きく飛び跳ねて逃げる。一撃さえ見舞えば気が済んだのかエクトプラズムは一旦立ち止まり、表情の見えないマスク越しに脇腹を抑える西岐を見下ろした。
「コウシタイトイウ希望・方向性モナイノカ」
「んー……んん、ないです」
警戒して距離をとった状態で頭を捻るが浮かんでくる気がしない。
ここに至って、ヒーローになるための自己主張の強さも将来へのビジョンも何もないことに気付いた。思うまま動ける力は欲しいが、それをヒーローとしてどう使うかなど考えたこともなかったのだ。
体育祭、ヒーロー名、その都度いちいち躓いていた理由はこれなのだろう。
「ナラバ手合ワセヲシナガラ方向性ヲ探ロウ」
怒るでも呆れるでもなく冷静に方針を告げるのはさすが最高峰雄英の教師。
頷き身構える西岐を前にして再び攻撃の体勢となった。
二本の脚と俊敏な動作に翻弄され訓練初日をあっという間に終えた。西岐とてそれなりの素早さと神出鬼没さを身につけてきていると思っていたが、エクトプラズムの身体能力はさらにその上を行き、数でも西岐を圧倒した。
ヒーローへの道はそう容易くない。
心身ともにへとへとになって寮へと帰ってきた。
どうにか部屋まで辿り着くとカバンを放り投げてベッドへとダイブする。ネクタイを緩め、スラックスを脱ぎ捨てながら布団に潜り込む。
結局、必殺技の方向性も何も見つからなかった。
どういうヒーローになりたいのかもう一度目蓋の裏に描いてみる。
「……だって……イレイザーさんの必殺技なんて見たことない」
静かな部屋に言葉が溶けていく。
それから眠ったのか目を閉じていただけなのか、部屋の中がすっかり真っ暗になった頃、扉がノックされた。
すぐに反応できずにいると、乱暴に何度も叩かれる。
「はーあーいー」
ベッドの上から返事をしてのそのそと起き上がる。
扉を開けると不機嫌顔の爆豪が立っていた。口を開きかけた爆豪は上から下へと視線を滑らせて目を見開いた。
「――ばっ、か、お前、なんて格好でドア開けてんだ!!」
西岐の身体を部屋の中に押し込み、後ろ手でドアを閉める爆豪に思わず身を縮こませる。未だに彼の恫喝的な声は恐ろしく感じてしまう。
そんな可笑しな格好をしていただろうかと自分の身体を見下ろして、あっと小さな声が漏れた。
制服のシャツ以外、身に着けているものといえば下着とタンクトップだけ。
「……あ、あ、ごめんね」
確かにこれはみっともない。
クローゼットから部屋着をとって手早く着替える。
どうしてか部屋に入ってきた爆豪はその間じっと見張るように扉を背にしている。
「あ、の…えっと」
「大概その無防備さはどうにかなんねぇのかよ」
いつものゆったりした部屋着に身を包むと今更ながら何の用かと問おうとして、爆豪のイライラした声が被さった。
「……? 善処します」
これ以上苛立たせないほうがいいだろうと意味を理解しないで頷くと、小さな舌打ちが聞こえた。
「まあいい、ちょっと来い」
今度は返事も聞かずに西岐の手を掴んで扉の外へと引っ張り出す。鍵を閉める時間も与えられずルームシューズだけはどうにかひっかけ、ぐいぐい引っ張られて一階まで連れて行かれた。
「よお、れぇ。やっと来たか」
「準備は万端だぜ、れぇちゃん!」
「安心して任せろよ!」
ダイニング横の空いたスペースで切島が椅子、上鳴が大きなビニール袋、瀬呂がコームとハサミを持って待ち構えていた。
板敷きの床には新聞紙が敷かれ、その上に椅子が置かれた。
「ほら、座れよ」
爆豪が掴んでいるのとは反対の手を切島がとると、爆豪の手が緩む。招かれるまま椅子に座り、首にビニール袋を巻かれハサミを持った瀬呂が正面に立つ。残りの三人は近くのダイニングチェアに座った。
どういうことなのかさっぱり分からず不安が顔に出たのか、満面の笑みだった切島たちの表情が陰りを見せる。
「え、爆豪、説明した?」
「今しろ」
「うっそだろ」
全員の視線が呼びに来た爆豪に集まるが、もちろん説明は一切されていない。端的に一蹴されて上鳴が乾いた笑いを浮かべた。
「れぇちゃんの前髪ずっとガタガタなままじゃん? だから俺が切ってあげようと思って」
瀬呂の指が西岐の前髪を指さす。視界に時々入る長い部分と額をくすぐる短い部分。確かにタイミングが無かったこともあって無残な状態のまま放置してしまっていた。
「それ見てっと俺らも気になるしな」
「嫌じゃなきゃ切ってもらえよ」
上鳴と切島が互いの言葉に頷きあって笑顔で西岐に向きなおる。
この前髪を見ていろんな人が気持ちを沈ませてきたのを自覚していた西岐は、そういうことなら是非と頭を下げる。
「あ……じゃあ、お願いします」
「はいよ、俺こういうの得意だから安心していいよ」
緊張をほぐすように言葉をかけてから瀬呂の指が髪に触れる。
「うっわ、髪やわらかっ」
「うるせーよ瀬呂」
「黙ってやれ」
反射的に声を上げた瀬呂に、上鳴と切島から野次が飛ぶ。
なんだか申し訳ない気持ちになって至近距離にある瀬呂の顔を見上げるが、しかし瀬呂には聞こえていないようで上機嫌で髪にハサミを入れ始める。
ハサミの音と優しい手つきに心地よくなって西岐は目を細める。
頬や鼻に落ちてくる髪の毛がこそばゆい。
前髪だけなので数分もかからずすぐにカットが終わって、瀬呂の指がそっと顔についた髪の毛を払いのけてくれる。
「なあ……れぇちゃんってあれだよな、前髪ない方がさ」
「俺は体育祭の時から気付いていた」
「お前らうっせーな」
背後で何やらごそごそ話す二人を瀬呂が野次り返すのを聞きながら、西岐は手渡された鏡を覗き込んだ。一番短い部分に合わせて切りそろえたからか全体がずいぶん短くなっているが、得意と言っただけあって自然に仕上げてくれている。
「わあ……ほんと上手、ありがとぉ」
「どういたしまして。れぇちゃんすんごい可愛いぜ」
お礼を言う西岐にへらへらと笑って返す瀬呂。
「さあさあ早く片付けないとな!」
「髪の毛散らばっちまうからな!」
それまで離れて見守っていた上鳴と切島がずかずかと割って入ってきて、西岐の首に巻いたビニールを剥がしたり、体についた髪の毛を払ったりしてから西岐をソファースペースへと追いやる。
自分の髪の毛の始末なのだからと手伝おうとするが、いいから座っていろと言われてしまい仕方なくソファーに座る。と、無言の爆豪が隣に腰かけ頬杖をついて覗き込んできた。
「……せいせいした」
彼にしては珍しく低くボソッとした声で聞き逃してしまった。
丸めた新聞紙とビニール袋をゴミ箱に押し込んで三人もそれぞれ腰かける。
「で、なんか悩んでる?」
切島から唐突に切り出されて戸惑っていると、三人のニヤニヤした顔が爆豪に向いた。どうも事の中心人物は爆豪らしい。
「れぇが煮詰まってるって、爆豪が」
「話聞いてやれって、爆豪が」
「そうそう、髪切るって口実で呼び出そうって、爆豪が」
「お前らマジでいっぺん殺ス」
畳みかけるような三人の言葉に爆豪が低く唸る。
「……お前必殺技のことで悩んでんだろ、いちいち視界に入ってきて鬱陶しいからさっさと話せ」
頬杖ついたままどうでもよさそうに吐き捨てる爆豪を見て、西岐の眉がへにゃりと垂れる。
前髪が短くなったせいなのか近頃は感情が表に出すぎているようだ。そんな風に気を使われてしまうなんて情けないことこの上ない。
口元に手を当てて自分を落ち着かせてからゆっくりと口を開く。
「必殺技、なんにも思い浮かばなくて……困ってる」
口に出してしまうと本当にそのまますぎて、相談にもならない気がしたが、三人は腕を組んでうーんと唸り始めた。
「れぇの戦闘スタイルって言ったらまず瞬間移動だろ」
「あれは外せない、鬼強!」
まるで自分のことのように真剣な顔つきで切島が西岐の一番得意とする能力をまず挙げ、上鳴も同意だと人差し指を向ける。
しかし瀬呂はさらに唸って首を傾げる。
「けど瞬間の移動だぜ。あれもう究極すぎて極めらんなくないか」
「それなんだよなぁ」
瀬呂の意見にも同意だとばかりに上鳴が頷く。
「あとは何ができるんだっけ」
上鳴からの問いかけに西岐は抑制・封印・幻影について説明した。
オールフォーワンによって無理やり植え付けられたものは、使うにしても人に知られるにしてもまだ抵抗があって言えなかった。
説明を聞いた三人は改めて知った西岐の能力に感嘆する。
「それだけの個性で必殺技かぁ……んー」
「組み合わせて技にしちゃう系?」
「いや、そういうのは状況で結構変わっちゃうぜ」
彼らが言うことも一通りは西岐も考えた。コンビネーション技に出来るならと考えてもみたのだが、技と呼べるほど昇華した組み合わせが浮かばない。切島の言う通り状況次第で組み合わせも変わるので、いろんなパターンを想定した組み合わせを考えることになり、現実的ではない。
答えのない問答に付き合わせてしまい申し訳ない気持ちでいると、上鳴が手をひらひらさせて苦笑する。
「つーか、いっこいっこの個性? 能力? それ自体もう必殺技じゃね? っていう」
上鳴は何気なく本音を吐き出しただけなのだろうが、西岐は目からうろこが落ちたような顔で上鳴を見つめた。
「確かに……これさえやれば勝てる、だな」
「じゃあもう必殺技はすでにあったってことか」
二人の声を聞きながら西岐は自分の二つの手のひらを見下ろす。
今使える能力自体がもう必殺技なのだと思ってもみなかった。そういう考え方はなかった。
「……いいのかな……それで」
もっと苦労して捻り出さなければ必殺技と呼んではいけないような気になっていた。そんなことは誰も言っていないのに。
不安と動揺に心を揺らしていると、切島にぽんぽんと肩を叩かれる。
「ダメだったらもう一回一緒に考えようぜ、な?」
切島の満面の笑みを見ていると胸にあった不安が消えていく。答えがないと思っていた悩みに答えを差し出される。
それならば今後は今ある能力をただひたすら伸ばしていけばいいだけ。
重く沈んでいた気持ちが一気に軽くなる。
明るさを取り戻した西岐の表情を見ていた爆豪が、目を細め口角を緩める。
「バカもたまには役に立つだろ」
聞き取りにくい音量で投げられた言葉はどこか満足そうだった。
これすなわち必勝の型・技のこと。
戦闘とはいかに自分の得意を押し付けるか。
技は己を象徴する。
ということでクラスメイト達がすでに取り掛かっている圧縮訓練に、西岐も遅ればせながら加わった。
「必殺技……か……」
順調に進んでいるらしいクラスメイト達を見渡して、西岐は途方に暮れた顔をしていた。
「……必殺技」
繰り返し呟いてみるが何かが浮かんでくる気配はない。
元々ヒーローを目指していたわけではないということもあってか、思い描いていた自分だけの技というものが西岐にはなかった。
そもそも、瞬間移動は瞬間移動、抑制は抑制。アレンジを加えて違う使い方をするなんて考えたこともなければ、そんなことが出来る気もしない。
自分の発想力の乏しさに頭を抱えそうになっていると、横から蹴りが飛んでくる。
「ヌボーットスルナ」
寸でのところで後ろに飛びのいて避けると、エクトプラズムの蹴りが二手三手と追いかけてきて結局横っ腹に一撃食らってしまう。
「……あたた、……せんせぇ、なんも浮かばない」
トン、トンと大きく飛び跳ねて逃げる。一撃さえ見舞えば気が済んだのかエクトプラズムは一旦立ち止まり、表情の見えないマスク越しに脇腹を抑える西岐を見下ろした。
「コウシタイトイウ希望・方向性モナイノカ」
「んー……んん、ないです」
警戒して距離をとった状態で頭を捻るが浮かんでくる気がしない。
ここに至って、ヒーローになるための自己主張の強さも将来へのビジョンも何もないことに気付いた。思うまま動ける力は欲しいが、それをヒーローとしてどう使うかなど考えたこともなかったのだ。
体育祭、ヒーロー名、その都度いちいち躓いていた理由はこれなのだろう。
「ナラバ手合ワセヲシナガラ方向性ヲ探ロウ」
怒るでも呆れるでもなく冷静に方針を告げるのはさすが最高峰雄英の教師。
頷き身構える西岐を前にして再び攻撃の体勢となった。
二本の脚と俊敏な動作に翻弄され訓練初日をあっという間に終えた。西岐とてそれなりの素早さと神出鬼没さを身につけてきていると思っていたが、エクトプラズムの身体能力はさらにその上を行き、数でも西岐を圧倒した。
ヒーローへの道はそう容易くない。
心身ともにへとへとになって寮へと帰ってきた。
どうにか部屋まで辿り着くとカバンを放り投げてベッドへとダイブする。ネクタイを緩め、スラックスを脱ぎ捨てながら布団に潜り込む。
結局、必殺技の方向性も何も見つからなかった。
どういうヒーローになりたいのかもう一度目蓋の裏に描いてみる。
「……だって……イレイザーさんの必殺技なんて見たことない」
静かな部屋に言葉が溶けていく。
それから眠ったのか目を閉じていただけなのか、部屋の中がすっかり真っ暗になった頃、扉がノックされた。
すぐに反応できずにいると、乱暴に何度も叩かれる。
「はーあーいー」
ベッドの上から返事をしてのそのそと起き上がる。
扉を開けると不機嫌顔の爆豪が立っていた。口を開きかけた爆豪は上から下へと視線を滑らせて目を見開いた。
「――ばっ、か、お前、なんて格好でドア開けてんだ!!」
西岐の身体を部屋の中に押し込み、後ろ手でドアを閉める爆豪に思わず身を縮こませる。未だに彼の恫喝的な声は恐ろしく感じてしまう。
そんな可笑しな格好をしていただろうかと自分の身体を見下ろして、あっと小さな声が漏れた。
制服のシャツ以外、身に着けているものといえば下着とタンクトップだけ。
「……あ、あ、ごめんね」
確かにこれはみっともない。
クローゼットから部屋着をとって手早く着替える。
どうしてか部屋に入ってきた爆豪はその間じっと見張るように扉を背にしている。
「あ、の…えっと」
「大概その無防備さはどうにかなんねぇのかよ」
いつものゆったりした部屋着に身を包むと今更ながら何の用かと問おうとして、爆豪のイライラした声が被さった。
「……? 善処します」
これ以上苛立たせないほうがいいだろうと意味を理解しないで頷くと、小さな舌打ちが聞こえた。
「まあいい、ちょっと来い」
今度は返事も聞かずに西岐の手を掴んで扉の外へと引っ張り出す。鍵を閉める時間も与えられずルームシューズだけはどうにかひっかけ、ぐいぐい引っ張られて一階まで連れて行かれた。
「よお、れぇ。やっと来たか」
「準備は万端だぜ、れぇちゃん!」
「安心して任せろよ!」
ダイニング横の空いたスペースで切島が椅子、上鳴が大きなビニール袋、瀬呂がコームとハサミを持って待ち構えていた。
板敷きの床には新聞紙が敷かれ、その上に椅子が置かれた。
「ほら、座れよ」
爆豪が掴んでいるのとは反対の手を切島がとると、爆豪の手が緩む。招かれるまま椅子に座り、首にビニール袋を巻かれハサミを持った瀬呂が正面に立つ。残りの三人は近くのダイニングチェアに座った。
どういうことなのかさっぱり分からず不安が顔に出たのか、満面の笑みだった切島たちの表情が陰りを見せる。
「え、爆豪、説明した?」
「今しろ」
「うっそだろ」
全員の視線が呼びに来た爆豪に集まるが、もちろん説明は一切されていない。端的に一蹴されて上鳴が乾いた笑いを浮かべた。
「れぇちゃんの前髪ずっとガタガタなままじゃん? だから俺が切ってあげようと思って」
瀬呂の指が西岐の前髪を指さす。視界に時々入る長い部分と額をくすぐる短い部分。確かにタイミングが無かったこともあって無残な状態のまま放置してしまっていた。
「それ見てっと俺らも気になるしな」
「嫌じゃなきゃ切ってもらえよ」
上鳴と切島が互いの言葉に頷きあって笑顔で西岐に向きなおる。
この前髪を見ていろんな人が気持ちを沈ませてきたのを自覚していた西岐は、そういうことなら是非と頭を下げる。
「あ……じゃあ、お願いします」
「はいよ、俺こういうの得意だから安心していいよ」
緊張をほぐすように言葉をかけてから瀬呂の指が髪に触れる。
「うっわ、髪やわらかっ」
「うるせーよ瀬呂」
「黙ってやれ」
反射的に声を上げた瀬呂に、上鳴と切島から野次が飛ぶ。
なんだか申し訳ない気持ちになって至近距離にある瀬呂の顔を見上げるが、しかし瀬呂には聞こえていないようで上機嫌で髪にハサミを入れ始める。
ハサミの音と優しい手つきに心地よくなって西岐は目を細める。
頬や鼻に落ちてくる髪の毛がこそばゆい。
前髪だけなので数分もかからずすぐにカットが終わって、瀬呂の指がそっと顔についた髪の毛を払いのけてくれる。
「なあ……れぇちゃんってあれだよな、前髪ない方がさ」
「俺は体育祭の時から気付いていた」
「お前らうっせーな」
背後で何やらごそごそ話す二人を瀬呂が野次り返すのを聞きながら、西岐は手渡された鏡を覗き込んだ。一番短い部分に合わせて切りそろえたからか全体がずいぶん短くなっているが、得意と言っただけあって自然に仕上げてくれている。
「わあ……ほんと上手、ありがとぉ」
「どういたしまして。れぇちゃんすんごい可愛いぜ」
お礼を言う西岐にへらへらと笑って返す瀬呂。
「さあさあ早く片付けないとな!」
「髪の毛散らばっちまうからな!」
それまで離れて見守っていた上鳴と切島がずかずかと割って入ってきて、西岐の首に巻いたビニールを剥がしたり、体についた髪の毛を払ったりしてから西岐をソファースペースへと追いやる。
自分の髪の毛の始末なのだからと手伝おうとするが、いいから座っていろと言われてしまい仕方なくソファーに座る。と、無言の爆豪が隣に腰かけ頬杖をついて覗き込んできた。
「……せいせいした」
彼にしては珍しく低くボソッとした声で聞き逃してしまった。
丸めた新聞紙とビニール袋をゴミ箱に押し込んで三人もそれぞれ腰かける。
「で、なんか悩んでる?」
切島から唐突に切り出されて戸惑っていると、三人のニヤニヤした顔が爆豪に向いた。どうも事の中心人物は爆豪らしい。
「れぇが煮詰まってるって、爆豪が」
「話聞いてやれって、爆豪が」
「そうそう、髪切るって口実で呼び出そうって、爆豪が」
「お前らマジでいっぺん殺ス」
畳みかけるような三人の言葉に爆豪が低く唸る。
「……お前必殺技のことで悩んでんだろ、いちいち視界に入ってきて鬱陶しいからさっさと話せ」
頬杖ついたままどうでもよさそうに吐き捨てる爆豪を見て、西岐の眉がへにゃりと垂れる。
前髪が短くなったせいなのか近頃は感情が表に出すぎているようだ。そんな風に気を使われてしまうなんて情けないことこの上ない。
口元に手を当てて自分を落ち着かせてからゆっくりと口を開く。
「必殺技、なんにも思い浮かばなくて……困ってる」
口に出してしまうと本当にそのまますぎて、相談にもならない気がしたが、三人は腕を組んでうーんと唸り始めた。
「れぇの戦闘スタイルって言ったらまず瞬間移動だろ」
「あれは外せない、鬼強!」
まるで自分のことのように真剣な顔つきで切島が西岐の一番得意とする能力をまず挙げ、上鳴も同意だと人差し指を向ける。
しかし瀬呂はさらに唸って首を傾げる。
「けど瞬間の移動だぜ。あれもう究極すぎて極めらんなくないか」
「それなんだよなぁ」
瀬呂の意見にも同意だとばかりに上鳴が頷く。
「あとは何ができるんだっけ」
上鳴からの問いかけに西岐は抑制・封印・幻影について説明した。
オールフォーワンによって無理やり植え付けられたものは、使うにしても人に知られるにしてもまだ抵抗があって言えなかった。
説明を聞いた三人は改めて知った西岐の能力に感嘆する。
「それだけの個性で必殺技かぁ……んー」
「組み合わせて技にしちゃう系?」
「いや、そういうのは状況で結構変わっちゃうぜ」
彼らが言うことも一通りは西岐も考えた。コンビネーション技に出来るならと考えてもみたのだが、技と呼べるほど昇華した組み合わせが浮かばない。切島の言う通り状況次第で組み合わせも変わるので、いろんなパターンを想定した組み合わせを考えることになり、現実的ではない。
答えのない問答に付き合わせてしまい申し訳ない気持ちでいると、上鳴が手をひらひらさせて苦笑する。
「つーか、いっこいっこの個性? 能力? それ自体もう必殺技じゃね? っていう」
上鳴は何気なく本音を吐き出しただけなのだろうが、西岐は目からうろこが落ちたような顔で上鳴を見つめた。
「確かに……これさえやれば勝てる、だな」
「じゃあもう必殺技はすでにあったってことか」
二人の声を聞きながら西岐は自分の二つの手のひらを見下ろす。
今使える能力自体がもう必殺技なのだと思ってもみなかった。そういう考え方はなかった。
「……いいのかな……それで」
もっと苦労して捻り出さなければ必殺技と呼んではいけないような気になっていた。そんなことは誰も言っていないのに。
不安と動揺に心を揺らしていると、切島にぽんぽんと肩を叩かれる。
「ダメだったらもう一回一緒に考えようぜ、な?」
切島の満面の笑みを見ていると胸にあった不安が消えていく。答えがないと思っていた悩みに答えを差し出される。
それならば今後は今ある能力をただひたすら伸ばしていけばいいだけ。
重く沈んでいた気持ちが一気に軽くなる。
明るさを取り戻した西岐の表情を見ていた爆豪が、目を細め口角を緩める。
「バカもたまには役に立つだろ」
聞き取りにくい音量で投げられた言葉はどこか満足そうだった。
create 2017/12/11
update 2017/12/11
update 2017/12/11