外が騒がしいと感じてはいた。
けれどそれは何処か遠くの国の出来事の様に感じていたもの、また事実だった。
ミミックによる騒動が激化すると共に、自ずと私の行動範囲は狭くなっていったけれど。
でもそれは今までだってそう変わらないことで。
だからこそ、私は私の為だけに誂えられた此の部屋で、怪我人の為の薬を調合していた。
漢方は、遅効性だ。
ゆっくりじわじわと効力を発揮する古からの叡智は、如何したって今のような戦場では役に立たない。
こんなものをこつこつ作るよりは、戦場に赴いて治療に当たる方が何倍も価値も意味もあるのだろう。
然し私は"下級構成員に異能を遣ってはならない"と云う縛りがある為、出来ることは如何したって限られてしまうのだ。
少しでも、役に立ちたい。
少しでも、痛みに呻く人たちの扶けになりたい。
結局は只の自己満足。
だけれど、其れを無意味と切り捨てる事は、兄代わり曰く"甘ったれ"である私には出来なかった。
無能であると判っていても、何かひとつくらいは自分を役立たせたかったのだ。
ゴリゴリと薬研で薬剤を細かく擂り潰していく。
漢方は個人の躯に合わせて調合していくものだけれど、下準備はなるべくでも済ませておいた方がいい。
今日はあと20種類の薬剤を擂り潰し、乾燥させておかなければ。
痛み止と、睡眠導入と、あと、あとはどれを作っておこう。
日中は救護室で銃痕等の処置に追われてしまうから、薬剤関係は夜の内に済ませて置きたいのだ。
フラッシュバックによって眠れない構成員も沢山いる。
ああそうだ、精神安定の薬も調合しなければ──。
「───やぁ。こんな時間迄、未だ起きて居たのかい?」
声に、ぱっと出入りの扉を振り向いた。
そうして其処に居た人に、私はきょとんと瞬きをする。
だって其処には、居る筈のない人が居たから。
「だ、だざ、い、様……? えっ、やだ嘘、いつの間にいらしたの?」
──此の部屋に至る迄の道中には、幾つかの仕掛けが施されている。
私は貴重な治癒能力保有者で、非戦闘員の非力な女。
だからこそ、私に辿り着く迄の経路を誰かが通ったら、直ぐ様小さく警報が鳴り、モニターが始動し、誰が近づいて来ているのか私に教えてくれるのだけれど。
其の警報が、モニターが。
何故か今、動いていない。
──不作動なんて、初めてかもしれない。
何か問題が起こる前に、森様にご報告して直していただかなければ。
けど、今此の忙しい時にお手を煩わせるようなことをしてしまっていいものか。
否でもなにか起きてからでは──なんて、思っていたら。
「……菫、此方をご覧」
「っ、!」
いつの間にか直ぐ側迄近付いていた太宰様に、顎を捕まれ、上を向かされる。
そうして驚くほど近くにある顔を、私は視界いっぱいにまじまじと見詰めることになったのだ。
「な、なん、なんですの……?」
「…………」
「……だざ──お兄様?」
呼び声が、自然と正される。
何故兄呼びに直してしまったのかは判らない。
けれど、何故か、こう呼ばなければならない気がしたのだ。
「……、…」
黒々とした黒曜石の様な瞳が、光りなく私のことを見詰めている。
たまにする目だ。何を考えているか判らない眼差しだ。
こうなった兄の頭の中では、私では及び知れぬ数多の思考がなされていて。
一度でもこうなってしまったら、私はいつだって兄の思考が終わるのを待つしかできない。
けれど、本当に。
こんなの、いつ振りだろうか。
そうして、ふと気づく。
兄の顔──包帯が、ない。
瞬間、何故だか胸がざわりと騒いだ気がした。
何でかは判らない。だけれど、なにかが起こる気がしてしまったのだ。
兄の瞳は、未だ私のことを見詰めている。
「お前、さ」
兄の指先が、私の瞳に掛かる前髪をゆっくりと払い除けていく。
切り揃えていた前髪はいつも気を抜くと私の瞳を隠してしまうから、兄は時折こうして私の前髪をよけたがる。
けれど今はそれが、如何にも違う意味を孕んでいるような気がした。
「──僕 のこと、すき?」
ゆっくりと、瞬きをする。
ぼく──僕。兄の一人称。
いつの間にかすり変わっていた、昔の兄の、自己の呼び名。
其れを聞いて、私はようやっと気がついた。
兄は今──傷付いている。
「…………すき、だわ」
思わず言葉を溢せば、兄の指先が私の頬に流れる。
そうして顎を掴んでいた手もゆっくりと這い上がり、私の顔は、兄の両手によって包まれた。
「それは、如何してだい?」
「それ、は、貴方が、貴方だから」
部屋は薄暗くしていた。
調合を済ませたら寝ようと思っていたからだ。
だからゆらゆら揺れる、間接照明の小さな光りのみが今私たちのことを照らしていて。
こうして角度が変わってしまえば、途端に兄の表情が判らなくなってしまう。
何を言えばいいのか判らない。
何を求められているのか、判らない。
だからこそ、私は胸についた言葉を只溢すのだ。
私は兄のような頭脳は持ち合わせていない。
そんな私だからこそ、飾り気のない本音は、意味を成すのだろうから。
「貴方は私の兄だから、私は貴方が大好きなのよ」
此れが本心。
此れが飾らない私の本音。
いつもは口にしない、私の本当。
血こそ繋がらないけれど、でも、出逢った時から兄は兄だった。
意地悪だった。よく泣かされた。だけれどそれでも、確かに私にとって、彼はひとりだけの兄だったのだ。
「……そう。お前は僕の、妹だものね」
顔が、ゆっくりと近付いてくる。
そうして私の躯は、兄の腕の中に閉じ込められた。
血と硝煙の臭いがする。
後は──煙草の、匂い。
それにすん、と鼻を鳴らし乍ら、私はゆっくりと兄の薄い背中に腕を回していく。
そうしてゆるゆると背中をなぞって、擦ってあげる。
座り込んでいる私と立っている兄じゃ、如何したって抱き込めるのは兄の方だ。
だけれど、それでも。
こうしてあげなきゃ、いけない気がした。
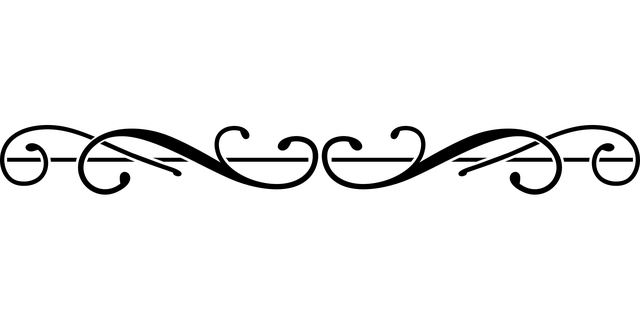
場所を変えて、ソファーの上で。
私と兄は、暗い部屋の儘、二人で寄り添って座っていた。
「落ち着いた?」
「……落ち着いた」
私の肩にぐったりと頭を預ける兄に、腕を回して其の頭を撫でていく。
包帯のない頭はとても撫でやすく、好き放題に伸びる其の蓬髪を指で梳き乍ら。
すっかり様子が戻った兄に、私はそっと息を吐いた。
先刻の不安定な兄は其処にはおらず、居るのはぐりぐりと私に頭を押し付けては何処かを惘乎と見詰めている"太宰様"だけ。
──屹度、流石の太宰様も、此の続く抗争に疲れてしまったのだろう。
そう思って、私は気持ちを切り替えるように、けれど優しくこう言葉を投げ掛けてみる。
「お茶を淹れましょう。美味しい茉莉花茶が手に入りましたの。躯も温まりますわ」
そう云って、席を立とうとした時に。
然し何故か、兄の腕が私を止めた。
「……否、私 が淹れるよ」
「えっ? でも……」
「私が淹れたいんだ。お茶くらい、私だって淹れられるもの。……茶葉と急須は何処にあるんだい?」
「ええと、其処の戸棚で……えぇ、湯呑みも其処に……。本当に、淹れてくださいますの?」
「うん。私が淹れる」
──なんだか、本当に今日は珍しい。
こんなにも私に弱さを見せることも今までなかったし、兄自らこうしてお茶を淹れてくれるだなんて、今の今まで一度もなかったように思える。
記憶を振り替えったって頭に過るのは、いつだって私を所有物のように顎で使う兄の姿だけで。
これは本当にお疲れなんだわ、と戦場に出ない身としては、なんだか酷く尽くしてあげたい気持ちになってくる。
そうだ。兄だって、他の構成員と同じように此の抗争で傷付いているのだ。
ならばこそ、こうして好きにさせてやるのが一番いいのかもしれない。
だから私はせっせとお茶の準備をする兄から目を反らして、中途半端に広げていた薬剤を纏めていく。
本当は作ってしまいたいものがあったけれど、でも、此の感じならもしかしたら兄は今日此処に泊まるかも知れない。
だったら、今日は此処迄で、続きは明日にしよう。
そうしていると、太宰様から声が掛けられる。
「淹れたよ。おいで、一緒に飲もう」
「はい」
確かにふわりと茉莉花茶の匂いが鼻先をくすぐった。
振り向けばソファーに座りながら、私に向かって太宰様が手招きしている。
其の手には、淹れたてであろうお茶が在って。
私は先程の同じように太宰様の隣に座って、手ずから淹れて下さったお茶を受け取った。
「私、中々淹れるの上手いと思うのだよね」
「……そうかもしれませんわね。なんだか、自分で淹れた時とは違う味がします」
何故だろうか。
以前自分で淹れた時よりも──あまい、気がする。
こんな味だっただろうかと思って、なんとなしに太宰様を見詰めてふと気づく。
「……お兄様の分は如何しましたの?」
「ん? ああ、淹れたら満足しちゃって呑む気なくなっちゃった」
「まぁ」
──けったいなお人。
まあでも淹れてくれたのだからと呑み進めて入れば、先刻迄とは打って変わって機嫌の良さそうな太宰様は私の隣でぷらぷらと足を動かしていた。
其れになんだか違和感を覚えるも、まあ、不機嫌で居られるよりもマシだろうと湯呑の中を全て煽る。
ふんわりとした茉莉花茶は鼻腔を突き抜けて、然し如何にも不思議と甘く感じる後味に、
矢張り少し不思議に思いつつも。
湯呑を洗って仕舞おうと立ち上がろうとした──ら。
「……、ぁ…?」
何故だか、一気に頭が重くなる。
ぼわつくと云うか、動きが鈍くなったと云うか──眠い?
でもなんで突然?
そうソファーの背凭れに手を付いたまま結局立てないでいる私に、太宰様は歌う様にこう囁いてきた。
「お前の大切なものはなんだい?」
「……えぇと、……漢方薬、かしら」
ねむい、眠い。
じわじわと色を染めるかのように躯が重くなっていく。目蓋が重たくなっていく。
次第に自分の頭すら支えきれなくなって、ソファーに項垂れる様に崩れてしまう。
ああなんだか、此れは少し──可笑しくないか。
「でも漢方薬っていっぱいあるよね。一番大切なものはどれ?」
「……それは、あの、赤い薬箪笥の金取っ手にある、犀角……」
「さいかく?」
「サイの、角なの……。絶滅危惧種だから、もう、中々手に入らなくて……それ、が、一番、」
「大切?」
「うん……」
目蓋がもう、持ち上がらない。
躯もすっかり力が抜けてしまって、声を出すのも億劫だ。
怠い──のとは、また違う。
強制的に眠りに落ちる様な──ねむり?
「に、さま……おちゃ、なに、」
「──他には、大切なものはあるかい?」
「た、いせ、……かみど、め……」
「髪留め? 其れはどれだい」
──それは、いま私がつけているものよ。
そう、言葉にしたいのに。
けれど其れは此の唇が開き切る前に空気に蕩け、消えてしまう。
最後にぐっと目蓋を持ち上げて、瞳に映すのは、薬箪笥の前に居る太宰様の姿。
其の姿を視界に入れて、私の意識は微睡みの中へと落ちていったのだ。
けれどそれは何処か遠くの国の出来事の様に感じていたもの、また事実だった。
ミミックによる騒動が激化すると共に、自ずと私の行動範囲は狭くなっていったけれど。
でもそれは今までだってそう変わらないことで。
だからこそ、私は私の為だけに誂えられた此の部屋で、怪我人の為の薬を調合していた。
漢方は、遅効性だ。
ゆっくりじわじわと効力を発揮する古からの叡智は、如何したって今のような戦場では役に立たない。
こんなものをこつこつ作るよりは、戦場に赴いて治療に当たる方が何倍も価値も意味もあるのだろう。
然し私は"下級構成員に異能を遣ってはならない"と云う縛りがある為、出来ることは如何したって限られてしまうのだ。
少しでも、役に立ちたい。
少しでも、痛みに呻く人たちの扶けになりたい。
結局は只の自己満足。
だけれど、其れを無意味と切り捨てる事は、兄代わり曰く"甘ったれ"である私には出来なかった。
無能であると判っていても、何かひとつくらいは自分を役立たせたかったのだ。
ゴリゴリと薬研で薬剤を細かく擂り潰していく。
漢方は個人の躯に合わせて調合していくものだけれど、下準備はなるべくでも済ませておいた方がいい。
今日はあと20種類の薬剤を擂り潰し、乾燥させておかなければ。
痛み止と、睡眠導入と、あと、あとはどれを作っておこう。
日中は救護室で銃痕等の処置に追われてしまうから、薬剤関係は夜の内に済ませて置きたいのだ。
フラッシュバックによって眠れない構成員も沢山いる。
ああそうだ、精神安定の薬も調合しなければ──。
「───やぁ。こんな時間迄、未だ起きて居たのかい?」
声に、ぱっと出入りの扉を振り向いた。
そうして其処に居た人に、私はきょとんと瞬きをする。
だって其処には、居る筈のない人が居たから。
「だ、だざ、い、様……? えっ、やだ嘘、いつの間にいらしたの?」
──此の部屋に至る迄の道中には、幾つかの仕掛けが施されている。
私は貴重な治癒能力保有者で、非戦闘員の非力な女。
だからこそ、私に辿り着く迄の経路を誰かが通ったら、直ぐ様小さく警報が鳴り、モニターが始動し、誰が近づいて来ているのか私に教えてくれるのだけれど。
其の警報が、モニターが。
何故か今、動いていない。
──不作動なんて、初めてかもしれない。
何か問題が起こる前に、森様にご報告して直していただかなければ。
けど、今此の忙しい時にお手を煩わせるようなことをしてしまっていいものか。
否でもなにか起きてからでは──なんて、思っていたら。
「……菫、此方をご覧」
「っ、!」
いつの間にか直ぐ側迄近付いていた太宰様に、顎を捕まれ、上を向かされる。
そうして驚くほど近くにある顔を、私は視界いっぱいにまじまじと見詰めることになったのだ。
「な、なん、なんですの……?」
「…………」
「……だざ──お兄様?」
呼び声が、自然と正される。
何故兄呼びに直してしまったのかは判らない。
けれど、何故か、こう呼ばなければならない気がしたのだ。
「……、…」
黒々とした黒曜石の様な瞳が、光りなく私のことを見詰めている。
たまにする目だ。何を考えているか判らない眼差しだ。
こうなった兄の頭の中では、私では及び知れぬ数多の思考がなされていて。
一度でもこうなってしまったら、私はいつだって兄の思考が終わるのを待つしかできない。
けれど、本当に。
こんなの、いつ振りだろうか。
そうして、ふと気づく。
兄の顔──包帯が、ない。
瞬間、何故だか胸がざわりと騒いだ気がした。
何でかは判らない。だけれど、なにかが起こる気がしてしまったのだ。
兄の瞳は、未だ私のことを見詰めている。
「お前、さ」
兄の指先が、私の瞳に掛かる前髪をゆっくりと払い除けていく。
切り揃えていた前髪はいつも気を抜くと私の瞳を隠してしまうから、兄は時折こうして私の前髪をよけたがる。
けれど今はそれが、如何にも違う意味を孕んでいるような気がした。
「──
ゆっくりと、瞬きをする。
ぼく──僕。兄の一人称。
いつの間にかすり変わっていた、昔の兄の、自己の呼び名。
其れを聞いて、私はようやっと気がついた。
兄は今──傷付いている。
「…………すき、だわ」
思わず言葉を溢せば、兄の指先が私の頬に流れる。
そうして顎を掴んでいた手もゆっくりと這い上がり、私の顔は、兄の両手によって包まれた。
「それは、如何してだい?」
「それ、は、貴方が、貴方だから」
部屋は薄暗くしていた。
調合を済ませたら寝ようと思っていたからだ。
だからゆらゆら揺れる、間接照明の小さな光りのみが今私たちのことを照らしていて。
こうして角度が変わってしまえば、途端に兄の表情が判らなくなってしまう。
何を言えばいいのか判らない。
何を求められているのか、判らない。
だからこそ、私は胸についた言葉を只溢すのだ。
私は兄のような頭脳は持ち合わせていない。
そんな私だからこそ、飾り気のない本音は、意味を成すのだろうから。
「貴方は私の兄だから、私は貴方が大好きなのよ」
此れが本心。
此れが飾らない私の本音。
いつもは口にしない、私の本当。
血こそ繋がらないけれど、でも、出逢った時から兄は兄だった。
意地悪だった。よく泣かされた。だけれどそれでも、確かに私にとって、彼はひとりだけの兄だったのだ。
「……そう。お前は僕の、妹だものね」
顔が、ゆっくりと近付いてくる。
そうして私の躯は、兄の腕の中に閉じ込められた。
血と硝煙の臭いがする。
後は──煙草の、匂い。
それにすん、と鼻を鳴らし乍ら、私はゆっくりと兄の薄い背中に腕を回していく。
そうしてゆるゆると背中をなぞって、擦ってあげる。
座り込んでいる私と立っている兄じゃ、如何したって抱き込めるのは兄の方だ。
だけれど、それでも。
こうしてあげなきゃ、いけない気がした。
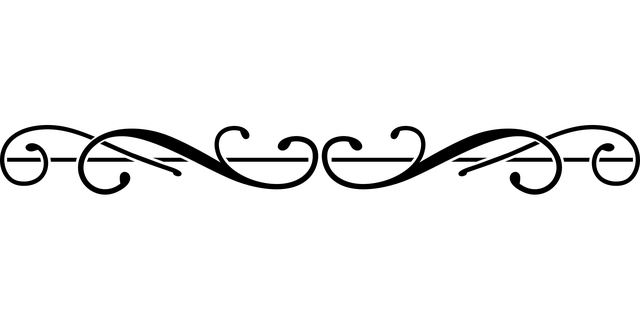
場所を変えて、ソファーの上で。
私と兄は、暗い部屋の儘、二人で寄り添って座っていた。
「落ち着いた?」
「……落ち着いた」
私の肩にぐったりと頭を預ける兄に、腕を回して其の頭を撫でていく。
包帯のない頭はとても撫でやすく、好き放題に伸びる其の蓬髪を指で梳き乍ら。
すっかり様子が戻った兄に、私はそっと息を吐いた。
先刻の不安定な兄は其処にはおらず、居るのはぐりぐりと私に頭を押し付けては何処かを惘乎と見詰めている"太宰様"だけ。
──屹度、流石の太宰様も、此の続く抗争に疲れてしまったのだろう。
そう思って、私は気持ちを切り替えるように、けれど優しくこう言葉を投げ掛けてみる。
「お茶を淹れましょう。美味しい茉莉花茶が手に入りましたの。躯も温まりますわ」
そう云って、席を立とうとした時に。
然し何故か、兄の腕が私を止めた。
「……否、
「えっ? でも……」
「私が淹れたいんだ。お茶くらい、私だって淹れられるもの。……茶葉と急須は何処にあるんだい?」
「ええと、其処の戸棚で……えぇ、湯呑みも其処に……。本当に、淹れてくださいますの?」
「うん。私が淹れる」
──なんだか、本当に今日は珍しい。
こんなにも私に弱さを見せることも今までなかったし、兄自らこうしてお茶を淹れてくれるだなんて、今の今まで一度もなかったように思える。
記憶を振り替えったって頭に過るのは、いつだって私を所有物のように顎で使う兄の姿だけで。
これは本当にお疲れなんだわ、と戦場に出ない身としては、なんだか酷く尽くしてあげたい気持ちになってくる。
そうだ。兄だって、他の構成員と同じように此の抗争で傷付いているのだ。
ならばこそ、こうして好きにさせてやるのが一番いいのかもしれない。
だから私はせっせとお茶の準備をする兄から目を反らして、中途半端に広げていた薬剤を纏めていく。
本当は作ってしまいたいものがあったけれど、でも、此の感じならもしかしたら兄は今日此処に泊まるかも知れない。
だったら、今日は此処迄で、続きは明日にしよう。
そうしていると、太宰様から声が掛けられる。
「淹れたよ。おいで、一緒に飲もう」
「はい」
確かにふわりと茉莉花茶の匂いが鼻先をくすぐった。
振り向けばソファーに座りながら、私に向かって太宰様が手招きしている。
其の手には、淹れたてであろうお茶が在って。
私は先程の同じように太宰様の隣に座って、手ずから淹れて下さったお茶を受け取った。
「私、中々淹れるの上手いと思うのだよね」
「……そうかもしれませんわね。なんだか、自分で淹れた時とは違う味がします」
何故だろうか。
以前自分で淹れた時よりも──あまい、気がする。
こんな味だっただろうかと思って、なんとなしに太宰様を見詰めてふと気づく。
「……お兄様の分は如何しましたの?」
「ん? ああ、淹れたら満足しちゃって呑む気なくなっちゃった」
「まぁ」
──けったいなお人。
まあでも淹れてくれたのだからと呑み進めて入れば、先刻迄とは打って変わって機嫌の良さそうな太宰様は私の隣でぷらぷらと足を動かしていた。
其れになんだか違和感を覚えるも、まあ、不機嫌で居られるよりもマシだろうと湯呑の中を全て煽る。
ふんわりとした茉莉花茶は鼻腔を突き抜けて、然し如何にも不思議と甘く感じる後味に、
矢張り少し不思議に思いつつも。
湯呑を洗って仕舞おうと立ち上がろうとした──ら。
「……、ぁ…?」
何故だか、一気に頭が重くなる。
ぼわつくと云うか、動きが鈍くなったと云うか──眠い?
でもなんで突然?
そうソファーの背凭れに手を付いたまま結局立てないでいる私に、太宰様は歌う様にこう囁いてきた。
「お前の大切なものはなんだい?」
「……えぇと、……漢方薬、かしら」
ねむい、眠い。
じわじわと色を染めるかのように躯が重くなっていく。目蓋が重たくなっていく。
次第に自分の頭すら支えきれなくなって、ソファーに項垂れる様に崩れてしまう。
ああなんだか、此れは少し──可笑しくないか。
「でも漢方薬っていっぱいあるよね。一番大切なものはどれ?」
「……それは、あの、赤い薬箪笥の金取っ手にある、犀角……」
「さいかく?」
「サイの、角なの……。絶滅危惧種だから、もう、中々手に入らなくて……それ、が、一番、」
「大切?」
「うん……」
目蓋がもう、持ち上がらない。
躯もすっかり力が抜けてしまって、声を出すのも億劫だ。
怠い──のとは、また違う。
強制的に眠りに落ちる様な──ねむり?
「に、さま……おちゃ、なに、」
「──他には、大切なものはあるかい?」
「た、いせ、……かみど、め……」
「髪留め? 其れはどれだい」
──それは、いま私がつけているものよ。
そう、言葉にしたいのに。
けれど其れは此の唇が開き切る前に空気に蕩け、消えてしまう。
最後にぐっと目蓋を持ち上げて、瞳に映すのは、薬箪笥の前に居る太宰様の姿。
其の姿を視界に入れて、私の意識は微睡みの中へと落ちていったのだ。