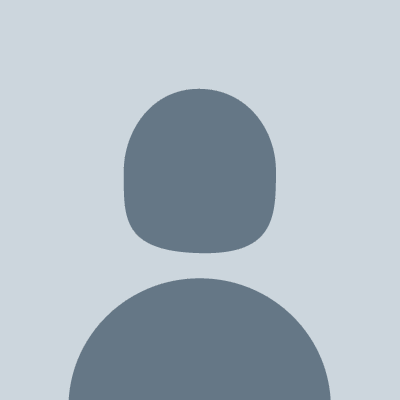
�ؕ�
�v���Ԃ�B���C���H
���T���A�Ök�ՂɐԖƍs�����ǎO����ꏏ�ɍs���Ȃ���
�@�o�X�P���̗��K�I����A��w�̃`�[�����C�g��ƃ��[������H�����A�蓹�ɍ��Z����̓������A�ؕ邩��A����ȓ��e�̃��b�Z�[�W���͂����B

�O�� ��
�v���Ԃ�B���C���B
�������ȁA�����s
�@�����܂ŕ��͂�ł������ăs�^�b�Ǝ肪�~�܂����B�]���ɇ��ޏ����̖ʉe���A�߂��������炾�B
�@�����܂ň������Ƃ��Y�ꂽ���Ȃ�ĂȂ���������ǁc�c���ȂɃA�C�c�͉�����Ǝv���Ă���̂�——����Ȃ��Ƃ��l���邽�сA�}�ɉ��a�ɂȂ��Ă��܂��̂��B���͐[�����ߑ���f�����B����ł������A����ł������Ǝv������������B�߂�Ȃ��ƒm���Ă��Ă��A�q�����Ă����������B�ʂ�Ă���͊w�Z�ł����܂ɂ�������Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��Ȃ��āA���肩��݊����Ə̂���鉴�ł��A�ޏ��������ĉ��Ƌ���������Ă��邱�Ƃ�F�߂���Ȃ��ɒu����āB
�@����ł����̒��ł͖Y����Ȃ����肾�B���������Ȃ����̂����ۂ��Ȋ肢�B�A�C�c���܂������D���ɂȂ�——����șR���肢�B����ł����́A�����ޏ��ɉ���������B
�@���͓��͂������͂������čēx�ł������Ƃ�������Ԃ����Ƃ������ɑ��X�ɑ��M�}�[�N���^�b�v���A�g�т��|�P�b�g�ւƗ��\�Ɏd�������B

�O�� ��
�v���Ԃ茳�C����B�T���͗��K�������čs�������ɂȂ��A����
�@—
�@——�Ök�ՁA�����B�����ʂ��w�Ńo�X�P�̗��K���I���ă��b�J�[���[���Œ��ւ��Ă����Ƃ��˔��q�������`�[�����C�g���u�O��A������Z�̊w�ՂȂ��āH�v�ƁA�u���ė����B
�u�c�c���H�Ȃ�Œm���Ă�v
�u��y�������Ă����H���A�s���Ȃ��́H�v
�@����ȁA���ƃ`�[�����C�g�̉�b���Ă����炵�����̘A�����u�����Ȃ́I�H�v��u�������������݂�Ȃōs�������[�I�v�ȂǂƁA�����ÁX�ɘb�Ɋ����ē����ė���B
�u�͂��H�߂�ǂ������A�s���ˁ[��v
�@���͐S�ꂩ��߂�ǂ������Ƃ����I�[���������o���Ă����f���̂āA�K���I�Ǝ����̃��b�J�[�̔���߂��B�������ƃ��b�J�[���[�����o�Ă������̌��ǂ��Ă����A�������́u�Ȃ�ł���[�A�O��ƈꏏ�ɎR���H�Ƃ�|���������o�[�����Љ�Ă�I�v�Ɣw�ォ�瓊���|����ꂽ���̌��t�ɉ��̓n�b�Ƃ���B������������Ɉ��C�͂Ȃ��B���������̑��݂����č��̃`�[�����C�g�͒m��Ȃ��킯�����A���������U���Ă���Ă���̂��A���������ł���Ƃ͂����������ɒf��̂��������������낤�ȂƎv�����������炾�B
�u�c�c�܂��B���Ⴀ�����A��o���Ă݂����H�v
�@���݂��ɂ߂ĉ��������ۂ�Ɨ낷�ƁA�����ɔw��Łu������[�I�v�Ɛ���オ���Ă���F�l�B�̐����w����D�������łĉ��͎v�킸������B
�@�Ök�Ɍ������܂ł̂������ɋ{�����A����Ȃ̘b�Ő���オ��A���X�ɕ�Z�߂Â��ɂ�āA�l���������Ă����悤�Ɋ�����B���N�����ς�炸����킢�̂悤���ȕ�Z�̊w�Z�Ղ́A�ƁA�v���Ώ����ւ炵��������B
�@�����ꂽ���������Ĉ�ԍŏ��ɖڂ��������̂́A�������̑��Ǝ��ɑ�����ǂݏグ�Ă��ꂽ���O�N���̐��k��������B�����ɁA���ƋC�t�����̂����ڂ���ł�����Ɠ����������Ĕ��˓I�ɉ��܂ށA�S���Ōy�����������Ԃ��B
�@���D�Ȃ��r�j�[���{�[���Ȃ��悭������Ȃ����A����̐�w�Ök���Z�w�Z�Ձx�ƊŔ̗������A�[�`��������Ƃ��A�����A���͂������̊w�Z�̐��k�ł͂Ȃ��ȂƉ��߂Ď������A���������₵���C�����ɂȂ����B
�@�`�[�����C�g�����������S���̉����`��������Ȃ��Ȃ����ړ��Ă̖ړI�n�ɂ܂ŒH�蒅�����Ƃ��o���Ȃ��B���ƈ���ĎЌ�I�ȃ`�[�����C�g��͌������q�����A���܂��ł�JK�Ȃ�ČĂԂ炵���������JK����ɕ@�̉���L���Ă���n���B
�@�����̗͑͑���ɗ]�O���Ȃ�����������������͂��̗]�O�Ƃ�������������̂��A�������Â����c�c�Ȃ��߂Ȃ�Ĕ����Ă͂��Ⴎ���̎p�����āA�������R�Ɩj���]��ł��܂��B�����Ă��̖Ȃ��߂̉���Ń`�[�����C�g�̑��������@��𒅂���l�̏��q���k���������ꂽ�ʒu�ɓ˂������ă`�[�����C�g��҂��Ă������̑��݂ɋC�t���A�ς��ς��Ƌ삯����ė���B
�u�O���y�ł���ˁH�I�v
�u���H�c�c���A�����B�����v
�@����ȋ����s�R�݂����Ȉ��A�����Ԃ��Ȃ������ɏ�Ȃ��Ȃ�Ȃ�����ޏ��Ɏ����𗎂Ƃ��ƁA�悭����Ό��J�m——�c����ƒ��̗ǂ��������k���������Ƃ�m��B�Ƃ������Ƃ͖ڂ̑O�̔ޏ��������O�N�����A�Ȃ�ĔN��肭�������v���^��B
�@���x�̓`���Ƃ��̎茳������Ζ�w�ɃV���v���Ȏw�ւ��͂߂��Ă��āu�܂��K�L�v�ƌ��������ɂȂ������B
�u���O�A�o�X�P���̉���ɂ��܂���H�v
�u�c�c�c�́H�v
�@�S�O�����������������G�X�ƌ����Ă̂���ޏ��ɁA�f���ڋ��ȕԎ���Ԃ��Ă��܂����B�|�J���ƌ����J�����܂܌ł܂��Ă��鉴���悻�ɔޏ��́A�u���v�ł��I���̎q�A���ܔގ����Ȃ���ŁI�v�Ƃ��u���A�ł����e���ł���[�H�����Ǒ��v�ł�����I�v�Ə���Ɏ��ȉ����������ē�����O�ɕԂ����t��������Ȃ��B����́c�c�Ȃ�̒����Ȃ�B�Ȃ�ŃA�C�c�̗F�l�݂͂Ȃ������f���Ŗ��邭�A�����Ė������Ȃ̂��B�ʎq�����肠�̃N�\���ӋC�ȁA�{��̖�Y������c�c�B
�u�c�c�������B���ǁ[���v
�u�����I�����A���Ⴀ���͉���ɖ߂�܂��ˁI�v
�@�����A�Ɠ��������ĉ���̕��ɖ߂��čs�����ޏ��Ɠ���ւ��悤�ɂ��ă`�[�����C�g���������̂Ƃ���ւƕ����ė����B���̎�ɂ́A�s���N��琅�F���Ƒ̂Ɉ������ȐF�����������َq�̑܂�������Ă���B�u�O����H�ׂ�H�v�ƁA�����Ȃ��猾��ꂽ���u����ˁv�ƌ����悤�ɁA����y���Ȃ��Ēf�����B
�@���̂Ƃ��A�y�����̉��t���o���[�h�ɐ�ւ�����̂��ă`�[�����C�g�炪�u�����v�Ȃ�Ċ�����������B�Ȃ���A�Ɠ˂����ޑ���ɉ��͏��������ߑ���f�����B
�@�������A��N�O�Ɠ������t�Ɏv�킸�S����������Ƙh�݂͂��ꂽ�悤�ɋꂵ���Ȃ��đ���ۂނ��w�߂Ď���Ƀo���Ȃ��悤�ɕ��R���B�w��ł́u�������Z�A�M�^�[���������v�Ƃ��u�y�������Ă�����������ȁv�Ƃ��A����ȉ�b���J��L�����Ă���B
�@�����Ȃ�����������Z�ɂ߂Ă݂���A����ς�w�ՂȂ�ĊW�˂��A�݂����Ȋ����Ō��C�ɃO���E���h�ŋS�������Ȃ����Ă�j�q���k��ڂ̒[�Œǂ��āA���ʂ������������Ƃ��B��Z�̕��i�Ȃ��������ꂽ——�]���ɏĂ��t���ė���Ȃ����Ԃ����̎p���ڂɉf�����B�̂��王�͂����͂����ƍ��ꂵ�Ă��鉴�̎����̐�A����ȑ����炵�������炵����y�����̒��ɁA��ԉ�����Ă��܂�Ȃ���������A�c����̔ޏ��̎p�������B���ł��������ĕς�炸�Ɏv�������Ă��鉴�̗c����͉��̏h�G�A����V�G——����Ȍ�y�ƈꏏ�ɗx���Ă�����A��炳��Ă�����A�y���C�ɏ��Ă���ޏ��̏Ί�ɁA�����l�܂�B
�@�������Ȃ��Ă��y�������ł悩�����B���Ȃ����Ȃ������āA��������āA���Ă��Ă���Ă悩�����B���Ȃ����Ȃ��Ă��A�����A���v�Ȃ���ȁB�Ȃ��A���O�A�������Ȃ��Ă��c�c�₵���˂��̂���——�B
�u——�I�C�B�v
�@���̂��̐��ɍ��܂œۋC�ɏ��Ă�����y��A�{��ƍʎq���A�ꏏ�ɂȂ��Ă������U��Ԃ�B������Ƃ�����B����Ȍ��t���܂��ɂ҂�����Ƃ����ӂ��ȕ��e�ŁA�������Čł܂��Ă���B
�u�c�c�Ȃɑ����łA���߁[��v
�@�{��ƍʎq���K�^���ƈ֎q���痧���������āA�u����͈Ⴄ���āv�Ƃ��u�^���̃J�[�h�̌��ʁv�Ƃ��A����炵�ǂ���ǂ�ɂȂ��āA�ꐶ�����ɕى������Ă���B�����A������͖Y��Ă���B�����A���������ԓx�������ƁA�����Ƌ@���˂�Ƃ������Ƃ�——�B
�u�^���̃J�[�h�����H�v
�u���I���������A���@�ɂ�����ꂿ�܂�����X�悠�̓�l�v
�u���������A����Ό��z�ł��B�t�@���^�W�[�I�v
�@���͓�����O�ɔ[�����Ȃ��悤�Ȋ���ŕД���݂�グ�Ȃ����l�������낷�B���̊Ԃ�BGM�ɂ͂��̏Ɏ����킵���Ȃ��y�����̉��t����o���[�h�����O�X�s�[�J�[��ʂ��Ė苿���Ă���B
�@���͎������A���ǂ������荇���ėx���Ă������˂Ɣޏ��̕��Ɍ������B�����ƕς��ʕ\��ŁA�������Ă�����ĂȂ�������̒͂߂Ȃ����͋C��Z���Ă��鐅�˂ƁA�}�ɋ����s�R�ɂȂ��Ă���c����̔ޏ��B���̂܂܈�x���͐��ł��炵�Ă���A��l�̌��ɕ��݊���čs���B��l�̖ڂ̑O�ɉ����������Ƃ����˂��y�������Ō������B
�u�ǁ[���A�݂����[�B�v���Ԃ�v
�u�c�c�Ԃ��v
�@�S�̒��Ō��������肪�A�{�肪��s���Ďv�킸�A�������ďo�Ă��܂��Ă������ƂɎ����ł��������B���Ȃ��B����ł�����ȐS�������Ȃ��悤�ɓw�߂Ė��\�����邱�ƂɈӎ���������B�������A���̐��͖ڂ̑O�ɗ��ޏ��ɂ��������Ă����̂悤�Ŕޏ��͐��˂��`���ƌ��グ�Ă����B�t�ɐ��˂͉��̂��Ƃ��ƌ��������ɁA����Ƃ�Ƃ��Ă���B���̔w��ł͋{�邽���o�X�P�������u���܁A�Ԃ����Č������H�v��u����A�݂����Č�������Ȃ������v�Ȃ�Ă��������Ɖ�c���n�߂Ă��邪�A���ׂĂ����܂Ŋە��������B
�@���˂��{�邽�����`�������Ĕޏ��̎��͂܂܁A�t�b�ƂЂƂ��B���͂���Ȑ��˂̑ԓx�ɂ܂��������߂��B�����Ė������ɐ��˂��������܂܂ł����ޏ��̎���������ƈ�������B
�@���˂��牴�ցA���͂⋭���Ɉ����n���ꂽ�ޏ��̂��̏����Ȏ�̉�����ɉ��������������Ȃ��獡���́A���N�Ԃ�ɔޏ��ƌq�����Ă���Ƃ������Ƃ��\�������ɉ����ׂ��ꂻ���ɂȂ����B
�@�������Ƃ�����������o���ɂȂ�Ȃ��悤�A�C���������߂Ĕޏ��������낵�Ă��陋�߁A���˂��u�^�R�Ă����܂��Ă�H�v�Ȃ�Č����ĉ�������u������ɁA�������̂ق��ւƕ����čs���Ă��܂����B
�@�悤�₭�ז��҂��r���ł��āA���̂܂ܔޏ��̎�������A�������߂����Փ��ɋ��ꂽ�������͗�Âő�l�Ȏ�����������ׂ���x�ޏ����王�������������́A���̖�����O���E���h�ɂ����ƉĂ���܂��ڐ���ޏ��ւƖ߂���ċz�u���Ăڂ���ƙꂢ���B
�u�c�c��������H�A�d���˂��ȁB�x��[���v
�@�V�S���S�ʂɏo�Ă��܂��Ƃł������悤�ȁA����ȑ��܂���ɖڂ����J�������ޏ��͈Ă̒�A�����ɂ��̑傫�ȓ����ׂ߂Ă���O���点�āu�Ȃ�Ŏd���ˁ[�ȁA�Ȃ�Č����ėx��Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯�I�H�v�ƁA�v���v����{���Ă����B
�u�����H�������A�x���v
�u���_�B�x��Ȃ��v
�@��͌q���ꂽ�܂܂ŁA���������������ς��߂鉴�����̔w�ォ��͏����ɍ������Đ����̗��ߑ������������C�������B����������˂��̂����˂́u�n�C�n�C�I�������Ɨx��I�v�Ƌ��A��������̂悤�Ȃ��̐����w���ɓ˂��h����A�����҂��Ă������̂悤�Ɏ����Ŗ�Y�B����̖쎟�����ł��āA���͍��Z����ɖ߂������̂悤�ɁA����Ȃ肷��B�܂��ЂƂA�`�b�Ɛ�ł������������]���Ă�������A�ޏ��̍��ɂ����Ɖ��B���̂������������Ĕޏ��Ƃ̋���������Ək�܂����B������������Ŗڂ̑O�������ς��ɂȂ��āA�����t�F�`����A�w���^�C���ȁA�Ǝ����Ŏ������������ɂȂ�̂�K���ɗ}�����ށB
�@���ɒ����ė����`�[�����C�g�����������쎟�ƌy�����̉��t�ɍ��킹�đt�ł�V�����B�̉̐��ÎQ�O�̓z��̏�����w�����Ȃ��猩�l���^���ł���Ă݂����ْ̂̋����Ă���̂����Ȃ̂��A���^���Ԃɂ����ڂ̑O�̗c����́A�����Ɖ��̑���ł���Ƃ����A���Ƃ��ޏ��炵���W�J�B
�u�c�c���̂Ȃ��A���I�v
�u�͂��H�v
�u�����Ɠ���ł�I�v
�u���A���c�c���߂�v
�@�������グ���ޏ��̂��̃^�R�݂����ɐ^���ԂȊ�����ė��\�ɓf���Ă��܂������t�Ƃ͗����ɁA���R�Ɖ��₩�ȕ\����ׂĂ��܂��B�������̒[��݂�グ�āu�o�[�J�v�ƚ����A�ޏ��͖j��Ԃ�߂Ȃ����Y��ɏ����B�܂������̂܂����̂ق��֕����Ă��܂������Փ������́A�Ȃ�Ƃ��K���ɗ}���邱�Ƃɐ�������B
�@���͂����ɓ�������܂ł̂������ɗ���Ă����Ȃ͉��̉ƂŔޏ��ƈꏏ�Ɋς�DVD�̂ЂƂA������ȉf��̒��ŗ���Ă����Ȃ������B���ՂŃO�[�O�[�ƐQ�Ă��܂������B���̂��ƁA�ޏ��ɉ��x���@���N������āA�Ȃ�Ƃ��Ō�܂ŊϏ܂������v���o�̉f�悾�B����������Ă������t���v���Ԃ��Ȃ��牴�͂悭�c�������������ł������̉̎��ƁA�ڂ̑O�̑�����d�ˍ��킹�Ă݂�B
�@�Ȃ��Ɠ�l�ŗx���
�@�Y��Ă��܂� ��������
�@���ߍ��� �������ꂾ����
�@�����Ƃ��߂�
�@���͗��� ���͐F����
�@�����Ă����� �ǂ�����
�@�� ���Ȃ��̘r�̒���
�@���Ƃ܂��o���
�@�������߂��� �������߂ā�
�@�ޏ����������Ɖ������グ��B�����Ă��܂������ɂȂ�B�Ȃ�ŘA���悱���˂���Ƃ��A���C�ɂ��Ă��̂��Ƃ��A�D���ȓz�͂ł����̂���Ƃ��c�c����������A����——�B
�@����ǁA����Ȃ��Ƃ��ՁX�ƌ�����E�C�Ȃ�Ď������킹�ĂȂ��āA�O���ł����ђ����Ɖ��́A�����|�������t���A����Ԉ��ݍ��B
�@�Ə����Ŏ肪�͂��̂�
�@����Ɩ{���̍K����
�@���̂܂� ���܂ł�
�@�����ƈꏏ�ɂ������̂�
�@���Ȃ��̂��Ȃ����E�Ȃ��
�@�߂�������
�@���� ���Ə����Ŏ肪�͂��̂�
�@����Ɩ{���̍K����
�@�ӂ���Ō��� ��������
�@�ǂ��� �܂��o�߂Ȃ��Ł�
�@����ȏ�A���̋������͂܂���——�B�ƁA���͔ޏ��̍��ɉĂ�������p�b�ƕ������B����njq����Ă����肾���́A���������Ȃ������B
�u�Ȃ��c�c�Z���A�ē������v
�@——�����������A�ꏏ�ɂ������B���̋C������`����̂ɂ͂���ȂԂ�����_�ŗD�����̌��Ђ��Ȃ����t�𓊂��|���邭�炢�����o���Ȃ����̉��ɂ͂���ȊO�̍őP�̕��@�͎v�����Ȃ������B
�u���A�Ȃ�Ŏ����c�c�v
�@�����������낤�ȂƂ͎v���Ă�������lj��́u��������ˁ[���v�Ɣޏ��Ƃ���ɋ���������Ă��̎���q�����܂܂ŐU��Ԃ�Ƌ{���Ɂu���傢�A��Ă������H�R�C�c�v�Ɠ��������A�q���ł����ޏ��̎����ɂ����Č������B�ǁ[���ǁ[���Ƒ��Ԏ��������͍̂ʎq�������B����ő����悤�Ɂu�����A�s�����s�����v�ƌ�������ɂ��̎�����������ď㉺�ɗh�炵�Ă���B
�@���͂����ڂ̒[�ŗ����āA�X�^�X�^�Ɣޏ��̎�������A���k������̂ق��Ɍ��������B
�@—
�@���k������ŃX�j�[�J�[��E������C���̂܂܍Z�ɂɓ���B���̂Ƃ��ł��爬������𗣂��Ȃ��ł��Ă��ꂽ�ޏ��ɑf���Ɋ������Ƃ�����������S�̒��ɗN���オ���ė���B
�@���炭�e�������`�������Ȃ��猨����ׂĈꏏ�ɘL��������B�r���A���b�ɂȂ����搶�����Əo��y�����A���Ă������̎��Ɍq���ł�������X�b�Ɨ�����Ă��܂����B�b���I���������ēx�q�������킯�ɂ��������A�莝���������ɂȂ�����������́A�H�D���Ă�����w�̃o�X�P����p�̃W���P�b�g�ɓ˂����B
�@���߁u�ق��Ƃ�������Ă����́H���F�B�v�ƁA�����ŕ����Ă������̊���f���悤�ɂ��āA�S�z�����Ȑ��œ����|����ꂽ�B
�u���H�����A�ǁ[�����ǂ�����Ă�[���ȁv
�u�ӂ���A�������c�c�v
�u�A�C�c�炪���ā[���Č�����������ɂ��܂����Ƃ���Ă�v
�u�c�c���́A����\��Ȃ������́H�v
�u���H���A�܂��c�c����v
�@���̂܂ܔޏ��͂Ȃɂ��b�������Ă��Ȃ������B����ȁA��������������ȁA���ܐ�A�ƂЂƂ蔽�ȉ������B���͗������Ȃ������B�����������Ă��܂����̂��낤�Ǝ@����B����Ǖى�����̂��Ȃς���ȁc�c�ƁA�l�������˂�B�܂��A���K�����������Ă͉̂R����Ȃ�����ǂ��B
�@����Ȃ��Ƃ��X�ƍl���Ȃ�������Ă�����A���R�ƁA����֑����K�i��o���Ă��܂��Ă����B�������˔@�������܂ŗׂ�����Ă���Ă����ޏ��̑����A����̊K�i�O�ł҂���Ǝ~�܂�B�s�ӂɉ��������~�߂ĊK�i�̓r���ŐU��Ԃ茩���낵���Ƃ��A�ޏ����Ȃ������ӂ��Ɍ������B
�u�����A����̓_������H�v
�u���H�Ȃ�Łv
�u�Ȃ�ł��āc�c�����āv
�@�����Ă������Ǝ~�߂Ă��������K�i�Ɍ������ޏ����A�����ɉ��ׂ̗ɕ��B�������ĉ��b�Ȋ�����鉴���`�����������ƁA��������̊K�i���������āu�����V�����J�b�v���̗��܂�ꂾ��H����v�ƁA���₩�Ȑ����Ō����B
�u�V�����J�b�v���H�v
�u�����B�������Ê����͓������Ⴂ���܂���v
�u�Ê������H�悵�A���̏Ök���x���Ă�J�b�v���ł������傭��ɍs���Ă�����v
�@�����ӋC�g�X�ƌ����ĉ��͂��̂܂܉���֑����K�i����i�z���œo���Ă����B���̌�납�炭�������Ə��Ȃ�����������Ƃ��������Œ����Ă����ޏ��̏㗚���̉����Ȃ��炻��ȉ��ł���S�n�悢�Ɗ����Ă��܂��̂́A���ɑ��ł��Ȃ������O���Ƃ������݂����邩�炾�Ɖ��߂čĊm�F����B
�@�������ĉ��͍��ł��������炢�Ɋo���Ă���B������d�����ׂĂ��B�����������āA���������ď���܂ŗe�Ղɑz���ł���B����ς�D�����ȂƏ���ɐS�̒��Ŏv���Ă��܂����Ƃ��炢�������͋����ė~�����Ǝv�����B
�@�Â��A���~���̃h�A�m�u�Ɏ���|���悤�Ƃ����Ƃ������悭�o���b�I�Ƃ��̔����J�������ꂽ�B�����Ă���Ԃ��Ȃ����q���k���҃X�s�[�h�ʼn��Ɣޏ��̊Ԃ������ĊK�i���~��čs�����B
�@�v�킸��l���āA���̏�Ɍł܂��Ă��܂�������₠���āA�������Ɖ���̊O�����������ɂ͒j�q���k���ЂƂ�A�����M���M���ƐH������悤�ɂ��ē˂������āA���������Ă���B
�u�߂낤��c�c�v
�@�������ł����ꂽ���A���̓`���Ɣޏ������āu�����������̐��k����ˁ[����ȁv�ƌ��̒[��݂�グ����ɑ��ݓ����Δw�ォ��A�͂��Ƃ������ߑ������������B
�u——���܂����̂��H�v
�@�˂��������܂܂ł��鐶�k��ǂ��z���n�ׂ��ɂ������~���Ă��猾�������̌��t�ɂ��̐��k���L���b�A�Ɖ��̂ق��ɑ����������C�z���������B
�u�c�c�N�H�v
�u���I���߂�ˁI�����̑��Ɛ��Ȃ́I�v
�@���炩�ɕs�R�҈������Ă��鐶�k�����Ĕޏ����Q�Ă�悤�ɁA�p�^�p�^�Ɖ���ɓ����ė��������w�ォ�畷������B�u�N���Ǝv�����疼����y����Ȃ��X���v�Ƃ��u���I�ȂA����ɂ����́H�݂�ȒT���Ă���H�v�Ƃ�������b������A�ӂ���Ƃ��猩�m��̂悤���B
�u����܂���A�T�{�����Ȃ������������ǁv
�u�c�c�͂́[��B���ẮB�܂����܂����Ȃ��H�v
�u���܂��[���A�A�C�c�A�Ȃ��Ⴂ���Ăāv
�@�s�ӂɂ���ȉ�b�����ɏ���Ēx��ĉ��̎��ɂ��͂��Ă����B�����ʼn��͂�������������܂܂Ŏp�����l�̂ق��ւƌ�����B
�u�Ȃ�A���������Ă��O�o�X�P���Ȃ̂��H�v
�@����ȉ��̎���ɐ�Ɋ����߂��̂͂Ȃ����ޏ��������B������ɖڂ����J�����Ă��鐶�k�̔w��Ŕޏ����u����ȏ�̓_���v�Ƃ����悤�ɁA�v���v���Ǝ�����ɐU���Ă���B����ł����́A�T�邱�Ƃ��~�߂�C�͂Ȃ������̂ŁA�@��ŏ��u�ȂA���P���肩��H�v�ƁA�f���̂Ă��B
�u�c�c�����A�o�X�P������ˁ[���X�v
�u�ӂ���H�c�c����ł������̂��H�v
�u�c�c�v
�u�c�c�܂��A���ɂ͊W�ˁ[���ǂȁv
�@���k�͂���ȉ��̑ԓx�ɖ�����l�ɂ������낭�Ȃ������Ȗʎ����Ńv�C�b�Ɖ�������w�����B�u���܂�����Ȃ�j���炿���Ǝӂ�ˁ[�Ƃȁv�Ɨ����n�ʂɕt���Ȃ���H����̋�������Č��������Ɂu�c�c�͂��H�v�ƒj�q���k������f���悤�ɐ���R�炷�B
�u����A�҂��āI�������ꌾ���闧��H�I�v
�@�}�ɔw��ɂ����ޏ����������̂ɋ������̂��A���̒j�q���k�͂�����Ƃ��Ĕޏ��������B�u���z�ƌ����͈Ⴄ���[�́v�u�́H�Ȃɂ���v�Ɖ��V���Ă��鉴���������݂Ɍ��Ă������k���A
�u����A�}�W�Ȃ�Ȃ���y�A���̐l�v�Ɩ������ɂ��A�����w�����s�R�҂ł�����ڂł����������B����ɑ��ĉ��͏�������X���Č������B
�u���A�����̖�����y�ƁA�t�������Ă����v
�u����I�I���I�H�v
�u�����I�I�I�I�I�v
�u��N�O�ɂȁv
�@�ł܂��Ă���ޏ����悻�ɒj�q���k�́u�����A���c�c�����I�I�H�v�ƕS�ʑ��݂����ɃR���R���ƕ\���ς��Č�����B����Ȕނ͋��������܂܁A�Ō�ɂ͂������Ɣޏ��̕��������B
�u������悭�����Ō��܂��Ă患�c�c�v
�u������ƁI�X�g�b�v�I�v
�@Ⴢ�����������炵���ޏ�����������ŁA���������Ɖ��̌��܂ŕ��݊���Ă���Ɛ����悭���Ⴊ�ݍ��B�������āu�����܂ŁI�v�Ɖ��̌��������Ȏ�̂Ђ�ŕ������B����������Ɣ��������͐�̌��t�𑱂���B
�u�ޏ��������Ă��A���Ⴂ�N�����Ă��Ƃ��Ă��A�Ƃ肠�������O����ӂ��Ă���v
�u�c�c�����āv
�u�����Ă��w�`�}���˂��I�ӂ��ăL�X�ł����i�ł�����Ⴀ�������������A���́B���Ԃ�v
�@�����ăP���P���Ə��Ă��鉴��ڂ̑O�̔ޏ��͕����ʂ�z���āA���͂�y�̂���悤�Ȏ������A���Ƃ��Ƒ����ė���B
�u�c�c�킩��܂����v
�u������ƁI�[�����Ȃ��ŁA����Ȑl�̈ӌ��I�v
�@��������Ə��˂����݂����܂��ޏ��ɉ��́A���̏�ŕ�������ď����B
�@—
�@���̂��Ƃ����ɁA�j�q���k�͉���𑖂��ďo�čs�����B�����ƁA�ޏ��̌��ǂ����̂��Ǝv���B�����A�����Ȑt���āA�Ȃ�Ċ��S�[���Ȃ���̓t�F���X��ڂ̑O�ɂ��Ēn�ׂ��ɑ���L����������ɂ��A��������������A���[���ƒ��߂Ă����B�^���ł͔ޏ������̌g�т���ɂ��Ē��̎ʐ^���y���C�Ɍ��Ă���B�قځA�o�X�P�֘A�����Ȃ��̂ŁA����ȂɊy�������̂ł��Ȃ����낤�ɁB
�u�������ˁA��w�̃��j�z�[���v
�u��������߁[��A���ׂ̈ɍ��ꂽ�悤�Ȃ����v
�u�Ȃɂ���A�������ˁB��������炸�̎��M�Ɓv
�u�o�[�J�B�����ł������ĂȂ������Ă��ˁ[�[�́A���K���߂��āv
�u�n�n�A�������v
�@���炭�Ƃ茾�݂����Ɂu���̐l�g�������ˁv�Ƃ��u�������ˁA�`�[�����C�g�Ɓv�Ƃ������Ȃ���g�т̒��̎ʐ^�����Ă����ޏ��̐����s�^�b�Ǝ~�B�s�v�c�Ɏv���ĉ��ڂɌ���u�܂��U�X�A�V�ѕ����Ă�݂��������ǂˁc�c�v�Ȃ�ĐO���点���ޏ��������Ă����g�т̉�ʂ��Ȃ��Č����Ă����B
�@�����ɂ͈ȑO�A��w�̘A�����������낪���ăl�b�g�ŏE���Ă������q�̎ʐ^����肭���������ĉ��Ƃ̃c�[�V���b�g�݂����ɍ�����ꖇ�������B����ׁA�����̖Y��Ă��c�c�Ɖ��͊����߂�����B�����Đ_��——����c����ɐ����ė��l�̂��Ȃ��̂���������Ȍ`�ł������߂��Ȃ��킯����Ȃ��Ɛ����ɂ��Č��������B����ɍ��ꂽ�A����ɁB����ł��Ȃ��A���₱��A�܂��ŁA����ɁI�Ƃɂ����ى���——�I
�u���c�c�I�Ⴆ�I����͂��v
�@�����Čg�т���肩�������ƌ��ɂ��Ă�������o�b�A�Ɛ����悭�ޏ��̑O�Ɏ����čs���A�T�b�ƌg�т������f�����ĉ���Ɏ��s�B
�@——���ǁA���̂Ƃ����Y�S�ŁA�ӂƎv���Ă��܂����B�������̋�J���m�炸�Ɉ����̑���A���˂ȂƓۋC�Ƀ_���X�����Ă����R�C�c�ɁA�������炢�d�Ԃ������Ă�肽�����āB�����v���̂͋ɂ߂āA���R�̗���Ƃ������Ȃ������āB
�@�����R�C�c�������o�����݂��������Ȃ��A�c�O���Z���i���͌����Z�������ǁj������ȁc�c����z���ꂽ�ƁA�Ђǂ��ő����ɋ����͂����B
�@�����āA���̐�͉��������̏u�ԂɎv���������b��W�J���ޏ��ɏł���o�������Ă����蔤�ł����̂͂ǂ����B��ŁA�v���X�J�{���ĉ�����o�čs�����Ƃ���ޏ���҂��čŌ�Ƀl�^�o���V�Ƃ�������——�������A�ǂ�Ȋ炷�����ȁc�c�B
�@���͖������ɓf��������ڂ��B���ꂩ���̔ޏ��̔�����z�����Ăق����މ���s�������ɒ��߂Ă���ޏ��B����Ȗϑz�̒��ŌJ��L���Ă����Ƃ��C�t���ƍ���ɐl���̊��G���o�����B���͔����āA�ޏ������߂Č����B
�u�c�c���A�Ȃ�ʼn��̎�A�����Ă�v
�u�ʂɁc�c�������Ⴞ�߁H�v
�u�_���A����˂����ǁc�c�Ȃ�[���v
�u�͂����茾���Ă���Ȃ���킩��Ȃ��v
�u���A�����Ɓc�c�Ƃꂭ�����̂ŁA��߂Ă��������ƁA�����܂����v
�u�������͐��˂���D���������Ɂv
�u�Ȃ��c�c�H�I�v
�u�{���ɁA���ꂪ���R�Ȃ킯�H�v
�@���ɂȂ��ޏ��̋@���������C������B��������A�����̎���Ă���ȏ_�炩�����������B���������łْ͋����ĂĎ�̊��G�Ȃ�čl���Ă�ɂ��Ȃ������B�������ł́A�����̗c����Ƃ����W���ł����Ȃ��ƌ����������Ă����Ƃ͂����A�������̉����i�X�ƕςȋC�����ɂȂ��Ă���B
�u�ƁA�Ƃɂ��������[���A���̎�c�c�v
�u�₾�v
�u�ȁA�Ȃ�ł���I�v
�u�������݂�Ȃ̑O�ł���ȂƂ��č��X���Ǝ���q���ł���_���ȗ��R�Ȃ���́H�v
�u�ˁc�c�ˁ[���ǁv
�u�c�c�R���v
�@�ޏ��͔����Ɏ������������Ƃ������Ă̕��������ēf���̂Ă�悤�ɁA�����ꂢ���B
�@��N�O�ɂ����̓����ꏊ�ŁA����ȑ䎌��f���ꂽ�Ȃ��Ă��Ƃ�s�ӂɎv���o���Ă��܂��ď������ɂȂ�̂�K���ɗ}����B
�@����ɂ��Ă��A���B�����͈�́A���ɂȂɂ����킹�Ă��c�c�����A���͔ޏ��ɉR��f�����o���͉����Ȃ��B�ƁA�����Ŕޏ��̂�����̎肪�n�ʂɒu���ꂽ�܂܂̉��̌g�тɏd�˂��Ă��邱�ƂɋC�t���B��������ʂ��B���悤�ɁB
�@——�������B�������̎ʐ^���������炱���̗l�q�����������̂��B���̐V�����ޏ����Ǝv���Ă�̂��A�Ȃ�قǂȁB
�u——���A�����B�������A����v
�u�c�c��v
�u�ޏ��ł��ĂȁB������Ȃ�[���A��������Ď���q�����̂́A������肪��c�c�v
�@����������������݂�Ȃ̑O�ł��̎��D���Ă����āA�Ǝv���Ȃ�����Ƃ肠�����l�^�o���V�͂܂��悾�낤�ƁA���́A�����Ɍ��p���グ��B����������Ȃ��Ƃ����ł��鉴���悻�ɔޏ��́u�c�c���߂��炻���������������B����ɉB�����Ƃ��Ȃ��Ă�����v�ƓƂ茾�̂悤�ɘR�炷�Ɩ��c�ɂ��������̎��������A�����Ǝ�𗣂����B���͕��C�Ɏ���ă|�J���Ƃ��Ă��܂��B
�u�ޏ�����̂ɂ��A���̎q�Ɏ�������Ă��f��Ȃ��Ȃ�āA�`���������v
�u�c�c�v
�u�ޏ�����߂��ނ�H�܂������̎q��������̂���Ȃ킯�H�ق�Ɓc�c�M�����Ȃ��v
�u�c�c�v
�@�ȁA�ȂB���̍߈����́B�������Ȃc�c���������A���������B
�@���ɔޏ����ł����h�b�L�����d�|���Ĕ����삯���ꂽ�Əő������o����������肾�����A���������܂ł́B�����A�ǂ��ɂ����邢�����Ői�߂��镵�͋C�ł͂Ȃ��������ƐÂ��ɏł肪�P���Ă���B
�u���ł����́H�v
�u�c�c���A��T�Ԃ��炢�O�A�����������ȁH�v
�u���̓����āA�����������ł���H�v
�u���v
�u�����������Ō����Ă��v
�u���A�܂��B�����A�����������A�C�B�������ǁv
�u���Ⴀ�A���̌�ɉ�����肵���H�v
�u���A�����v
�@�c�c�Ȃ���A�q�₩�H�ޏ��̉�������ڂ��|������B����ڂŎE�������ƌ����Ă��ߌ�����Ȃ��B�������ޏ��͓r�[�ɃJ���b�Ƃ������F�Łu�悩���������v�ƌ������B���͈���ŁA���H�ƕ����Ԃ��B
�u�����Ɣޏ��ق������Č����Ă���ł���H�v
�u�c�c����A�v
�u�����[�^����O�ɕ������v
�u���A�����c�c�܂��ȁv
�@�ȂA���������܂�����C�ɂȂ��Ă˂����B�ƁA���͌��Ȋ��������B���������v���Ԃ�ɉ���̂ɁB�����Ƙb���������ƂƂ������ς��������͂��Ȃ��ǂȁB���[���A������ĂA���B
�u���Ⴀ���ꂩ��͎��A���̕����ɍs���Ȃ�����������ˁH�v
�u�́H�I�Ă�����c�c�ʂ�Ă��痈�����ƈ�x���ˁ[����˂�����v
�u�����Ă��Ȃ������A�s�������āv
�u�܂��A���˂����ǁB���͈�l��炵������ȁv
�u�����Ĕޏ��ł�����ł���H���ɑ��̏��̎q�����̎��Ƃɏo���肵�Ă���A�ޏ������C�������Ȃ������v
�u����́A�������������ǂ�c�c�v
�@�ޏ��͍����グ��ƁA����̔��̕��Ɍ������Ă����B�������āu�C�ɂȂ��Ă�l������Ȃ�c�c�_���X�Ȃ�ėU���Ăق����Ȃ������v�Ƃ�����ɂɂ͈�A�ڂ������Ȃ��܂₵�����ɂڂ₭�B�r�[�ɁA�����̂悤�ɉ��̒��ʼn����̔O����C�ɉ萶�����B
�u�܁A�҂Ă��āA���O�I�v
�@�ƁA�v�킸����A�ޏ����h�A�m�u�Ɏ���������܂܂œ������~�߂��̂Ŕޏ��̌��ɋ}���ŋ삯������B
�u���A�������̎ʐ^�ȁH��w�̓z���������č������Ȃ��āv
�u�c�c�v
�u���A������I�Ȃ�[�����A�ޏ��Ƃ��ł��Ăˁ[���I�v
�u�c�c�c�c�͂��H�v
�@�ْ�������������̋�C���o�ɂ��Ă����B�ޏ��̕��������������A�����������܂��Ă����B
�@—
�@——������B�������͂܂��t�F���X�̑O�ɍ��x�͌����������č����Ă����B�u�A��������Ȃ��́H�I�v�Ɖ��ٖ̕����I�������ƁA�ޏ��̓q�N�q�N�Ɩj��c�܂��Ȃ���A�S����ꂽ�悤�ɔl�|���Ă���B
�u�c�c�����B�����������炢�d�Ԃ����Ă��ā[�Ȃ��āv
�u�d�Ԃ��H�v
�u�ȂA�������[�y�������Ɋw�����C�t�����Ă�ȁ[���āc�c�v
�u�҂��āv
�u���H�v
�u�d�Ԃ��Ƃ��A��w���ɂ��Ȃ��Ă�邱�ƁH�v
�@�傫�Ȗڂ����J�����Đ��_���q�ׂė���ޏ��ɉ��͈�u�����Ɖ����ق�B����ł�������ɂ��A�������͂���킯�ŁA�Ƃ肠�����A�ق����t�ł��ޏ��ɕK���ɓ`���悤�Ɩ�p�����Ɍ������B
�u�����B�ł���A���������o�X�P�Ђ��Ȃ��Ă鎞�ɓۋC�ɑ��̖�Y�ƃ_���X�Ȃx���Ă�����v
�u�c�c�v
�u������Ɨ��K���K�`�Ńn�[�h�����āA�t���X�g���[�V�������܂��Ă���v
�@�����A�͂��Ɨ��ߑ������Ă��Ȑ����悤�ɓ��������Č㓪�����K�V�K�V�Ƒ~���ƁA�ۂ�A�u�d�Ԃ�����ɂ������āA����Ȃ������Ȃ��łق��������v�Ɣޏ����������B�����Ă��̗��Ƃ������̃g�[���Ɠ����悤�ɘ낭�B
�u��A�����������āB���ɔޏ����ł������z���ꂽ���ďł邩�Ǝv���Ă�v
�u�ł�Ȃ���A�����Ɖ��������c�c�H�v
�u��������̂���c�c�������đ������[�́v
�u�Ȃ�ł�I�v
�u���Ȃ��ƁA��������������ˁ[��I�v
�@�����c�c�����r���Ă��܂����B�����������B���ǁA�������͑f���ɂȂ�Ȃ��܂܁A�ʂꂽ�ƂĊ�����킹��ƁA�������Č��܂��Ă�����ȂȁA�Ɖ��������ł��Ă��Ȃ��������g�Ɣޏ��ɃC���C��������Ă����B����ł��ꖇ��肾�����̂́A����ς�ޏ��̕��������B
�u�킴�킴�c�c�h�b�L�����Ȃ���킩��Ȃ��H�v
�u���H�ǁ[�����Ӗ����H�v
�u�c�c������A�Ȃ�ł��Ȃ��v
�u�c�c�Ƃɂ������������B������x�Ƃ��˂���v
�u���̎q�ɂ������_������A����Ȃ��Ɓv
�@�����ꂢ�āA�X�J�[�g�ɂ��������悤�ɂ��Ĕޏ��͗����オ�����B�������Ƃ�——�Ԃ����t���Ȃ��B����ł������u�ǂ��s����v�Ɩ₦�u�����߂�c�c����[�ˁv�ƕς�炸�@����������܂ܔޏ�������Ԃ��Ă��܂��B
�@�h�N�h�N�ƐS���̌ۓ������܂��Ă����B���̂܂ܔޏ���߂点�Ă����̂�——�����킯���˂��I���͌ł���������ƁA����Ɖ��������Ă����ޏ��̔w���Ɍ������āu�߂�Ȃ�v�ƁA�ꂢ���B�ޏ��͗����~�܂��Ă�����肱�����U��Ԃ�B
�u�́H�v
�u�������ɁA���̈�A�̗���ʼn����C�����ˁ[�قǓ݊�����ˁ[���́A�������āv
�@�ޏ��́u�c�c���B���A�Ӗ��킩��Ȃ��v�Ɠ��h�����悤�Ƀv�C�b�Ƃ܂������ۂ����������A���̖j�͏����Ԃ����܂��Ă����B���͌��̒��ɗ��܂�������������ƈ��ݍ���ł���u——�Ȃ��v�ƁA�����|����B
�u���Ⴀ�Q�[���ŕ�������������̖]�݂���������ă��[���ŁA�ǂ����H�v
�@������o���Ɓu���c�c�H�v�Ɣޏ��̌����s�N���Ə㉺�����B
�u�Ȃ�ł����肾�B�������A������ȁv
�@���b�̍d���̂��ƁA�ޏ��͍ēx�A�`�����Ɖ��Ɏ����𑗂��Ă���B�����āu�Q�[�����Ⴘ�邢�v�ƁA����܂��ӌ����q�ׂĂ����̂ŖʐH�炤�B
�u���̕����Q�[���͓��ӂ����v
�u�o�J�A�N���o�X�P�ŃP�����悤�Ȃ�Č����Ăˁ[����v
�u�ł����A��Ε��������v
�u���Ⴀ�n���f����ɂ��Ă���v
�u���[��c�c�Ă��A�W�����P���ł悭�Ȃ��H�v
�u�W�����P������c�c���Ⴀ�A�W�����P���ȁv
�@�ޏ��͂킸���Ɍ��p���ɂ߂�Ɖ��ׂ̗ɖ߂��ė����B������m�F���āu���O�A�n���f�v�Ɖ��������Ɓu��H�v�Ə�����X���Ȃ��牴�̉��ɂ܂��������B���͂����A�Ƒ������ݍ��ݐ^�������ɔޏ����������Č����B
�u���̓O�[���o������A���O���������A��v
�u�͂��H�I�c�c�ȁA�Ȃ�ŁH�v
�u�������B���̗���ŕ�����ˁ[�̂���A�������H������������A���Ƃ܂�——�v
�u�c�c�v
�u����ρA�����Ă���ł����B�Ƃ肠�������O��������v
�u�c�c�v
�u�����ȁH���̓O�[�o������ȁA�_�ɐ����āv
�@�D�����H�̕����ӂ���̂�������ʂ�߂���B�t�F���X�̉��A�Z�납��͕������ꂽ�Ԃ��V�哪�̌�y��̊y���C�Ȑ��������܂ŕ������Ă���B
�u�Ȃc�c��������ȃ��[�����ˁv
�u���߂��ɂ͌���ꂽ���ˁ[��v
�u�n�n�c�c�������Ɂv
�u���O�A�v
�u��H�v
�u�������H�v
�@���R�ƌ݂��̖j���オ�肻�̏ꂪ�����ȏ����ɕ�܂��B���݂͒�オ�������̒[���A�����ƐH�������Č����������E��������o���B�ޏ����S�O���Ȃ��炨�������ƉE��������o�����Ƃ���ŁA���͖ڂ����ׂ߂�B
�@��������Ɣޏ��Ǝ����������������Ƃ��A�����|�������������B
�u——�ŏ��̓O�[�A�������I�v
�@���܂� �����Ȃ� �ӂ��̐��E�B
�i�Ȃ�Ńn���f�t�����̂ɏ���c�c�j
�i����A���˓I�Ɂc�c���ɂ͕��������Ȃ������j
�i�́[���A�Ȃǂ��Ɣ�ꂽ���j
�i�c�c���Ă��ƂŎ��̖]�݁A�����Ă�ˁH�j
�i�ȂA�����Ă݂�j
�i�������c�c��A�q������——�j
�i�͂��H�Ȃ��̒��w���݂Ă��Ȗ]�݂́j
�i�����A���邳���Ȃ��c�c�j
�i�܁A�������ǂ�B�z���A�肥�o���j
�i����c�c���A�ԉΎn�܂��B�߂�����I�j
�i�n�C�n�C�B�j
���w366���^�����x���ނɁB
��Lyric by�w ���ɂ��ā^���@�ɂ������� �x
�@Back / Top