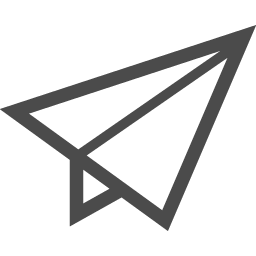
2024バレンタイン(仁王/tns)
「チョコちょうだい」
前の席、後ろ向きにどさりと腰掛けた仁王が放った一言に私は目を丸くした。もちろん、私たちは付き合っているし、こちらには用意もあるので、チョコをあげること自体はやぶさかではない。けれど、ストレートな物言いを避けがちな彼がらしくないことをするものだから驚いた。
これはきっと、何か他の意図があるに違いない。終始仁王に振り回されっぱなしの私でも、最近ようやく“何かある”と察するくらいはできるようになったのだ。さて、今日は何が起きるのか。そう身構え、仁王をじっと見つめてみても、悔しいことに、楽し気に細まる目からは何の企みも読み取れなかった。
ここで「はいどうぞ」と大人しくチョコを渡す選択肢もあるけれど、たまには私だって反撃してみたい。ふつりと湧き上がったちょっとした悪戯心は、彼から伝染したのかもしれなかった。
「チョコならいつも自分で持ってるじゃん」
「生憎、今日は忘れた」
「ふーん。でも今日なら他の子も持ってると思うよ」
「プリッ。でも、おまんも持っとる。女子と交換しよったろう?手作りのやつ」
「あら、よくご存知ですこと。その通り。“交換”は受け付けております」
頭をフル回転させてなかなか上手い反撃をしたつもり。それなのに、仁王は待ってましたと言わんばかりに口角を上げた。
「それなら交換こしてくれるか、お嬢さん」
うやうやしくそう告げると、左手を差し出す。その先にはいつの間にか真っ赤な薔薇が一輪握られていた。白い指に、赤がよく映える。
好きな人に花をもらうなんて、初めてだった。映画やドラマでよく見かけるシーンが、実はこんなに幸せな気持ちになれると知ったのももちろん初めてだ。
予想だにしなかった出来事に、開いた口が塞がらない。
「食いもん以外とは交換不可かのう?」
自分で自覚できるほど頬がゆるんでいる。私が喜んでいるのなんて顔を見ていれば一目瞭然なのに、ニヤついたまま言葉を誘う仁王の意地悪さったらない。
やっぱり振り回されるのは私の役回りだった。
「交換可!」
きちんとラッピングを施した本命チョコを渡せば、当然、花は私の手に納められた。
「わざわざ花屋に?嬉しい……私ってば愛されてる……」
うっとり呟くと、彼はケタケタ笑った。
「わざわざ手作りしてもらって、俺も愛されとるぜよ」
再度目を合わせると、また楽し気に、優しく目が細められる。企みを先読みできずとも、自分が幸せ者であることだけは確かだった。